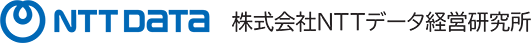令和7年度当初公募 6 介護保険施設等に対する指導の実施率向上に関する調査研究事業
(概要)
介護サービス事業所に対する自治体の運営指導は、本来6年間に1回以上の実施が求められているものの、実際の指導の実施状況は自治体間に大きな差が生じている。その背景には、担当職員の不足やノウハウの未蓄積、地理的制約による移動負担など、地域特性に応じた多様な課題が存在している。本事業では、全国の自治体等を対象としたアンケート調査およびヒアリング調査により運営指導が実施できていない自治体の現状と課題を整理・分析するとともに、広域連携やICT活用、事務受託法人制度などの先進的な取組事例を収集し、加えて、都道府県による市町村支援の好事例も整理する。これらの成果を踏まえ、運営指導に取り組む自治体が実施に向けた第一歩を踏み出すための実践的な支援資料を作成することを目的としている。
令和7年度当初公募 8 地域包括ケアシステムと地域共生社会の推進に向けた継続的・発展的な取組に関する調査研究
(概要)
市町村による地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の推進を支援する方策として、他市町の取組に関する情報共有は一定のニーズがある。九州厚生局がとりまとめ共有している、管内の取組好事例について、各自治体の取組の参考となる情報の提供のあり方を検討するため、以下のような事項について検討を行う。
・地域包括ケア・地域共生社会の推進に係る好事例(ホームページ等における過去の掲載事例)の追跡調査による継続状況の検証
・取組の創出~継続の各段階における課題及びその対応に向けたポイントの整理
・自治体における取組課題や情報提供ニーズを踏まえ、事例の情報の更新や、新たな好事例の発掘
令和7年度当初公募 18 ケアプラン点検の効果的な実施方法に関する調査研究事業
(概要)
ケアプラン点検は、適切なケアマネジメントの実施により、介護サービスを必要とする高齢者に過不足なくサービスを提供することで、要介護高齢者の尊厳の保持や自立支援の実現を支援し、その結果として給付の適正化が期待されているものである。
これまでの調査研究において、ケアプラン点検の実施方法の平準化と職員の事務負担軽減等を目的に、「ケアプラン点検支援マニュアル」を改定し、「ケアプラン点検項目」及び「ケアプラン点検支援ツール」と共に「ケアプラン点検支援パッケージ」として取りまとめた。
本事業では、「ケアプラン点検支援パッケージ」がケアプラン点検の実務において適切かつ効果的に運用されるよう、保険者に向けた研修の在り方を検討し実施する。さらに、ケアプラン点検項目、点検支援ツール、ケアプラン点検のためのアセスメント様式およびケアマネジャーのセルフチェックに活用できるツールについて、令和6年度事業において残された課題の検討を行い、改良を進める。これらの取り組みを通じ、地域包括ケアにおける自立支援に資するケアマネジメントの実現を目指す。
令和7年度当初公募 30 訪問介護の令和6年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業
(概要)
令和6年度の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬や特定事業所加算の見直し、同一建物減算の新たな区分創設などが実施された。これを踏まえ、次回改定に必要な対応を検討する基礎資料を得るため、訪問介護事業所へのアンケートやヒアリングを通じ、見直しが行われた加算・減算を中心として、その算定状況や課題、地域や併設施設の有無による経営状況などを調査する。
令和7年度当初公募 31 小規模多機能型居宅介護等の更なる普及促進に向けたサービス提供の在り方に関する調査研究事業
(概要)
小規模多機能型居宅介護ならびに定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及に向けて人材確保が大きな課題となっていることなどを踏まえ、令和6年度介護報酬改定において各種加算の創設や強化によって普及に向けた対応が行われている。
本事業においては今後の普及促進に向けて、人材確保が難しいことや、サービスの特徴が十分に認知されていないこと等の普及を妨げる要因に令和6年度報酬改定がどのように影響したか、収支の不安定さがサービス提供のあり方にどのように影響しているか、その他のサービスとの差別化等について検証することを目的として、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、ならびに全国の自治体に対するアンケート調査を実施するとともに、普及にあたっての課題を把握するために居宅介護支援事業所に対するヒアリング調査を実施する。
令和7年度当初公募 56 海外における福祉用具の効果検証手法の把握及び福祉用具の効果検証の推進に関する調査研究事業
(概要)
介護保険における福祉用具の新たな種目・種類の取り入れや拡充等については、厚生労働省の「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」(以下、評価検討会)において、「介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」に基づいて、提案内容の妥当性を検討・判断している。令和4年度老人保健健康増進等事業「介護保険制度における福祉用具の範囲及び種目拡充等に関する提案・評価検討のあり方についての調査研究事業」では、提案者が有効性・安全性・保険適用の合理性の3つの視点で提案内容やデータが整理できるよう「介護保険制度における福祉用具の新たな種目・種類の追加・拡充に関する提案の手引書」(以下、手引書)が整理されたが、その後の提案内容は製品のアピールが中心になる傾向があり、検討・判断にあたり十分な情報が得られていない。また、諸外国において福祉用具のIOT化が進む中、本邦でも通信機能を有する福祉用具の開発が進んでおり、評価検討会の中で給付対象とする用途や費用の範囲、リスク等に関する議論がなされている。 本事業では、ヒアリング調査・文献調査によって、提案者の提案内容・データ整理にあたる実態と、諸外国における福祉用具の評価検証手法を把握する。その上で、有識者による作業部会と検討委員会を開催し、手引書の改訂案を取りまとめるとともに、手引書の普及啓発に資するツールを作成する。また、介護保険福祉用具の効果検証手法に確立に資する諸外国の評価検証手法等を報告書に取りまとめる。
令和7年度当初公募 64 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究
(概要)
高齢者の生活支援におけるニーズは多様化している。独居や認知症の高齢者等様々な状況により従来型のサービスだけでは対応しきれない状況があり、特に高齢者自身が選択できるサービスや地域住民とのつながりを重視した取組が求められる
こうした課題に対応するため、地域の実情に応じたサービス提供体制の構築や高齢者の自立支援・重度化防止に向けた効果的な取組の推進が急務となっている。また、サービスの質の向上や持続可能な運営を実現する仕組みづくりも重要な課題である。
本調査研究は、総合事業の充実に向けて令和6年に改正された政省令や地域支援事業実施要綱等の内容を踏まえ、アンケート調査やヒアリング調査等によりサービスの状況や制度等改正による影響を把握し、さらなる総合事業の充実に向けた方策を検討することを目的とする。
令和7年度当初公募 95 海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業
(概要)
現在、自治体における外国人介護人材の確保は重要な課題であり、自治体にはより積極的な取組が求められている。各自治体では、海外現地の行政機関や学校等との覚書の締結、人材の定着を支援するセンターの設立等、戦略的な人材確保に向けた取組が進められている。
本事業では、令和6年度に実施した自治体向けアンケート調査結果を踏まえ、自治体における確保・定着に関する取組状況や課題、必要な支援を把握するためのヒアリングを行い、自治体が活用しやすい形で整理・公表する。
また、日本の自治体が海外で営業・交渉を行う際に活用できる対外発信資料(令和6年度作成)について、実際に使用した自治体や団体に対しヒアリングを実施し、効果や課題を把握のうえ、資料の改善に反映する。
さらに、自治体や介護事業者を対象としたセミナーを開催し、先進的な取組事例の共有や自治体間のネットワーク構築を促進することで、自治体の負担を軽減しつつ、効果的な人材確保と受入体制の整備を支援する。
令和7年度当初公募 101 中山間地域の高齢者における対話型ロボット等を活用した介護人材の業務負担軽減等に関する調査研究事業
(概要)
中山間地域等では人口減少や地域全体の高齢化により、介護人材の不足が深刻化しており、介護人材の業務負担軽減が喫緊の課題である。また、高齢者においてコロナ禍以降、人との交流が制限されたことで社会的孤立がさらなる課題となっている。
一方で、コロナ禍以降、デジタルツールの活用のハードルが低くなっている傾向もあることから、高齢者分野でデジタルツールを上手に活用して上記の課題の解決も期待ができる。
そこで本事業では、資源が特に限られている中山間地域等での対話型ロボット等を活用するモデル事業を通して介護人材の業務負担軽減や高齢者のコミュニケーション不足解消の一助になりうる場面や期待される効果、課題について検証を行い報告書にとりまとめる。
令和7年度当初公募 109 介護情報基盤を活用した医療介護連携に関する調査研究事業
(概要)
全国医療情報プラットフォームの一部となる介護情報基盤では主治医意見書、また、電子カルテ情報共有サービスでは診療情報提供書として患者の情報が医療機関から電子的に共有されることとなっている。一方、各地域では、医療介護連携サマリ等が電子的あるいは紙による情報連携が行われている。今後、全国医療情報プラットフォーム上で、患者の情報のさらなる電子的な共有を推進するためには、医療介護連携サマリ等の医療機関と介護事業所の間でやり取りされている情報について、電子的な共有のあり方を検討する必要がある。
本事業では、医療介護連携において電子的な共有が有用であると考えられる内容(情報項目)を整理し、介護情報基盤を通じた医療機関と介護事業所等間で連携される情報の内容、ネットワーク構成、セキュリティ要件等を整理する。
令和7年度当初公募 119 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営に向けた地方自治体の取組に関する調査研究事業
(概要)
養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、地域の実情に即した自治体独自の改定等も行うよう要請するなど、国として活用を促しているが、地域によっては行政職員も含めて認知度が低く、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの安定的な運営等の障壁になっている場合がある。
そのため、アンケート調査による市町村や都道府県の取組や課題の把握、自治体の担当者等による地方ブロック単位の会議の開催等により、自治体職員の認知度向上・理解促進を図ることを目的とする。
令和7年度追加公募 13 介護事業所における協働化等による職場環境改善の効果検証等に関する調査研究事業
(概要)
日本は2040年に向けて急速な少子高齢化が進み、65歳以上人口が3割を超える一方、生産年齢人口は約1,200万人減少する見通しである。その結果、介護分野では約100万人規模の人材不足が懸念され、特に中山間地域では事業継続の困難が顕在化している。そうした中、地域単位での社会福祉連携推進法人の活用や小規模事業者のネットワーク構築を通じた協働化・大規模化、さらに報酬請求や記録作成といったバックオフィス業務の効率化が、持続可能な介護サービス提供の鍵であると指摘されている。
本事業では、特にバックオフィス業務の効率化に焦点を当て、テクノロジー導入や業務連携による成功事例を収集・分析し、その成果を整理・提示する。また、全国に整備予定の生産性向上総合相談センター(ワンストップ窓口)が担うべき支援内容も検討する。これにより、介護事業所の安定経営と職員の働きやすい環境整備を支える実践的な指針を提示し、将来的な介護サービスの持続可能性に資することを目指す。
令和7年度追加公募 15 介護事業者への経営支援モデル事業
(概要)
介護業界は急速な高齢化と深刻な人材不足に直面しており、2040年には約57万人の追加的介護職員が必要とされる一方で、生産年齢人口の減少により人材確保は極めて困難となっている。また、経営面でも2024年には過去最多の倒産が発生し、その多くが小規模事業者であったことから、経営基盤の脆弱性が深刻化している。こうした状況を受け、介護事業者の経営支援を地域関係者と連携して進める必要性が指摘され、全国で介護生産性向上総合相談センター(ワンストップ窓口)の設置が進められている。しかし、現場では相談内容に応じて適切な支援機関につなぐ判断が難しく、実効的な連携が課題となっている。
本事業では、全国から地域性と実効性を加味して選定した都道府県をフィールドとする調査研究を行う。ワンストップ窓口に寄せられる相談事例を収集・分析し、ワンストップ窓口における実際の連携過程や課題を可視化することで、効果的な支援モデルを検討する。
令和6年度当初公募 6 事務受託法人を活用した運営指導の効率性の向上等に関する調査研究事業
(概要)
自治体における介護サービス事業所への運営指導は、新型コロナウイルス感染症の影響や自治体の人手不足により、国が定める頻度での実施が困難な状況にある。国は指導業務の一部を委託できる「事務受託法人制度」を推奨しているが、地域に担い手となる法人が不足していることや財政的理解が得られにくいことなどの理由から普及が進んでいない。
本事業では、自治体や事務受託法人に対してアンケート調査やヒアリング調査を実施し、運営指導の実施状況や事務受託法人の活用効果、活用に際しての課題を整理した。これらの調査結果を基に、他の自治体や法人が事務受託法人制度を導入する際の参考となるよう、活用のポイントや実際に活用している自治体および事務受託法人の事例を取りまとめた事例集を作成した。事業報告書では、今後、事務受託法人制度の活用を拡大するために自治体が検討すべき視点や、新規参入を促進するために法人に対して行う支援策について整理し、とりまとめた。
令和6年度当初公募 14 地域包括支援センターにおけるICTの導入促進のあり方に関する調査研究
(概要)
地域包括支援センター(以下、センター)においては職員の業務負担の大きさが課題となっており、ICTの活用による業務負担の軽減や業務の効果的な実施が期待されている。一方で、センター業務のICT活用はまだ十分に進んでおらず、センターのICT導入にはいくつかの課題(障壁)があることが明らかになっている。そのため、九州・沖縄地域において、新たにICTを導入するセンターを対象とした実証的な調査を行い、ICT導入による効果の可視化、現場の導入プロセスを踏まえたICT導入における課題とその対応策の検討、およびそれらの成果の普及を図ることを目的として、調査を実施した。
調査の結果、ICTの導入により、利用者訪問1件につき10-20分程度、訪問後の記録や書類作成にかかる業務時間が削減される可能性が明らかになった。業務の改善・質向上の観点での効果としては、相談業務がしやすくなること、持ち運ぶ紙資料の減少による情報漏洩リスクの減少、災害対策における活用等が挙げられた。また、実証的調査の取組経過から示唆された、課題への対応策に共通する考え方として、計画・実施・検証・改善のPDCAサイクルに沿った導入を行うことの重要性が挙げられた。
令和6年度当初公募 17 ケアプラン点検に係るマニュアル及びAIを活用した支援ツールに関する調査研究事業
(概要)
ケアプラン点検は、適切なケアマネジメントの実施により、介護サービスを必要とする高齢者に過不足なくサービスを提供することで、要介護高齢者の尊厳の保持や自立支援の実現を支援し、その結果として給付の適正化が期待されているものである。
これまでの調査研究において、ケアプラン点検の実施方法の平準化と職員の事務負担軽減等を目的に、「ケアプラン点検支援マニュアル」を改定し、「ケアプラン点検項目」及び「ケアプラン点検支援ツール」と共に「ケアプラン点検支援パッケージ」として取りまとめた。
本事業では、「ケアプラン点検支援ツール」を活用した点検方法の周知を目的とした保険者向け研修や、「ケアプラン点検項目」及び「ケアプラン点検支援ツール」の改良を行った。また、ケアプラン点検のためのアセスメント様式や、「ケアプラン点検項目」を参考にケアマネジャーがセルフチェックに活用できるツールについても検討した。
今後は、受講生の背景に応じたより有用性の高い研修の実施や、「ケアプラン点検項目」のブラッシュアップ、「ケアプラン点検支援ツール」の機能強化と社会実装に向けた具体化を図ることを課題とした。また、ケアプラン点検のためのアセスメント様式や「ケアプラン点検項目及び項目マニュアルセルフチェック版案」の確定に向けて、引き続き検討する必要がある。
令和6年度当初公募 33 生活期リハビリテーションにおけるアウトカム指標の検討
(概要)
生活期リハビリテーションについては、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告等において、評価すべきアウトカム及びアウトカム指標の設定が必要とされている。そこで本事業では、アンケート調査及びヒアリング調査を実施し、生活期リハビリテーションの現場でとり入れられているアウトカム及び効果測定の考え方を把握した上で、生活期リハビリテーションにおけるアウトカム評価の在り方を検討した。
本事業における検討の結果、生活期の高齢者においてはリハビリテーションのみの効果を切り出すことは困難であり、各種指標を単純にリハビリテーション提供のアウトカムとして評価することは適切ではないことが示唆された。そこで本事業では、個々の状態に応じた「アウトカム」ではなく、生活期リハビリテーションが及ぼす影響を評価する指標を検討した。
今後の検討に向け、生活期リハビリテーションが及ぼす影響は多岐にわたることから、影響を心身機能・身体構造、活動、参加、心理・社会的側面に分類し、分類ごとに指標を検討することを基本方針とした。特に参加、心理・社会的側面については、現場で広く活用されている指標がないため、その評価方法そのものを検討することを今後の課題とした。
令和6年度当初公募 37 後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究
(概要)
高齢者人口がピークを迎える2040年頃に向けて、医療と介護の複合ニーズを有する患者・利用者が一層多くなることが見込まれ、地域包括ケアシステムをさらに進化・推進させていくことが必要である。在宅業務を行っている薬局数は年々増加しており、全体として薬剤師による在宅における薬剤管理は進んでいるが、在宅患者の医療・介護の複合ニーズに対応するためには、薬剤師・薬局による患者の状態に応じた薬物治療の提供や薬学的支援、多職種連携等を更に進める必要がある。
本事業では、①高齢者等が抱える服薬上の諸問題と薬剤師の介入による効果の把握、②薬局ならびに病院の薬剤師における在宅訪問薬剤管理指導等の業務実態の把握、③薬剤師が在宅医療・介護において担っている在宅サービスの実施上の課題と対応策の検討を目的とした。
本事業の結果、高齢者等が抱える服薬上の諸問題と薬剤師の介入による効果、および薬局・病院薬剤師における訪問薬剤管理指導の実態をアンケート調査結果から全国網羅的に把握した。その具体例としては薬局・病院薬剤師ともに訪問薬剤管理指導により、患者における薬剤の保管不適切などの問題が改善するなどの介入効果が表れていることを把握した。
また薬局・病院薬剤師による在宅訪問薬剤管理指導等の詳細な実態をヒアリング調査結果から把握した。その具体例としては訪問薬剤管理指導により、患者の適切な服薬やADLの向上・不安軽減などに寄与している状況や、業務負担や経営負担・人材不足などの課題に直面している状況などを把握した。
令和6年度当初公募 42 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の今後のあり方に関する調査研究事業
(概要)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、「定期巡回サービス」という。)、夜間対応型訪問介護(以下、「夜間訪問」という。)はともに、定期訪問を中心とした柔軟なサービス提供を軽度者から中重度者であっても在宅生活を継続したい利用者に提供するという点などで共通しており、社会保障審議会介護給付費分科会において「将来的には統合することが夜間対応型の利用者にとって効果的」と提言されている。
本事業では、改定後の定期巡回サービス事業所及び夜間訪問事業所、並びに両サービスの利用者への影響や夜間訪問事業の今後の事業継続の考え方等について調査を行った上で、有識者や事業者団体等により組織する委員会において分析等を行い、両サービスの将来的な統合に向けた課題・方策等を検討した。
令和6年4月の報酬改定で新設された夜間対応型区分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護Ⅲ)の利用者の状況、実際に定期巡回サービスと夜間訪問を統合させていくうえでの課題や今後求められる方策等について報告書にとりまとめた。
令和6年度当初公募 45 訪問介護におけるサービス提供の実態に関する調査研究事業
(概要)
訪問介護において、訪問介護員等の人材不足、高齢化は喫緊の課題となっており、他サービスと比較して事業規模が小さいことから、事業所の収入も少ない状況である。上記をふまえ、訪問介護員等が専門性を発揮し、利用者の状態に応じた安定的なサービス提供のため、介護報酬上の評価のあり方を含め必要な方策等を検討する必要がある。
そこで本事業では、訪問介護におけるサービス提供の実態、訪問介護員の専門性や役割等について調査等を行った上で、有識者や事業者団体等により組織する検討会において分析等を行い、報告書として取りまとめた。
本事業の結果、訪問介護事業所に対する調査結果から、医療ニーズのある利用者に関する疾患知識や専門的な資格を有すること、高度な対人能力を有することが専門性の指標となり得ることが把握した。また、訪問介護事業所としてはサービス内容ごとに専門性を踏まえて訪問介護員を割り当てたいという意向があると考えられるものの、訪問介護員によっては利用者ニーズを上手く把握できない場合があることやイレギュラーな対応は常勤職員やサービス提供責任者が対応せざるを得ない場合があることから、サービスごとに訪問介護員を割り当てることが難しい状況も把握した。
居宅介護支援事業所に対する調査結果から、代替的にケアプランに位置付けられた訪問介護以外のサービスの具体的な内容を把握した。また、代替的なサービスによって利用者が継続して居宅生活を実現している好事例も把握した。一方で地域によっては訪問介護の代替的な社会資源が不足している状況なども把握した。
自治体に対する調査結果からは、社会資源の過不足状況や「同居家族がいる場合には一律、生活援助は不可としている」と回答した自治体もわずかながら存在することなどを把握した。
令和6年度当初公募 71 高齢者の生活支援・社会参加に関わる施策の省庁横断的調査研究事業
(概要)
高齢者の生活支援・社会参加に関連して、①地域づくりの取組を支える制度や助成金等の施策の情報の収集・整理、②自治体等の取組事例の収集・整理、③高齢者の生活支援・社会参加を促す地域づくりの取組を推進するためのポイント及び事例等を自治体・住民向けに共有することを目的として事業を実施した。
地域で持続する取組には「原動力がある」「チャレンジがある」「参加しやすい環境がある」ことが共通していた。また、①人、②環境、③つながり④地域の歴史・文化が影響して具体的な取組の形が決まっていた。さらに、補助金等制度を幅広く活用することによって、関係者は取組に関する経済的な負担を軽減できるだけでなく、制度を活用する過程で住民等関係者と行政等との信頼関係が構築されていることがわかった。
地域の活動を維持するためには、関係者がお互いに気軽にやりとりをすることができること、地域づくりについて目的意識を共有すること、必要な情報がタイミングよく得られること、住民と行政とが取組のためにとれる方法を柔軟に考えていくことが重要である。
事業では、これらのポイントをふまえつつ、市町村や地域の関係者に向けたセミナーを開催したほか、事例集を作成した。
令和6年度当初公募 95 外国人介護人材の受入れ・定着にむけた効果的なICT機器等のツールの利用に関する調査研究事業
(概要)
外国人介護人材が介護施設・事業所で就労する際、言語をはじめとするさまざまな課題が生じることが想定される。ICT機器等の活用は、言語の障壁を低減し、外国人介護人材の業務の理解を助けるとともに、安心して働ける環境づくりにも寄与する。そのため、外国人介護人材の受入れや定着を支援するうえで重要な役割を果たすと考えられる。しかし、ICT機器等の導入経験がない事業者においては、導入前の課題の明確化や適切な機器の選定、さらに、実際の活用方法の確立が難しい場合が多い。
本事業は、ICT機器等のツールを導入・活用することにより、外国人介護人材の受入れ・定着に一定の効果を上げている施設・事業所にインタビュー調査を実施し、外国人介護人材に対するアンケート調査も行った。これらの調査結果をもとに、「外国人介護職員の受入れ・定着のためのICT機器等の活用事例集」を作成し、ICT機器等が外国人介護人材との協働にもたらす効果や、活用のポイントを整理した。事例には、これから受入れが本格化する訪問系サービス事業所でのICT機器等の活用事例も含まれる。また、調査結果等の周知を目的として、事例報告会を動画配信型で実施した。
令和6年度当初公募 121 ICT・AIを用いた要介護認定審査のあり方に関する調査研究
(概要)
要介護認定業務におけるICT・AIの活用の可能性について、公開情報の調査及びヒアリングによって事例を調査し、今後の見通しについて整理した。
認定調査においては、調査自体にAIを活用した事例は見られなかったものの、AIを用いて調査票の内容確認を補助するサービス事例があった。主治医意見書の作成においては、調査時点ではサービス化までは至っていなかったものの、電子カルテ等の情報から意見書を生成する仕組みの構築が期待される。認定審査会については、AIによって審査会資料をマスキングし、資料作成を効率化するサービスが存在していた。また、現在開発中で実用化の可能性がある技術として、二次判定により要介護度が変更される可能性が高い者を分析する等、人による審査を補助するAI技術があった。
今後のAIの開発には、テキストデータ化された認定調査結果や主治医意見書を用いることが適切である。そのために、自治体規模等条件を考慮しつつ、将来的には認定審査に使用する認定調査票、主治医意見書等の情報のテキストデータ化が進められることが理想である。
令和6年度当初公募 131 地域共生社会の実現に向けた養護老人ホーム及び軽費老人ホームの取組のあり方について
(概要)
本事業では、全国の養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおいて地域共生社会の実現に向けた取組を促進するため、先進的な取組を実施しているモデル施設に対する伴走的な支援を実施し、その成果や課題を整理・分析した。また、モデル施設での具体的な取組内容や課題解決に向けた手法を明らかにするとともに、成果報告会を開催し、積極的な横展開を図った上で、地域共生社会の実現に向けた取組のあり方と促進方法を取りまとめた。
具体的には、全国8か所のモデル施設(養護老人ホーム4施設、軽費老人ホーム4施設)を選定し、施設の実情に応じた取組計画の策定支援や地域連携体制の構築支援等を行い、モデル施設である養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおいて、地域共生社会の実現において果たし得る役割を踏まえた様々な取組が行われた。一方、施設の取組を進める上では、自治体との継続的な協議と支援の必要性といった課題が浮き彫りとなった。これらを踏まえ、取組の実行体制や地域との連携方法等の取組の手順を整理するとともにポイント・留意点等をとりまとめた。
さらに、本事業では、取組の普及啓発として、モデル施設による成果報告会を開催し、参加者の反応を収集・分析した。今後の地域共生社会の実現に向けて、施設への取組の意義・基本的な手順の理解を促す研修の充実、意見交換の場の設置、取組事例の蓄積等、普及啓発活動と取組事例の創出に向けた仕組みづくりが求められることが示唆された。
令和6年度三次公募 3 海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業
(概要)
現在、自治体における外国人介護人材の確保は重要な課題であり、自治体にはより積極的な取組が求められている。各自治体では、海外現地の行政機関や学校等との覚書の締結、人材の定着を支援するセンターの設立等、戦略的な人材確保に向けた取組が進められている。
本事業では、外国人介護人材の確保・定着に関する自治体の取組状況を網羅的に把握するため、アンケート調査を実施し、「海外との覚書や合意」、「海外とのつながり」、「国内での外国人介護人材の確保・定着に関する取組」等を収集し、そのプロセスや課題を明らかにした。また、積極的に人材確保に取り組む複数の自治体にヒアリング調査を行った。
さらに、日本の自治体が海外の現地国で直接営業や交渉を行う際に活用できる資料として、日本の介護分野を説明する対外発信資料(パワーポイント形式)を日本語と英語で作成した。
令和5年度当初公募 3 地域ケア会議と生活支援コーディネーターの協働に関する調査研究事業
(概要)
地域ケア会議と生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が協働することで、より効果的に地域課題を発見し、地域に支え合いの体制を作っていくことが期待されている。
本事業では、高齢化と人口減少の著しい東北地方において両者の協働を促進することを目指し、東北地方の市町村の事例収集や、地域ケア会議関係者や生活支援コーディネーターを対象としたワークショップを実施した。その上で、実際に取り組まれていた工夫やワークショップで出された意見等をもとに、パンフレット「地域ケア会議もっとよくするヒント集」を作成した。
少子高齢化の状況を踏まえると、家族資源に頼らず、地域資源や社会サービスで支える地域づくりに取り組む必要がある。地域の介護予防に関わる市町村や地域包括支援センターの職員、生活支援コーディネーター、専門職等が、地域づくりの方針や会議の目的、検討の視点(「予後予測」や「自立支援」等)を共有することが重要である。また、会議の結果を具体的な資源開発や政策形成につなげるためには、困難ケースだけでなく、要介護度が比較的軽度で地域に共通する「よくあるケース」の検討を複数重ねることが重要である。
令和5年度当初公募 14 地域包括支援センターの機能強化に向けたICTの活用に関する調査研究事業
(概要)
地域で複雑化・複合化されたニーズへの対応の必要性が高まる中、センター職員の業務負担が大きな課題となっている。そのため、センターにおける業務負担の軽減や、効果的な運営のためのICTの一層の活用が期待される。
そこで本事業では、センターにおけるICTの活用状況や活用における課題等を把握するため、九州・沖縄内のセンターを対象にアンケート調査を行った。また、ICT活用に取り組むセンターを対象にヒアリング調査を行い、具体的なICTの活用内容や成果、導入プロセスにおける課題への対応の工夫等を把握した。
調査の結果、センターでは「場所を問わずに情報の記録や確認ができる環境の整備」「外部関係機関との情報連携のデジタル化」のためのICTの活用が期待される一方で、現状ではそのような観点でのICT導入は必ずしも進んでいないことが明らかになった。また、その背景には、ICT導入・運用に必要な費用の確保、職員の機器の慣れへの対応、個人情報保護・セキュリティ面での対応等の課題があることが明らかになった。これらの課題に対応するため、市町村は、ICTのモデル的な導入を行うことができる環境の整備、国の指針等を踏まえた市町村としての個人情報保護・セキュリティのルールの整備など、センターのICT活用を促進するための取組の工夫が求められると考えられる。
令和5年度当初公募 20 ケアプラン点検に係るマニュアル及びAIを活用した支援ツールに関する調査研究事業
(概要)
ケアプラン点検は、適切なケアマネジメントの実施により、介護サービスを必要とする高齢者に過不足なくサービスを提供することで、要介護高齢者の尊厳の保持や自立支援の実現を支援し、その結果として給付の適正化が期待されている。
しかし、令和3年度研究事業により、ケアプラン点検の実施方法は保険者により様々であり、多くの保険者で専門的な知識やスキルを有した職員の確保が課題となっていることが明らかとなった。
このため、令和4年度研究事業により、ケアプラン点検の実施方法の平準化と職員の事務負担軽減等を目的とし、平成20年に策定された「ケアプラン点検支援マニュアル」の改定版の骨子案の策定や、令和3年度研究事業で作成した「ケアプラン点検項目」の改定、AIを活用したケアプラン点検の支援の実装化(ケアプラン点検支援ツールの開発)を行った。
これらの成果を踏まえ、今年度事業では、各3回開催した検討委員会、ワーキング・グループでの議論と実証実験(保険者のケアプラン点検担当者・ケアマネジャーを対象としたアンケート・ヒアリング調査、ケアプラン点検支援パッケージの試験運用)の結果を踏まえ、「ケアプラン点検支援マニュアル」を改定するとともに、ケアプラン点検項目、ケアプラン点検項目マニュアル、ケアプラン点検支援ツールのブラッシュアップを行った。
令和5年度当初公募 33 介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しに向けた調査研究事業
(概要)
介護保険における福祉用具の選定の判断基準(以下「判断基準」という。)は福祉用具が要介護者等に適正に選定されるために、個々の福祉用具毎にその特性や、利用者の状態から判断して明らかに「使用が想定しにくい状態」及び「使用が想定しにくい要介護度」を提示しているものであるが、平成17年以降は見直しがされていない。また、厚生労働省において開催されている「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」の議論の整理では、給付対象として追加された福祉用具への対応、軽度とされている者の利用も踏まえた検討、多職種連携の促進等の観点から、見直しの必要性についてまとめられたところである。
このような経緯を踏まえ、本事業では、文献調査、利用事例及び事故・ヒヤリハット事例を検証・精査し、現在の給付における特徴や課題を整理した。これに併せて、有識者に対して判断基準の課題等に関するヒアリングを実施し、判断基準改訂案のたたき台を作成した。
これを基に、福祉用具に関わる有識者で組成した地域検討会において、多職種の観点から様々な知見を収集し、それらの内容をもとにワーキング・グループで判断基準改訂案をとりまとめ、検討委員会ではその内容について検討・審議し、判断基準改訂案及び事業報告書を作成した。
令和5年度当初公募 37 地域密着型サービス事業所における運営推進会議等に関する調査研究事業
(概要)
本事業では、運営推進会議等の運営および運営推進会議等を活用した外部評価を効果的・効率的に実施するための対応策の検討に資する情報を得るため、地域密着型サービス事業所や市区町村に対するアンケート調査、ヒアリング調査を通じて、以下1)~4)を行った。
1)運営推進会議等の実施・支援の実態把握と課題抽出
2)運営推進会議等における外部評価の実施・支援の実態把握と課題抽出
3)効果的・効率的に運営推進会議等の運営や外部評価を実施している事業所の取り組みの好事例の把握
4)1)~3)を踏まえた今後の対応方針の提言
また、上記の結果について有識者や事業者団体等により組織する検討会において検討を行い、報告書として取りまとめた。
本事業の結果、地域密着型サービス事業所における運営推進会議等の実施目的や工夫している点、課題などが把握された。また外部評価の運営状況や課題、外部評価で得られた情報等の活用状況が把握された。また市区町村における運営推進会議等や自己評価・外部評価への支援の実態が把握された。
また本調査で得られた情報を踏まえ、地域密着型サービス事業所が運営推進会議等の運営や外部評価を行う際にマニュアルを活用できるようにするための施策の促進について提言した。また市区町村における事業所の改善状況の把握や、事業所への支援の促進、市区町村・事業所・地域が一体となった地域づくりの促進について提言した。
令和5年度当初公募 39 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及等に関する調査研究事業
(概要)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、「定期巡回サービス」という。)は中重度になっても住み慣れた地域での在宅での暮らしを支える仕組みとして創設され、サービスが提供されている。しかしながら、経営面の課題や人材確保の難しさ等から、利用者数・事業所数ともにまだ十分な数に到達しているとはいえない状況であり、さらなる普及が期待されている。
本事業では、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)において今後の課題とされた定期巡回サービスの更なる普及を図るための方策やこれらのサービスの機能・役割の検証等を行う観点で、中重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、24時間365日の在宅生活を支援する定期巡回サービスの更なる普及を図るための方策について引き続き検討するため、主に次の点について調査等を行った上で、有識者や事業者団体等により組織する委員会において分析等を行った。具体的には夜間帯等におけるサービス提供状況、計画作成責任者の業務内容、地域との連携に関する取組の状況、ICTの導入状況・効果について調査を行い、定期巡回サービスの現状の把握に加え、更なる普及を図るための課題や方策について整理することができた。
特に、定期巡回サービスの普及に向けては、個別の事業所の実態を踏まえない自治体の独自ルール(いわゆるローカルルール)の是正、計画作成・変更時等におけるケアマネジャー・訪問看護との連携推進、地域との連携や地域資源の活用、ICTの活用促進が重要であると考える。
本事業で把握された地域連携・地域資源の活用、ICT活用等についての実践事例を集約し、自治体・事業者団体等から提示することや、併せて、個別の実態を踏まえないローカルルールの是正等が図られることで、定期巡回サービスがサービスの質を維持しながら効率的な運営が可能となる環境が整備され、更に普及していくことを期待する。
令和5年度当初公募 40 通所系サービスにおける新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査
(概要)
新型コロナウイルス感染症の流行により、通所系サービス事業所(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション)は、休業、サービス時間の制限、人口密度緩和のための1日あたり利用者数の制限等の対応をとり、利用者自身も自主的に利用を控える等、サービスの運営に大きな影響を及ぼした。本事業では、通所系サービス事業所、利用者・家族、居宅介護支援事業所に対して、新型コロナウイルス感染症への対応状況についてアンケート調査を行い、今後感染症が流行した際に事業所や行政に求められることについて内容を整理し、とりまとめを行った。
令和5年度当初公募 57 生活支援コーディネーターを中心とした、地域づくり・生活支援に資するさまざまな「つながり」の構築及び強化に関する調査研究事業
(概要)
自治体では生活支援体制整備事業において、生活支援コーディネーターを中心に高齢福祉分野に単独で地域資源の開発及びマッチング等が行われてきたが、そのアプローチは地域の資源が限られる中山間地域においては限界がある。本研究は、自治体が地域づくりを効率的かつ効果的に推進するために、高齢福祉分野以外の生活支援に関わる様々な自治体の施策や地域の諸主体の活動が存在する中で、自治体や生活支援コーディネーターの活動をどのように位置づけることができるか、2つの中山間地域のフィールド調査を踏まえ、検討したものである。
令和5年度当初公募 61 医療機関等と連携した通いの場をはじめとする介護予防の取組の推進に関する調査研究事業
(概要)
介護予防の観点から、通いの場の取組を推進しているが、通いの場に参加していない高齢者の中にも、フレイル等のリスクを有している者も多く含まれることが懸念され、不参加者へのアプローチが重要である。高齢者は外出の機会は少ないが、多くの人は医療機関を定期的に受診している。そのことから、地域の医療機関等と連携して、フレイル等のリスクがある高齢者の早期発見、介護予防の取組につなげる仕組みの構築が求められている。
本事業では、令和4年度事業において抽出された課題等を踏まえ、より効果的な介護予防の取組に関する医療機関との「連携モデル」を実践的な検証を通じて構築するとともに、この実証を通じ、医療機関等を対象としたモデル研修を実施し、その効果検証を行った。また、自治体等における、先進的なフレイル等に関する介護予防の取組の実態調査を行い、現状の分析および課題整理を行った。
その結果、フレイル等の疑いのある患者の抽出と介入の両面で成果が確認され、さらに、先進的な事例の横展開に向けた取りまとめと併せて、医療介護連携やフレイルの認知度不足等が介護予防の取組の推進への課題であることが明らかになった。
令和5年度当初公募 64 地域支援事業における地域の社会資源の活用と庁内連携に関する調査研究事業
(概要)
高齢者の介護予防においては、地域のつながりや活動の活性化が重要であり、そのために地域の多様な社会資源を活用が必要である。またその際には、自治体の高齢福祉部局だけでなく、関係する庁内の部局や庁外の関係者との連携も重要である。一方で過年の研究によると市区町村内の関係部局間の連携(分野間連携)はまだ少なく、その障壁として職員は通常業務が多忙で他分野との連携を行うことに対する時間と心の余裕がないことが指摘されている。しかし連携による業務効率化などのメリットも想定されるため、今年度では、地域包括ケアシステムにおける地域の多様な社会資源の把握及び積極的な活用及びその資源を有効に活用するための庁内外の望ましい連携のあり方を明らかにすることを目的に調査を実施した。
社会資源の活用に資する制度や支援策等の収集・整理(関東信越管内の支分部局へのヒアリング)、好事例の取組を実施する自治体等の調査の実施(市区町村へのアンケート及びヒアリング)、事例付手引きの作成及び報告会の実施及びこれらに関する検討委員会の設置・運営を実施した結果、分野連携により活用できる資源が広がることのメリットとして、地域支援事業においてもサービスを届けられる人が増えることや、既存の資源を活用することによる効率的な事業の推進が可能となること等が示唆された。また、連携のポイントとして関係者間での対話により理念・目的を共有すること、相互の強みの理解と共にそれを補完すること、既存の資源・取組を活用することにより効果的に事業を推進すること、仕組み化を行うことにより属人化を避け継続性を担保することの4点が整理された。
今後は、地域の社会資源の把握と活用のためには分野連携によるメリット及び地域の取組を支援する制度や支援策の普及啓発をより一層行うことや、庁内外の連携において対話の重要性、楽しさやワクワク感から新しい取組が生まれること、取組を継続させるための仕組づくりに関する重要性の理解を促進することが期待されると考察した。
令和5年度当初公募 68 医療・介護連携の推進に向けた情報提供のあり方にかかる調査研究事業
(概要)
高齢者の増加とともに、医療と介護双方のニーズを有する高齢者が増加する。それぞれの高齢者が“ときどき入院、ほぼ在宅・施設”のどの場面においても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、医療においてはより「生活」に配慮した質が高い医療を、介護においてはより「医療」の視点を含めたケアマネジメントが求められている。
このような医療・ケアの実現に向け、医療・介護の関係者、関係機関間の情報提供や共有、相互の理解といった連携を更に推進する必要がある。関係者間の情報提供、共有にあたっては、医療・ケアが継続的に提供されるように情報を必要十分に伝えることが不可欠であり、情報提供時の様式はそれを支援するものであることが求められる。
他方、「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、介護情報も含めた「全国医療情報プラットフォーム」の構築が進められている。デジタル化された医療・介護情報を利活用することにより、医療・介護サービスの更なる質の向上や業務負荷軽減に資することが目指されている。
本事業では、将来的な全国医療情報プラットフォームの整備等も見据え、関係機関間の情報提供や共有、相互の理解向上を目的に、入退院の場面において医療機関・介護事業所間で情報提供を行う際に用いる様式について、関係団体や専門家等の意見を踏まえ、必要な項目等の検討を行い、改訂版入院時情報提供書(在宅版・施設版)および改訂版居宅介護支援事業所向け診療情報提供書を作成するとともに、検討内容を報告書にとりまとめた。
令和5年度当初公募 73 中山間地域等での情報通信機器等を活用した歯科をとりまく在宅医療介護連携に関する調査研究事業
(概要)
中山間地域等の高齢者は口腔に関する課題を抱えている方も多いと思われ、フレイル・がん等の対策の観点からも、医療へのアクセスが容易でない中山間地域等の高齢者のICTを活用も含めた歯科専門職との連携・オーラルフレイル予防等に関しての状況を把握することを目的に、四国4県の市町村及び医療機関、歯科医療機関、介護施設、訪問看護ステーション、に対して実態調査を行った。
調査結果より、在宅医療介護連携において、歯科領域との連携が進んでいない医療機関・施設等が一定数あることが確認できた。また、歯科領域の分野において専門職種間のコミュニケーション不足や知識の差があると考えている歯科医療機関・施設も多かった。一方で、地域の歯科専門職と連携ができている自治体は多かったが、連携内容や連携頻度・密度については課題が多く挙がった。ICTの活用についても取組みがまだ進んでいないことも把握ができた。
また、本調査研究事業では、歯科領域におけるICTの活用も踏まえた高齢者のお口の確認方法・相談内容の伝え方の手引書も作成した。この手引書を活用し、高齢者を取り巻く関係者の積極的な歯科領域の交流が生まれることが望まれる。
令和5年度当初公募 79 認知症の人や家族の心理的・社会的サポートに関する調査研究事業
(概要)
近年、診断から支援につながるまでの期間の重要性が認識され、ピアサポーターによる早期からの支援活動や、認知症当事者を見守る仕組みが各地で展開され始めているが、認知症の診断を受け止めるための心理的サポートは未だ不足している可能性がある。
本事業では、当事者の「語り」の質的分析やヒアリング調査を実施し、診断直後~支援先につながるまでの最も心理的不安が大きい時期の心理的支援について、現状、課題やニーズ、あるべき姿を検討した。
検討の結果をもとに、77人の認知症当事者(本人:26人、家族:51人)の声を盛り込み、地域の関係機関や団体、事業所等の相談先・支援先で活用可能、かつ当事者にとっても生活基盤の支援者に自分たちの思いを伝えることができるハンドブック「認知症の人と家族の思いにふれあうハンドブック~聞いてください、認知症とともに今を生きる私たちの声~」を作成した。
ハンドブックは全4章で構成し、支援の第一歩となる、当事者の思いを知ることに役立てるため、当事者の率直な思いや支援者へのメッセージを多く盛り込み、これまで認知症当事者とかかわったことがない/かかわる機会が少なかった支援者でも手に取りやすいイラストを用いたデザインで作成した。
また、本事業の実施過程や検討委員会における議論から、産官学連携のもと取り組むべき今後の検討課題として、国民の「認知症」に対するイメージの変容、支援者による認知症の人との接し方の変容、認知症の人と家族が話しやすい環境整備、認知症の人が普通に暮らせる、当事者を線引きしない社会の実現(「認知症基本法」の理念実現)が示唆された。
2024年(令和6年)は「認知症基本法」施行元年であり、今後これらの課題解決・理念実現に向けたきっかけづくりに資することを目指し、報告書をとりまとめた。
令和5年度当初公募 91 外国人介護福祉士の活動実態に関する調査研究事業
(概要)
介護現場における外国人介護人材は、現在4つのルート(「特定活動(EPA)」「介護」「技能実習」「特定技能」)から受け入れている。その中で、介護福祉士取得者は、かつては経済連携協定(EPA)による介護福祉士候補者の合格者、又は、介護福祉士養成施設卒業者のみであったが、現在は「留学」や「技能実習」、「特定技能」による介護福祉士の取得ルートが拡大し、介護福祉士として就労する外国人介護人材が増加している一方、外国人介護福祉士全体の実態は定かではない。
本事業では、公益財団法人社会福祉振興・試験センターの協力のもと、介護福祉士に登録している外国籍の方を対象に、介護福祉士の取得ルート、介護福祉士取得から現在に至るまでの生活や就労、将来の意向等についてのアンケート調査を実施した。
報告書では調査結果を踏まえ、今後、外国人介護福祉士の実態を正確に把握する上で必要となる対応や、外国人介護福祉士が一層活躍できるようになるために必要と考えられる支援を整理し、とりまとめた。
令和5年度当初公募 92 地域の外国人高齢者に対する外国人介護人材の役割に関する調査研究事業
(概要)
近年、日本に住む外国人の高齢化が進んでいる。また、外国人人材の受入れについても加速しており、将来日本に長期滞在する者、家族を形成する者が増加し、今後も外国人住民の高齢化が進むことが見込まれる。一方で、外国人高齢者への適切な支援や体制づくりが、社会全体で行われているとは言い難い状況である。
本事業では、令和4年度事業を踏まえ、外国人高齢者に対するより包括的な支援の在り方や外国人高齢者の支援における外国人介護人材の役割を明らかにすることを目的とし、外国人高齢者への情報提供や支援等のために活動している団体や事業所等にヒアリングを行った。また、外国人高齢者の支援ニーズを把握するため、介護サービスを利用する外国人高齢者やその家族にもヒアリングを行った。
本事業で集めた外国人高齢者の支援の事例や取組、外国人介護人材の活躍は、今後、外国人高齢者の支援に関わる人々に役立ててもらえるよう、事例集にまとめた。加えて、自治体や施設・事業所、住民等に外国人高齢者の課題や今後の在り方等について周知することを目的に、「外国人高齢者の支援に関する事例報告会」を開催した。
令和5年度当初公募 94 海外における外国人介護人材獲得に関する調査研究事業
(概要)
人口減少・高齢化社会に対応した人材確保の取組は日本のみならず諸外国でも進められている。日本では、2017 年9 月より在留資格「介護」、2017年11 月より「技能実習(介護)」、19 年4 月より「特定技能」の受け入れを開始し、国内介護人材として従事するための入り口を段階的に拡充してきた。
コロナによる入国制限の影響があったものの、入国制限が緩和された2022年春以降、待機していた技能実習生をはじめとする介護人材の入国が急速に増加している。人材の主要送出国であるベトナム、インドネシア、フィリピンでは、送出機関、介護事業者などが活発な採用活動を展開している。しかし、従来に比べて良質な人材獲得に苦戦する声が介護事業者から伝えられている。この背景には、日本が入国制限をしていた期間にも他国が積極的な採用や教育活動をしていたこと、為替の影響、待遇格差など様々な要因があると伝えられている。これらの問題は急速に高齢化が進むアジア各国の状況を踏まえると、一時的とは考えづらく、今後、介護事業者を取り巻く外国人材獲得競争は一層厳しくなるとが予想される。
本事業では、介護人材獲得を積極的に進める国(「受入国」:カナダ、ドイツ、台湾)と、介護人材を各国に送り出す国(「送出国」:フィリピン、インドネシア、ベトナム)の状況について、文献調査・ヒアリングを通した情報収集・分析等を行うことにより、各国の政策・支援内容等に関する現状や課題について明らかにした。また、国内調査においては、外国人介護人材受入に関わる政府機関及び介護事業者等における対応状況について情報収集・分析を実施し、日本がとるべき対応策案と具体例(神戸モデル、東川町モデル等)を整理した。
受入国・送出国に共通する課題を踏まえ、日本がとるべき対応策案として、(1)受入れルートの多様化、(2)情報発信・伝達ルートの確立、(3)好循環の創出が重要な時期に至っていると考えられる。
令和5年度当初公募 105 介護ロボットの効果的な導入支援に関する調査研究事業
(概要)
介護ロボット等のテクノロジーの効果的な活用に向けては、単に機器を導入するだけでなく、現場の課題把握や課題に応じた機器の選定、機器の効果的な使用方法等に関する研修等、開発企業および販売事業者(以下、企業)による導入前後の支援等も重要である。
本事業では、企業における介護ロボット等の購入者に対する支援・販売状況や行政機関が行っている機器の活用に関する支援(研修・リスキリング等)の状況、購入者が企業や行政に求める支援等を調査した。
調査の結果、一部の企業が、業務見直しの提案や導入効果の測定・分析といった、機器の導入・活用支援の担い手となりつつあることが確認された。今後は、介護現場が企業等の支援者を有効に活用し、機器の導入・活用を進めていくことが想定される。そのために、①企業による支援方法の整理・提示および支援者としての企業の人材育成、②企業による支援の効果を得やすくするための介護現場の環境構築・人材育成、③外部支援者を効果的に活用するための介護現場の人材育成が必要と考えられる。
また、令和3年度に作成した「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」を更新し、介護現場において活用されるテクノロジーについて、現在、我が国において上市されている製品108件を掲載した。
令和5年度当初公募 112 要介護認定情報のデジタル化・電送化に関する調査研究事業
(概要)
要介護者・要支援者の適切な介護サービスの必要度を判断する要介護認定は、今後、その申請件数が増加することが予想される。しかし、要介護認定実務を担う保険者や認定調査員等の人材不足が著しく、その負担軽減が求められている。現在、介護情報等を利用者や保険者、医療機関、介護事業者等が電子的に閲覧できるよう「介護情報基盤」の整備が進められており、それに伴う要介護認定実務作業のデジタル化・電送化による効率化・時短化が期待される。
本事業では要介護認定に関わる、①主治医意見書の作成依頼・授受、②要介護認定調査、③開示請求における実態調査を行い、今後のデジタル化・電送化に向けて、課題抽出を行った。その結果、①から③の全てにおけるやり取りはほぼ紙媒体で行われており、それに伴う様々な課題が明らかとなった。課題の一部は要介護認定情報のデジタル化・電送化に加え、主治医意見書や認定調査票の様式を全国的に統一することで解決可能と考えられる。本事業では新たな様式案等の検討を行った。
令和5年度当初公募 120 地域医療情報連携ネットワークと介護情報連携基盤に関する調査研究事業
(概要)
全国医療情報プラットフォームの一部である介護情報基盤において、利用者・市区町村・介護事業所・居宅介護支援事業所・医療機関間にて共有すべき情報について検討が進められている。本事業では、各地域において医療・介護情報の共有を進めている地域医療情報連携ネットワーク(以下、地連NWとする)5事例に対してヒアリング調査を行い、介護情報基盤で共有すべき情報やユースケース、地連NWと介護情報基盤の在り方について検討を行った。
調査結果により、要介護認定情報、請求・給付情報・LIFE情報・ケアプランについて、業務の効率化や介護・医療サービスの質の向上につながるユースケースと共有すべき情報を明らかにした。また調査結果を踏まえ、介護事業所等が介護情報基盤を利用するメリットについて考察した。
地連NWと介護情報基盤を含む全国医療情報プラットフォームは、その目的や用途が異なり、両者を統合するメリットは存在せず併行して運用することが望ましい。連携の在り方として介護情報基盤において要介護認定情報、請求・給付情報、LIFE情報、ケアプランや医療情報基盤の情報を着実に共有した上で、地連NWにおいて介護情報や医療情報をリアルタイムに情報共有を行うことにより医療・介護サービスの質の向上の更なる向上が期待できる。
令和5年度追加公募 9 養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける地域共生社会の実現に向けた取組の促進等に関する研究事業
(概要)
本事業では、全国の養護老人ホーム・軽費老人ホームにおける地域共生社会の実現に向けた取組の促進方法を取りまとめるため、地域共生社会の実現に向けた従来の枠にとらわれない積極的な取組を行い、安定的な運営状態にある養護・軽費老人ホーム等に対して、ヒアリング調査を実施した。なお、ヒアリング調査及び検討委員会での議論を踏まえて、モデル施設支援計画を策定し、モデル施設の地域共生社会の取組の実施に関して、助言等の支援を実施した。
調査の結果、先進事例施設で調査枠組みとした地域共生社会の実現に向けた従来の枠にとらわれない積極的な取組を振り返ると、今後の地域共生社会の実現に向けた養護老人ホーム・軽費老人ホームが果たしうる役割は多々あることがうかがえた。
また、今後より多くの養護・軽費老人ホームにおける、地域共生社会の実現に向けた取組を促進し、地域共生社会の実現に寄与する施設としての存在意義を明らかにしていくためには、多様な事例の創出を図るとともに創出された事例における継続的な取組の経過を踏まえた分析を行うことで、地域ニーズの把握、場合によっては、地域ニーズの把握のあり方やそれに関する自治体との連携・協働のあり方、取組の手順の体系化(PDCAサイクルの確立)や評価指標の可視化に向けた検証を進める必要がある。さらに、地域共生社会の実現に向けた取組の普及・啓発に向けて、モデル施設による成果報告会の開催等の普及啓発活動の実施やそれらの参加者の反応をモニタリングして、次の打ち手を検討していく必要があると考える。
令和4年度当初公募 24 AIを活用した効果的・効率的なケアプラン点検の方策に関する調査研究事業
(概要)
ケアプラン点検は、適切なケアマネジメントの実施により、介護サービスを必要とする高齢者に過不足なくサービスを提供することで、要介護高齢者の尊厳の保持や自立支援の実現を支援し、その結果として給付の適正化が期待されている。
しかし、令和3年度研究事業により、ケアプラン点検の実施方法は保険者により様々であり、多くの保険者で専門的な知識やスキルを有した職員の確保が課題となっていることが明らかとなった。
このため、本年度調査では、ケアプラン点検の実施方法の平準化と職員の事務負担軽減等を目的とし、平成20年に策定された「ケアプラン点検支援マニュアル」や、令和3年度研究事業で作成した「ケアプラン点検項目」の改定、AIを活用したケアプラン点検の支援の実装化(ケアプラン点検支援ツールの開発)に向けた検討を行った。
その結果、「ケアプラン点検支援マニュアル」改定案の骨子を作成することともに、「ケアプラン点検項目」の改定や、点検項目の設定意図を明らかにするための「ケアプラン点検項目マニュアル」を作成した。また、「ケアプラン点検支援ツール」の開発に向けた教師データの収集、有効性の検証等を目的とした実証実験を行い、その結果を基に「ケアプラン点検支援ツール」の初版を開発した。
今後は、「ケアプラン点検支援マニュアル」改定版の完成に向けた検討を行うとともに、「ケアプラン点検項目」及び「ケアプラン点検支援ツール」をブラッシュアップさせ、一体的に現場で活用されるよう、運用方法を検討するとともに、現場への周知方法を検討する必要がある。またこれらを活用したケアマネジャーによる自己点検を促し、ケアマネジャーの自立支援に向けたケアプランへの気づきと学びを促すことも重要である。
令和4年度当初公募 30 要介護認定事務の効率化に向けたICTの活用に関する調査研究事業
(概要)
我が国では、高齢者、特に後期高齢者数の増加に伴い、要介護認定者数も増加することが見込まれている。要介護認定者が増加することで、認定調査員の不足や介護認定審査会における審査件数の増加等による業務負担への影響が想定されている一方、被保険者が結果を受領するまでの期間を短縮する必要があることから、要介護認定業務の効率化を図る必要がある。
そこで本事業では、令和3年度事業の全国実態調査等を踏まえ、要介護認定業務のうち、特に認定調査票作成~一次判定までの工程におけるICTの効果的・効率的な活用方法について検討した。まずはヒアリング調査によって先進事例を収集し、その結果をもとに複数の保険者に対してICTを試験的に導入し、実証実験を行った。
結果、要介護認定業務において効果的・効率的にICTを活用していくには帳票やデータ連携の「様式の標準化」やシステム導入の「普及モデルの確立」の課題があることが明らかになった。
令和4年度当初公募 45 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業
(概要)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及び(看護)小規模多機能型居宅介護は、中重度になっても住み慣れた地域での在宅での暮らしを支える仕組みとして創設され、サービスが提供されている。しかしながら、両サービスとともに、経営面の課題等から利用者数・事業所数ともに、まだ十分な数に到達しているとはいえない状況であり、さらなる普及が期待されている。本事業においては、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)において、今後の課題とされた定期巡回サービス、小多機の更なる普及を図るための方策やこれらのサービスの機能・役割の検証等を行うため、事業所調査において、事業所の人材確保、利用者確保及びサービスの質の向上に関する取組等の状況について調査を行うとともに、保険者調査において、保険者の整備方針、意向について調査を行い、定期巡回サービスと小多機の普及に向けての課題や方策について整理した。
定期巡回サービスと小多機の普及に向けては、事業所における人材確保・利用者確保についての取組をその背景と併せて整理し、周知していくことが有用であることや、保険者における支援策の充実が重要であることが確認された。
また、夜間訪問と定期巡回サービスの今後の在り方については、令和3年度調査を踏まえて追加のヒアリング調査を行い、夜間訪問と定期巡回サービスが統合された場合の影響について、現在の夜間訪問の利用者が、定期巡回サービスまたは24時間対応が可能な訪問介護を利用することができることが確認された。
令和4年度当初公募 54 介護老人保健施設における薬剤調整にかかる調査研究事業
(概要)
本事業では、介護老人保健施設を対象としたアンケート調査、ヒアリング調査を通じて、令和3年度介護報酬改定で見直されたかかりつけ医連携薬剤調整加算の算定状況および、算定が進んでいない場合にはその困難要因、また、加算算定の困難要因と考えられる事項に対して、工夫して対応している事例などを把握し、困難要因やその対応策の詳細な分析を行うとともに、現場で好事例として参考となるようとりまとめることを目的とした。
本事業の結果、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)の算定状況は介護老人保健施設の13.9%が算定しており、令和3年度調査結果の6.2%より割合が高くなり、同様に加算(Ⅱ)は10.3%、加算(Ⅲ)は8.5%であることが把握された。加算(Ⅰ)を算定する上での主な困難要因は、主治医との連携と研修受講であることが把握され、これらの対応策として、文書の活用と周知、別紙様式8の見直しなどを提案した。加算(Ⅱ)を算定する上での主な困難要因は、LIFEの活用において、提出データを作成する作業に負担を感じること、処方薬の入力に煩雑さを感じること、データを提出する作業に負担を感じることが把握され、これらの対応策として、LIFEの改善、施設における工夫を提案した。
薬剤調整を行う上での困難要因は、入所前の病歴、処方歴、処方意図などの情報が十分に得られないこと、薬剤によっては、処方見直しにより問題が無いか否かの判断ができないこと、その他に薬剤調整に対する施設スタッフの姿勢が慎重であることなどが把握され、これらの対応策として、施設の薬剤師が情報を得るよう努めることや、入所前の医療機関の医師による情報提供、本調査で効果が高いことが示された取組の実施などを提案した。
また、かかりつけ医連携薬剤調整加算の算定や薬剤調整の推進に向けた取組事例をとりまとめた。
令和4年度当初公募 65 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業は、現在でも従前相当サービスを中心に運営している市町村が多い状況であり、生活支援・介護予防を目指すために、市町村における多様なサービスの活用を推進する必要がある。また、生活支援体制整備事業については、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて生活支援コーディネーターの配置及び活動が進められているものの、市町村によって体制に差があることが明らかになってきた。これらの状況を踏まえ、令和4年度の調査では、総合事業の多様なサービスの推進に向けて市町村における取組状況を詳細に把握することを目的に、市町村で運営されている事業の内容や実施要件等の実態を調査した。生活支援体制整備事業については、生活支援体制整備事業の推進と今後のあり方の検討に向け、生活支援コーディネーターの状況を中心に、体制整備事業の活用状況等について調査を行った。
総合事業の多様なサービスの推進に向けては、現在サービスAを実施している市町村についてより効果的にサービスを実施・活用できるよう、現在の事業の適切な評価と必要に応じてサービス内容の見直しを推進する必要があると考えられる。現在サービスを実施している市町村においてサービス実施の効果が現れることがひいては現在多様なサービスを実施していない市町村においてもサービスの活用を検討するきっかけになるものと考える。また、今後の体制整備事業の推進に向けて、民間企業や協同組合等地域の多様な主体との連携の強化を推進するとともに、各層の生活支援コーディネーターや協議体の役割を整理する必要があると考えられる。
令和4年度当初公募 74 都市型の生活支援ネットワークの構築に関する調査研究事業
(概要)
高度経済成長期に開発された郊外住宅地の多くでは、今後後期高齢者人口の急増に伴い生活支援ニーズや社会参加ニーズが急増するため、地縁等のコミュニティ機能が希薄化した都市部における生活支援体制整備のあり方が求められている。
本事業では、コミュニティの課題解決力を向上させるためのプロセスを整理するとともに、そのプロセスに沿って地域の実情に応じた働きかけをすること、そのために、行政が様々な資源のマネジメントや制度・仕組みの整備を行うことが望ましいと整理した。
また、都市部の生活支援体制整備事業におけるコミュニティ機能の土台として、地域の中に生活支援ニーズ(社会参加ニーズを含む)をキャッチするアンテナ役となる主体(住民や団体、企業等)を位置付けること、フレイル予防に関する学びを自治会・町会等ごとに行い高齢期における社会性維持の重要性への気付きを地域に広げること、生活支援ニーズ(社会参加ニーズを含む)のある人を居場所や各種イベントへつなぐこと、日常生活圏単位のネットワークを前提としてICTシステムも活用することなどを、生活支援ネットワークに必要な要素として整理した。
令和4年度当初公募 79 中山間地域等における移動支援を中心とした生活支援に関する調査研究
(概要)
九州・沖縄の各県と全市町村(274市町村)に「中山間地域等における高齢者の移動支援を中心とした生活支援に関する施策の実施状況」について取組み状況のアンケートおよび取組みの詳細インタビュー調査を行い、地域包括ケアシステムの構築に資する中山間地域等における移動支援を中心とした生活支援事例や構築方法の普及を目的として実施した。
県を対象としたアンケートは、福祉部門と交通関連部門に回答を依頼し共に7県が回答した。市町村を対象としたアンケートは、福祉部門101市町村、交通関連部局132市町村が回答した。インタビュー調査は、アンケートに回答した中から6自治体を対象に、取組み背景・概要、成果、今後の展開、高齢者移動支援の実施にあたってのポイント等について詳細調査を実施した。
2つの調査から、高齢者の移動支援を中心とした生活支援は、画一的に定型的な内容を実施すればよいという事ではなく、高齢者の生活圏や生活スタイルを考慮し、その地域の特性を活かした支援が必要であると考えられ、4つの観点(「課題・ニーズ把握」「調整・整備」「実装」「評価」)を継続的に実施し、その時に必要とされる支援を実施していく必要があることがわかった。
また、住民の移動支援に対するニーズを満たしつつ、最新の情報通信技術等の活用も視野に入れ、今ある地域資源を最大限に活用(地域公共交通等との共存・共栄)することを第一に、自治体内の福祉部門と交通関連部局等が連携して多様な関係者を巻き込んだ調整を進めていくことが重要である。
本調査研究は、「課題・ニーズ把握」の必要性がより明確化され、自治体において「課題・ニーズ把握」が課題であることも確認できた。
令和4年度当初公募 101 介護現場における多様な働き方に関する調査研究事業
(概要)
生産年齢人口の減少が本格化していく中、介護サービス施設・事業所が多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくためには、多様な年齢層・属性(中高年、主婦、学生等)をターゲットとした、多様な働き方、柔軟な勤務形態による効率的・効果的な事業運営が必要である。
本事業では、令和3年度に地域医療介護総合確保基金の事業メニューに追加された「介護現場における多様な働き方導入モデル事業」において実施される「多様な働き方導入の取組」について、介護サービス施設・事業所における取組の狙い、実施内容及びその効果の検証を行った。また、多様な働き方の導入にあたっては、リーダー的介護職員を中心としたチームケアが重要であると考えられるため、リーダー的介護職員の役割やチームにもたらす効果について整理した。
令和4年度当初公募 111 外国人高齢者に対する効果的なケアのために外国人介護人材が果たす役割に関する調査研究事業
(概要)
日本国内の総人口は年々減少傾向にある一方、在留外国人は増加傾向にある。外国人人材の受入れが加速する中、将来的に日本に長期滞在する者、家族を形成する者はより増加することが予測される。外国人高齢者においても日本人高齢者と同様、介護が必要となった場合であってもこれまで住み慣れた地域で安心した生活の継続への支援が求められており、出身地域や年齢層に応じた配慮以上に、異なる国の生活習慣や文化等の多様性への配慮が求められる。
本事業では、外国人介護人材が外国人高齢者に対して介護を行う際の配慮や、外国人高齢者への支援の実態を把握するため、2つの自治体にアンケート調査と、外国人高齢者への情報提供や支援等のために活動している団体や施設等にヒアリング調査を実施した。調査からは、外国人介護人材が外国人高齢者への支援やケアに対してもたらす効果や、果たす役割が大きいことが明らかとなった。また、外国人高齢者に適切な支援をするためには、外国人高齢者のニーズの把握や情報の共有・連携が重要であるということ等も明らかとなった。
調査で明らかとなった点を踏まえ、報告書では、外国人高齢者の一層の支援のために、外国人高齢者、外国人介護人材、外国人高齢者を受け入れる介護事業所、行政、地域等、それぞれが求められる役割を整理したうえで、今後必要な取組について検討を行った。
令和4年度当初公募 114 介護助手等の導入に関する実態及び適切な業務の設定等に関する調査研究事業
(概要)
介護現場における、いわゆる介護助手等(以下、介護助手等)の活用は、介護現場における生産性の向上やケアの質の向上等が期待されるものであり、また、介護助手が担当する業務の範囲(業務の切り分け)を適切に行うことにより、導入効果が一層高まると考えられるものである。
本年度は、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護型の4サービスを対象にアンケート調査、ヒアリング調査を実施した。介護施設における介護助手の導入状況や導入手順、業務実態等を把握するとともに、有識者による検討委員会を実施し、介護職員の業務負担軽減、介護の質の向上の観点から介護助手等に対応いただく業務の切り分け方、各サービス種別の特徴等を体系的にまとめた。また、導入する際の留意事項や導入効果を高めるために留意するべきポイントを整理し、報告書に取りまとめた。
令和4年度当初公募 115 介護生産性向上総合相談センターを通した地域単位の効果的な支援方策等に関する調査研究事業
(概要)
介護現場の生産性向上の取組を全国に普及していくために、生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的・横断的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐ地域に根差したワンストップ型の支援の枠組みを構築していくことが効果的であると考えられる。本事業は、介護分野における生産性向上に資する都道府県単位の支援の枠組みの立ち上げ、運営にあたり必要な事項や求められる人材や支援等を明らかにし、取りまとめることを目的とした。
本事業の調査結果から、センターの設置・運営にあたっては、介護サービス事業所に対して介護現場における生産性向上の意義や取組手法について普及・啓発を丁寧に行い、生産性向上についての機運の醸成を図るとともに、センターや自治体、関係機関の間で介護現場への包括的な支援に向けたネットワークを構築することが求められることが明らかとなった。
また、センターにおいて継続性・実効性を担保するためには、生産性向上に関する課題を抱えた事業所に対して、専門的な知識を持った相談対応や伴走的に支援できる人材を、中長期的に育成していく必要性も認識できた。
さらに、全国的に生産性向上の取組に対する機運の醸成を後押しするとともに、各センターや関係機関等で得られた種々の情報やノウハウを集約・整理し、全国のセンターに提供する等、各センターの取組を支援する中央管理機能を持った機関が必要であると考えられた。
令和4年度当初公募 117 介護事業所における生産性向上の更なる普及促進に向けた調査研究
(概要)
介護サービスにおける生産性向上に資するガイドラインでは、「一人でも多くの利用者に質の高いケアを届ける」という介護現場の価値を重視し、介護サービスにおける生産性向上を「介護の価値を高めること」と定義している。介護現場の生産性向上の取組を今後さらに推進していくためには、自治体が国と連携しつつ、介護現場の経営者層や多様な関係者が一体となって地域全体で取組を推進していく必要がある。本事業では、生産性向上の取組を支援・普及する事業の進め方を自治体向けに取りまとめること、また介護サービス事業者の経営者層向けには、経営者層の視点から生産性向上に取り組むべき目的や取組を通じて得られる効果等を取りまとめることを目的として調査研究を行った。
自治体における生産性向上に資する事業等に関する調査の結果、多くの自治体では、セミナーや研修会の開催、もしくはモデル事業所の創出(コンサルタントによる取組の伴走支援)の2つを実施手法として、生産性向上に資する事業を実施していた。調査結果を基に、自治体において生産性向上の取組に資する事業を推進する際のポイントを取りまとめた。
経営者層向けリーフレットの作成に向けた調査においては、介護業界の共通の課題は人材の確保であり、生産性向上の取組は人材確保に有効であること、さらに、生産性向上の取組で成果を上げるには経営者層の取組に対する支援が必要であることが分かった。調査結果を基に、未だ生産性向上の取組に疎遠な経営者層向けにリーフレットを作成し、取組を行った事業所の経営者層の声を伝えた。また、自事業所で抱えている課題を解決する手段として生産性向上の取組を捉えてもらうための内容や、事例を通じて生産性向上の取組に関心を深めつつ、ガイドライン等の各種ツールへ誘導する内容を記載した。
令和4年度当初公募 131 養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員の処遇改善の在り方に関する調査研究事業
(概要)
養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおいては、従前より赤字の施設が多いことが指摘されており、令和3年度老人保健健康増進等事業「養護老人ホーム及び軽費老人ホームの経営の在り方に関する調査研究事業」では、持続的な経営を行うために地域共生社会の実現を踏まえた自治体との連携などの経営努力の必要性や自治体における措置費、事務補助金等の見直しの重要性等が明らかになったところである。
このような中、養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員について必要な処遇改善が図られるように、厚生労働省より、令和3年12月24日に「老人保護措置費に係る支弁額等の改定について」(令和3年12月24日老高発1224第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)(以下、厚生労働省通知と称す)が発出されている。
本調査では厚生労働省通知を踏まえた各自治体における施設への処遇改善の対応として、老人保護措置費に係る支弁額等の改定状況等の実態を把握すること、ならびに施設における影響として養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける職員の処遇改善の実施状況等の実態について確認を行い、職員の処遇改善の在り方及び処遇改善の推進策を検討するための基礎資料を取りまとめた。
調査結果を通して、厚生労働省通知が発出されたこと、厚生労働省通知の発出と併せて、現場のニーズとして関係団体から自治体に要望を行うことの意義が明らかとなった。まとめと提言の中では、養護老人ホーム・軽費老人ホームの今後の持続可能な経営とその基本的課題の一つである処遇改善の推進にあたり、地域の自治体や関連機関・団体等との連携の強化、地域の福祉の向上を目指した活動や機能の発揮、新たな事業展開等による提言を行った。
令和4年度追加公募 3 訪問介護の令和3年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業
(概要)
令和3年度介護報酬改定では、訪問介護について各種見直しが行われたところである。令和3年度改定の影響等を把握し、改定事項に係る各事業所の取組を促進する必要があるため、次期介護報酬改定も見据えた調査を実施する必要があると考えられた。
このため、本事業では、令和3年度改定が訪問介護事業所及びその利用者への介護サービス提供等に与えた影響等について、施行後の実態を詳細に把握した。また、当該改定で見直された事項に加え、現状の課題等についても把握し、次期介護報酬改定に向けた検討に資する基礎資料を得ることを目的として、訪問介護事業所を対象としたアンケート調査、ヒアリング調査を行った。
調査結果を踏まえ、令和3年度介護報酬改定で見直しが行われた訪問介護に関わる加算等の算定状況および、算定が進んでいない場合には算定を困難とする要因について分析し、次期介護報酬改定に向けた検討に資する基礎資料を得た。
令和4年度追加公募 6 在宅で療養する要介護高齢者に対する多職種連携と適切なサービス提供に係る調査研究事業
(概要)
在宅で療養している要介護高齢者の増加が見込まれる中、利用者が居宅で安心して療養できる環境を整える上で、介護支援専門員や医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・管理栄養士等の専門職種間で密な連携を行うことで、利用者への必要なサービス提供につなげる必要があると考えられた。
また、令和3年度介護報酬改定における医療介護連携の推進方策のうち本事業に関係する事項として、「医師等による居宅療養管理指導において、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、関連する情報をケアマネジャー等に提供するよう努めることとする」こと等が打ち出された。
本事業では、在宅で療養している利用者に対して定期的に訪問を行っている医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員の専門職による居宅療養管理指導の実態を、利用者の状態等を含めて把握し、また専門職間における多職種連携や社会生活面の課題への対応状況について、当該職種が勤務する医療機関(医科、歯科)、薬局及び居宅介護支援事業所を対象としたアンケート調査を通じて実態を把握し、その調査結果から課題を抽出した。またヒアリング調査を通じて多職種連携と社会生活面の課題への対応の好事例を把握した。
これらの調査結果をもとに、利用者への適切なサービス提供を行うための効果的な多職種連携の方策や社会生活面の課題への対応等について、有識者により構成する検討会で検討し、報告書にとりまとめ、今後に向けた対応方策の提言を行った。
令和4年度追加公募 11 生活支援コーディネーターと協議体や認知症地域支援推進員等の活動プロセスを踏まえた体制整備の推進に関する調査研究
(概要)
生活支援体制整備事業・認知症総合支援事業は、地域支援事業における包括的支援事業(社会保障充実分)に位置付けられた事業である。当該事業においては、市町村における生活支援コーディネーターや協議体、認知症地域支援推進員等(以下、生活支援コーディネーター等)の人員や会議体の配置・設置の状況は調査によって把握されているものの、全国的な状況の把握や活動のプロセスの具体化、評価手法の確立に向けた検討は十分に進んでいない状況であった。また、活動に対して地域支援事業交付金が交付されているものの、活動に対する実際の費用の状況は把握されていなかった。
そこで、本事業においては、全国の生活支援コーディネーター等の活動内容とその成果を把握し、効果的な活動プロセスへの示唆を得ることを目的として、全国の生活支援コーディネーター等へのアンケート調査を実施するほか、地域支援事業交付金の生活支援体制整備事業・認知症総合支援事業等に要する費用の分析を実施した。調査、分析結果を報告書にとりまとめるとともに、生活支援コーディネーター等の活動のプロセスの具体化や評価手法の確立に向けた提言を行った。
令和4年度追加公募 12 医療機関等と連携した介護予防の推進に関する調査研究事業
(概要)
介護予防の観点から、通いの場の取組を推進しているが、通いの場に参加していない高齢者の中にも、フレイル等のリスクを有している者も多く含まれることが懸念され、不参加者へのアプローチが重要である。高齢者は外出の機会は少ないが、多くの場合は医療機関を定期的に受診している。このことから、地域の医療機関等と連携して、フレイル等のリスクがある高齢者の早期発見、介護予防の取組につなげる仕組みの構築が求められている。
上記の問題意識の元、本事業では、4つの地域の医療機関において、介護予防やフレイル対策に関する一定の研修を受けた看護師・准看護師が、フレイル等のリスクがある高齢者を抽出し、地域包括支援センターや地域の介護予防の取組等につなげるモデル実証を実施した。さらに、実証の課題を明らかにするため、実証後調査としてアンケート調査とヒアリング調査を行った。
実証では、医療機関等にはフレイル等の疑いのある患者が多く通院している一方で、患者自身にフレイルについての知識や危機感がない等の理由により、介護予防サロンの参加までつながらないケースも多いこと等が明らかとなった。今後の展開としては、医療機関と介護予防の一層の連携強化のため、研修内容のさらなる充実化や、フレイルの周知、地域包括支援センター等との連携や実証の課題を踏まえたさらなる展開が期待される。
令和3年度当初公募 8 ICTを活用した都市型の生活支援ネットワークに関する調査研究事業
(概要)
本事業は、都市郊外地域に展開可能な、「ICTを活用した支え合いシステムのあり方」を検討することを目指し、生活支援ネットワークの普及展開モデルを明らかにするための先進事例調査、支え合いシステムに求められる要件を整理するための千葉県柏市豊四季台地域を対象とした実態調査、ICTを活用した支え合いシステムの効果・効率向上の可能性を明らかにするための同地区在住の高齢者及び支えあいシステム事務局を対象とした実証を実施した。
調査の結果、都市型の生活支援ネットワークの一つのモデルとして、「ニーズの発掘・対応機能」「相談対応・コーディネート機能」「広域連携機能」「ICTによる機能と強化」という要素をもって、地域の高齢者の具体的なニーズに応えていくことが必要と考えられる。
令和3年度当初公募 12 中山間地域における地域共生社会を見据えた地域包括ケアシステムの深化に関する調査研究事業
(概要)
高齢者が住み慣れた地域で生活をできるだけ長い期間維持・継続していくには、本人の力や住民相互の力も引き出しながら介護予防や日常生活支援を進めていく必要があり、そのための地域づくりが求められている。
しかし、地域づくりの必要性を認識しつつも、着手できずにいる自治体は少なくない。また、取組を始めたとしても、形式的な会議等に終始し、効果の創出まで至っていないケースもみられる。
本事業では、多様な主体によるまちづくりの先進的な取り組みを実施している自治体・団体を対象に調査を実施し、成功要因として以下のようなポイントを抽出し、オンラインフォーラムを通じ広く情報を展開した。
- 住民から直接地域の課題やニーズを聞き、住民との信頼関係を築く
- 介護予防に限らず、地域にある様々な活動に目を向ける
- 支援する/される側は固定ではなく、高齢者や持病のある方等、多様な住民が自分にできることで地域に関わる
- 協力先が見つからない・実現に至らなかったときは、シーズを温めながら、地域にアンテナを立てて、地域の声が高まるまで待つことも必要
- とりあえずできることから初めて、効果が出なければ方向性を見直す
など
令和3年度当初公募 13 地域包括支援センターの効果的な運営に関する調査研究事業
(概要)
本事業では、地域包括支援センター(以下センター)における業務負担の状況や負担軽減に向けた取組状況について把握し、センター業務の業務負担軽減、ひいてはセンター運営の推進に向けた効果的な方策を検討するため、市町村及びセンターに対するアンケート調査とヒアリング調査を実施した。その際、センターの業務負担の中でも、これまでの調査研究によって深刻な課題であると明らかにされている介護予防に係るケアプラン作成業務と3職種が実施する事務的業務に特に焦点をあてて、調査を実施した。
調査の結果、業務負担軽減に向けた効果的な取組とそれを推進するための具体的なポイントが明らかになった。また、センター業務を効果的に進めていく上では、個々の取組の前提として、以下に挙げるようなセンター運営における関係者との”土壌づくり”や課題解決に対する取組姿勢が重要であることが明らかになった。
- センター業務のあるべき姿と現状の”差”から、業務負担軽減の必要性を検討すること
- 業務負担が発生している要因の分析を行うこと
- 市町村・センター間で活発なコミュニケーションを行うこと
- 業務実態を数値化し把握すること
業務負担軽減に向けた具体的な取組のポイント等については別冊「地域包括支援センターの業務負担軽減に向けた取組のポイント」を作成し、記載を行った。
令和3年度当初公募 19 AIを活用した効果的・効率的なケアプラン点検の方策に関する調査研究事業
(概要)
ケアプラン点検は平成18年度に介護給付等費用適正化事業の一環として位置づけられた。一部の保険者は、平成20年に厚生労働省より発行された「ケアプラン点検支援マニュアル」を基にケアプラン点検を実施していること等が過去の調査研究事業によって確認されている。一方で、全国の保険者の実態については包括的な調査がこれまでに実施されていないことから、全容が明らかとなっていなかった。
そのため、本事業では、全国の保険者のケアプラン点検の実態を把握するとともに、全国で活用可能なケアプラン点検項目を開発し、ケアプラン点検の平準化に向けて検討を行った。さらに、ケアプラン点検におけるAIの活用に向け、AIプロトタイプを開発した。
全国の保険者を対象としたアンケート調査の結果、ケアプラン点検の目的及び具体的な実施方法は保険者によってばらつきがあること、多くの保険者が専門的な知識・スキルを有する職員の確保を課題として認識していることが明らかとなった。
同時に、ワーキンググループでの協議を踏まえ、ケアプラン点検項目を開発した。開発したケアプラン点検項目を実際のケアプラン点検業務に活用する実証を行うことで、ケアプラン点検結果データを収集し、ケアプラン点検支援AIのプロトタイプ版を開発した。複数のAIを作成し、精度を比較した結果、保険者または点検者によってケアプラン点検の判定基準に違いがあること、そのような判定基準の違いをAIが学習することで、判定精度が向上することが明らかとなった。
最後に、本事業を通して明らかになった点をケアプラン点検業務そのものに係る課題と、AIによってケアプラン点検業務を支援する際の課題に大別し、総括として整理した。
令和3年度当初公募 24 感染症対策や業務継続に向けた事業者の取組等に係る調査研究事業
(概要)
介護保険サービスは、利用者やその家族が生活を送る上で不可欠であることから、感染症の集団感染や自然災害が発生した場合であっても、介護サービス事業者は継続的にサービスを提供することのできる体制を構築することが重要である。このため、令和3年度介護報酬改定では、感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、災害への地域と連携した対応の強化、会議におけるICT等の活用等が盛り込まれた。
感染症や自然災害の影響によらず、安全・安心に利用し続けられる介護保険サービスの提供体制の構築に資する情報を得るため、本事業では、介護サービス事業者を対象としたアンケート・ヒアリング調査を通して、令和3年度介護報酬改定に盛り込まれた事項の実施状況等の実態を把握し、課題及び対応が必要な事柄を整理した。
本事業の結果、令和3年度介護報酬改定で介護サービス事業所・施設に策定が義務付けられた業務継続計画(以下、「BCP」という)の策定状況については、3年の経過措置期間が終了する2024年3月時点では、事業所・施設の4分の3が策定する見込みであり、また経過措置期間を過ぎても策定できないところが出る可能性もあることが示唆された。このため、本事業のヒアリング調査で収集したようなBCP策定の事例等を、各種研修等を通じて広く周知することなどにより、BCPの策定に向けて動き出すように促すことが必要であることを提言した。この他、小規模法人でBCP策定が進んでいないことへの対応の方向性や、事業所・施設が関係機関と地域内で連携する必要性についても提言した。
令和3年度当初公募 27 要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究事業
(概要)
我が国では、高齢者、特に後期高齢者数の増加に伴い、要介護認定者数も増加することが見込まれている。要介護認定者が増加することで、認定調査員の不足や介護認定審査会における審査件数の増加等による業務負担への影響が想定されている一方、被保険者が結果を受領するまでの期間を短縮する必要があることから、要介護認定業務の効率化を図る必要がある。
そこで本事業では、保険者の要介護認定業務の現状をアンケート・ヒアリング調査及び実証を通して、ICTを活用した今後の具体的な方策と実現に向けた課題を整理・検討した。
調査の結果、ICTの活用によって効率化が期待できる業務として、認定調査の記録、認定調査票の確認、主治医意見書の作成・授受、介護認定審査会の開催等を提言し、ICTによる効率化に向けた課題を整理した。
令和3年度当初公募 41 通所系サービス・短期入所系サービスの新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査研究事業
(概要)
通所系サービス(通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)及び短期入所系サービス((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護)は、サービス特性上、新型コロナウイルス感染症による影響を受けやすく、より感染症対策を徹底してサービス提供を継続する必要があった。このため、同サービスに対し必要な対応を検討する上での基礎資料を得ることを本事業の目的として調査を実施した。
本調査では検討委員会を設置した上で、アンケート調査を実施した。アンケート調査は通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所および居宅介護支援事業所と、通所系サービス事業所および短期入所系サービス事業所の利用者とその家族を対象とした。
通所系サービス事業所や短期入所系サービス事業所において、自主的な休業や予めサービスを利用する人数の制限を行った事業所は、少数であり、多くの事業所では、職員・利用者・事業所の運営体制全ての観点から感染防止策を実施しており、これにより継続的なサービス提供が図られていたと考えられた。
また、通所系サービス事業所や短期入所系サービス事業所において、サービス利用中に新型コロナウイルスに感染することを不安に思った等の理由により、自主的に利用を控えた利用者がいた。このことから、新型コロナウイルス感染症の影響として、少なからず利用者やその家族の心身への影響や事業所経営への影響があったことが考えられた。
令和3年度当初公募 46 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業
(概要)
本事業では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及び(看護)小規模多機能型居宅介護の更なる普及を図るための方策について検討を行うとともに、各サービスの機能・役割を改めて検証した上で、在宅生活の限界点を高めるために必要な対応の総合的な検討を行った。さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護がこれまで果たしてきた機能や役割を踏まえつつ、夜間対応型訪問介護の機能や役割の整理を行うことで、今後の在り方について検討を行った。
調査目的の検証のため、各サービスの事業所に対するアンケート調査に加えて、ケアマネジャーの視点から普及状況や機能・役割を検証する目的で、居宅介護支援事業所を対象としたアンケート調査も実施した。併せて、保険者における各サービスの普及状況等を検証するためのヒアリング調査を実施した。
調査結果からは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及び(看護)小規模多機能型居宅介護の更なる普及については、各種事例紹介などを通じた更なる周知が重要であることや、両サービスの利用者の状態は創設当初からほぼ変わっておらず在宅生活の継続に寄与していること、夜間対応型訪問介護は今後定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合していく方向性等がそれぞれ示された。
令和3年度当初公募 66 介護予防・日常生活支援総合事業等の推進に向けた効果的な研修プログラムの開発に関する調査研究事業
(概要)
令和2年度までに当社が開発した「実践型地域づくり人材育成プログラム」(以下、プログラム)を発展させ、再現可能・展開可能な地域づくりのノウハウを持った市町村の養成と市町村の役割発揮を支援できる都道府県の輩出を目的とする研修プログラムのあり方を検討するため、市町村向けプログラムの改善・体系化と効果検証、都道府県の参加によるプログラムの活用可能性の検証を行った。また、検証の一環として、過去のプログラム受講生に対する現況調査を実施した。
市町村向けプログラムには17市町村が参加し、受講者が行政目線から住民目線に視点を転換し、わがまちの課題検討にチームで取り組んだ結果、一定の手応えと実効性のある解決策を検討することができた。過去のプログラム受講生への調査では、多くの市町村で様々な施策の具現化に向けた検討等に発展していることが確認され、再現性のあるノウハウを獲得していることが確認された。都道府県向けプログラムでは、高齢者の暮らしの困難さを解決するという明確な目的意識を持つことができ、課題把握や支援策検討の質の向上も見られた。一方、現場や住民との距離が遠いことや定期的な職員の異動により、知見やノウハウが蓄積されにくく、市町村支援技術の習得は容易ではないこと等が明らかとなった。
今後は、本事業で開発したプログラムを活かし、市町村や都道府県が地域の実情に応じて地域包括ケアシステムを構築していくために必要な基礎的な技術を、実践の中で学び体得してくための基盤を構築していくことが必要であると考える。
令和3年度当初公募 68 介護予防・日常生活支援総合事業等の効果的な実施に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業等の効果的な実施に向けて、令和3年度から対象者やサービス価格(単価)の上限の弾力的な運用が開始されたことに対し、全国の市町村における弾力化の実施状況をアンケート調査を通じて把握した。
また、経済財政政策の観点から、一定の基準で算出される上限額の範囲内で効果的に運営していくことが求められていることを踏まえ、市町村の総合事業の上限額の引き上げに関する個別協議の現状を市町村の申請データをもとに整理した。
弾力化に関しては、弾力化開始1年目(令和3年度)の時点では、弾力化を実施する市町村の数が限られていたこと等から、当面、弾力化による影響は大きくないと考えられる。対象者の弾力化、サービス価格(単価)の上限の弾力化のいずれについても、弾力化への対応状況は市町村によって様々であったことから、今後、必要に応じて適切な運用方法を示していくとともに、継続的な状況の把握が必要である。
上限額の引き上げに関しては、個別協議を行った市町村と個別協議を行わなかった市町村の上限額の水準の差が、個別協議を経て小さくなっていたことから、個別協議が保険者間の事業費の水準の平準化に貢献していると考えられる。今後は、保険者にとってよりわかりやすく運用していくとともに、事業の効果については、事業費の推移、要支援者・事業対象者や要介護者の数の推移のほか、介護に関連するその他の費用も含めて事業の効果を捉えていく必要があると考えられる。
令和3年度当初公募 80 通いの場づくり等に係る市町村支援に係る調査研究事業
(概要)
都道府県が介護予防・生活支援の推進に向けた市町村支援に、より効果的に取り組めるよう、市町村支援にあたり注力すべき事項を抽出しとりまとめることを目的とし、具体的には市町村の情報収集から市町村支援策検討に係る近畿管内府県の市町村支援の実態と課題・ニーズの分析、奈良県・兵庫県への市町村ヒアリング等への伴走支援、都道府県向けの市町村支援ガイドの作成を行った。
事業を通して、都道府県が限られた体制や時間の中で地域や市町村の実情に応じた支援を展開していくために、特定の地域や市町村の実情を深く理解することによって市町村支援を展開する取り組み方を整理し、都道府県向けに「市町村の個別事例から考える市町村支援」のガイドとして取りまとめた。
令和3年度当初公募 85 在宅医療・介護連携推進事業の推進に係る市町村と医療関係団体との連携に関する調査研究
(概要)
在宅医療・介護連携推進事業は企画立案時から郡市医師会などの医療関係団体や介護サービス施設・事業所等との協働が重要であり、医療・介護関係者や都道府県(保健所等)と緊密に連携し、将来的な在宅医療と介護の連携の在り方の検討が必要である。
そのためには、普段から行政と医療・介護関係者が良好な関係(顔の見える関係、気軽に本音で話が出来る関係等)を築くとともに、企画立案の前に、顔合わせも含めて簡単な意見交換(ヒアリング)を行うことも、市町村と地域の医療・介護関係者の連携のハードルを下げることにつながり、その後の事業推進が円滑に実施できることが考えられる。
本調査研究は、在宅医療・介護連携推進事業において、九州内の市町村に効果的な医療関係団体との連携関係構築方法を普及させることを目的とし、九州内の市町村および県へアンケート調査を実施した(市町村の回答率;67.9% 県の回答率;100%)。さらに市町村へはインタビュー調査(8自治体)も実施した。
調査結果から県および市町村における在宅医療・介護連携推進事業の今後の進め方について取りまとめを行った。
令和3年度当初公募 95 介護施設等における認知症者の感染防止・安全管理策に関する調査研究事業
(概要)
平成12年に介護施設等における身体拘束が原則禁止となり、さらに実務的な対応のための「身体拘束ゼロへの手引き」が平成13年に提示され、身体拘束は「やむを得ない事情(切迫性、非代替性、一時性)」がある場合に限るとされた。平成30年には介護報酬制度の中で身体拘束廃止未実施減算規定が出されている。しかしながら、新型コロナウイルスの感染が拡大する状況下においては、今までの手引きの解釈では判断が難しい「感染症拡大防止を目的として行われる行動制限・身体拘束」が必要な場合があったことが想定される。
そこで、介護施設等に入所中の認知症者に対する新型コロナウイルス感染症下における行動制限・身体拘束等の実施実態を把握すること、医療従事者や介護従事者が留意すべきことを導出することを目的として調査を行った。従来の身体拘束よりも広く実態を捉えるために、身体拘束を含む6つの項目を行動制限として整理している。
アンケート調査やヒアリング調査の結果、感染予防のために、面会制限や移動制限、日常生活動作の制限、隔離等が一部の施設で行われ、認知機能やADLの低下が危惧されているといった実態が明らかとなった。また、感染対策と日常生活の維持の優先度を判断することの難しさや、認知症により依頼を忘れてしまう方への感染対策の依頼方法の難しさ、等があげられた。
医療従事者や介護従事者が留意すべき点として、様々な行動制限によって認知機能やADLが低下してしまうことを認識すること、行動制限を実施している場合であっても、日々利用者の状態を確認し、利用者の尊厳の確保や認知機能・ADLの低下抑制に向けて工夫をすること、等があげられた。
令和3年度当初公募 114 介護現場における多様な働き方に関する調査研究事業
(概要)
生産年齢人口の減少が本格化していく中、介護サービス施設・事業所が多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくためには、多様な年齢層・属性(中高年、主婦、学生等)をターゲットとした、多様な働き方、柔軟な勤務形態による効率的・効果的な事業運営が必要である。
本事業では、令和3年度に地域医療介護総合確保基金の事業メニューに追加された「介護現場における多様な働き方導入モデル事業」において実施される多様な働き方導入の取組について、介護サービス施設・事業所における取組の狙い、実施内容及びその効果をヒアリング調査により把握するとともに、調査検討委員会を設置し、取組の類型化、効果の検証を行った。また、多様な働き方の導入にあたっては、リーダー的介護職員を中心としたチームケアが重要であり、リーダー的介護職員の役割や取り組むうえでの注意点も整理した。
なお、本事業では、得られた内容と全国の施設・事業所の取組事例を通じて、介護現場における「多様な働き方」を普及啓発するため取組事例集を作成した。
令和3年度当初公募 118 企業との連携による福祉現場の活性化に関する調査研究
(概要)
各地域にて福祉・介護に対して抱いているイメージを向上させるための「体験型・参加型イベント」の開催や「世代横断的な広報活動」の展開、「若年層、子育てを終えた層、アクティブシニア層、介護事業者」に対するターゲット別のアプローチを実施し、福祉・介護分野における多様な人材確保対策が行われているが、介護現場の人材不足は改善されていないという現状である。
本調査研究では、地域社会に貢献する取り組みを積極的に行っている地元企業が通いの場等に人材を派遣するモデル事業と現状調査を実施し、資格を要しない業務や作業の人材不足を補うとともに、地元企業との連携関係構築手法や通いの場等が求めている人材ニーズと企業のニーズのマッチング手法について調査結果を取りまとめた。
調査研究を通して、企業が通いの場等へ出向くことを促すために自治体側に求められるサポート(つなぎ)に必要な事項として、「①自治体における、通いの場等および企業の情報収集(課題・ニーズ収集)」「②自治体の通いの場等と企業をつなぐ基盤づくり」「③自治体と企業、自治体と通いの場等のネットワークづくり」の3点を整理した。また、通いの場等と企業をマッチングするための自治体からの支援方法は、「会合等での個別マッチング」「相互交流の場でのマッチング」「冊子配布による日常的マッチング」が考えられた。
令和3年度当初公募 127 介護現場における生産性向上の取組の効果的な推進方策に関する調査研究事業
(概要)
介護現場の生産性向上の取組については、これまで「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」の普及啓発や好事例の横展開等を通じてその取組の推進が図られてきた。しかし、いまだ生産性向上の取組に未着手、あるいは、着手しても継続性のない一過性の取組にとどまっている施設・事業所が少なくない。
本事業では、介護現場において生産性向上の取組の着手や継続を阻害している要因や成功要因、国や自治体における生産性向上の取組の普及や促進のあり方についてとりまとめることを目的とし、介護サービス事業所や自治体を対象にアンケート調査とヒアリング調査を実施した。
調査結果から、介護サービス事業所において生産性向上の取組を継続して行うためには、十分な準備をすることや活動への動機付け、目的や活動過程の見える化、職員の主体性を尊重する支援・促しが重要であることが示唆された。また、都道府県において効果的に生産性向上の取組を普及させるためには、オンラインセミナー等を通じた先進事例の紹介や、事業所同士のディスカッションが有効である。
令和3年度当初公募 139 介護サービス情報の公表制度の効率的・効果的な活用方策に関する調査研究事業
(概要)
介護サービスの情報の公表制度は、介護サービスの利用者等が介護サービス事業所や施設を比較・検討して適切に選択するための情報を提供する仕組みである。今後、認知症高齢者や1人暮らしの高齢者など、インターネットを活用して自ら比較・検討を行うことが難しいと考えられる高齢者の増加が見込まれていることから、より広い層への介護サービス情報公表制度の周知を推進していく必要がある。
本事業では、介護サービス情報公表システムの更なる活用促進を目的として、介護の当事者となる高齢者やその家族が必要とする情報、より活用しやすくするサイト構成、そして、介護分野以外における当該制度の活用のあり方などをアンケート調査等にて情報を収集し有識者と検討した。
調査結果から、介護の当事者となる高齢者やその家族はケアに関する情報に加え、法人や事業所等の経営状況や新型コロナ対策がわかる情報を求めていることが分かった。また、インターネットに不慣れでも必要な情報に簡便にアクセスできるよう、例えば、トップ画面における「一般の方」と「専門の方」の選択ボタンの設置、チャットボット機能の搭載、キーワード検索機能の搭載などが有効と考えられた。
令和3年度追加公募 2 介護保険サービスにおける人員配置基準等の自治体ごとの解釈・運用等に関する調査研究事業
(概要)
介護保険サービスにおいては、人員配置基準等、省令で基準を定めているが自治体ごとに解釈・運用等が異なる事例が存在すると指摘されている。本事業では、自治体ごとの介護保険サービスの省令における解釈・運用状況をアンケート調査、ヒアリング調査を通じてあきらかにしたうえで、検討会での議論を通じて報告書を取りまとめた。
結果、省令で定める人員配置基準のうち「管理上支障がない場合」、「利用者の処遇に支障がない場合」の兼務について自治体ごとに異なる解釈・運用の余地がある事がわかった。多くの自治体では、極端な事例でない場合は兼務を認められている等の結果が得られた。一方で都市部では事業者数が多く、兼務数等の制限が一律で定められている可能性があること、地方部では事業者とのコミュニケーションが取れる事業者数であるため事業者の意見を伺い、対応している事がわかった。
令和3年度追加公募 12 介護報酬における介護職員処遇改善の推進に向けた方策にかかる調査研究事業
(概要)
令和3年度介護報酬改定では、介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進を目的として、以下①②の2つの見直しが行われた。
①介護職員等特定処遇改善加算について、平均の賃金改善額の配分ルールにおける経験・技能のある介護職員はその他の介護職員の「2倍とすること」を「より高くすること」とした。
②介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の職場環境等要件について、区分及び内容を見直すとともに当該年度における取組の実施とした。
本事業では、介護サービス事業所・施設を対象としたアンケート調査を通じ、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算にかかるこれらの見直しによる、賃金改善以外の処遇の改善状況や人材確保への影響等の実態について把握・整理した。また、ヒアリング調査を通じ、職場環境改善の取組の内容、工夫点、効果などについても把握・整理した。
事業実施による主な成果としては、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件に位置付けられている職場環境改善の取組について、小規模法人や小規模事業所・施設では取組が進んでいないという課題を明らかにした。またこの課題への対応として、管内の事業所・施設の状況を十分に把握している自治体により、加算の取得促進を通じて、特に職場環境改善のノウハウや事例をあまねく伝えることが重要であることを示した。
この他、職場環境改善の好事例として、ICT導入の取組により業務量の削減などの定量的な効果が出ている事業所・施設や、コミュニケーションの促進などの取組により職員の信頼が深まるなどの定性的な効果が出ている事業所・施設など、職場環境改善の取組によって様々な効果が出ている事例を把握し、全国の介護サービス事業所・施設で参考にできるよう整理した。
令和3年度追加公募 14 安全な介護ロボットの開発に関する調査研究事業
(概要)
利用者の自立支援や介護現場の生産性向上に寄与するより良い介護ロボットを開発するために、開発企業は介護施設等の利用者に開発の途中段階で機器を利用してもらい、効果や課題についてフィードバックを貰う「実証」の機会を求めている。
実証の段階において、開発企業は安全性を担保するためにリスクアセスメントを行っているが、どのような危険源に対して安全設計を施し、どのような危険源は介護現場での運用による工夫で担保するのか、その判断は開発企業に委ねられている。
そこで、リスクアセスメントの運用を前提としながらも、介護ロボットの開発・実証過程における安全性担保の状況と運用でのカバーが必要な事項を明らかにする、介護現場と開発企業双方が活用可能なチェックリストを作成することを目的として本事業を実施した。
本事業で実施した調査結果より、開発企業の多くは製品のコンセプト設計時や実証時にリスクアセスメントを実施し、実証を安全に行えるよう取り組んでいることが分かった。一方でリスクアセスメントを実施しない企業や、実施してもその結果を介護現場に共有していない企業も少なからず存在したことが分かった。
チェックリストは、主にノミナル・グループ・ディスカッションというディスカッションに投票のプロセスを加えて意見を集約する手法を用いて作成した。構成は①どの機器で実証を行う場合でも確認を行うリスクアセスメントの実施状況等に関する項目と、②どの機器で実証を行う場合でも確認を行う利用場面等を想定した安全性を確認するための具体的な項目、及び③6分野13項目の機器毎に安全性を確認するための項目としている。
令和3年度追加公募 16 介護現場におけるテクノロジーの実態調査研究事業
(概要)
日本の高齢化は、世界に例を見ない速度で進行しており、介護人材の不足が大きな課題となっている。介護分野の人材を確保する一方で、限られたマンパワーを有効に活用する解決策の一つとして、高齢者の自立支援を促進し、質の高い介護を実現するためのロボット・センサー等の製品(以下、介護テクノロジーとする)の活用が期待されている。今後さらに介護テクノロジーの活用を推進するためには、介護現場への介護テクノロジーの周知や介護現場のニーズをふまえた介護ロボットの開発が重要である。
そこで本事業では、介護テクノロジー市場に対する企業の参入動向および参入検討のために企業が必要とする情報等を把握すること、及び開発企業のニーズと介護ロボット開発における課題について整理することを目的として、介護テクノロジーを上市済・未上市の企業計5,312社に対してアンケート調査等を行うとともに、有識者検討会によって調査結果に対する考察を行った。
調査の結果、多くの企業が介護分野への参入に関心を示す一方で、期待する収益を得るための出口戦略を描くことに対して難しさを感じていることが分かった。また、多くの企業が参入検討や開発の過程で抱えている課題が4点(①新しく介護分野に参入する企業における介護分野の特性の理解、②介護現場のニーズ把握、③介護現場での実証評価、④製品の販売拡大)あることが分かった。
また、上記調査とは別に、介護現場がテクノロジーの導入活用を検討する際に参考となるよう、国内で活用される介護テクノロジー102製品を掲載した便覧を取りまとめた。
令和3年度追加公募 18 高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくりのための自治体による計画策定と評価に関する調査研究事業
(概要)
高齢者虐待防止法は、高齢者虐待等の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応(悪化防止)、再発防止を通じて、高齢者の権利利益を擁護することを目的としており、その体制整備の促進が重要となる。本事業では、介護保険事業(支援)計画等における高齢者虐待等を防止するための体制整備について、セルフ・ネグレクト等の高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害、高齢者虐待防止法27条において虐待としての対応が求められる消費者被害の体制整備についても対象に加え、その実態を机上、アンケート、ヒアリングにより明らかにするとともに、その結果から得られた知見に基づいて、今後の対応策を検討した。
研究結果を踏まえ、A(アセスメント)-PDCAサイクルを踏まえ高齢者虐待防止等における体制整備についての計画策定の推進、高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備の計画的な体制整備、高齢者虐待防止法第27条に規定されている消費者被害についての計画的な体制整備、養護者と養介護施設従事者等による虐待防止についてそれぞれの計画策定及び体制整備、そして、都道府県の市区町村支援を中心とした体制整備のあり方の明確化、を提言している。高齢者虐待防止等の権利擁護支援を促進していくためには、今後、庁内及び保健医療福祉関係機関を横断した取り組みが求められ、そのための体制整備を視野に入れて検討していくことが必要である。また、自治体がどのように体制整備を進めていけばよいか、具体的な道筋を示すことが必要である。
令和3年度追加公募 20 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの経営の在り方に関する調査研究事業
(概要)
養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウス(以下、施設と称す)においては、地域包括ケアシステム及び地域共生社会の実現に向けて、複雑化・多様化する地域のニーズに対する支え手としての役割が期待されている。しかしながら、近年の先行研究等においては、これらの施設経営の約3~4割は赤字であり、持続的な経営を行う上で改築等に要する資金の確保等の課題が指摘されている。さらには、地域における施設のあり方について、自治体・施設の双方の共通認識が持てているとは言えない実態が明らかとなっている。
これを踏まえ、本調査研究事業では、施設の経営や設備等の状況及び、各自治体の措置費及び補助金の実態、施設と関係機関との連携状況等を明らかにするとともに、地域共生社会の実現を果たすために、施設の持続可能な経営の在り方とそれに向けた今後の課題を検討するための基礎資料をとりまとめた。
調査結果より、在宅の低所得高齢者や、虐待被害を受けた高齢者、精神疾患や認知症等をかかえる高齢者への対応等が期待され、施設が地域共生社会の実現を支える上で重要な社会資源であることが改めて確認された。また、措置費、事務費補助金において、施設への加算の支給実績や消費税増税時の対応に自治体間の格差があること、養護老人ホームにおける措置費制度の縛り(措置控え)の問題、軽費老人ホームにおける経過措置施設の位置づけに係る課題等、今後さらに検討が必要な課題が明らかとなった。まとめと提言の中では、施設の多様な活用や機能強化、地域公益活動及び地域とのネットワーク化の推進等について提言を行った。
令和3年度追加公募 21 介護事業所に対する調査等における更なる負担軽減に向けた方策等に関する調査研究
(概要)
公的介護保険制度の適切な運用には介護サービス事業所等向けの調査研究が欠かせないが、同一設問に繰り返し回答するといった回答負担の指摘がある。また、指定申請手続等の負担軽減を目的とした電子手続の検討も重要な課題である。
本事業は、介護サービス事業所等が協力するアンケート調査について電子化により負担軽減が可能な方策の検討に資する基礎資料を作成することや、指定申請等の電子化に向けた介護サービス事業所側の技術的課題や運用上の課題を整理すること、介護支援専門員の登録手続の電子化の可能性を検討することを目的として、アンケート調査等を実施した。
調査結果より、多くの調査で聞き取る法人情報や常勤換算数などの項目は介護サービス情報公表システムに掲載されていることから、調査実施者が法人情報等を当該システムから取り寄せアンケート結果と連結できる仕組みの構築が有用と考えられた。
また、総合事業の指定申請手続における電子手続の円滑な普及には、国から電子申請システムの導入から活用支援の用意と周知等が重要になる。
介護支援専門員の登録手続の電子化推進では、全国的に電子化を目指す場合はシステムの簡便な操作の実現と、介護支援専門員等に対する周知が有用と考えられた。
令和2年度当初公募 6 産官学協働の持続的な支援体制の構築等に関する調査研究事業
(概要)
現役世代が急減していく中、地域の様々な課題の解決は、もはや自治体等の単独主体では難しく、多主体での協働が不可欠である。そこで、市区町村等が多主体協働を進めるにあたっては、地元の大学や都道府県等の支援機関による支援が重要となるが、支援体制が十分に整備されている地域は少ない状況である。
そこで、本事業では、市区町村における多主体協働を支援機関が主体となり支援するための持続可能なモデルを示し、市町村支援体制を構築していくことを目的として、多主体協働の事例調査、支援事例調査、支援機関向けの勉強会、多主体協働促進のためのイベント等の調査研究を実施した。その結果、多主体協働に向けた市区町村の課題と必要な支援策、及び支援を実施するにあたっての支援機関の抱える課題が明らかになった。
(参考資料1)企業アンケート調査_単純集計(PDF/769KB)
(参考資料2)産官学連携を促進するためのイベント_案内資料(PDF/1.51MB)
(参考資料3)産官学連携を促進するためのイベント_登壇者資料(PDF/33.8MB)
(参考資料4)産官学連携を促進するためのイベント_企業紹介冊子(PDF/6.49MB)
令和2年度当初公募 12 介護分野におけるマイナンバーカード活用に向けた調査研究
(概要)
令和元年度に実施した「介護分野におけるマイナンバーカードによる資格確認に関する調査研究」では、アンケート(介護事業者)及びヒアリング(保険者、介護事業者)調査にて被保険者証等の現在の利用実態について調査を行い、今後検討すべき課題について整理を行った。本調査研究では、前年度事業において明らかとなった課題を踏まえ、現在の介護分野における被保険者証の在り方を検討するとともに、マイナンバーカードの活用によって、事務効率化が期待できる運用の在り方の整理を行った。
現在被保険者証等の確認で負担となっているのは、被保険者本人が被保険者証等を管理できず必要な時に情報が得られない場合であり、そのような状況であっても自治体から事業者に直接情報を共有することが可能になれば、事務負担軽減が期待できると考えられ電子的に共有できる仕組みのシステム化について検討を行った。
電子的に共有するシステムとして、連携する情報をファイルに出力し授受する「ファイル連携方式」と、連携する情報をDBに集約した上で参照・連携する「DB集約方式」の2案が考えられる。
この2案について、コスト等の比較観点ごとに概要を整理し比較を行い検討委員会で議論を行った結果、介護現場の負担軽減や今後の情報活用への拡張性を勘案した場合、DB集約方式案がより効果的ではないかと考えられた。
今後は、DB集約方式案を前提に本調査研究において整理した検討課題について更に議論を進めていくとともにシステム化に向けた実証等を実施していくことが考えられる。
令和2年度当初公募 28 AIを活用した効果的・効率的なケアプラン点検の方策に関する研究
(概要)
保険者機能の強化に伴い、保険者は、これまで以上に自立支援に資するケアマネジメントの実現、またその結果としての給付の適正化を進めることが求められている。保険者によるケアマネジメント支援の取組としてケアプラン点検が挙げられるものの、実施には保険者の労力、時間、コストを必要とするほか、点検の担当者の資質によって指導内容にばらつきが生じるため、統一的には実施されていない現状がある。一方で、介護分野では、AIをはじめとする先端技術に注目が集まっており、業務効率化に対する期待が寄せられている。このような背景から、保険者が効果的・効率的にケアプラン点検を実施するための方法を明らかにするとともに、AIを活用したケアプラン点検の可能性を探るため、本調査研究を実施した。
保険者を対象としたヒアリング調査とケアプラン点検の結果データを分析した結果、ケアプラン点検時にケアマネジャーと面談すべきケアプランの抽出や、面談時に確認すべきポイントの提示等にAIを活用することで、効果的・効率的にケアプラン点検を実施することができる可能性を提示した。
令和2年度当初公募 43 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及促進に関する調査研究
(概要)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、「定期巡回サービス」という。)は、医療ニーズ、介護ニーズの両方に対応しながら要介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みとして、平成24年度に創設されたサービスであり、地域包括ケアシステムの中核サービスのひとつとして普及・拡大が期待されている。
一方、定期巡回サービスの利用者・事業所が増加しない理由の一部として、「ケアマネジャーへの周知が不足している」ことや、「事業所の経営が厳しい(要因の一つとして、ケアマネジャーとの連携不足が挙げられる)」ことが課題となっている。
これらの背景を踏まえ、ケアマネジャー・利用者への調査により、ケアマネジャーへの適切な周知方法・連携体制について明らかにするとともに、定期巡回サービス利用者への調査によって利用者のニーズやメリットを把握することで、普及促進するための方策について検討を行い、今後の更なる普及に向けて定期巡回サービス・ケアマネジャーの関連団体・行政(国・指定権者等)において求められる対応をとりまとめた。
令和2年度当初公募 68 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業
(概要)
本事業では、現行の介護予防・日常生活支援総合事業・生活支援体制整備事業について、制度上の実施状況等を把握するとともに、市町村の地域課題の解決に向けた達成感や手応え等を調査することで、質的な進捗状況を確認した。あわせて、総合事業の対象者及びサービス価格の上限の弾力化に向けて、今後、国が総合事業の利用状況を定期的に把握・公表する仕組みを検討した。
本調査の結果から、市町村の意識や取組状況、成果認識等が非常に多様化していることが明らかになった。画一的な取組方法や支援ではなく、市町村が地域の実情に応じて総合事業・整備事業を展開できるような支援や、市町村が自ら地域の課題を抽出し解決する能力を底上げすることが必要である。
弾力化に関しては、当面影響を受ける対象者数が限られていると見込まれることから、群間比較ではなく個々の事例により影響を把握することになるものと考えられる。具体的な把握内容や方法については、制度の施行状況を見ながら引き続き検討していく必要がある。
令和2年度当初公募 69 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の効果的な推進方法に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業(以下、総合事業等)の取組状況は市町村によってばらつきが見られる。取組の推進にあたって、都道府県には市町村を支援する役割が期待されているが、全国的な現状や、市町村支援の方策については明らかになっていない。そこで、本事業では、都道府県が果たすことのできる役割やその実現に向けた課題を明らかにすることを目的とし、都道府県を対象とした調査を行った。
調査の結果、都道府県に求められる役割は市町村の課題解決を支援することであり、そのために、現状を把握し、関係者と情報共有し、個別的な支援や広域的支援を講じること、そしてそれを実現する組織づくりが求められると整理した。また、都道府県がこれらの役割を果たしていくための課題として、高齢者の暮らしの困難さを解決するという明確な目的意識を持つこと、市町村支援に必要なマネジメント能力の習得、担当事業や庁内外の垣根を超えたチーム(組織)づくりあるとした。さらにそのためには、国や厚生局による都道府県に対する広域的支援が必要であると提言した。
令和2年度当初公募 70 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の推進に向けた研修カリキュラムの開発に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業(以下、「総合事業等」)をより力強く推進するためには、市町村が地域の実情に合わせて課題設定し、総合事業等の活用により、地域の多様な主体と協働して解決を図るといった地域マネジメント力の向上が不可欠である。しかし、多くの市町村ではいかに制度を運用・実行するかに意識が向いており、国から示される事例を踏襲している実態が見受けられる。これは、市町村職員が、高齢者が望む暮らしの課題や地域社会として本当に解決すべき課題を把握し、解決を図るという自らの役割を十分に理解していないことが原因と考えられる。
このような現状があるにも関わらず、市町村職員がこのような役割を学び、実践できるよう後押しするツールが十分には存在していない。
本事業では、総合事業等を担当する市町村職員に対するヒアリング調査の結果や、「実践型地域づくり人材育成プログラム」の講師及びアドバイザーの意見をもとに、総合事業等を担当する市町村職員が、わがまちで取り組むべき地域課題を見極める力を養うことができるよう、地域づくりの導入ツールとしてテキストを作成した。
令和2年度当初公募 71 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の推進に向けた実践研修に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業や生活支援体制整備事業の効果的な推進に向けては、地域の現状分析、課題の設定や解決策の検討、関係者との協働等といった地域マネジメント力が重要である。令和元年度、当社は、総合事業等を担う市町村職員の課題解決能力の向上や地域づくりにおける意識・考え方の習得を目指した集合型研修プログラムを実証し、講義・ワーク・個別アドバイス等の多面的な市町村支援を行った。その結果、受講者の意識変容・課題解決スキルの向上・市町村における事業推進等に係る成果がみられた。
今後の研修プログラムの普遍化や拡充に向けては、市町村支援技術(受講者や市町村の現状理解、到達点の設計、受講者の意識変容・行動変容を促すノウハウなど)の体系化が求められることから、今年度事業では、市町村支援機能としての研修プログラムの仕組み化を見据え、プログラムの質の向上・普遍化と市町村支援技術の体系化を目的に、プログラムを実証的に開発した。
結果として、プログラムの前後で受講者の意識変容・課題解決スキルの向上・取組意欲の向上等における成果がみられた。また、受講者が地域の多様な関係者と地域課題の解決に取り組むことで、関係者へ学びが波及・継承される様子がうかがえた。オブザーバー参加をした都道府県においても、プログラムを通して市町村の実態への理解を深め、地域課題解決のプロセスや市町村支援のあり方について学ぶ場としての有用性が高いことが示唆された。
また、受講生の課題検討アクションが多様化するなど、プログラムとしての質の向上や学びを支援する仕組みの強化に係る成果がみられた。今後は、市町村支援や人材育成を継続展開していくために、支援ノウハウのさらなる体系化と、支援者を養成する方策についても検討していくことが求められる。
令和2年度当初公募 82 通いの場づくり等に係る市町村支援に関する調査研究事業
(概要)
通いの場づくり等の地域づくりを推進するためには、市町村職員の意識を変革し、意欲を育て、課題解決の能力を身に付けることが有効であることが先行研究で示されている。そして、その実現にあたっては都道府県や厚生局による市町村支援が重要と考えられる。しかし、有効な市町村支援のあり方はまだ確立されているとはいえず、また、都道府県においては市町村支援の必要性認識やその取り組み状況にもばらつきがある。
そこで、本事業では、近畿厚生局管内市町村の取組の実情や課題認識を調査・分析し、市町村の課題と解決策例の資料・ツールを開発した。また、市町村支援の有効な方策を検討するため、府県担当者や有識者とともに、府県による市町村支援のあり方や支援の具体的な方策について検討を行った。府県の市町村支援の取組実態としては事業の研修などの一律・画一的な支援が中心であるが、市町村の地域づくりに係る困りごとや課題は多様であるという現状を踏まえ、市町村の実情を踏まえた支援を企画・実行する重要性が挙げられた。また、市町村支援のPDCA推進と市町村の個別課題への支援の2つの観点の重要性が示唆された。
令和2年度当初公募 85 高齢者の保健事業と介護予防の一体実施を行うための取組に関する調査研究
(概要)
本調査研究では、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」に資する効率的かつ効果的な取り組みについて、民間企業等が蓄積してきた人材発掘・育成ノウハウを活用した効果的な地域の担い手づくりの方法を市町村に普及させることを目的とし、以下の3点を研究した。
- 担い手発掘・育成の実証(健康医学士養成)
- 担い手発掘・育成モデルの可視化(健康医学士養成プログラムの作成)
- 普及展開モデルの検討(他地域へ普及させるための方策)
具体的には、健康増進や介護予防に関する知識や技術をもつ有資格者を有している民間企業が、「体験型健康医学教室」を実施し、多様な担い手(医療専門職、介護予防事業者、一般企業社員、市民等)を健康医学士として養成し、地域の自助力を高め、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に資する効率的かつ効果的な取り組みについて実証的研究を行った。さらに、その検証から民間企業等が蓄積してきた人材発掘・育成ノウハウを活用した効果的な地域の担い手づくりの方法を市町村に普及させる観点での普及展開モデルの検討、地域の事業者が教室のノウハウを活用して一般市民向け、企業及び従業員向けのサービスとして展開するモデルについても検討を行った。
令和2年度当初公募 86 地域包括ケアに向けた薬剤師の看取り期への関わり方に関する調査研究事業
(概要)
地域包括ケアシステムの構築が進む中で、薬剤師がその役割を発揮していくためには在宅業務へのより一層の取組が必要であり、中でも看取り期においては、患者の状態に応じた医薬品、医療材料等の供給や他職種との連携が重要となる。このため本事業では、看取り期や看取り期に至るまでの時期を人生の最終段階と位置付けた上で、人生の最終段階の利用者・患者に対する薬剤師の在宅業務の実態、薬剤師に求められる役割をアンケート調査・ヒアリング調査を通じて明らかにした上で、薬剤師がその役割を果たすために必要な事項等を検討会での議論を通じてとりまとめた。
本事業で得られた具体的成果として、人生の最終段階の利用者・患者に対する在宅業務では通常の在宅業務と比べて薬剤師が他職種と連携する機会が増えていることや、他職種は薬剤師に様々なことを期待していること、また薬剤師がその期待に応えられている業務とそうでない業務があることなどが明らかになった。
令和2年度当初公募 115 介護人材の確保・資質の向上に向けた市町村の取組促進に関する調査研究事業
(概要)
高齢化の進展に伴い介護人材の需要は増大しており、2025年度に向けて2016年度の約190万人から約55万人の介護人材を確保していく必要があると推計されており、また、2025年以降は現役世代(担い手)の減少が進み、高齢者介護を支える人的基盤の確保が各地域で大きな課題となると予想されている。このような状況下で、これまで以上に地域に実情に応じた取組みを推進すべく、第8期(2021~2023)の介護保険事業計画においては、新たに市町村としても介護人材の確保及び資質の向上並びに業務効率化対策を計画に位置づけることとなっている。本調査研究事業は、先進的に介護人材確保等の取組みを行っている市町村へヒアリング調査を行い、効果的な介護保険事業計画策定に向けたポイントを整理・提示することで、新たに介護人材の確保及び資質の向上並びに業務効率化対策を計画上位置づけることとなる市町村の計画策定を支援することを目的として実施した。
本調査研究事業をとおして、市町村が介護人材確保等の取組みを進める上では、「介護人材確保施策を企画・推進するプラットフォームを設けること」「アンケート等を通じ事業所の状況を把握し、課題抽出・施策検討・進捗評価を行うこと」、そして「都道府県等とコミュニケーションを図り、柔軟に財源を確保すること」の3点がポイントとなることが分かった。また、調査結果を整理した情報提供資料は、厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 発出の令和2年8月7日事務連絡「市区町村の介護人材確保に係る先進取組み事例調査結果ついて」として、都道府県介護人材確保対策担当者を経由して、各市区町村に情報提供された。
令和2年度当初公募 117 チームケア実践力向上の推進に関する調査研究事業
(概要)
生産年齢人口の減少が本格化していく中、多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくためには、リーダー的介護職の育成をはじめ、介護職員のキャリア・専門性に応じたサービス提供体制のもとで、多様な人材によるチームケアの実践をさらに進めていくことが必要である。
本事業では、令和2年度予算において実施される「介護職チームケア実践向上推進事業」において取り組まれる多様な人材によるチームケアの実践力向上に資する取組について、介護サービス事業所が実施する取組の狙いや実施状況をヒアリング調査により把握するとともに、事業の効果測定、検証、都道府県による所見の分析、整理等を行い、地域の特性や状況に応じた取組の方向性、課題について調査検討委員会での議論を踏まえて取りまとめた。
本事業の具体的な成果として、介護職のチームケアの実践力向上の取組が、①研修等を通じた介護職チームのチームリーダー育成、②生産性向上に向けた業務システム構築、③介護助手等導入の3つの類型の取組に整理されること、また、それら3つの取組により、多様な人材の介護分野への参入促進、リーダー的介護職員の育成及び介護職員のキャリアや専門性に応じたサービス提供体制によるチームケアの実践力の向上が図られること、ひいては利用者の自立支援や満足度の向上につながることが明らかとなった。
令和2年度当初公募 136 高齢者介護(高齢者支援)におけるICT利用などによる生産性向上及び人材確保の取組に関する国際比較調査研究
(概要)
我が国は、超高齢社会に伴う様々な課題が山積しており、介護の現場では特に、介護人材の不足が喫緊の課題として広く認識されています。介護人材を確保するための施策として、労働・雇用条件等の労働環境の改善や外国人材の活用、生産性を向上するための施策として、ICTの活用などが検討されているものの、現場の理解やコストの問題により、期待されるほど導入が進んでいない現状がある。
一方で、社会の高齢化と介護人材の不足は、先進国を中心として、世界的な問題となっている。我が国における取組の示唆とすることを目的とし、高齢化が進んでいる12か国の取組について、文献調査及びヒアリング調査を行った。
調査結果は、各国の高齢社会化・介護を巡る現状について概略をまとめた上で、介護人材の確保とICTの活用等を通した生産性の向上の2つの観点から整理した。さらに、調査結果を踏まえ、諸外国の取組を参考とした我が国への示唆を提示した。
令和2年度当初公募 150 認知症がある高齢受刑者等の出所後の介護サービス等の受け入れ実態と福祉的支援の課題解決に関する調査研究
(概要)
認知症施策推進大綱において、適当な帰住先がない受刑者等が、釈放後に必要な福祉サービス等を円滑に利用できるよう、関係機関が連携して矯正施設在所中から必要な調整を行う「特別調整」等(出口支援)を推進するとされている。そこで、本調査研究では、自治体、介護サービス事業所・施設、並びに、地域生活定着支援センターに対し、アンケート調査やヒアリングを行い、認知症を発症した高齢出所者等の円滑な地域生活への移行、適切な福祉サービスへつながることを阻んでいる要因を明らかにし、当該阻害要因を解消するために有効な対応策を検討した。その結果、こうした者の円滑な社会復帰のためには、福祉サービスに関する実施主体となる自治体の決定を円滑に行うためのルールの明確化や、介護サービス事業所・施設での受け入れを促進するために必要な財政的な支援やサービス利用者に関する情報提供の充実などさまざまな施策が必要であることが明らかになった。さらには、矯正施設と自治体、福祉サービス事業所・施設との仲介役を果たしている地域生活定着支援センターはもとより、地域における多機関のネットワークの形成や、出所者に限らず、そもそも「身寄りのない高齢者」の暮らしを地域で支える仕組みの構築など地域の福祉力自体をどうアップするかという課題も見えてきた。
令和2年度当初公募 160 社会的リスクを抱える高齢者の支援体制に関する研究事業
(概要)
限られた医療・介護資源の中で高齢者が地域で暮らし続けるための体制を構築するためには、高齢者の心身機能低下に対し早期に対応し、予防的な介入を行うことが重要とされている。一方で、日ごろから近所付き合いの少ない高齢者においては、生活習慣改善や介護予防といった自助に困難を抱えているケースが多いものの、住民の相互扶助のみでは対応に限界があることから、結果的に、重症化してから介入が始まることが多いのが現状である。このような社会的リスクを抱える高齢者に対応するためには、住民の相互扶助や地域包括支援センター等のこれまでの取組みだけでなく、医療機関(かかりつけ医)や行政の果たす役割は非常に大きいと考えられることから、本調査研究事業では、かかりつけ医や行政関係者等が高齢者を地域資源に結びつける取組みを行っている国内の先進事例を調査し、社会的リスクを抱える高齢者の支援のあり方に関しての整理を行った。
本調査研究事業の調査及び検討委員会での議論等から、社会的リスクを抱える高齢者の状態像を体系的に整理するための枠組みを提示するとともに、支援の体制構築・実施、及び評価を行う上でのポイントをまとめることができた。今後の課題としては、先進的に行われている支援事例を広く横展開していけるモデルとして再整理する取組みが必要である。
令和元年度当初公募 22 AIを活用したケアプラン作成支援の実用化に向けた調査研究事業
(概要)
昨今、AIやICTによるケアマネジャーの業務支援への期待は大きいものの、AIを活用することによる業務効率化やケアマネジメントの質向上、利用者の自立支援等の効果は十分に検証されていません。そこで本調査研究では、ケアプラン作成を主とするケアマネジメント業務において実際にAIを活用することで、ケアマネジメントの質向上やケアマネジャーの業務効率化等に対する効果検証を行い、今後の更なる研究開発・現場理解の促進に向けた課題やケアマネジャーとAIの相互補完モデルの検討を実施しました。
AIを活用した音声入力システムおよびケアプラン作成支援システムを用いて、実業務等への導入効果を「業務効率化」「ケアマネジメントの質の変化」「利用者の自立支援」の観点で分析したところ、実用化に向けたケアマネジャーを補完する形でのケアマネジメントの質向上やケアマネジャーの業務効率化等に対して、一定程度のAI活用可能性の効果が明らかになりました。
令和元年度当初公募 77 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業は、全国の市町村で進められています。しかし、昨年度(平成30年度)調査では進捗状況にはばらつきがあり、事業評価の実施率も3割にとどまっていることが分かりました。
そこで、本事業では、アンケート調査(全国1,741市町村)、ヒアリング調査(10市町村、8団体)を実施し引き続き事業の進捗を把握するとともに、検討会において事業の課題を整理し、総合事業評価のための評価指標案を作成しました。
その結果、総合事業の事業所(団体)数や利用者数に大きな変動はなく、総合事業の効果の点検・評価を実施している市町村も4割程であることが分かりました。
今後、効果的に事業を推進するためには、必要量のサービスを提供できる担い手の確保やサービス類型ごとの具体的なノウハウの把握が課題となっています。また評価指標を有効に活用した事業の推進も課題であると考えられます。
令和元年度当初公募 78 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の効果的な推進方法に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業(以下、総合事業等)の取組状況は市町村によってばらつきが見られます。取組を推進するためには、市町村の抱える課題に応じた支援策を講じる必要があるものの、効果的な方策は未だ確立されていません。そこで、本事業では、2つの研究事業の実施を通して、市町村に対する効果的な支援方策を検討しました。
1つ目の研究事業である地域づくり支援プログラムでは、東海北陸圏域の12市町村を対象に、講義やワークショップを含む各回2日間のプログラムを5か月間実施しました。プログラムを通して気づきを与え、学んだことをわがまちで行動に移せるよう後押しし、行動して見えた新たな障壁やその理由をともに考えることを繰り返しました。
2つ目の研究事業である伴走的支援では、長野県内の3市町村を対象に、1か月に1回程度の訪問を計5回実施しました。長野県をはじめとする支援チームが支援先市町村へ訪問し、悩みや進捗に寄り添うことで、市町村担当者が客観的な視点でわがまちを振り返り、試行錯誤ができるよう支援を行いました。
どちらの研究事業においても、市町村職員を主体的な取組姿勢に変化させることができただけでなく、総合事業等の取組に係る具体的アクションにつなげることができました。
令和元年度当初公募 135 一人暮らし高齢者等の生活課題と互助組織による支援に係る調査研究事業
(概要)
生活支援を必要とする一人暮らし高齢者等が増加する一方で、支え手となる地域の人口は(多くの地域において)減少していく見通しです。そのような中で、「既存の社会資源活用の可能性を探る」ことが生活支援の充足にあたって重要とされています。そこで、本調査事業では、一人暮らし高齢者等の生活課題及び地域互助的な役割を担う住民組織の実態を把握することを目的として、全国市区町村を対象としたアンケート調査(悉皆)・モデル地域を対象としたヒアリング調査 等を実施しました。調査結果から、住民組織等の地域の主体にはそれぞれ得意とする領域があること、そして、複数の主体がそれぞれの得意領域を持ち寄ることによって持続的な生活支援サービスの提供が可能になるという示唆が得られました。
令和元年度当初公募 149 介護職の機能分化の推進に関する調査研究事業
(概要)
本事業は、「介護職機能分化等推進事業」の実施主体の協力を得て、都道府県等が実施する機能分化に資する事業及び介護サービス事業所が実施する取組の実施状況やその狙いを随時把握するとともに、効果測定、検証、各都道府県による所見の分析、整理等を行い、地域の特性や状況に応じた取組の方向性、課題について調査研究を実施しました。
その結果、介護助手等の導入の取組が、介護職員が専門的な業務に集中でき、より質の高い介護を提供することなど介護現場の生産性向上が図られ、就労環境の改善につながることを把握できました。
令和元年度当初公募 159 AIを活用した健康管理システムによる重症化予防に関する調査研究事業
(概要)
各地域では効率的かつ質の高い地域包括ケアシステムの構築のため、限られた地域資源で多職種が組織を超えて、連携・情報共有を行い、個人の特性を反映した診療・看護・ケアを行うことが必要です。しかし、現在各地域において行われている情報共有は、利用者の状態悪化を早期発見することで重症化予防、要介護度の改善につながるような仕組みは構築されていません。更に、ICTを活用した情報共有・連携は、持続可能な運営が求められているにもかかわらず運営費の捻出に苦慮している地域が多く、運用を休止している地域も少なくありません。
本事業は、利用者の状態悪化を早期発見することで重症化予防、要介護度の維持・改善に資する体制づくり、横展開可能なモデル策定をするために、「AIを活用した健康管理システム」を在宅患者へ実証し活用可能性を検証しました。また、システムの活用可能性拡大に向け通いの場への導入の検討も実施しました。
令和元年度追加公募 3 介護分野におけるマイナンバーカードによる資格確認に関する調査研究
(概要)
少子高齢化が進行する中で、医療保険制度や介護保険制度を効果的かつ効率的に運用していくことが重要です。医療分野で先行して導入が進められているオンライン資格確認を、介護分野においても導入した場合の自治体や介護事業者、利用者への影響について調査を行い、導入時の課題を整理して、介護保険制度を効果的かつ効率的な運用に資するかどうかを本調査研究にて明らかにすることを目的としました。
本事業では、現在の介護保険被保険者証等の利用実態を明らかにするとともに、オンライン資格確認の仕組みを導入した場合に想定される課題や影響について整理し、仕組みの在り方について検討を行いました。今後は被保険者証そのものの在り方の検討を実施し、事務運用の見直し等を含めた関係者(保険者、介護事業者、国民健康保険団体連合会等)による議論が必要となります。
令和元年度追加公募 28 2040年に向けたロボット・AI等の研究開発、実用化に関する調査研究事業
(概要)
我が国において2040年には、2020年に28.9%である高齢化率は35.3%と予測されており、3人に1人以上が高齢者となる見込みである。更には要介護者数や認知症の人数、独居高齢者数等も増加が見込まれる一方、介護人材の供給は追いつかず、担い手不足が大きな課題となる。そこで本事業では、未来イノベーションワーキング・グループにおいて検討された2040年の社会における健康・医療・介護のイメージを基に、介護・介護予防・認知症ケア・人手不足の領域において2040年における社会像と社会像を実現するために必要な研究開発ロードマップ及び組織体制・制度等を具体化した。更に、ムーンショット型研究開発制度において、「2050年までに達成すべき6つの目標」(令和2年1月23日、総合科学技術・イノベーション会議決定)が決定される中、同領域における具体的な目標設定に寄与すること目的に、2040年以降のロボット・AI像を策定した。
令和元年度追加公募 30 介護記録法の標準化に向けた調査研究事業
(概要)
介護現場における日々の介護行為の記録については、統一的な記録方法が存在せず、叙述的な内容が多く分析が難しいなどの指摘があります。一方で、医療分野では一定の記載方法が浸透しており、介護分野においても同様の取組が普及することで、記録業務の効率化、介護の質の向上に資することが考えられます。そこで介護記録の記録方法についてアンケート調査やインタビュー調査を実施して実態を把握しました。これらの調査結果をもとに、多職種連携、ICT化の推進、生産性の向上等、介護現場をめぐる課題に対応する観点から、適切な介護記録の記録方法のあり方について、学識経験者や、関係団体、システムベンダーを含む検討会において検討し、報告書に取りまとめました。
令和元年度追加公募 32 複数の介護サービス事業所が連携等して行う取組に関する調査研究
(概要)
介護分野において人材確保が厳しい状況にある中、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら介護保険制度の持続可能性を高めていくことが重要です。このような中、改革行程表2018において事業者の経営の大規模化・協働化等の取組状況等を把握することとされたことを踏まえ、本事業では複数の介護サービス事業所が連携等して行う人材育成・採用等機能や地域展開に関する取組の具体的内容や成果、工夫点や課題等について調査を行いました。
調査の結果、複数の介護サービス事業所が連携し人材の確保・定着・育成を効率的に展開している好事例が把握されました。その特徴を分析するため、連携の類型を独自の切り口で設定し事例を分類・分析したところ、法定拘束力を背景とした契約ベースの連携ではなく、理念の共有や地域への連帯意識といった観念的なつながりを根拠として連携する形態があることが明らかになりました。またメンバーシップ型や業界団体や学術教育機関との連携を通じて介護人材対策に取り組んでいる注目に値するケースも把握されました。
令和元年度三次公募 4 介護離職者にかかる調査研究事業
(概要)
厚生労働省雇用環境・均等局で実施した「平成24年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業」では、介護離職者の離職理由等についてアンケート調査を実施していますが、正社員である就労者及び正社員であった介護離職者のみを調査対象としたものでした。そこで、本調査研究事業では、ウェブ調査会社に登録するモニターのうち18~69歳の就労中の非正規雇用労働者、介護離職経験者をそれぞれ男女別に500人ずつを対象として、介護離職者の状況について離職理由等について調査し、介護を行いながら就業している場合との比較などを行い、その実態について報告書としてまとめました。
平成30年度当初公募 20 AIを活用したケアプラン作成の基準に関する調査研究
(概要)
介護保険制度において、ケアマネジメントの質の確保が喫緊の課題となっており、また介護業務の生産性向上が必要であるとの観点から、人工知能(AI:Artificial Intelligence)を活用したケアプラン作成支援に対する試みが行われています。そこで、本事業では、AI開発ベンダーにおけるケアプラン作成支援システムの現状調査を行うと共に、ケアマネジャーを対象としたフォーカスグループインタビューを通して現場側からみたAI活用可能性を検証することで、ケアマネジャーが活用できるAI導入可能性のあり方の検討を実施しました。
その結果、ケアマネジメント業務においてAIによる支援ニーズが高い機能が整理され、AI活用によりケアマネジャーの業務効率化や自立支援への新たな「気づき」につながり、結果として利用者・関係者との関係性構築や利用者の意欲の引き出し、意思決定支援等の対人援助業務に注力できることへの期待が明らかとなりました。
平成30年度当初公募 47 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業
(概要)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域包括ケアシステムの中核的なサービスとして平成24年に制度化されました。全国で約23,100人(平成30年10月審査分:介護給付費等実態統計月報)が本サービスを利用していますが、半数近くの自治体(保険者)でサービス提供が開始されていないなど、地域によって普及状況にバラつきがあり、更なる普及拡大が求められています。
そのような状況の中、平成30年度報酬改定では、サービス供給量を増やす観点、機能強化・効率化を図る観点から、同一建物等居住者へのサービス提供に係る報酬の見直しや、オペレーターの兼務など人員基準の緩和等の改定が行われました。
そこで本事業では、サービスの提供状況、オペレーターの兼務状況、ならびにサービスの質を維持するための体制整備状況など、改定後の影響を実態調査により分析するとともに、都道府県による普及啓発のための具体策の検討を行い、普及啓発ツールの作成を行いました。
平成30年度当初公募 72 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)及び生活支援体制整備事業(以下、「体制整備事業」という。)は、平成27年より順次実施され、総合事業は平成29年度、体制整備事業は平成30年度中より全ての保険者で実施されています。
平成29年度に弊社で実施した調査では、従前相当サービス以外の多様なサービス(従来より基準を緩和したサービス、住民主体による支援等)を実施する事業所が、訪問型サービス・通所型サービスそれぞれで1万箇所以上にのぼる一方、総合事業や体制整備事業の取組については、市町村ごとに進捗状況等にばらつきがあることがわかりました。
そこで、総合事業及び体制整備事業の進捗状況と課題を把握し今後の推進策に関する検討を行うことを目的に、平成30年度も引き続き総合事業・体制整備事業の実施状況に関する調査を実施し、両事業の進捗状況と課題を明らかにしました。
平成30年度当初公募 73 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の効果的な推進方法に関する研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の市町村の取り組み状況の進捗はばらつきがあり、取り組みが進んでいない市町村の課題に着目した個別支援が重要です。しかし、地域づくりにおいては地域の実情等に応じた柔軟な打ち手が必要であり、模範解答のような普遍的な手法を示すことが難しい現状です。
本事業では、事業推進・支援の豊富な経験を有する有識者や市町村担当者らでモデル市町村の支援チームを構成し、支援チームによるモデル市町村訪問やヒアリング、先進地視察等の伴走型支援を実施しました。そして、モデル市町村がわがまちの実情に応じた方策を考え、取り組みをはじめるに至った考え方や取み組み方のエッセンスを抽出し、今後の効果的な事業推進のための支援方策とともに取りまとめました。
(別冊資料編)「介護予防・日常生活支援総合事業 生活支援体制整備事業 これからの推進に向けて ~伴走型支援から見えてきた事業推進の方策~」(PDF/17.8MB) を掲載しました。
平成30年度当初公募 114 介護ロボットの普及促進に資する啓発イベントの実施モデル事業
(概要)
次世代の介護人材確保対策の一環として、若い世代、特に福祉学部や工学部などの学生の介護に関する関心を高める事を目的に、学生が現状の課題を自らの視点で分析し、ロボット活用のアイデア提案や活用事例の取りまとめなどを行うことで、明るく魅力的な介護現場を実現するイノベーション提案を発信するイベントをモデル的に実施しました。
平成30年度当初公募 119 介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業
(概要)
「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月閣議決定)において、「介護サービス事業所に対して国及び自治体が求める帳票等の実態把握と当面の見直しを来年度中に実施するとともに、その後、事業所が独自に作成する文書も含めた更なる見直しを含め、帳票類の文書量の半減に取り組む」こととされています。本事業は、介護報酬請求及び指定申請に関する文書を対象とし、介護サービス事業者に対し、国及び自治体が提出を求める帳票類の実態把握を実施し、文書量の削減に向けた提案を行いました。
平成30年度追加公募 20 高齢単独世帯に対する地域での支援の課題と対応についての調査研究
(概要)
我が国では65歳以上の高齢者の単独世帯が急増しており、限られた社会資源を有効に活用して地域で(分散して居住する)高齢者の生活支援を行うモデルの構築が、喫緊の課題となっています。そこで、本調査事業では、基礎調査(事例収集、既存調査の収集・整理、類型化・マップ化)、ヒアリング調査、アンケート調査等を行い、それらの結果を踏まえながらモデルの検討を行い、高齢単独世帯が健康な状態から地域との関わりを確保する拠点として「複合型拠点モデル」の必要性と構築のポイントを整理・提言しました。「複合型拠点モデル」とは、日常生活に密着しており高齢者だけでなく多世代が集いやすい“食”を起点とした集まりの場が、行政単独ではなく既存の地域資源と連携して構築されたものです。
平成30年度追加公募 28 介護福祉士の資格取得方法の見直しによる効果に関する調査研究事業
(概要)
「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)等により、介護福祉士の資格取得方法については、平成28年度から実務経験ルートに実務者研修が、平成29年度から介護福祉士養成施設卒業者への原則国家試験義務付けが導入されました。この見直しに伴い、介護福祉士養成施設や学生、介護現場における介護福祉士等の知識及び技能の習得や資質等に関してどのような効果が認められたか調査を実施しました。
平成29年度当初公募 1 保険者等取組評価指標の作成と活用に関する調査研究事業
(概要)
平成29年地域包括ケアシステム強化法において、市町村の保険者機能を強化する一環として、保険者の様々な取組の達成状況を評価できるよう、客観的な指標を設定した上で、市町村等に対する財政的インセンティブを付与することが取り決められました。これにより、各市町村、都道府県が積極的に地域課題を分析して、その実情に応じた取組を進めるとともに、その進捗状況を客観的な指標により把握できるといったことが期待されています。そこで本事業では、平成28年度に検討された取組評価指標候補について更に精査するとともに、指標を活用した客観的な進捗状況等の把握や取組推進の可能性について検討しました。
平成29年度当初公募 66 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業
(概要)
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)は、平成27年4月から移行開始し平成29年4月から全自治体にて実施されました。過去の調査において、従来の専門的なサービス以外の多様なサービスの出現が確認された一方で、介護サービス事業者以外の多様な主体による取組が十分に広がるには至っていないことが確認されました。その背景として、多様なサービス・主体を創出する生活支援コーディネーターや協議体の取組が十分に機能していないことが考えられています。
そこで本調査では、総合事業における多様なサービスの出現の背景として、総合事業及び生活支援体制整備事業における実態・課題把握に資する調査を、自治体・事業者・利用者それぞれの視点から行い、その現状と課題を明らかにしました。
平成29年度追加初公募 7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の経営モデルの調査研究事業
(概要)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「本サービス」という)は、医療ニーズ、介護ニーズの双方に対応しながら要介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みとして平成24年度に創設されたサービスであり、地域包括ケアシステムの中核サービスのひとつとして普及・拡大が期待されています。しかし、利用者数・事業所数ともに、まだ十分な数に到達しているとはいえません。
本調査では、本サービスの普及・拡大を阻む供給面の要因として、採算性への不安による事業者参入不足があるものと想定し、アンケート調査およびヒアリング調査によって、事業者等がどのような観点で事業を運営しているか、明らかにしました。さらに経営安定化に向けた各種取組をヒアリング調査によって収集し、事業開設から現在までの実施時期等に沿って事例集としてとりまとめ、新規参入を検討する事業者等に対して本サービスの将来性・継続性を示しました。
平成28年度当初公募 3 地域包括ケアシステムの構築や効率的・効果的な給付の推進のための保険者の取組を評価するための指標に関する調査研究事業
(概要)
地域包括ケアシステムの一層の推進が求められる中、すべての保険者が、保険者機能を強化し、地域の実情に応じた取組を進めていくことが急務となっています。具体的には、全保険者が地域課題を分析し、これに応じた目標設定と実行、評価のPDCAサイクルを強化していくことが重要です。また、国や都道府県による積極的な保険者支援が重要であるとされています。
そこで本事業では、介護保険部会意見の内容を踏まえ、自立支援・介護予防の推進という観点に着目しつつ、アウトプット指標(プロセス指標)及びアウトカム指標で構成される、介護保険者機能の評価のための指標を作成するための調査を実施しました。
平成26年度当初公募 42 生活期リハビリテーションにおける多職種協働・連携の実態に関する調査研究 事業
(概要)
生活リハビリを機能させるためには、多職種協働が重要である。
多職種チームが、「利用者の意向」、「解決すべき課題」、「長期・短期目標」を共 有化した上で、 課題解決に向けたケア方針を相互に理解し、その方針に添った個別サービスの 提供を行うことが重要(ケアプランと個別援助計画の融合)である。
これを徹底する場が「サービス担当者会議」であり、その機能強化を図ること が必要である。しかしながらサービス担当者会議の実態は明らかになっていない。
そこで、今回、サービス担当者会議の現状と課題を明らかにする。