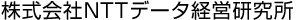(「環境新聞」2012年12月19日より)
リサイクルビジネス講座(21)
ソーシャルビジネスとの連携可能性
「市民の目線」を共有せよ
| NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部 シニアマネージャー 林 孝昌 |
収益活動を通じて社会的課題の解決に取組む事業をソーシャルビジネス(以下「SB」)と呼び、その事業主体と「SB事業者」という。一般企業がSBに取り組むことも可能だが、その担い手はNPO法人や一般社団法人が多く、利益分配などは行えない。かつてボランティアと呼ばれた団体は、こうした法人格を取得しており、善意だけでなく、知識や技術を保有する専門家集団も増えている。SBによる事業の自由度は高いが、収益確保が困難で株式会社などが手を付けない社会的課題に取り組むという点自体がその特徴と言える。
リサイクルはSBになじむ社会的課題だが、収益確保が可能なビジネスとして成立している。ただし、労働集約型でかつ地域密着型産業であるため、SBとの協調やシナジー発揮の余地は十分にある。本稿では、SBとリサイクルビジネスの連携可能性などに係る検討を行う。
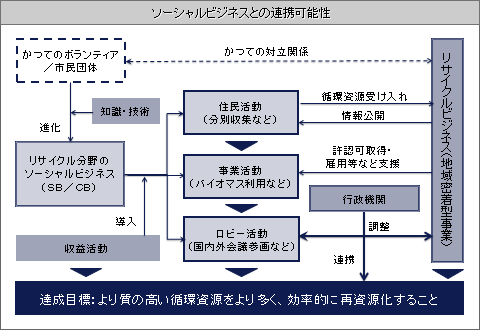
かつての市民活動は、「経済活動にかまけて社会的問題を引き起こす企業や行政に対する抵抗」という受け身のニュアンスが強かったが、今や環境や福祉、地域活性化などの分野では主体的機能を果たしている。こうした中、リサイクルビジネスとの接点は、「住民活動」、「事業活動」、「ロビー活動」の3つの切り口で考えられる。
まず、古紙や飲料容器などの分別回収、海岸など公共施設でのごみ拾いなどの伝統的な住民活動がある。住民活動の本質は、住民の善意や労働力をSBのリーダーシップで集約し、公益性の高い役割を果たすことにある。取り組みへの対価は、一般的に行政支出で賄われるが、収集された循環資源の受け入れは、リサイクルビジネスの役割となる。ここで最も重要な課題は、受け入れ後の処理に係る情報開示である。循環資源がどう再資源化されて動脈物流に還元されるかについて、具体的に分かりやすく説明することが、住民の理解やさらなる協力を得るための前提条件となる。
次に、SBによる事業活動には、食品廃棄物の堆肥化、廃食用油のBDF化などのバイオマス関連事業が多い。回収から利活用までを一貫して行うSBとリサイクルビジネスに接点はないが、許認可取得や障害者雇用などに係る経験を踏まえた支援や提携などは可能である。ビジネス目線で見ても、迷惑施設と言われる処理施設にとって、地域住民との共生は不可欠であり、SBとの連携は中小零細でも実践可能なCSR活動にも位置付けられる。
最後にロビー活動である。知識や技術で地力を付けたSBの発言力や影響力は、確実に高まっている。例えば国際会議や審議会などでも、市民代表のSBが参画し、制度設計における一定の役割を担っている。その達成目標は、より質の高い循環資源をより多く効率的に再資源化することに尽きる。事業継続には採算性確保が不可欠との認識が共有されている以上、テクニカルな課題解決手法以外に、一般ビジネスとの本質的な対立軸は存在しない。
ただし、現実には不毛な議論や利害対立も生じており、その調整は行政の役割となる。リサイクルが行政一部事務の範囲を超えた今、政策は解決策ではなく、目標設定である。その実現に向けたカギは、「連携」という一見陳腐な言葉にこそ、見いだすことができる。