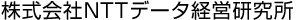(「環境新聞」2012年10月24日より)
リサイクルビジネス講座(19)
バイオマス事業化の可能性と行政支援のあり方
産業超えた付加価値創出を
| NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部 シニアマネージャー 林 孝昌 |
今年9月に、「バイオマス事業化戦略」が決定された。2020年にはバイオマス関連産業規模を約5千億円、計画等策定市町村数600市町村を目指す。また、企業と自治体の広域的な連合により「バイオマス産業都市」を構築するとのことである。バイオマス(化石資源以外の再生可能な有機性資源)のリサイクルなどによる産業振興への期待などは十分理解できるが、総花的な印象で、具体的な事業の輪郭ははっきりしない。
バイオマスは発生源が分散しており、未利用または再生可能な燃原料としての活用が進めば、農村部でも雇用や富を生み出す可能性がある。06年の「バイオマスニッポン総合戦略」策定以来、バイオマスタウンと呼ばれる地区が全国318にまで広がった理由はそこにある。一方、成功事例は限られており、政府の行政刷新会議からばらまきとの批判も受けている。
本稿では、バイオマスの産業としての可能性などに関する検証を行う。
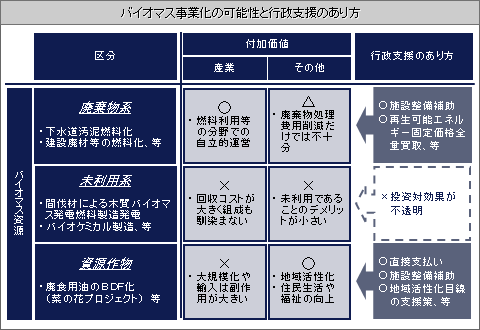
バイオマスは、「廃棄物系」、「未利用系」、「資源作物」の3つに区分される。成功事例が多いのは「廃棄物系」であり、その成立要件は、発生源・性状が安定しており、効率的な回収が可能で、処理後製品の受け入れ先が明確であることである。具体的には、「下水汚泥燃料化」、「建設廃材等の燃料化」などへの期待が高い。さらに各処理手法は、主に燃料利用、すなわちエネルギー回収を目的とした事業であり、初期投資費用を支援すればその後の運転稼動は自立的に行えるケースも多い。
逆に筋が悪いのが食品廃棄物である。性状が不安定で出口の堆肥などの需要も限られているため成功事例は少なく、廃棄物削減のみに力点を置いたビジネスモデルは成立困難なことがうかがえる。
次に「未利用系」について、未利用な理由は概ね回収コストの大きさ、または出口製品の品質にある。例えば間伐材の回収利用には人力を活用せざる得ないため、人件費を抑えたビジネスモデル構築は望めない。稲わらやもみ殻など農作物の非食用部は正に不要物であり、その材質からも高度利用には適さない。一般論として、未利用系は事業化との親和性が低い。
最後に「資源作物」である。例えば菜の花プロジェクトは、休耕田で菜種を栽培して、刈り取った菜種から油を抽出、食後の廃食用油をBDF転換して農耕機などに活用するバイオマス利活用の先進モデルである。農地を農地として利用し、エネルギー需給の自立を促すことで、地域活性化に寄与する。ここにビジネスのロジックを持ち込むと、途上国からの資源作物輸入がより合理的との結論となり、金銭換算困難な付加価値は全て失われる。米国がエタノールへの補助金を導入したことで、ブラジルなどで穀物価格が高騰したことは記憶に新しい。
産業の本質は競争と淘汰を通じた成長に限定される。一方、農業や農地が生み出す付加価値は、より本質的に人々の生活や福祉を向上させる。そこにビジネス目線の支援策を導入して歪んだバイオマス利活用を推進することに大義はない。
「バイオマス事業化」への行政支援には、スコープの絞り込みが不可欠となる。また、バイオマスには、独特な産業を超えた付加価値があることを見落としてはならない。