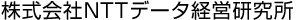(「環境新聞」2012年5月16日より)
リサイクルビジネス講座(14)
海上静脈物流の活性化に向けて
海上静脈物流で震災がれき処理促進を
| NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部 シニアマネージャー 林 孝昌 |
「リサイクルポート」とは、低エネルギー・低コストの船舶を活用して循環資源の大量輸送を促進することで、港湾物流等を活性化する政策である。主な輸送対象は、「鉱さい」「木くず」「石炭灰」等のバルク品となる。バルク品は、全国の港湾地域等で「建設用資材」「発電燃料」「セメント原料」等に利用されるが、無論、逆有償でも取引される。大量輸送が必要で単位当たりの付加価値が低いバルク品の場合、海上物流のコスト優位性は明らかだが、リサイクルポートの成功事例は少ない。本稿では、海上静脈物流の拡大に向けた課題を整理するとともに、その応用可能性の検討を行う。
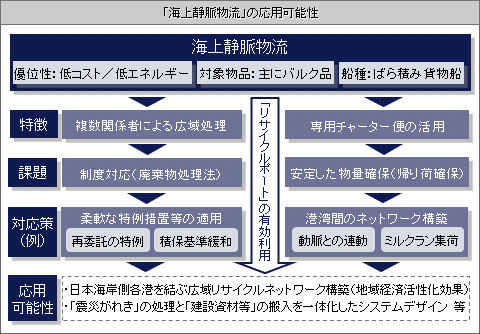
海上静脈物流の課題は、「制度対応」と「安定した物量確保」である。「制度対応」とは、逆有償で取引される場合の廃棄物処理法上の諸規制を指す。同法やマニフェスト制度は「非広域の陸上輸送」を想定しているため、海上物流の諸手続きは煩雑となる。例えば「再委託の原則禁止」条項は、排出者に「横持ち」や「荷役」等全ての輸送業者との個別契約締結を義務付ける。積地と揚地の双方で収集運搬業の許可も必要であり、自治体間の事前協議が条例でも定められてもいる。
そもそも、「排出者から処分費を受け取って山に捨てる」という古典的な不法投棄モデルへの懸念は、海上静脈物流には当てはまらない。船社は、揚地の荷主に輸送して初めてその費用を受け取れる。また、バルク品は原燃料であり、取引事業者間でその品質や量に係る契約が成立して初めて荷が動く。「逆有償取引なら廃棄物扱い」という機械的な基準を当てはめると、需給変動で廃棄物と有価物の境界を跨ぐ品目の取引を阻害し、結果的に最終処分量が拡大する。仮に海上静脈物流への一定の規制緩和が行われれば、間違いなく取引量の拡大・活性化に直結する。リサイクルポート等に対しては、柔軟な特例措置等の適用も検討すべきであろう。
次に「安定した物量確保」である。バルク品は、「バラ積み貨物船」で輸送されるため、船一艘分の集荷が輸送条件となる。コンテナ船とは異なり、定期航路が利用出来ず、スポットでの傭船が行われ、帰り便が空でも往復の費用が必要となる。物量の安定確保が容易な行き荷のみならず、帰り荷の確保も輸送コスト低減の必須条件となる。そのための具体策としては動脈物資の運搬が有効であり、建設資材や飼料等の取引とセットで航路を確保することが考えられる。また、いわゆる「ミルクラン」により、航路上の各港で集荷しつつ積地に戻れれば、輸送コストは分散出来る。例えば、バラ船の往来が少ない日本海側の各港をネットワーク化すれば、帰り便の選択肢も増加し、静脈・動脈の貨物取扱量が増大することで、地域経済活性化の効果も期待できる。
現在海上物流の活用が最も急がれるのは、震災がれきの広域処理に他ならない。今後、広域処理が本格化すれば、次の課題は輸送を含むコストの低減となる。「震災がれき受入地域からの帰り便で建設資材等を運び込む」などのシステムデザインは、我が国最大の課題である震災復興を加速する手段にもなる。