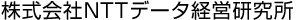(「環境新聞」2012年8月29日より)
リサイクルビジネス講座(17)
市場規模と業界構造
素材市場対応で生き残りを
| NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部 シニアマネージャー 林 孝昌 |
混迷する欧州経済や中国経済の減速といったマクロ経済動向の影響を受けて、素材市場の相場が世界的に低迷している。天然資源取引価格の下落は、リサイクルビジネス全体に直接的に悪影響を及ぼす。業界全体の趨勢を左右するのは、国内規制などではなくマーケットにあるとの現状認識を、官民関係者が受け入れるべき時が来ている。本稿では、リサイクルビジネスの市場規模を整理した上で、その業界構造に係る検証を行う。
環境省が発表した「環境産業の市場・雇用規模の推移」によれば、廃棄物処理・資源有効利用の市場は約38・9兆円で環境産業全体の約56%に及ぶ。ただし、「リース・レンタル」などのセグメントを除いた上で小項目レベルの調整を加えると、リサイクルビジネス全体の規模は約14・6兆円となる(以下、「トータル」という)。さらにその内訳を見ると「廃棄物処理業」が約2・7兆円、「解体処理業」が約1・1兆円、「流通業」が約3兆円、「素材製造業」が約7・7兆円となる。ちなみに、「素材製造業」の市場規模は、主に各素材の工業統計出荷額を、重量ベースの「循環資源受入割合」で割り戻して算出された素材メーカの収益である。その分を差し引いた純粋なリサイクルビジネスの市場規模だけでも、約6・9兆円に及ぶ(以下、「ネット」という)。
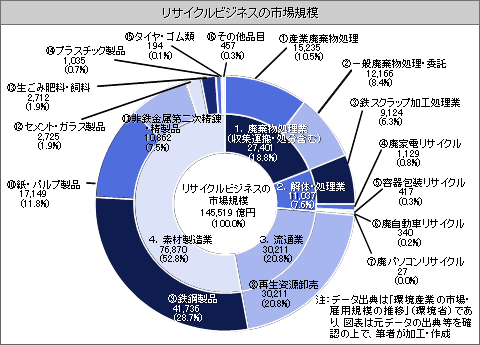
図が示す通り、トータルでは素材製造業のセグメントが全体の過半を占めている。このセグメントは循環資源を加工・流通した後の最終的な付加価値を示すが、取引量が一定でも、天然資源の価格が下がればそのまま市場規模は縮小する。天然資源は投機対象でもあり、その価格変動は大きく、動きも速い。この変動を吸収するためのビジネスモデル構築や企業体力の強化は、資源循環を支えるリサイクルビジネスが生き残るための必要条件となる。
次にその業界規模自体も重要な意味を持つ。ネットのみで比較しても、例えば「広告業界」(6・6兆円)や「旅行業界」(6・4兆円)などを上回る規模にある。製造業で見ても、「紙・パルプ業界」(7・4兆円)をやや下回る程度の水準であり、当該年度の国内総生産(GDP=10年度は479兆円)の約1・44%である。今も主力が中小零細企業であることは事実だが、業界保護的な観点で政策的に支え得る規模をはるかに超えている。生産性向上などによる業界全体の底上げは、個別企業の知恵と努力の積み上げで実現するほかない。
最後に、制度的関与が可能なセグメントが限定的なことも明らかである。制度が関与できるのは廃棄物処理業と、解体・処理業(鉄スクラップ除く)のみであり、その合計はトータルの約2割に過ぎない。産業廃棄物処理業や家電リサイクルのセグメントは逆有償での取引額の総和だが、処理後、原料として川下の素材マーケットが生み出す付加価値とは比較にならないほどに小さい。
リサイクルビジネスの特殊性を語る時代は終わった。マーケットに相対する普通のビジネスになった以上、さらなる競争と淘汰を避けることは不可能であり、業界全体の成長と進化はその先にこそ見据えることができる。