「NTTデータ経営研究所 対談シリーズ」第9回目では、神戸大学大学院経営学研究科教授の三品和広先生にお話を伺いました。三品先生は、日本企業がグローバル市場で勝ち抜くためには「競争戦略」「立地戦略」「時機読解」に基づく実戦的な経営戦略が必要だと語ります。
世界市場で成長した日本企業の成功のポイント
本日は経営戦略論の第一人者である神戸大学の三品和広先生をお呼びしてインタビューしたいと思います。
私は三品先生と一緒に、『デジタルエコノミーと経営の未来』(三品和広・山口重樹著:2019年東洋経済新報社)および『信頼とデジタル 顧客価値をいかに再創造するか』(三品和広・山口重樹著:2020年ダイヤモンド社)という2冊の書籍を執筆させていただきました。
また、私がNTTデータの副社長を務めていたときに、同社のアドバイザリーボードの立場から、いろいろとご意見、ご指導をいただきました。
もっと早くインタビューさせていただきたいと思っていたのですが、三品先生がちょうど新しい本の執筆にかかられておりました。『実戦のための経営戦略論』(東洋経済新報社)がまさに2024年4月に発売されたばかりですね。お忙しい中、ありがとうございます。

三品先生は経営戦略理論の専門家として日本企業について多くの戦略を分析されています。三品先生の研究の特徴は、具体的に独自の戦略のフレームワークを作られ、それを多くの企業の事例に当てはめた上で、成功パターン、失敗パターンなどを実際的に実証されているところで、私も大変関心を持って勉強させていただいています。
三品先生は米ハーバード大学で博士号を取られ、その後、ハーバード大学でも教えられ、海外の事例についても大変詳しいです。そこで今日は三品先生に、日本企業が今、どういった課題に直面しているのか、それらをどのように解決していけば、さらに成長できるのかというお話をお伺いしたいと思います。
三品先生は、利益率を上げた企業、占有率を上げた企業、成長率を上げた企業など、多くの企業を分析されています。その中で、うまくいっている企業、うまくいっていない企業の特徴とはどのようなものなのでしょうか。
うまくいかない会社または事業の特徴は、他社の後追いになっていることです。既に誰かが手をつけているのを見て、「あれ、いいじゃないか」といって追いかけるケースです。後から参入して逆転に成功し、そのフィールドでナンバーワンになった企業は意外と少ないのです。
後ほど「事業立地」について詳しくご紹介します。立地をどう定義するかにもよりますが、一見、後追いに見えるけれども、実はそうではなく、逆転に成功したケースもあります。例えばダイキンの例です。
ダイキンは長い間、家庭用のエアコンは取扱っていませんでした。オフィス用すらやっていなかったのです。ただし、歴史を振り返ると、同社は海軍の潜水艦の空調装置といったところから出発しているのです。その意味では、エアコン製造では日本で一番古いのです。それが後ほど、店舗・オフィス用、そして住宅用と立地を動かしてきたのです。しかも動かすタイミングが絶妙でした。
ホンダも事業立地をうまく動かした事例です。本田宗一郎はもともとピストンリングの生産で創業し、二輪に入って、そして四輪に参入しました。自動車とくくると後追いです。ところが、ホンダが最初に四輪事業に入る時、当時トヨタも日産もやっていなかった農家用の軽トラックから入ったのです。これは非常に面白い立地の選択です。そのような実用車というくくりで見るとファーストなのです。ホンダが最初に馳せ参じたわけです。
そういった独自の工夫がなく、ただ漫然と、「あそこは盛り上がってるね」と後から駆けつけるようでは、勝ち目はありません。
さらに注目すべきは、ダイキンもホンダも、まずは体力見合いで小さいところからスタートする工夫を効かせていることです。エアコン市場、四輪市場と見ると大きいのですが、両社はともにその大きな市場の端のほうの周辺部にまず足がかりを作って、そして実力が上がってくるに従って、だんだんと中心部ににじり寄っていきました。そのフィールドの大将に直接喧嘩を挑むのではなく、ステルス的に攻めていく技の効かせ方がうまいところです。
今、DXやAIが盛り上がっているから、とにかく片足を突っ込めといった入り方をするところは、あまり先が見込めないと思います。
ほかにも、日本の企業の戦略としてうまくいった事例にトヨタの米国進出があります。トヨタが自動車に参入した時、米国ではGM(ゼネラル・モーターズ)やフォードがはるか前を走っていました。なのになぜ、米国の市場で逆転できたのか。
同じようにテレビでも、ソニーやパナソニックは、先行する米国のRCAやGE(ゼネラル・エレクトリック)を逆転することに成功しています。
理由の一つは、長らくGMやフォード、またはRCAやGEが米国の市場で独壇場を築いていたため、いわゆる驕りが出てしまい、サボっている状態に入ってしまったことです。しかもそこで、大きな貿易摩擦にならずに済んだ。最初は貿易摩擦になるのですが、それをやり過ごすと、米国で大きなマーケットシェアを取っても、もう「Who cares?(誰も気にしないよ)」と許してもらえたのです。
実は、トヨタの対米自動車輸出台数は、日米貿易摩擦になった1980年代より、今のほうが多いのです。ところが、今はうんともすんとも言われない。レクサスのような高級車をどんどん輸出しても怒られない、それはなぜか。
それは、米国の国益という観点から見るとわかりますが、本当に大事なのはエネルギー産業なのです。具体的にはエクソンモービルです。同社のマーケットバリューはトヨタを凌駕しています。こちらのほうがはるかに儲かるのです。こちらを伸ばすためにはガソリンをどんどん消費してくれる車を世界中にばらまく必要がある。ところがGM、フォードは米国であぐらをかいているだけで、世界で市場を広げようとしない。だったら品質のいい車を安く作って世界中にばらまいてくれるトヨタにやらせたほうがエクソンモービル、または米国のエネルギー産業にとってはありがたいのです。
同じようにテレビでも、米国が本当にやりたい事業はハリウッドのコンテンツ制作です。これを広げるためには、安くて品質のいいテレビや映写機を大量に世界中にばらまいてくれたほうがありがたい。それをやってくれる米国の会社がないのだったら、日本にやってもらって構わないということなのです。
米国の国益と正面から衝突する事業はつぶされます。ところが、米国が本当にやりたいことをアシストするポジションを取っている事業は、ある意味かわいがってもらえ、生き残るという図式になります。もちろん、トヨタ、ソニーが初めからそこまで考えて、そういう事業を選んだのかどうかまでは分かりませんけれども、少なくとも結果的に非常にいい立地になったことは確かです。
一方で、日本企業が本当にクリエイティブ(創造性)を発揮して世界で受け入れられるようになった事業もいくつかあります。目立たない、知られていない会社が多いのですけれど。
例えば、電子製品のなかで使われるプリント基板用超硬ドリルを製造しているユニオンツールという日本の企業があります。現在、半導体需要が高まっていますが、半導体にはこれを据え付ける回路基板が必要です。半導体のような素子は表面実装で置くだけではダメで、今のプリント基盤は、10層、20層になっていて、これらの内部に穴を開けて銅でメッキをして通電します。同社はこの穴を開けるドリルに強く、隠れた世界企業になっています。スルーホールのニーズが出てきたときに、米国ではそれができる企業がありませんでした。ユニオンツールは米国のIBMに「君たちは歯医者さん用の小さなドリルをやっている。プリントもできないか」と要請を受けて参入したそうです。
もちろん、普通のドリルでは面白くない、消耗品なので安く作らなければならないと、独自の構造を持つドリルを作って世界を制覇しました。これは王道ですけれども、そういう独創性で勝った企業も日本には一握りながらあります。
松下幸之助に見る、成功する「時機」の見極め
自分の力をよく見極め、その中で次にどこに行くべきか、三品先生がおっしゃる転地を果たしたわけですね。どう考えればその行き先が読めるのでしょうか。
かっこいい答えがあればいいのですけど、基本は泥臭いものです。足で稼ぐことです。
私は時機、すなわちタイム&オポチュニティ(機会)と言っていますけれど、オポチュニティをつかんでも、早すぎたり遅すぎたりしてはだめなのです。逆にタイミングよく出ていっても、そこにオポチュニティがないのでは、これもアウトです。タイミングとオポチュニティが両方ぴったりと合った時のみ新しい事業は成功します。
まず、タイミング関して言えば、新聞、雑誌、テレビなどのメディアが大きく取り上げるようになると、もう完全に周回遅れです。お祭りになっているところに飛び込んでもうまくいきません。
山口さんはよくご存じかと思いますが、私は日本企業のケーススタディ600編以上を収録した実戦シリーズ3部作『高収益事業の創り方(経営戦略の実戦(1))』『企業成長の仕込み方(経営戦略の実戦(2))』『市場首位の目指し方(経営戦略の実戦(3))』(いずれも東洋経済新報社)を、10年あまりをかけて書いてきました。日本の中でもいい事業があるだろう、いい会社があるだろうと、それらを網羅的に取り上げ、うまくいっているところは、なぜうまくいっているのかを考えてみた本です。
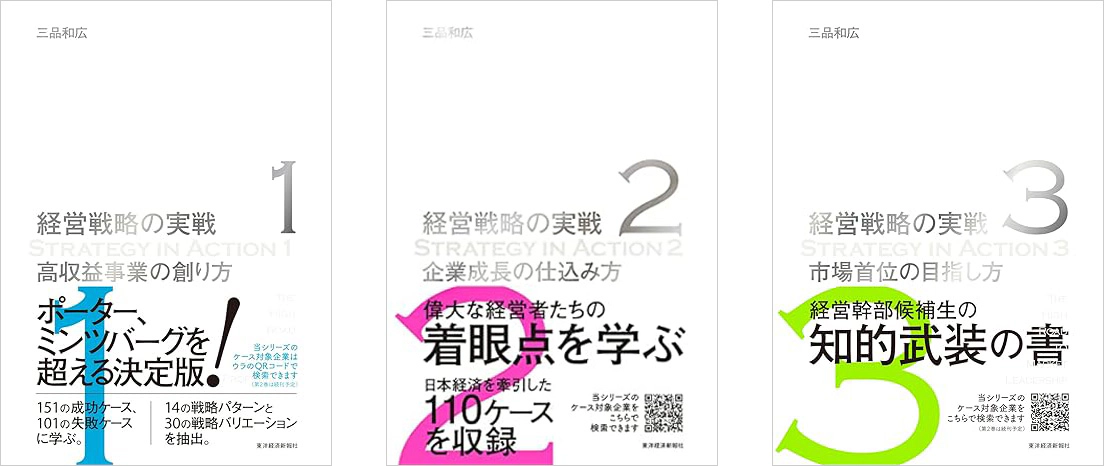
ちなみに、うまくいっている事業の着手タイミングを見てみると、意外にも最初は「こんな事業がうまくいくはずがない」と言われながらも始めた事業が多いのです。
皆さんも今、イーロン・マスクが生成AIを始めるらしいとか、今度「Chat(チャット)GPT」のバージョン5が出るらしいとか、そんなことを騒ぎ立て情報収集するのに貴重な時間使う暇があったら、むしろ私の本を読んで、すでにうまくいくと証明された事業が、一体どういうタイミングで、何に目をつけてそこに着手したのか、これをひも解いてもらったほうがよほどヒントになると思います。
うまくいっている事業は、着手したタイミングで、そんなものが伸びると思ってる人はどこにもいない、誰も騒いでいない。なのにそこに足が向かったということなのです。そのきっかけは風呂に入っているときにひらめいたといったものではありません。日々の業務に忙しくしている中で、小さいながらすでにやっている事業や仕事があって、その渦中でふと気が付いた、ここなのです。
分かりやすい事例では松下幸之助さんがなぜ松下電器産業を作ったのかが挙げられます。彼は当時、配線工事をやっていました。大阪の劇場にネオンのような照明を取り付ける工事をやっている時に、これからは電気の時代が来ると実感したそうです。ただし、そこで商業用照明を取り付ける事業で起業していたら、松下電器産業、パナソニックにはなりません。彼はそこでひとひねり入れました。こんな素晴らしい電気が公共性の高い建物の装飾に使われるだけで終わるはずはない、必ず家庭に来るはずだと。ただ、家庭で電気を使うためには、裸電球用の配線だけでは足りません。そこで、アイロンやトースターなど、電灯と別の家電が同時に使える二股ソケットを開発したのです。
米国には二股ソケットなどありません。なぜなら米国ではずっと前にコンセントが家庭に来ていたからです。当時、日本の安普請の家屋にコンセントを引く工事をしても高く付きました。という中で、米国のような文明生活を日本に持ってくるために、その課題を解決するのが二股ソケットだったのです。そこには、誰も注目していなかった、こういうのが本物の時機の見つけ方ですね。
単品のマーケットの一片だけを見るのではなく、これが広がってきたら、あれもこれも必要になるだろうという見方ですね。
そうです。幸之助はその後も、自転車につける砲弾型電池ランプを考案しています。終始、この電気の恩恵を一般人にもたらすにはどうすればいいかという、そういうテーマを持っていました。
経営者はそういう見方をしなければなりませんね。まさに時機を読むと。
そこです。さらに夢物語ではなく、フューチャリスティック(未来的)な話でもなく、今の現実に落とし込むことをやっています。
こういうのは、いろいろな事例を見て、自分の頭の引き出しを増やすことによって、自分たちに近いフィールドでも応用できる、新しいアイデアを生み出すことができるようになるのです。

『実戦のための経営戦略論』で示された3つの戦略
発売されたばかりの『実戦のための経営戦略論』は、大きく3部構成になっていますね。「第1部 勝つか負けるかの戦略論」では「競争戦略論」、「第2部 勝てる土俵を選ぶ戦略論」では「立地戦略論」、「第3部 浮かぶ立地を知る戦略論」では「時機読解論」がそれぞれ1章を割いて詳しく解説されています。この本の構造についてお聞かせください。
「競争戦略論」「立地戦略論」「時機読解論」は、多くの知見が積み上がっている確かなところから順番に並べています。
「競争戦略論」は、マイケル・ポーター先生が1980年に作られたもので、私はポーター先生の授業を受けて今日に至ります。ただ、ポーター先生の本は、本人が30代の前半で書かれていることもあって、少し分かりにくいのです。また、ポーター先生の本は、米国の事例ばかり、しかもマイナーな事例が多いので、日本の読者にはピンとこない。そこで、論理構造をきれいにした上で、さらに皆さんに分かりやすい日本の事例で、これを説明し直すという作業を行いました。
「立地戦略論」は私が過去20年ぐらいかけて作り上げてきたものです。
「時機読解論」は、先ほど申し上げた『経営戦略の実戦シリーズ』を書きながら、やはりこれは大事だ、戦略の上流は時機を読み解くことだと気が付き、まだ蓄積は薄いのですけれども入れることにしました。
理想的な環境のもとでは、時機を読み解き、そして、それに応じて良い立地を選ぶ、そしてそこで守るに値する高収益事業ができ上がったら、競争戦略を駆使して守り抜く…という流れになってきます。
すでに高収益事業があれば競争戦略を酷使して守り抜けばいいのですけど、今の基幹事業が低収益でそんなに儲かっていない場合には立地戦略を駆使します。今の技術、今の販路、今のお客さんを必ずしも捨てることなく、事業の立地、すなわち誰を相手に何を売るかというところを微妙に上手にずらすこと、あるいはもう少し小さく絞り込むことにより、収益性が大きく改善します。今の日本企業は収益改善を求められています。今すぐ使えるソリューションと言えば、この「立地戦略論」ということになります。
ただ、長い先を見た時には、やはり新たな成長事業に張っていかないと未来は安泰になりません。そのためには、「時機読解」に挑戦する必要があります。
ただし、この本に書き込んだ内容だけではまだ足りないなと思い、今、この続編を書き始めています。企業はもっと歴史の流れ、時の流れを読み解いて、それに寄り添うべきです。そこをきちんと解き明かして整理する本が必要だと思いました。
一般的に、経営戦略論と言えば、競争戦略が中心だと考える人が多いと思います。三品先生の理論は、そこに立地と時機の観点を加えたことで、体系的に理解できるようになったと思います。
三品先生がご指摘のように、事業の成果が10年後に出るかどうかには時機が重要だというのもよく分かります。
NTTデータ経営研究所のようなコンサルティング企業にとっても、そういう戦略の体系がコンサルタントの皆さんの頭に入っていて、そしてクライアントの抱えている問題に応じて、この場合は競争戦略、この場合は立地戦略、この場合は時機読解の観点から行くべきだと使い分けができたら、最強だと思います。
その点で、日本の企業は目の前の改善に力が入りすぎていて、フォーサイトに基づいた戦略が立てられていない、実行されてないという議論もあります。
人材の流動性が低いことが日本企業の大きな課題
一番大きな問題は、日本企業では人の流動性が低いことです。特に企業のトップのポジションにたどり着くような人は、新卒で入って、ずっと生え抜きで上がってきたような経緯をたどることが多い。その会社の基幹事業もトップが入社した時からあったとなると30年以上の歴史があります。そういう事業を中心になってやってきた人がトップに就きますので、まだまだやれると、しがみついてしまうのです。新しいことに挑戦するとなると不確実性だらけです。ならば、日銭が稼げているこの事業があるじゃないかと。下手に浮気するよりも、やるべきことをきちんとやったほうが手堅いと思ってしまうのです。
米国の企業であれば、古いところにしがみついている経営者はすぐクビになってしまいます。日本の企業も、大きく転進しなければならない時には、「昔取った杵柄」という発想の人は取り除いて新しい人を持ってきたいところです。いわゆる新しい血を入れることによって新しい境地に挑戦できるのです。
IBMというと、ブルーチップ(優良企業)と呼ばれ、伝統的で立派な大企業というイメージがありますが、同社の沿革を見ると、設立当初はパンや肉のスライサーなども作っていました。社名のIBM(インターナショナル・ビジネス・マシーン)は、国境を越え、カナダでもこれらの製品を売っていたことに由来します。まさにパン屋さん、肉屋さんのビジネスを支える製品です。
その後、トランジスタを使ったメインフレームコンピュータ、デスクトップPCと移り、サーバーに出ていき、さらにコンサルティングやワトソンのAIなどへと事業を変えてきています。
1990年代にIBMを立て直したのはルイス・ガースナーです。IBMの歴史で初めての外部からの経営者ですが、それが功を奏したと言えますか。
IBMの創業者はトーマス・ワトソン・シニアで、その息子のトーマス・ワトソン・ジュニアにバトンタッチしたときに商用コンピュータに本格進出したわけですが、ワトソン家の経営の下でやっていた時、あるいは彼らの息のかかった人がやっている間は、結局このメインフレームコンピュータを捨てることができませんでした。そこでガースナーが来て、「これからはコンピュータ」じゃないと言って、サーバーに大きく乗り換えていくわけです。
経営者が変わることで、そういう新たな事業立地を作り出すということもあるということですね。
そうです。日本では今、DXやAIにかき消されてしまっているところがありますが、少し前には、猫も杓子もイノベーションといった状況でした。ただ、そのイノベーションを日本では技術革新、すなわち理系の人がやる仕事だと解釈してしまっているところが、そもそも大問題です。
イノベーションという言葉を生み出したのは、経済学者のヨーゼフ・シュンペーター先生で、彼の定義によると、既にあるものの新しい組み合わせ(新結合)がイノベーションなのです。よって本物のイノベーションを起こしたければ組み合わせなければならないのです。ずっとそこにいた同じメンバーが頭を突き合わせて、ああだこうだ、とやってもイノベーションは生まれません。米国の会社が新しい血を外から入れる、またはダイバーシティに本気で取り組む理由は、新しい血を入れないことには新しい組み合わせが起こらないからです。
日本ではずっと同じ釜の飯を食ってきた人が信用できる、というところから脱却できていないので、イノベーションとは縁のない世界で生きていくことになるのです。
日本の労働市場というか、内部昇格型の日本の人事システムが変わらない限り、イノベーションは出てこないということでしょうか。
日本が米国をお手本にして追い付け追い越せで来た時は、体育会系のノリで、ヒエラルキー組織のもと集団戦で、みんなで手分けしてやるというのでよかったのかもしれません。しかし、1980年代に米国に追いついたと言われるようになってからは、日本も新しいものを作ることを迫られているのです。それに対して成果を出せていなかったのが、今の日本の困窮状況の根本原因だと思います。
イノベーションを起こすには、経営者は時機を読んで、新たなマーケットに立地を開拓してやっていく必要があります。その基本となるのは、新しい組み合わせによりどんな顧客価値を作っていくかだと思います。
はい。事業の立地というのはまさに、誰を相手に何を売るかということです。同じ相手であれば、お客さんにとってどうでもいいものよりは、よりミッションクリティカル(顧客にとって必要不可欠)なものに軸足をずらしていくべきです。
それを実践した成功例としてテルモがあります。同社は体温計の国産化からスタートしました。病院から見ると、体温計は待合室で患者さんに使ってもらうものです。同社はそこから注射器を開発します。待合室ではなく処置室の中で使うものに変わっていきます。その後は一歩進んで輸液バッグ、輸血バッグを発売します。今度は入院病棟に行けるようになりました。最後の決め手はカテーテルです。血管の中にカテーテルを挿して診断・治療する器具で、手術室で使うものです。
つまり、病院の待合室から手術室ににじり寄って、ミッションクリティカルな度合が上がることによって収益率もぐっと上がってきたという事例です。

米国に比べて日本企業は15年遅れている
米国に比べて日本は遅れているという人と、もう米国から学ぶことはなくなったという人ととの、両論があります。
三品先生は、日本は15年遅れているとおっしゃっていますね。どのような点が遅れているのでしょうか。
例えばベアリングなどずっとあるものは、その世界だけ見ていると、もうほぼキャッチアップは完了していますし、もう米国から学ぶものはないと言いたくなる気持ちは分からないでもありません。
ただ問題は、それらは米国ではもうすでにオールドエコノミーで、そのような企業の株価はまったく上がっていないのです。むしろ下がっています。
今の米国はそういうところではなく、「マグニフィセントセブン(米アルファベット、米アップル、メタ、米アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、米テスラ、米エヌビディアの7社の総称)」と言われるようなところが株価を引っ張っています。この中に日本の企業は一社もありません。つまり、米国が新陳代謝の中で捨てようとしているところに追いついたと喜んでいていいのかということです。
人間も新陳代謝により細胞をどんどん置き換えて生きているわけです。それと同じように産業社会でも、古くなったビジネスは捨てて、中国に譲る、ベトナムに譲るという発想が要るのです。日本でも今、多くの会社の屋台骨になっている事業は、米国から譲ってもらったものです。米国では、例えばベアリングの事業を売却したり、もう製造業は大々的にやっていません。どうするかと言えば、日本から技術指導料を得たり、また事業を売却した資金を運用するという方向に向かっています。今、日本企業に襲いかかっているアクティビストファンドの原資になっているマネーは、今から2~30年前に、日本の企業が米国の企業や技術を買った時に支払ったお金がもとになっているのです。皮肉なブーメランなのです。
米国のすごいところは、次から次にゲームを変えてくる、新しいゲームを作ってくるところです。日本の企業はゲームに入れてすらもらえない。全く太刀打ちできていません。そういう意味では、私が留学していた当時よりも、もっと米国と日本には差がついたと思っています。
それに追いつくのには何が必要でしょうか。三品先生は流動的な雇用市場を作らなければならないという話もされていましたが。あるいはもう、文化的にもなかなか難しいから諦めるべきなのでしょうか。
諦める前に、米国の真髄、米国の強さの源泉を本当に尋ねて知ったという人はほとんどいないのではないでしょうか。みんな表面をさっと撫でただけで分かった気になっています。あるいは分かった気になって記事を書いているマスメディアを通して知ったつもりになっているので、もっとたちが悪い。
事業について経営者に聞きに行っても、本当のことを教えてくれる人はいません。本当に大事なことは隠します。人に自慢し、ペラペラと喋ったりしません。本当に大事なことは撫でれば触れる表面のところよりずっと下のほうにあります。努力に努力を重ねなければ奥の院には届きません。それをやった人が何人いるのかということなのです。
これはまずいと私も気が付いたので、今執筆している本を通じて、日本にいては分からない、そういう深い真相の世界について私が知ったこと、学んだことを少しでも皆さんと共有できればと思っている次第です。

NTTデータグループのフォーサイト起点でのコンサルタントに期待
ありがとうございます。最後に、私たちコンサルタントに、日本企業をさらに元気にしていく、または米国に対抗できないとしても、ある部分で存在感を出すためには、コンサルタントは企業の経営者に対して、どういう観点でどういうサービスをしていけばいいのか、アドバイスをお願いします。
企業の基幹事業については、ずっとそれを育んできた経営者が一番よく知っています。そこをお手伝いに行くようなタイプのコンサルティングはあまり有望ではないと思うし、そこに群がる会社が増えたことによって、コンサルティングのコモディティ化がずいぶん進んでしまっていると思います。
今、日本の社会において価値が高い大事なことは、今までの事業を通して知見を積み重ねたわけではない新しいことに挑戦しなければならないという時に、どうせ挑戦するならこれが面白い、これに挑戦すべきだと経営者と一緒にテーマを選んでいくことです。
米国の強さは安心・安全を求めないところにあると思います。日本は安心・安全を求めるところから抜け出ていませんが、安心・安全を求めると安心・安全は絶対に手に入らないということをまだ皆さん学んでいないのです。
逆説ですね。
逆説なのですが、現実問題として、安心・安全を担保しながら挑戦したいという企業や経営者が多いのです。よって。いきなり清水の舞台から飛び降りろと言っても、なかなか踏み切れない。
という中で、きちんと資料を用意してあげたり、上手に背中を押してあげたりといったところで、コンサルタントが果たせる役割は結構大きいと私は見ています。
経営者以上に未来が見える、または今盛り上がっているフィールドの隅のほうがよく見える、その隅に落ちている事業機会を上手に拾うために鍛錬や経験を積んでいる。そういう成功経験があると、説得力を持って経営者に話ができます。経営者も耳を傾けてくれるでしょう。
残念ながら日本の上場企業には日本の未来を変えていく力がないことは、もう過去2~30年かけて証明されています。そこで、コンサルタントの人たちに本当に勉強してもらって、経験を積んでもらって、変われない日本企業の背中を押して変えていくという仕事をしていただければ、その価値は非常に大きいと思います。
ありがとうございます。ちなみに私たちNTTデータグループではフォーサイト起点のコンサルティングを目指しています。
三品先生の言葉で言えば、時機を読み、事業立地を考えていくというのがフォーサイトだと思います。それで新たな領域をどう作っていくかに力を入れるのは、今、三品先生がおっしゃった方向と合っていると思いますがいかがでしょうか。
山口さんとは一緒に2冊も本を書きました。その際、そのあたりを山口さんはしっかりと理解され、そのような方向を指向されていると感じました。社員の皆さんも、大いに期待できるのでは、と楽しみにしています。
ありがとうございます。私たちもこの4月に『フォーサイト起点の社会イノベーション』(日本経済新聞出版)という本をリリースしました。
日本企業は目の前のモノ作りの改善に注力しすぎたのではないか。これは大変重要なことですが、この本では、やはり顧客の価値、すなわち、このモノがどうお客さんに使われて、どんな課題解決のために使われているか、そこをデジタルでやっていくことが、一つの方向感ではないかと提言しています。
確かに、ビジネスとは、いかにお客さんに近づくかです。しかも応接室で話しているだけではだめで、相手のオペレーションの本丸、中核部分に足を踏み入れて初めて、お客さんが何に困っているかが分かるのです。ですから、お客さんに近づいて、本音ベースで困っているところをよく見た上で、それに対してソリューションを当てていく、これが王道なのです。
ソリューションは、デジタルもあればデジタルでないものもあります。今はデジタルということが多いですけれども、デジタルが目的になってはいけません。
デジタルを取り入れない経営はないけれども、デジタルを取り入れたから会社が変わる、DXが起きるわけではないですね。
そこはある意味当たり前で。私が80年代、米国にいた時にPCが登場し、これによってオフィスが変わる、経営が変わると言われ、マネジメントインフォーメーションシステム(経営情報システム)といった言葉も生まれました。しかし、蓋を開けてみると、パソコンの使い方の上手い下手で競争優位になっている会社はないのです。当たり前のようにどこも使っています。みんなが同じところへ来てしまうと、ツールになってしまいます。空気や水のようになるのです。
まさに今、私たちも、お客様の真の課題を解決するサービスを提供していくことですが、日本企業がより価値を高められていく、モノから顧客価値や顧客課題というところに視点をずらしていくべきじゃないかと思っています。
そうですね。もう一歩踏み込むと、困っているということに気が付いていない経営者もいるのです。それは、今の地に安住して、持っている目標が低すぎるからです。目線を上げれば、もっとやらなければいけないことも見えてくる。でも、それをやろうと思うと、あれがない、これがない、そこで初めて困ったとなるわけです。それを補うのがコンサルタントの皆さんの役割であり、それにより付加価値を提供することができます。
分かりました。ありがとうございます。コンサルタントの仕事はお客様のコアのビジネスの改善もあるけれども、さらにお客様が新たな事業立地、新たなビジネスを始められるところに、経験と知見を持って経営者の相談相手になることを目指すべきということですね。
今日は三品先生に、目の前のことに特化するだけでなく、歴史を紐解いて、過去と将来を見ていく時間軸の大切さも教えていただきました。また、日本企業が直面する経営の課題、それを解決するコンサルタントに対する期待もお話しいただきました。本当にありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
対談動画はこちらからご覧いただけます。


