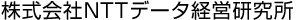(「環境新聞」2012年3月28日より)
リサイクルビジネス講座(12)
「発電燃料」としての循環資源
電力逼迫の今こそ商機
| NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部 シニアマネージャー 林 孝昌 |
東日本大震災以降の原子力発電所稼働停止を受けて、国内の電力需給が逼迫している。昨秋以降は電力供給に制限がかかるわけではなく、火力発電所に利用する石炭や石油等の増大に伴う電力料金値上げというかたちで、全国民に影響を及ぼしている。来年度からは石油石炭税も増税となり、再生可能エネルギーの全量買取制度も導入される。今後間違いなく、電力や化石燃料の価格は高騰する。
この異常事態はリサイクルビジネスにとっての商機にもなり得る。「廃タイヤ」、「RPF」(廃プラスチックと古紙を混合した固形燃料)、「木くず」など発電燃料となる循環資源の相対的な価格競争力が高まるからである。本稿では、「発電燃料」となる循環資源(以下、「燃料資源」という)に係る整理を行うとともに、今後の政策動向がその競争力に与える影響などを検証する。
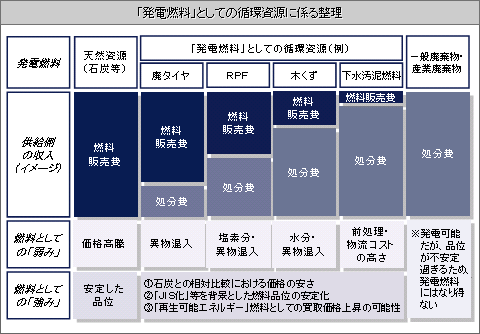
一般に燃料資源は、石炭の代替燃料に位置付けられる。石炭の発熱量は6千キロカロリー程度であり、例えば廃タイヤチップは8千キロカロリー超の発熱量を有しているため、燃料本来の性能としては十分以上の競争力がある。また、RPFの場合、10年にJIS規格が制定され、6千キロカロリー超、あるいは8千キロカロリー超の代替燃料としてその品質が確保される体制が整った。
さらに建設廃棄物等由来の木くずでさえも、約4千キロカロリーの発熱量を有するとされる。しかしながら、循環資源に特有の異物混入などを含め、燃料としての欠点を有する点は否めない。例えばRPFの場合、塩素分の含有率が高いため、製紙メーカーなどのユーザーがその利用を制限するケースもある。
また、木くずの場合、水分含有量によって発熱量に大きな差異が生じるため、受け入れ基準を満たす前処理が困難なケースもある。
一方、燃料資源の製造を担うリサイクルビジネスは、廃棄物処理に伴う処分費を受け取ることができる。だからこそ、炭化した「下水汚泥」でさえも燃料としての混焼が行われているのである。品位が安定した燃料資源は、処理費と物流費を踏まえた経済合理性さえ確保できれば、発電燃料になり得る。
燃料資源は今も「売り手市場」が続いている。火力発電所での負荷追従運転などが避けられない現状から、燃料資源の生産・販売に伴う利幅は今後も拡大する。さらに、現在審議中の再生可能エネルギー全量買取制度でも、循環資源を利用したバイオマス発電は、その対象手法に含まれている。
石炭との混焼発電が買い取り対象に含まれるか、あるいは混焼対象の循環資源にはどの品目が含まれるかなどの詳細は、本稿執筆時点では決まっていない。とは言え常識的に、燃料資源単独の発電以外は対象外との政策判断はばかげており、フェアでない。
ユーザー側がトレーサビリティなど明確な根拠をもって、自ら利用した燃料資源の割合や実績を示すことができた場合、その化石燃料削減効果は認められるべきである。となれば、燃料資源の需要はさらに高まり、その競争力も高まる。電力需給逼迫を好機に、新たなビジネスモデルを構築するチャンスは、「今」である。