コラム・オピニオン 2015年01月05日
なぜ私たちは70歳代まで働かねばならないのか~~社会生活から考える日本経済
山本 謙三
筆者のかねての主張は、「70歳まで元気に働こう」だ。経済的な理屈づけは別稿に譲り、本稿ではやや直感的な議論を紹介してみたい(2013年9月「70歳まで働いて帳尻を合わせよう」 参照)。
「老後を楽しむ」というのは、動物のなかで唯一ヒトにだけ与えられた特権だろう。他の動物は、生存のために一生自ら餌を探さなければならない。
ヒトにそうした特権が許されるのは、「(高齢者や子供などの)働いていない世代」が消費する財やサービスを、その時々の「働く世代」が稼ぎだしてくれるからだ。たしかに、個々人でみれば、老後は貯蓄をとりくずして過ごすことになる。しかし、マクロ的にいえば医療であれ旅行であれ、老後の消費のほとんどが、その時々の「働く世代」による生産物にほかならない。
では、「働く期間」と「働いていない期間」のバランスはどう推移してきただろうか(参考1)。
(参考1)「働く期間」と「働いていない期間」のバランス
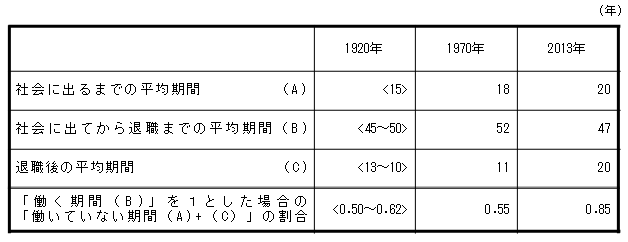
(注)試算の方法、資料は本稿末尾に記載。なお、老後、孫の面倒をみたり、家事を行うことも、当然「働くこと」と観念される。しかし、本稿では問題の所在を明らかにするため、いわゆる「職業に従事している期間に相当する年代」を「働く期間」と定義している。
試算結果をみると、1920年と1970年の間では、バランスに大きな差はみられない。「社会に出るまでの平均期間」も「社会に出てから退職までの平均期間」も、50年の間に若干延びた。一方、「退職後の平均期間」はほとんど変わらなかった。この結果、「働く期間」と「働いていない期間」のバランスはおおむね1:0.5が保たれた。
劇的な変化が生じたのは、むしろ1970年以降だ。大学進学率の上昇とともに、「社会に出るまでの平均期間」は一段と延びた。また、「退職後の平均期間」は長寿化の進展とともに大幅な延びを示した。
一方、「社会に出てから退職までの平均期間」は逆に短くなった。「身体の続く限り働く」としてきた産業(農業等)や企業(自営業等)のシェアが低下し、定年制を採用する企業の割合が高まったことが大きいとみられる。この結果、「働く期間」と「働いていない期間」の割合は1:0.85まで高まった。
錯覚しがちだが、「働く期間」を短くできたのは、生産性の向上が主因ではない。生産性の上昇は、主として、働く世代を含む国民一人ひとりの生活水準の向上に寄与するものだ。「働く期間」の短縮に直結するものでは必ずしもない。
「働く期間」を短くできた主因は、やはり、団塊世代が1970年前後から「働く世代」となり、その後40年以上にわたり「働く世代」であり続けたことだろう。団塊世代の数の多さが、高齢者や子供の消費を支えるに十分な生産物をつくりだし、上の世代が早めに退職する余裕を生み出した。いわゆる人口ボーナスである。
しかし、人口ボーナスの時代はとうに終わった。最近では団塊世代も65歳を超えた。
仮に「働く期間」と「働いていない期間」の割合が1:1までさらに進むようであれば、私たちは生存期間の半分しか働いていないこととなる。しかし、それはありえない。若い世代の人口が少なくなっている以上、むしろバランスを過去に戻す必要がある(注)。そうでなければ、将来の「働く世代」の負担が増すばかりだ。「70代まで働く社会づくり」を急がなければならない。
(注) 仮に「社会にでるまでの平均期間」を現状と同じ20年とし、「働く期間」と「働いていない期間」を1:0.5へ戻そうとすれば、「社会に出てから退職するまでの期間」は計算上60年弱が必要となる(「退職後の平均期間」は10年弱)。
わが国の若手・中堅層の割合がすでに1950年代半ばの水準まで低下していることを踏まえれば、上記の割合を1:0.5に戻すことは不合理ではない。しかし、これを実現しようとすれば、80歳弱まで働かねばならないこととなり、健康年齢との関係からみて現実的ではない。
このことは、平均寿命に比べた健康年齢の短さ(あるいは、健康年齢時点での平均余命の長さ)がいかに重たい問題であるかを示唆している。
次に、「親が子育てに費やす期間」と「老後面倒をみてもらう期間」のバランスをみてみよう(参考2)。
(参考2)「親が子育てに費やす期間」と「老後面倒をみてもらう期間」のバランス
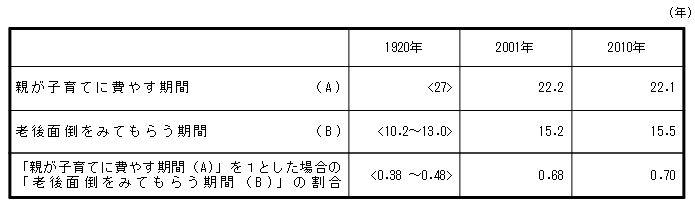
(注)試算の方法、資料は本稿末尾に記載。
試算結果をみると、「親が子育てに費やす期間」(第一子出生から末子成人までの期間)は、現在では1920年に比べ5歳ほど短くなった。一人の子供だけをとれば、成人までの期間は当然今の方が長い。しかし、子供の数が大きく減ったため、第一子を産んでから末子を産むまでの期間が大幅に短くなった。
一方、「老後面倒をみてもらう期間」を「健康寿命(日常生活に制限のない期間)時点での平均余命」と定義すると、データのとれる2001年以降、この期間はわずかに延びた。健康寿命も延びたが、それをわずかに上回るテンポで平均余命も延びたことになる。
残念ながら、「健康寿命」に相当する過去データは見当たらない。しかし、以前は、「身体の続くかぎり働く」としてきた産業や企業のウェイトが高かったことを踏まえれば、1920年頃の「老後面倒をみてもらう期間」は、今よりも短かったものと考えられる。
以上を踏まえ試算すると、「親が子育てに費やす期間」に対する「老後面倒をみてもらう期間」のバランスは、1920年当時の1:0.4程度から足もと1:0.7程度まで高まっている。
もし、このトレンドが今後も続くようであれば、いわば、「育ててもらったことに感謝しつつ、老親の面倒をみる時代」から、「老後の面倒をみてもらうために、子供を育てる時代」となりかねない。
結局、大事なことは、長く働くことであり、健康寿命を延ばすことだ。それも、平均寿命の延び以上に健康寿命が延びることが望ましい。身体のケアに努め、長く元気に働くことはその一助となろう。
【参考1の注】
社会に出るまでの平均期間:1920年は鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社(2000年)の成人年齢の定義による。1970年、2013年は文部科学省「学校基本調査」の進学率を基に試算。
社会に出てから退職までの平均期間:1920年は退職年齢を60歳ないし65歳とした場合の試算。1970年、2013年は、総務省「労働力調査」を基に労働力人口比率(男)が50%となる年齢を推定し、試算。
退職後の平均期間:1920年は厚生労働省「第4回完全生命表(1921~25年)」、1970年は同「第13回完全生命表(1970年)」、2013年は同「平成25年簡易生命表」を基に、退職年齢時点での平均余命を試算(男女を単純平均)。
【参考2の注】
親が子育てに費やす期間:第一子出生から末子成人までの期間。1920年は、鬼頭宏(前掲)による。2001年、2010年は、厚生労働省「国民生活基礎調査」の「児童のいる世帯の平均児童数」を基に試算(2001年、2010年の第一子出生と第二子出生の間隔は2.5年と仮定)。
老後面倒をみてもらう期間:健康寿命時点での平均余命。1920年の健康寿命は60歳ないし65歳と仮定。2001年、2010年の健康寿命は、厚生労働省「健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料」を基に試算。平均余命は、1920年は厚生労働省「第4回完全生命表(1921~1925年)」、2001年は同「第19回完全生命表(2000年)」、2010年は同「第21回完全生命表(2010年)」を基に試算(男女を単純平均)。
以 上
【関連コラム】
■ 定年制の廃止はなぜ難しいのか(2018.03.01)
■ なぜ働き方改革には「定年制の見直し」が欠かせないのか~~人口ボーナス、人口オーナスの大いなる誤解(2017.08.01)
■ どうやっても人手は不足する~~国の課題は「需要不足」でなく「人手不足」(2017.04.03)
■ 人口減少の何が問題で、何を問題視すべきでないのか~~60年後の日本の人口は、今のどの国と同じか(2016.12.01)
■ 70歳まで働いて帳尻をあわせよう ~~長寿高齢化社会の道理を考える(2013.09.02)
■ わが国は豊かさを感じにくい国となるのか ~~高齢化と労働市場の構造変化が示唆するもの(2015.03.02)
■ なぜ人口は首都圏に集まるのか ~~東京一極集中論の虚実(2015.05.07)
■ 急低下する生産年齢人口比率をどうみるか ~~3~4年後には戦後すぐと同じ水準に(2015.06.01)
■
本当は誰が最大の消費主体なのか(2015.11.2)

