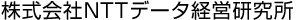(「日経コミュニケーション」2012年3月号より)
マルチデバイス対応
提供する経験価値を明確に
双方向コミュニケーションも重要
|
今の社会は、様々な部分で機械化やIT化が進み、同時に情報流通が盛んになったことで、あらゆる物やサービスの品質に大きな差異がなくなった。つまり、コモディティー化が進んでいるわけだ。例えば消費者におけるIT化では、携帯電話が一般化し、最近はスマートフォンへのシフトも加速している。平成23年版 情報通信白書にある携帯インターネット利用状況を見ると、全体で約6割、13~19歳では75%、20~29歳は実に90%が携帯電話を利用している(図1)。
図1:IT端末を携帯することが当たり前の時代に

(データは総務省「平成23年版 情報通信白書」の「属性別携帯インターネット利用状況」から引用 ) |
そしてコモディティー化は、消費者の価値観を従来とは違うものに変えつつある。流行に乗った周囲と同じものではなく、自分自身が良いと思えるものへと、急速に価値観がシフトしてきている。
こうした社会においては、企業は顧客(消費者)を自社のビジネスに組み入れ、行動や心理を細かく分析して、それぞれに合わせたモノやサービスを提供する必要がある。ユーザー中心、あるいはユーザー参加型の社会である。米国の経営学者であるフィリップ・コトラーは、これをマーケティング3.0と呼んだ。
実はこの社会的シフトは、システム開発に大きな影響を与える。システムで提供する情報の内容を、消費者一人ひとりに合わせてデザインする必要が出てくるからだ。この考え方はさらに、システムを利用するためのユーザーインタフェースのデザインにも影響する。
経験の価値を高めるデザインに
北欧やシリコンバレーを中心とした米国では、これらの考え方を「人間中心イノベーション」と呼び、技術やビジネス起点とは違うアプローチでのイノベーションだとして、国家レベルで研究を進めている。そこで重要になるのが、人間とシステムの接点となるインタフェースである。既存のシステム開発の延長上でインタフェースを検討するのではなく、「使っていて気持いい」という視点から抜本的にシステムをとらえ直す必要が出てくる。システム開発で「ユーザーエクスペリエンス」や「アジャイル」が重視されるようになっていることが、これらのトレンドを裏付けている。
筆者は2011年7月にNTTデータが開催した対話セッション「10年後の情報社会を考える」の企画に携わったが、そこでも、ユーザーインタフェースの重要性を示唆する発言が目立っていた。
重要なのは、ユーザーインタフェースを進化させることで、最終的には人同士がより直感的、かつ直接的に情報をやり取りできるようにすることだ。つまり、ユーザー中心・ユーザー参加型の社会に求められる、よりリアルなコミュニケーションを実現することである。
少し別の言い方をすると、情報を取り扱う者がこれから最も注目しなければならないのは、「経験価値を高めるデザイン」である。この経験価値を念頭に、インタフェースとして既存のやり方にとらわれないインタラクティブ性を、いかに作り出せるかが問われる。
冒頭に説明したように、世界中でサービスがコモディティー化、フラット化してきている。どのサービスを享受しても使い勝手や効果は変わらない。だとすれば、重要なのはその先に何があるのか、得られる経験は何かに注目が集まることになる。
ユーザーインタフェースに着目
こうした状況を踏まえ、今回は、ユーザーインタフェースに着目したシステム提案を募ってみることにした。実際のところ、一口にユーザーインタフェースと言っても幅広い。例えばAR(拡張現実)技術でのインタラクションの可視化、ペン型コントローラーによる「感触」の伝達、各種センサーを組み合わせたジェスチャーなど、アイデアは多様だ。
ただ、ユーザーインタフェースは、情報の利用者が持つ端末の能力などによって実現可能性が大きく左右される。とりわけBtoCはそうだ。このため、現実のビジネス環境でのユーザーインタフェースの考え方は限られる。
直近で考えやすいのは、スマートフォンやタブレット端末、ゲーム機、テレビなど多様な端末を想定し、ユーザー個別のコンテンツを提供すること。つまりマルチデバイス対応とパーソナライズである。
図1のモバイルIT端末の統計データを見ても明らかなように、今、若者を中心に最も身近に共感や経験を得られるものはモバイル端末である。少なくとも、システム提供者の多くは、消費者の価値の源泉がスマートフォンを含めたモバイル端末に移行していることに注目している。
典型的な例がソーシャルアプリやソーシャルゲームである。この業界ではペルソナと呼ぶ仮想の人格を設定し、それを基にシナリオを作り、それぞれのユーザーの「自分だけの空間」を演出する。アプリの中でのインタフェースやインタラクションに力を入れ、有料でも利用してもらえる仕組みをたくさん組み込んでいる。
こうした経験価値を提供できるのは、ソーシャルゲーム/アプリに限らない。ショッピングサイト、店舗、銀行、図書館、病院、行政サービスなど、あらゆるサービスにおいて意識レベルから根本的に全面的に見直される可能性がある。
会員個別のポータル画面を要求
そこで今回の仮想案件では、スマートフォンやタブレット端末対応をきっかけに、インタフェースを見直すという設定とした。想定する案件は、フィットネスクラブを経営するABC社の運営統合システムの強化プロジェクトである。会員管理のほか、会員の設備利用状況、フィットネスマシンの利用履歴などの情報を一元管理しているシステムだ。
ABC社はフィットネス業界では中堅で、顧客管理などのシステム投資を進めるなど効率化も図り、なんとかやり繰りしてきた。ただ、過当競争により、いまだ苦戦を強いられている。この数年の顧客獲得方法の方針変更などもあって、クラブに通う会員の数は減少傾向にある。そこで、会員の満足度を高められるようシステムをさらに強化することにした(表1)。ポイントは、会員がフィットネスクラブに通っているときに限定せずに利用したくなるシステムとする点である(表2)。
|
|
具体的には、会員がクラブ以外からでも情報を閲覧できるようにすると同時に、クラブ内のフィットネスマシンの情報だけでなく、例えば万歩計などの情報を自分で登録し、併せて管理できるようにすること。そして、健康管理の画面を会員ごとに最適化し、かつ会員が手軽にカスタマイズできるようにすることが要件である(図2)。
図2:想定するシステムの概要

|
また運動履歴、生体情報の履歴などをタイムライン表示する仕組みとし、タイムラインのスケールをユーザーが自在に変更できることも要件に含めた。もちろん、会員ごとに利用する端末の種類は幅広い。パソコン、従来型の携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機やテレビなど、どの端末からアクセスしても適切に情報を表示し、入力できるようにする。
もう一つ、このプロジェクトの会員との関係を深めるという目的に合わせて、担当者が質問に答える、食事などのアドバイスをするなど、顧客との双方向コミュニケーションが可能なシステムを設けることも要件の一つとした。
将来の拡張に備えた質問も盛り込む
今回提案の対象としているのは、会員に関する情報を管理している既存の運営統合システムそのものではなく、それをマルチデバイス対応させるための仕組みと、双方向コミュニケーションの仕組みである。ただ、今後のビジネスの強化を考えると、これでシステムが完結するわけではない。
例えば会員向けのポイントシステム。ABC社は既にポイントシステムを運用しているものの、運営統合システムとは連動していない。将来的には、運営統合システムと連携させ、さらなる会員獲得、あるいは会員の利用頻度アップにつなげたい。
ABC社は、フィットネスマシンから収集する情報、血圧などの健康情報、そして万歩計のデータや食事内容など会員による登録情報に加え、将来的には医療情報まで取り込み、会員が常に利用するシステムに発展させたいという考えを持つ。
そこでRFP(提案依頼書)には、これらの方針を踏まえて、将来のシステム拡張をどのように進めるか、そのポリシーを尋ねる質問も含めた。提案自体はオンプレミスでもクラウドでも構わないものとしたため、今後のクラウドへの移行を想定した場合の手順について、その考え方を示すことも求めた。
ベンダーの提案を確認する場合、マルチデバイス対応、コスト抑制などの要件を満たすことや、上記の質問にきちんと回答することは、最も重要なポイントである。さらに、会員のプライバシーに関わる情報になるため、情報保護、漏洩防止の策は不可欠。こうした点への配慮も十分にチェックしたい。
UI設計は利用者の人物像から考える
なお、今回はシステム提案を求めたため、ユーザーインタフェースそのものについての細かなコンサルティングや設計は求めていない。ただ、利用シーンや使い勝手に直接関わるため、この部分だけをコンサルティング会社などに委託してもよいだろう。
設計のポイントは、ユーザーの生活動線、行動動線、日常の生活(BtoBであれば業務動線)の中でのシステムとユーザーの関係性を洗い出すことだ。その手法として挙げられるのが、顧客、特にその中でも特殊な顧客を抽出し、彼らを徹底的に観察することで示唆を抽出し、設計に反映していくアプローチ(エスノグラフィー)。アンケートなどの統計から定量的に分析すると同時に、インタビューや観察、場合によっては動画の解析を通じて、定性情報を丁寧に拾っていく。
もう一つ、複数の属性を組み合わせてユーザーとなり得る人物像(ペルソナ)を構成し、その人物が取りそうな行動を考え、ストーリーを作っていく方法もある。