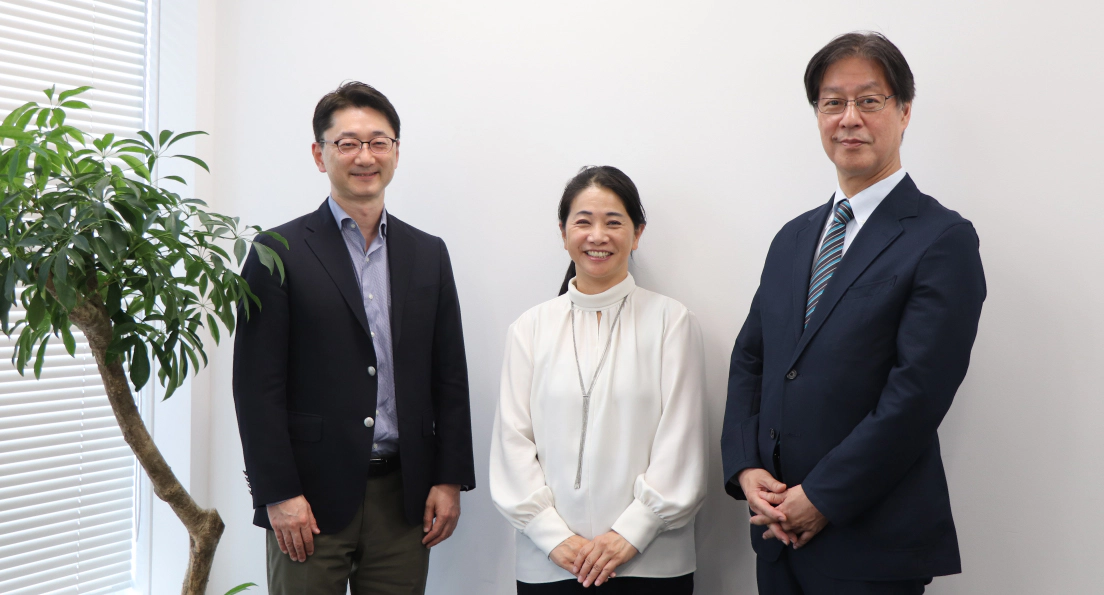本鼎談は、経済産業省情報技術利用促進課長、AIスタートアップ企業の人材政策担当、コンサルタントの三者が、日本のデジタル人材育成とDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の課題・展望について議論したものである。2020年代以降、生成AIの登場等で急速に変化する社会・産業構造のなか、日本企業や個人がどのように変わり、何を学び、どんな人材が必要となるのかを多角的に論じた。
はじめに
本日は「日本のデジタル人材育成の現状と課題」についてディスカッションしていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いいたします。
経済産業省の情報技術利用促進課長をしている内田です。この3年間、企業のDX推進とデジタル人材の育成に関わってきました。特にAIの進化に伴い人材育成のあり方を根底から見直す必要が出てきていると感じています。今日はよろしくお願いします。

エクサウィザーズというAIスタートアップで、AI時代の人材マネジメントについて研究と情報発信をしている石原です。もともとリクルートワークス研究所で人材マネジメントや労働政策の研究をしていたのですが、「デジタル時代には働く人にも新しいスキルが必要だ」と思っていたところご縁があり、3年前に同社に転職しました。ちょうどその頃からコロナでリモートワークが広がり、さらに生成AIも登場して、この3年間の変化は本当に大きかったと感じています。

ありがとうございます。最後にNTTデータ経営研究所の三谷です。今回はモデレーター的な立場で参加させていただきます。実は3人とも経済産業省の「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」のメンバーです。本日は、先般公開された研究会報告書の内容も含めて、デジタル人材に関して広く語っていただければと思います。

日本企業と個人が「学ばない」理由
はじめに、日本の企業が「人材投資」を十分に行っていないこと。そして、個々人が「自己啓発」をあまり行っていないという現状について、皆さんはどう思われますか?
日本は長い間、安定した会社に入って、そこでずっと働くのが理想とされてきました。OJT(仕事をしながら学ぶ)が中心で、会社の中でいろんな部署を経験しながら成長するスタイルです。だから「会社の中で真面目に働いていれば大丈夫」という安心感が強くて、わざわざ外で新しいスキルを学ぶ必要性を感じにくいんですよね。
そうですね。企業も個人も「今のままで十分」と思いがちです。実際、社会人で月5時間以上学んでいる人は1割程度。しかも、デジタル技術やAIを学んでいる人はさらに少ない。多くの人が「自分には関係ない」と思ってしまっているのが現状です。
なるほど。企業側も仕事を行ってもらうのであれば「OJTで十分」と考えているし、個人も「会社にいれば安泰」と思っている。だから大人が学ぶ習慣が根付きにくいんですね。
そうなんです。大人になると、学ぶといっても、「趣味で歴史を学ぶ」とか「神社巡りや仏像巡り」はあっても、「デジタル技術を学んでおかないとまずいよね」とか「マーケティングについて学びたい」とはなりにくい。これまでの成功体験が、逆に学び直しを阻害している面もあると思います。

日本型雇用の強みと限界
先ほど述べた通り、日本企業の人材育成はOJTが中心で、さまざまな部署を経験させながら幅広い知識を身につけさせる方式でした。しかも、これらは会社の独自ルールを学ぶとか組織風土の理解とかが中心です。もちろん、会社全体のビジネスを理解できるとか、社内ネットワークが広がるという良さもありますが、外部で専門スキルを磨く文化が根付きにくいという弱点もあります。
それに加えて、スキルを身につけても適正に評価されなかったり、適材適所に配置されなかったりするという問題もありますよね。処遇の向上につながりにくいから、「学んでも意味がない」という悪循環が生まれてしまう。
そうですね。それから日本企業の多くは「受託型・労働集約型」のビジネスモデルが多いんです。つまり「言われたものを作る」という形態が多い。そうすると、飛び抜けて高度なスキルが必要になるかというと、そうでもないんですよね。むしろ「みんな仲良く安定的にやろう」という平均点ぐらいの人がたくさんいる方がいい、という考え方に近いんです。
なるほど。産業構造自体が、新しい知識をどんどん身につけて新しいビジネス創出に向けて試行錯誤していくというよりも、受注したものを、きちんと納期と品質を守って完成させることを重視する形になっているわけですね。
そうです。20世紀までの間は、それで日本は確実に成長してきました。でも、これからの変化にどう対応するかが描けていない。私は21世紀を4つに分けて考えていて、最初の25年(2000〜2025年)は20世紀の価値観を慣習的に踏襲していた時期。これからの25年(2025〜2050年)で本格的に変わり、2050年頃にはちょうど21世紀らしい価値観が花開くんじゃないかと思っています。
生成AIとビジネスの変革
生成AIの登場で、ビジネスのやり方自体が大きく変わりつつあります。今までは「人間が作ったビジネスプロセスのどこをAIに任せるか」を考えていましたが、これからは「AIがプロセス設計から全て担う」時代になります。
つまり、「A地点からB地点に行きたい。リソースはこれだけ。どう行くかはAIに考えさせる」というアプローチです。そうすると、今までの強固なビジネスモデルやプロセスが根本から変わる可能性があります。
DXという言葉は10年以上前から言われていますが、当初はIT投資や情報システムの改革といった局所的なものだと誤解されていました。最近になってようやく「DXは価値創造のための手段」という認識が広がってきました。AI時代には、価値創造という企業活動の根幹の相当部分をAIが担うことが期待されます。
面白いのは、大企業ほど強固なレガシー(過去の仕組み)があって変わりにくいということです。例えば「この仕組み全部なくして、AIに任せたらどうなる?」と言っても、数千人も従業員がいる大企業では簡単に変えられません。
だから私は、中堅・中小企業の方がAI時代には有利だと思っています。既存のビジネスプロセスを壊すコストも小さいので、「全部AIにやってもらったらどうなるか」を試せるからです。

失敗を恐れる文化からの脱却
日本企業の現場では「成功事例がないと動けない」「失敗事例も知りたい」という声が多いですよね。でも、「事例」の出現を待っていると変化に乗り遅れます。
本当にそうですね。日本の企業でよく見られるのが、若手が「これをやりたい」と言ってきたら、上司が「事例を持ってこい」と言い返すという風景です。でも、事例があるということは既に後手に回っているということですからね。
そうなんです!さらに「成功事例はいいけど、失敗事例も持ってきてほしい」とか言われることもある。これって「どれだけ自分で意思決定したくないんですか?」と言いたくなります。失敗したくないから、リスクを取らないんですよね。
政府での政策の検討も、以前は「出来上がった社会をどう変えるか」という後追いが多かったのですが、生成AIについては「走りながら考えよう」というスタンスに変わりました。2023年5月に松尾豊先生の元でAI戦略会議を立ち上げ、その2週間後には論点整理をして各省が課題に取り組み始めるという過去にはないスピード感です。
そうですね。2025年5月に可決したAI推進法も、ヨーロッパが慎重論に寄っている中で、日本はかなり攻めた内容になりましたよね。私は当初、AIガバナンスの話が強く出すぎて規制寄りになるのかと心配していましたが、意外にも積極的に活用していくという、前向きな法律ができて良かったと思います。
これからの人材育成と若手の活用
では、これからどんなデジタル人材が必要になってくるのでしょうか?多くの企業において、皆さんこの質問に対する答えを欲しがっています。
生成AIの登場で、学びのあり方自体が変わってきています。これまでのように2年間座学をする、一度学んだら終わりということではなく、「走りながら学び続ける」「必要な時に必要な学びをして、それをすぐに活かす」というアジャイルな学び、そして学び続けることが求められています。
デジタルの時代、若い人たちの方が、適応が早いと感じています。だから若い人に権限を委譲したり、裁量を広げたりすることが大事です。でも多くの会社では、まだまだ若い人の意見が軽んじられがちです。給与水準は少し変わってきたかもしれませんが、メンタリティーとしての年功序列はまだ強い。「新しい物事については、若い人の方が絶対に知っているし、早く習熟する」ということを素直に受け止められるシニアが増えることが大事だと思います。
最近の若手は、企業において以前よりは権限を与えられるようになってきていますが、気になるのは「失敗を恐れる」傾向があることです。特に優秀な若手人材は、よい学校に入るために、成功し続けてきたという自負もあって、リスクを取ることに慣れていないように感じます。
問題は、教育が変わるのが一番遅いということです。今でも「偏差値が高い学校に行くために受験に勝てる教育指導をがっちり行います」という学校が多くあり、そういう学校が人気でもあります。
でも、実は私は若い人たちのことはあまり心配していないんです。確かに今は保守的で失敗を恐れているように見えても、すぐに変わると思うんですよ。楽しいことをやっている人が出てきたり、面白い「ゲーム」に参加したりすることで、どんどん変わっていくと思います。
実際、最近は受験エリートのような若者の中にも「最初から自分でベンチャーを起こす」とか「聞いたこともない海外企業に行く」という選択をする人が増えています。そういう人たちを見て「自分もそっちのゲームに参加した方がいいかも」と思う瞬間が20代のうちに来るんじゃないかと期待しています。

教育と社会の変革
教育の話が出ましたが、確かに教育現場はすごく保守的ですよね。私も大学教育に多少関わっていますが、「大学でデジタル人材育成を強化します」と言われても、正直「かなりハードルは高いだろうな」と考えてしまいます。
そうですね。高校生や中学生の「デジタル教育」なんて言いますが、実はそんなに必要ないかもしれません。子どもたちは学校で教えてもらわなくても、自分で勝手に学んでいくと思うんです。
そうですね。若い世代の中には、デジタル技術やAIに対する適応力が高く、自発的に新しいことに挑戦している人たちが増えていると思います。政府としても、そういった若い人材の力を活かせるような環境づくりを進めていく必要があります。
今の子どもたちの多くは、私たちが想像もしていない職業に就くでしょうし、必要になれば自分でどんどん学んでいくと思います。
ただ、社会全体としてのエントリーレベル、つまり「デジタル技術やAIを使い始める最初のハードル」をどう下げるかは大事な課題だと思います。
最後に
本日はデジタル人材育成の現状と課題について、様々な角度から議論してきました。日本型雇用の強みと限界、生成AIがもたらす変革、若手人材の活用、そして教育の課題まで、幅広いテーマを扱いましたね。
そうですね。これからの時代に必要なのは「走りながら学び続ける力」「失敗を恐れずチャレンジする姿勢」「若手の力を活かす組織文化」だと思います。そういった変化を後押しする政策を進めていきたいと考えています。
私も同感です。日本企業や社会が変わるのはこれからだと思います。生成AIの登場をきっかけに、ビジネスモデルや働き方、学び方が大きく変わる可能性があります。特に中小企業や若い世代に大きなチャンスがあると思いますので、ぜひ積極的にチャレンジしてほしいですね。
ありがとうございました。日本社会全体で「変化を楽しむ」マインドセットを育て、これからも日本の人材育成とデジタル変革について考え続けていきたいと思います。本日はありがとうございました。
本鼎談では、日本の人材育成やDX推進の現状と課題、そしてこれから求められる人材像について、現場感と政策の両面から議論。
そして「学び直し」や「失敗を恐れないチャレンジ精神」「若手の活用」「アジャイルな学び」が、これからの日本社会にとって不可欠であることが、三者の共通認識としてしめくくられた。