調査概要
Ⅰ.企業経営者・個人事業主向けアンケート調査
(1)調査方法
| 調査対象 |
調査会社に登録している20歳以上のインターネットモニター |
| 調査票回収数 |
・プレ調査数:131,286名
・借入経験者: 1,117名 |
| 調査方法 |
インターネット調査法 |
| 調査期間 |
平成21年1月5日~1月13日 |
| 調査主体 |
日本貸金業協会 企画調査部 |
| 調査機関 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 |
(2)調査目的
| プレ調査 |
事業資金を貸金業者から借りている経営者・個人事業主、及び個人としての借入を事業資金に転用している経営者・個人事業主の抽出 |
| 借入経験者 |
借入れ経験がなければ回答できない項目に関する調査 |
(3)標本構成:職業・年商・事業形態・資本金
当該調査対象者の事業形態構成では、個人事業主55.3%、会社法人32.1%、その他12.6%となっており、うち会社法人については、資本金2,000万円未満の企業が80%を占める。
【標本構成 / 職業・年商・事業形態・資本金(会社法人のみ)】
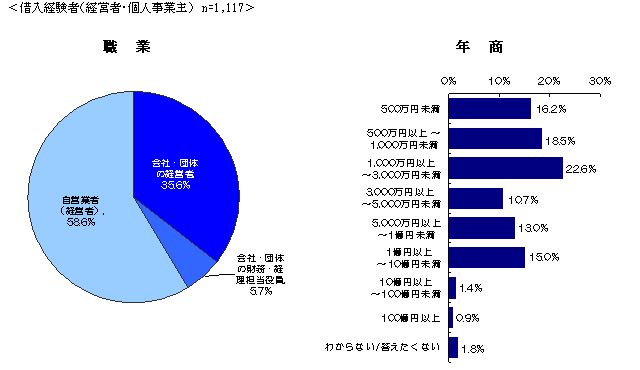
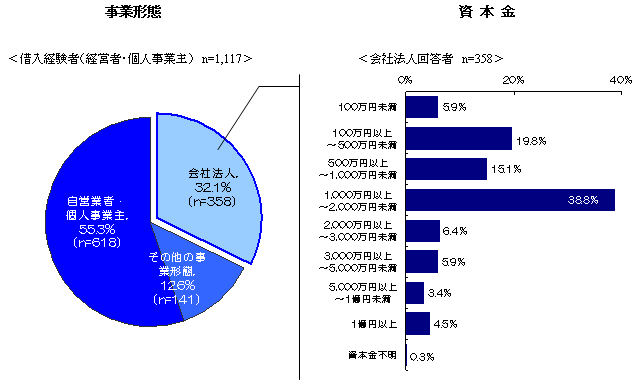
Ⅱ.消費者向けアンケート調査
(1)調査方法
| 調査対象 |
調査会社に登録している20歳以上のインターネットモニター |
| 調査票回収数 |
・プレ調査数:119,042名
・借入経験者: 3,177名 (内843名が現在残高のある「借入利用者」)
・一般消費者: 3,329名 |
| 調査方法 |
インターネット調査法 |
| 調査期間 |
平成20年11月21日~12月2日 |
| 調査主体 |
日本貸金業協会 企画調査部 |
| 調査機関 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 |
(2)調査目的
| プレ調査 |
消費者金融会社、クレジットカード・信販会社等からの借入経験者、ヤミ金融等非正規事業者からの借入経験者の抽出 |
| 借入経験者 |
借入れ経験がなければ回答できない項目に関する調査
|
| 一般消費者 |
借入れ経験の有無にかかわらず、比率を把握できる項目に関する調査 |
(3)標本構成:個人年収別
当該調査においては、専業主婦を中心とした無収入層も調査対象とした。
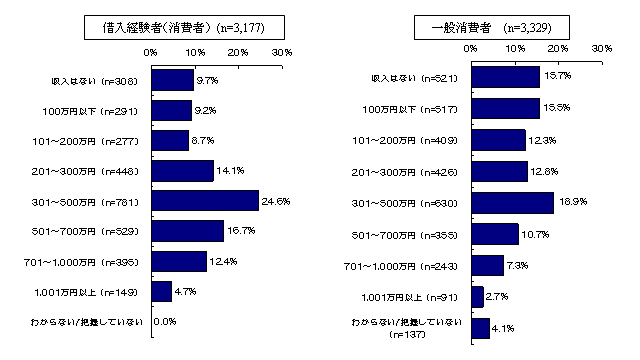
| (注1) |
一般消費者のサンプル抽出については、H17国勢調査結果を利用して、性別、年代、居住地域(9地域)別の20歳以上の人口割合に基づいた割付を実施 |
| (注2) |
収入はない(借入経験者n=308・一般消費者n=521)の内訳では、専業主婦の占める割合が、借入経験者80%、一般消費者76%となっている。 |
調査結果
(1) 事業資金の借入先
企業経営者・個人事業主に対して、事業資金の借入先を尋ねたところ、「銀行」が54%で最も多く、次いで、「信用金庫・信用組合」(34%)、「日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫)」(31%)という順になった。
「貸金業者」は13%で一定の比率を占める結果となったが、資本金2,000万円未満の中小企業(個人事業主を含む)では16%、個人事業主では23%となるなど、事業規模が小さくなるほど、「貸金業者」からの借入比率が高くなる傾向にあることが分かった。
【図1 事業資金の借入先】
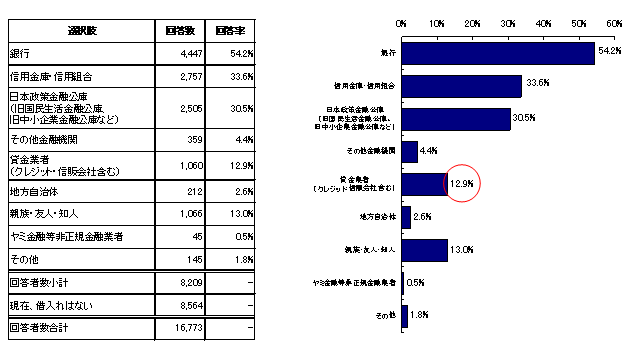
(注)重複回答があるため、回答数と回答者数小計・合計は一致しない
【図2 事業資金の借入先/資本金2,000万円未満の中小企業、個人事業主】
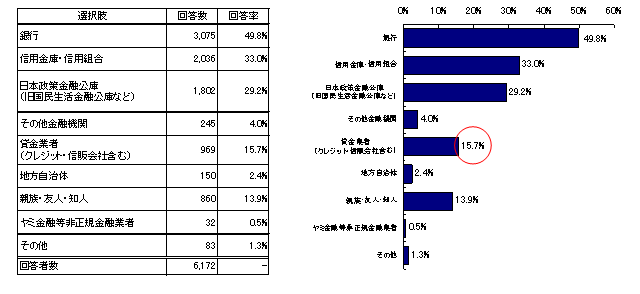
(注)重複回答があるため、回答数と回答者数(合計)は一致しない
【図3 事業資金の借入先/個人事業主】
(注)重複回答があるため、回答数と回答者数(合計)は一致しない
(2)担保・保証人の有無
業態毎に事業資金の借入がある企業経営者・個人事業主に対して、担保・保証人の有無(※1)を確認したところ、銀行からの借入は「無担保・無保証」が43%、「担保なし・保証人あり」36%、「担保あり」が30%という結果になった。
貸金業者からの借入は、「無担保・無保証」が74%と圧倒的で、「担保なし・保証人あり」13%、「担保あり」が7%であった。
また、貸金業者を利用している企業経営者・個人事業主に対して、なぜ貸金業者を利用しているのか、その理由を尋ねたところ、「無担保で借入ができたから」が60%で最も多く、次いで、「手続きが簡単だから」(56%)、「保証人を立てる必要がなかったから」(54%)が続く結果となった。
(※1)代表者の個人保証は除く
【図4 業態毎の担保・保証人の有無】
【図5 貸金業者の利用理由】 (n=518)
(3)直近1年間の融資姿勢
企業経営者・個人事業主に対して、業態毎に直近1年間の融資姿勢を尋ねたところ、銀行の融資姿勢が、「大変厳しくなった」「厳しくなった」と回答した比率は、合わせて46%となり、「非常に緩和した」「緩和した」の6%を大きく上回る結果となった。
貸金業者についても、銀行の比率は下回ったものの、「大変厳しくなった」「厳しくなった」が32%で、「非常に緩和した」「緩和した」の7%を上回る結果となった。
【図6 業態毎の直近1年間の融資姿勢】
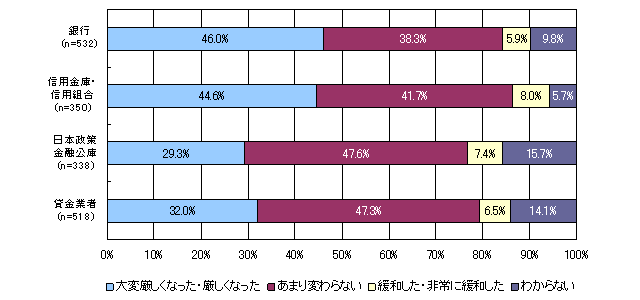
(4)事業資金の借入に関する優先順位
貸金業法改正によって、上限金利の引下げやさらなる融資姿勢の厳格化が予想される中、企業経営者・個人事業主にとって、最も優先度が高いのは、「これまで通り必要額の融資を受けられ、かつ、金利は従来よりも下がる」という回答であった。次に優先度が高いのは「借入額が従来通り確保でき、金利も従来通りの水準」で、業法改正により、今後、「金利は従来より下がるが、借入額も減少する」状況が想定されるものの、企業経営者や個人事業主が考える優先順位では、「金利」よりも「借入額」が上回る結果となった。
【図7 事業資金の借入に関する優先順位】 (n=518)
(5)個人の資金繰りが事業の資金繰りに与える影響
個人での生活資金名目等での借入を事業資金に転用したことのある比率は22%、過去に転用したことのある経験者も含めると、約4割が個人での借入金を事業資金に転用したことがある結果になった。
また、仮に、現在の借入先を含め、個人として生活資金名目等で一切の借入ができなくなったと仮定した場合の、事業の資金繰りへの影響を尋ねたところ、58%が影響あり(支障がある)と回答しており、個人の資金繰りが事業の資金繰りにも大きな影響を与えていることが分かった。
【図8 個人での借入を事業資金に転用したことのある企業経営者・個人事業主】
【図9 個人の借入が一切できなくなった場合の事業の資金繰りへの影響】(n=1,117)
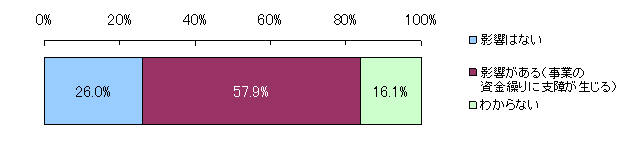
【図10 個人の借入が一切できなくなった場合の事業の資金繰りへの影響
/資本金2,000万円未満の中小企業、個人事業主】(n=903)
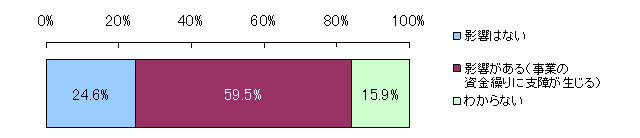
(6)総量規制の影響
借入総額の年収に占める割合を確認したところ、消費者金融会社から借入のある回答者の44%が、年収の1/3を超える借入がある(総量規制に抵触している)ことが判明した。
職種別では、「経営者・個人事業主」や「主婦」が、既に年収の1/3を超えた借入を抱えている比率が高く、業法改正4条施行により総量規制が導入されると、総量規制抵触者は、借入枠内での反復利用も含め、追加での借入ができなくなる可能性があるため、特に、「経営者・個人事業主」に関しては、事業の資金繰りへの影響も懸念される状況であることが分かった。
【図11 消費者金融利用者(現在残高あり)の総量規制抵触割合】
【図12 総量規制抵触者の職種別割合】
(7)貸金業法改正の認知状況
貸金業法の改正について、「内容も含めて良く知っている」「ある程度は知っている」は合わせて21%にとどまり、「内容を理解していない」「改正を知らない」「貸金業法を知らない」という回答が約8割を占める結果になった。
回答者を現在借入残高のある方に限定しても、「内容を含めて良く知っている」「ある程度は知っている」は合わせて40%にとどまった。
また、「内容も含めて良く知っている」「ある程度は知っている」と回答した回答者に具体的な項目について確認したところ、85%の回答者が「上限金利が利息制限法の金利に引き下げられる」を選択した一方、その他の項目(総量規制、収入証明の提出、信用情報機関への登録等)は、12%~38%にとどまる結果になった。
法改正の認知状況については、企業経営者・個人事業主に対しても同様の調査を実施したが、全般的に認知が進んでいないという傾向に変わりはなかった。
【図13 貸金業法改正の認知状況/一般消費者】
【図14 貸金業法改正の認知状況/借入利用者(現在残高あり)】
【図15 改正項目別の認知状況】(n=334)
【図16 改正項目別の認知状況/企業経営者・個人事業主】
以上
|

