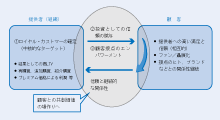顧客ロイヤルティとマネジメント 第1回
顧客ロイヤルティとマネジメント
|
|
顧客ロイヤルティとマネジメント
「顧客満足(CS)から顧客ロイヤルティへ(生産財を中心にCS経営を考える)」を3回に分けて論じたなかで、既存顧客を中心に顧客関係性の深化として顧客ロイヤルティについても触れてきた(※1)。
企業経営において、CSだけでなく顧客ロイヤルティが大事と言われる一方で、「具体的に何をすればよいのか?」という疑問から、「お客さまに忠誠を求めるとは失礼だ」という誤解まで、さまざまなご指摘を受ける。さらには、「顧客ロイヤルティは(CSスコア同様に)測定可能なのか」、「顧客のLTV(ライフタイムバリュー)を見ておけば良いのか」等々の疑問が出されることもある。そのなかで最も現実的で多いものが、「大事であることはわかっているし、正しい目標方針だと思うのだが、実際にはうまくいかない」との悩みである。
図表1:顧客ロイヤルティの一般的概要
出所:嶋口,四條他著“顧客ロイヤルティの時代”(同文舘出版)における嶋口充輝慶大名誉教授の見解およびディスカッション等をもとに筆者作成 |
そもそもマーケットが伸長する成長経済下では、既存顧客内に新たな事業機会が生じるし、また新規顧客の獲得機会も多い。そこではシェアを争う「戦争型」の妥当性が高いとも言えるが、成熟経済下では既存顧客との関係性を指向する必要性が高まってくる(※2)。 関係性を指向した結果、深く長く付き合うことができる(心許せるような)強固な関係が理想的であるとするならば、そういう想いを持つ同士になることがロイヤルティ指向の要諦ということになる。
そのような強固な顧客との関係性(良質かつ長期的なもの)を形成し、実際にうまくいくようにするためには、企業として明確な方針だけではなく、さまざまなマネジメントの仕組みが必要になる(図表1)。本稿でも生産財を中心に据えつつ、一部で消費財にも触れながら、論じていくことにしたい。
※2 上記連載第一回記載。戦争型と恋愛型のアナロジーは嶋口充輝慶大名誉教授による
売上利益は顧客ロイヤルティ指向の結果である
顧客との良好な関係性を追求することは、顧客接点での満足を指向して、それらを積み重ねていくことが「必要条件」になる。そのような条件を満たすことが、タイムラグがあるとしても、結果をもたらすことに気づく企業も増えてきていると思われる。
消費財の事例になるが、資生堂は2006年度に、顧客接点であるビューティーコンサルタントから売上ノルマを外し、同時に応対満足度評価を行うことにした。これはビューティーコンサルタントのミッションを、顧客に最適なカウンセリング(問題解決)を行うことに絞ったという意味であり、顧客満足とロイヤルティ醸成の中心を担うことになる。また筆者が実践してきた営業マネジメントの革新においては、生産財(特に資本財)の営業のカギは顧客の問題解決に役立つことである。その為営業担当者の売上ノルマを外して、組織として対応する仕組みを導入してきている(※3)。
つまり顧客ロイヤルティを大事にする指向は、顧客の中核的な課題を解決することに役立つことであり、その結果として(多くの場合)自社の製品サービスが売れるという結果をもたらすことになる。
そもそも顧客の問題解決に役立とうとすることは、生産財ではよく見られる活動であった。多くの場合、営業担当者が顧客に個別に相対して、時には本業から外れたサービスも提供してきた。顧客のことをよく知っていることを前提に、問題を身近に考え、顧客自身にとって最適になるように対応することが、結果として「損して得取れ」ということを可能にしていたのである(※4)。
※4 ただしこのような営業等の活動は、自分の顧客が求めることを自社内に通して便宜/融通をはかることと短絡してはならないだろう。営業と顧客がお互いのメリットで結び付いてしまい、社内のプロセスや他部門に横車を押すようなこと(いわゆるビッグクライアントの名を借りた「声の強さ」)を是認することは、会社として最適な組織的な関係性強化にはならない点に留意が必要である。
マネジメントの不整合が問題
それにもかかわらず、顧客ロイヤルティ指向が定着しないのは何故なのであろうか。例えば営業ノルマと顧客への最適な対応の両方を同時に強化しようとすることは、矛盾を営業担当個人に押しつけることにほかならない。前述のように、顧客にとって最適な問題解決に取り組めないならば、そのために営業ノルマを排除することも一つのマネジメントの考え方である。そこで、ロイヤルティ指向や活動がスポイルされる大きな要因は、マネジメントの不整合にあると筆者はみている。
問題を引き起こす不整合のうち、代表的なものは次のようなものである。
①顧客から選んでもらえる企業・商品サービスになることがすべてである
顧客から選択されるようになることが大事であり、自社が最初に顧客を選択するようなことは、もってのほかという考え方である。おそらく顧客を均一に扱わないことは差別的であって、関係性を強化したいターゲット顧客を選択することもよくないとの見方のようである。どのような顧客にもお客さまとして取り組ませていただくという構えは良いとしても、そのことと大事にしたい顧客がいることとは、本来は矛盾しないはずである。
そして顧客との関係は相互性がポイントになることからすれば、相手に評価されたからという受け身ではなく、まず自分がコアのターゲット顧客設定をして働きかけを開始するものではないだろうか。消費財の最寄り品などと異なり、とりわけ金融サービスや生産財では、顧客獲得と維持のコストが高いこと(つまり関係性は高コスト)から、売上利益に結び付きにくい顧客を多く抱えることは、経営上からも負担が大きくなってしまうのである。
② 顧客ロイヤルティを一律に評価したい
例えば現時点での売上利益の絶対額に基づいてコアのターゲット設定を行い、その顧客の顧客満足度の高さ等の指標を用いれば、顧客ロイヤルティを評価できると思われている場合がある。単一事業、顧客が限定的(同じ業界など)、製品ラインが狭いなどの場合は、妥当する場合もあろう。生産財(特に資本財)では、顧客の投資サイクルや提供する製品サービスの個別性が大きいことから、一律の見方を取ることは、現時点での高収益顧客の抽出とその満足の確認をすることにとどまってしまうであろう。顧客の業界特性・投資性向や競争状況などに応じて、柔軟にロイヤルティの状態を評価することが求められる(※5)。
③ 顧客ロイヤルティには唯一の測定方法がある
②の一律評価に対応するように、唯一絶対の計測基準がないかと聞かれることがある。そもそもCSスコアにしてもニュートラルで絶対的な設定はないと思っている。ロイヤルティはそれ以上に測定し難い。そもそもロイヤルティは、個別の顧客の相違を大事にして、相互の関係性を見ているため、一律の把握や唯一の測定は困難である。
④ 顧客ロイヤルティの向上をKPIによって、コントロールしたい
社内組織や従業員の活動について、KPI(重要業績評価指標)を最大化(最適化)することをもってドライブするように、顧客ロイヤルティもコントロールできないかと考えられることもあるようだ。そもそも顧客という相手あってのことである。商取引を介したさまざまな付き合いを通じて、自分たちが相手にどのように評価され位置づけられるのか、ということに関わるため、それを指標でドライブすることは極めて困難である(※6)。
※6 営業等の顧客接点にKPIとしてロイヤルティを定め、そのためのアクションを求めることは、特に短期的な評価に用いられる場合は問題が大きい
コアターゲットを大事にして満足と信頼を
顧客ロイヤルティを求めるマネジメントは、どのように考えれば良いだろうか? 次回以降で論じるマネジメント施策の前提として、いくつかの基本的な前提を押さえておく。
第一には、コアのターゲット顧客を明確にすることである。ターゲットが明確であることは、自社の製品サービスとその特徴が確立されていることを示す。同時にそれらと顧客の適合性を見ているということは、顧客を理解できていることを示している。例えば売上重視で非ターゲット顧客に対しても営業した場合、手離れが悪ければ結果的に収益に影響をもたらしてしまう。筆者は資本財の企業での顧客選択の一要素として、この「手離れが悪くないか」という基準を見ることがある。ターゲティング条件の一つに、顧客の能力が入ってくることもあり得るのである。付き合いが長い顧客、世間で見てビッグネームの顧客など、さまざまなターゲット顧客選択のバイアスがあるなかで、自社(事業)にとってコアとなるターゲット顧客を決め切れるのかということが、マネジメントの課題の一つとなるだろう。
第二に挙げられるのは、ターゲット顧客に対する信頼をもとにした「投資」を行えるかという点である。経営的には(特に短期的な収益管理からは)受注等に先行したサービス活動等の「投資」は無駄とみなされる懸念がある。短期的なリターンを求めることは、顧客関係性ではなく個々の案件受注営業の取り組みである。本来の顧客営業では、案件に限定されない「サービス」(顧客の問題抽出など)を行うことが多く、それが信頼関係の基盤になっている。つまり顧客を信頼して「投資」を行うことが、顧客内での自社への信頼と行動を生み出すことにつながっている(※7)。
顧客が何に「感応」して満足と信頼が醸成されて、関係性が長期に良い状態になっていくかという点については、さまざまな考えがあり、唯一絶対のカギ(働きかけ方)はないと見ている。それは顧客のなかで形成されるために、個別相違が大きいからである。しかし顧客に向けて自社から信頼し始めていくことは、有効に機能するものである。そして顧客内の信頼をもとに、取引が継続・拡大をしていくことによって、結果として計数上の果実が生じることになる。
ここでご参考までに図表2をご覧いただきたい。かつて個人向けの金融商品に関して、筆者は「満足度」と「活性度」の2軸から顧客をセグメンテーションし直して、クライアントにとってのコアターゲットと各セグメントに対する活動を切り分けた。もちろんその後には時系列での関係性軸が経年でついてくる。ここで満足度軸は、ほぼ同様の商品サービスを購買している顧客群の満足(離反せずに継続、再購買する)、一方で活性度軸は、自社の他商品サービスの追加購買をしてくれたか(くれそうか)、そして家族や知人等へ紹介を行う口コミの伝道師になってくれるか、といった複数の要因から見ている。これらのセグメンテーションごとに関係性の意識や売上収益への影響が異なるため、適切なリレーション評価を行い最適なコミュニケーション等の施策を打つことで、主ターゲットのみならず各セグメントのLTVの向上を実現したのである。
図表2:個人向け金融商品におけるターゲットカストマー例
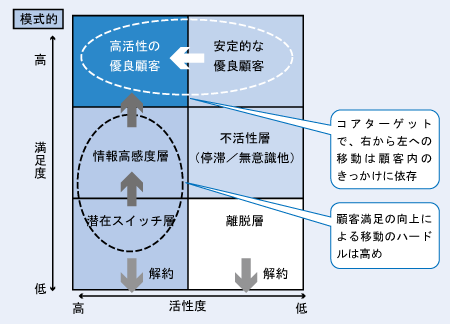 出所:筆者によるA社の顧客分析とマーケティング施策の実践に基づき作成 |
次回は、顧客への働きかけ(顧客最適化)と営業ノルマ(経営上の収益の要請)という要素をどのように統合するのか、そしてどのような価値を出していくのかという点を検討する。これらを営業担当等の個人単位で消化させるのではなく、企業組織としての仕組みで対応することは、マネジメントの課題そのものになる。