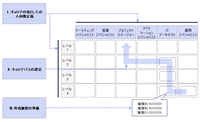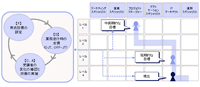変化に対応するキャリア・ディベロップメント・プログラム(CDP)とは 前編
社内CDP制度の特長とは何か
|
|
1.グローバル化をはじめとした劇的な環境変化の中で、社員を持続的に成長させるには
日本における景況は持ち直してきつつあるものの、企業にとって、また個人にとって、この持ち直しは「以前と同じ状況」へ戻る道では決してないことは、昨今のグローバル化の流れを見ても自明であろう。製造業をはじめとして、工場の移転(国内外とも)や、業務の海外化はますます加速している。また、M&Aを通じた事業拡大や、逆に事業の撤退なども急激に進んでいる。このような事象を個人(社員)に置き換えると、これまで国内で従事していた仕事が、急に外国で行う仕事にとって変わる、あるいは自分のキャリアの柱と考えていた業務が、企業から必要とされなくなる、といったことが加速的に、かつマクロ的に起こっているのである。
このような状況下で、個人(社員)の流動化は(自発的だろうが、そうでなかろうが。また社内的にも、社外的にも)ますます進むだろう。少なくとも経験を積んだ社員が退職してしまうということは、一時的には企業にとってダメージとなる。社内における配置転換は、育成や社員の志向を考慮できずに実施してしまうと、結果として社外への流動化の引き金になりかねない。
それでは、グローバル化をはじめとした劇的な環境変化の中で、企業力を維持しながらも、社員を引きとめ、かつ個人(社員)が活躍するために、企業はどのような点を考慮すべきであろうか。
本稿では前編・後編の全2回シリーズで、筆者が長年取り組んでいるキャリア・ディベロップメント・プログラム(Career Development Program)を根底とした社内制度の活用による、アプローチを考えてみたい。
前編ではこれまでの日本における社内CDP制度について、後編では社内CDP制度の活用を阻む2つの限界と、限界を超える「変化に対応する社内CDP制度」について述べる。
2.これまでの社内CDP制度
そもそもCDP(Career Development Program)とはどのような意味合いかを今一度整理したい。株式会社野村総合研究所『経営用語の基礎知識』 によれば、CDPとは「従業員の能力を長期的な計画に基づいて開発するシステム・プログラム体系のこと」と定義される。社内制度として実施する場合は、特に配置(ローテーション)を重視した内容が多いが、定義自体も利用するものによってさまざまに解釈されている。
キャリア理論の内容や歴史については本稿では詳細は記さないが、少なくとも近年の日本企業によるそれ(社内CDP制度)は、2つの側面を持って運用されてきたように思える。1つは個人(社員)のキャリア意識に企業として応えるため仕組みとして、2つ目はOJTとの連携をより強化した育成の仕組みとしてである。
1つ目(個人“社員”のキャリア意識への対応)については、グローバル化をはじめとする経済環境の変化の中で、個人の将来が展望しにくくなり、自分のキャリアを企業任せにはできない状況に陥ったことによって生じた、「個人のキャリアに対する不安」に対しての企業としての返答である。「自社内のみならず、業界全体でも通用する価値のある人材に育つ」ことを目的とした社内CDP制度の運用により、個人は自己のキャリア形成との相乗効果を認識し、育成に対してより動機付けることが可能となった。IT業界であれば業界スキル標準であるITSS(ITスキル標準 Skill Standards for IT Professionals)を軸にした社内CDP制度の導入がそれに当たる。
2つ目(OJTとの連携をより強化した育成の仕組み)は、個人のキャリアに対する意識が醸成されてきたことに加え、企業も「社員のプロ化(自律化)」を目指すために、人材育成のエンジンとして社内CDP制度を活用してきたということである。従来の階層別研修(新入社員、若手・中堅社員、管理職、役員)では対応が難しかった「業務における実践的な専門性」に力を入れることで、社員のキャリア意識とリンクする形で人材育成を運用することが可能となった。また、より実践的な専門性に主眼を置いたことから、「プロ(現場)がプロ(現場)を育てる」といった気運が芽生え、結果として育成制度全体の集中と選択(対象者についても、コストについても)が行われた。また、社員のプロフェッショナル度を測る軸が専門的なスキル寄りになったことから、企業としては(結果的に)要員管理がしやすくなったという側面は否めない。
これらの背景をもとに進展してきた社内CDP制度ではあるが、人事制度上の変化(職能から役割や成果へ)、雇用の流動化(終身雇用の崩壊、中途採用の活発化、早期退職などの取り組みの実施)も促進要因であったと考える。いずれにしても大きなパラダイムシフトの中で生まれた仕組みであることは間違いないだろう。
3.一般的な社内CDP制度の構造(設計)
さて、上記のような背景・目的から誕生した社内CDP制度について、実際の構造を簡単に解説する。なお、社内CDP制度は個社ごとに固有であるものが多く、今回は総じて共通項となると思われる要素のみを一般化して記載していることをご了承いただきたい。
Ⅰ.キャリアの柱としての人材像の定義
目指す姿として定義される人材像は、幾つかの人材像の定義と、そのレベル段階で表される。目指す姿は、汎用的な職種タイプとして表される場合が多いが、導入企業のバリューチェーン(価値連鎖を伴う企業活動)を網羅することが望ましい。
レベルの違いを表す「ものさし」は、それぞれの企業における育成段階として論じられることが多いが、具体的にはスキルや役割、コンピテンシーなどが盛り込まれる。一般的にはキャリアフレームと呼ばれている。
レベルを決める「ものさし」の具体的な要素として何を用いるべきか、が議論になることも多いが、社員の多様な能力を段階化するに当たって、経験やスキル、知識など幾つかの要素を複合的に盛り込むケースが多い。
ただし、複数の要素を盛り込む場合の弊害も認識しておくべきで、人材像に帰結して整合性を取ることが難しくなったりすることもある。
いずれにしろ原則としては、企業が人財開発として注力している要素や、ビジネス上の訴求力となる要素が盛り込まれているべきである。
Ⅱ.キャリアパスの設定
キャリアフレームの上位レベルに上がるために必要な経験やスキルなどを、キャリアフレーム上で定義する。これが実際のローテーションや、体系的な研修計画のベースとなる。このキャリアパスは決して垂直に一直線で上がるだけではなく、実際には横の経験を積む中で軸としての人材像に近づく場合もある。具体的には既に活躍している人材の過去の経験などを参考に作成することも多い。
キャリアパス設計時に、実際の配置先(組織や担当)を見越したローテーションパスを設定するのか、それとも能力開発の段階論として、スキルや経験のパスのみを設定するのかということが論点として挙げられることも多い。しかし、実際には各組織・担当を意識しながら配置を実施するにしても、組織変更や担当変更などの変動要素によって社内CDP制度を都度変更しなくてもよいように、まずは能力開発の段階として、スキルや経験のパスのみを設定しておくほうが、柔軟性が増すだろう。
Ⅲ.育成施策の準備
次に、キャリアパスに沿って、上位レベルに上がるために必要な経験やスキルなどを、どのように身につけるかを定義する。実際には育成施策(研修等)の準備であり、キャリアパス上に育成施策が充実することによって、「体系的な育成」を行うことができる。
施策内容は知識研修にとどまらず、経験や行動変容を促すような施策も含めるべきであろう。単なる能力開発ではなく、キャリア開発としての総合力が社内CDP制度の特長とも言える。
4.一般的な社内CDP制度の構造(運用)
次にその運用方法について見てみたい。基本的には各施策を受講したことによって、受講者に期待していた効果が現れたかをモニタリングすることで、本人に適切な動機付け(次のステップへ進むための施策や、改善点を補強する施策の受講)を行い、かつ社内CDP制度や各育成施策の改善をしていくことが求められる。これらの運用の流れを、改善サイクルであるPDCAに沿って整理してみたい。
Ⅰ.【P:育成目標の設定】
まずは育成目標を設定する所からすべてが始まると言っても過言ではない。目標を明確に意識付けできないままの研修受講は、結果として多くの気づきを生まず、やらされ感すら漂ってしまう。個人単位で考えるのであれば、本人の前年度評価や長期的な育成計画に照らし合わせて短期的な育成目標を設定することが望ましい。また、全社単位で考えるのであれば、人材像ごとに特に顕著な育成課題を抽出し、その強化・補強を短期的な目標として設定することも必要である。
いずれにしろ上記は、キャリアフレーム上のキャリアパスに沿って全体計画が実行されている上での目標設定であることに留意いただきたい。
Ⅱ.【D:業務遂行時の支援(OJT、OFF-JT)】
育成目標にしたがい、必要な施策を受講していくことになるが、3.のⅢでも述べたように、施策は単なる知識研修にとどまらず、個人のキャリア開発を総合的に担保できることが望ましい。よって、より業務遂行に密接な施策(OJTの補強)なども含めて用意し、実施できる環境が望ましい。
Ⅲ.【C、A:受講者の変化の確認と改善の実施】
受講者の変化を確認する理由は幾つかあるが、全般的には以下3つの目的のためと考えられる。
(1) 受講者の次の育成目標を設定するため
(2) 施策の改善を行うため
(3) 社内CDP制度自体の改善を行うため
(1)については、受講者の次の育成目標を人事や上長が確認するために、個別施策の理解度のみならず、総合的な個人の成長度合いを測ることが望まれるが、そのために、キャリアフレーム上の上位レベルに到達できたかどうかを確認する運用がなされている。 多くの企業でこの行為が「資格認定」や「アセスメント」として行われている。また、人事評価と関連付けている企業では「評価」そのものが個人の育成の到達度を測るものとなっている。
(2)については、施策の目的に応じた受講者への効果の度合いを確認する必要があるが、実際問題としてそのような確認は難しい。例えば、知識研修ではなく、受講者の行動変容を求めるもの(OJTと密接した施策等)などはその類だろう。このような研修については研修終了後に一定期間をおいてフォロー研修を行い、業務において期待する行動が取れているかを確認したり、上司等に事後ヒアリングを行ったりする例も多い。
(3)については、上記2点の他、各人材タイプにおける上位レベル到達率や、各人材タイプの志向度の分布などを総合的に判断して、キャリアフレームの構成要素(人材タイプ、レベル、内容)を変更していくことが必要となる。
以上、前編では社内CDP制度の背景・目的や、その構造を、制度面・運用面から述べた。後編では社内CDP制度をうまく活用するために気を付けたいポイントを、幾つかの阻害要因から考えてみたい。
|