(「月刊マーチャンダイジング」2014年3月号より)
チェーン本部 管理体制高度化のヒント
できる!管理部門カイゼンのすすめ
「販管費削減」と「店舗サポート力アップ」を同時に実現しよう
シニアコンサルタント 櫻田 隆司
はじめに
ある担当者の会話 担当A“あれ、○○さんは今どこの店舗にいるんだっけ?”
担当B“この間異動したはずだが、なかなか見つからないな...、探してくれない?”
本来、営業現場を適時適切にサポートするはずの管理部門。
どうしても営業現場(MD、接客等)の直接的・即効的なカイゼンが優先され、足元をすくわれない為の経営の土台づくり、営業からの要請に応える為の管理高度化、更なる競争激化に備えての管理効率化、まではなかなか手が回らないのではないだろうか。
しかしながら、管理の高度化・効率化による恩恵は大きいはずである。ここでその効果を販管費削減に絞って考えてみよう。仮に、売上100万円、営業利益率5%の状態から営業利益額を上げようとした場合、1万円(5ポイント)の販管費削減は、20万円の売上増に値する。(詳細下図)100万円の販管費削減では、2,000万円の売上増ということである。
ちなみに筆者の経験では、カイゼン対象範囲内で10~20ポイントの削減効果は出るものである。
[図表1]営業利益に対する売上と販管費
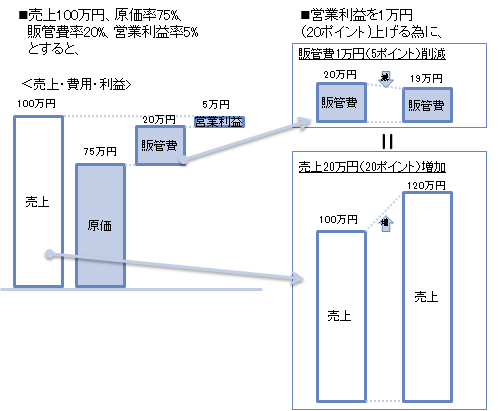
さらに、管理の高度化ということであれば、売上増という効果も期待される。
本稿では、筆者の他業界でのカイゼン経験を踏まえて、管理部門の高度化・効率化のための5つのヒントをご紹介する。
ヒント1(最重要)
カイゼン目的、解決方向性の整理 担当A“月次報告データは、項目数が多くて見にくいわりに欲しい切り口での分析がないよね。出てくるのも遅いしね。”
担当B“給与計算、交通費精算、その他の経理処理ではかなり手間がかかっているみたい。〆日には、やっと数字が合ったってホッとしていたよ”
担当A“問題が多すぎて、とても手が回らないよ”
意外に思われるかもしれないが、検討着手にあたり“何のためにカイゼンするのか” “どのような解決方法を想定しているのか”を整理しきれていないことが多い。
これが曖昧なままだと、思いつきによる枝葉の問題への対応、あれもこれもやろうとして結局頓挫、ということになりかねないため、まずは以下例のようなカイゼンの大方針を整理・決定・周知することが重要である。
[図表2]カイゼン目的の例
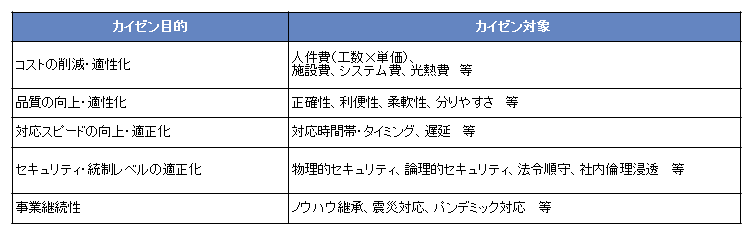
[図表3]解決方向性の例
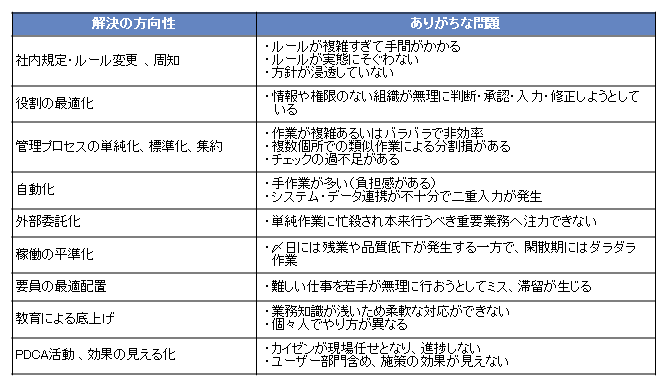
目的や打ち手を整理するにあたり、“優先すること”だけでなく“後回しにすること”を明確にしつつ、スコープを絞ることを強くお勧めする。
スコープを絞ることで、検討オーナーの決意“この範囲は絶対にやる”を示すとともに、“このテーマであれば○○さんが必要不可欠、逆に○○さんは要らない”と、検討適任者が明らかになる。
ヒント2
現状把握①(問題の大きさ) 担当A“月締め作業は大変大変と言っているけど、どの程度大変なの?”
パートC“測ってはいませんが、うちの部署は特別に忙しいんです”
現状把握を正しくできればカイゼンは殆ど終わったも同然である。かといって、つぶさに現状を把握しようとしても、労多くして功少なしである。
まずはカイゼン目的に応じて問題の大きそうなところに当たりをつけることで効率的な検討が可能になる 。
[図表4]大きい問題にあたりをつけるための観点例
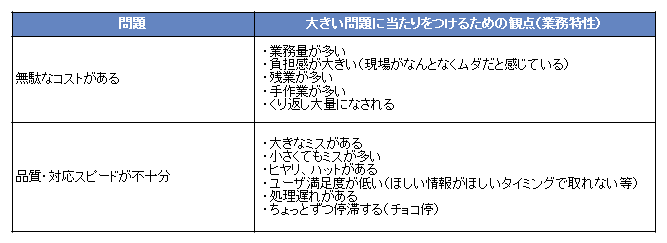
大きな問題の特定にあたり、印象に残った事象や直近の事象によって“思い込み”が発生しがちであるため、日誌、残業記録、トラブル報告、アンケート等からFACT情報を整理することが基本である 。
ヒント3
現状把握②(真の原因) 担当A“給与計算や交通費支給ってどうして〆日に混乱するの?”
パートC“いくら言っても○○さんがちゃんと仕事してくれないんです!”
問題の原因を知るためには、業務を知っている人と話す必要がある(必ずしも責任者ではない)が、業務を知っている人はその所掌範囲でしか原因をつかめていないことが多い。また、下手をすると個人攻撃に繋がる場合もある。
従って、真の原因にたどり着くためには、こちらから質問(仮説)をぶつけることが効果的。以下にその例を示す。
[図表5]ぶつける質問(仮説)の例
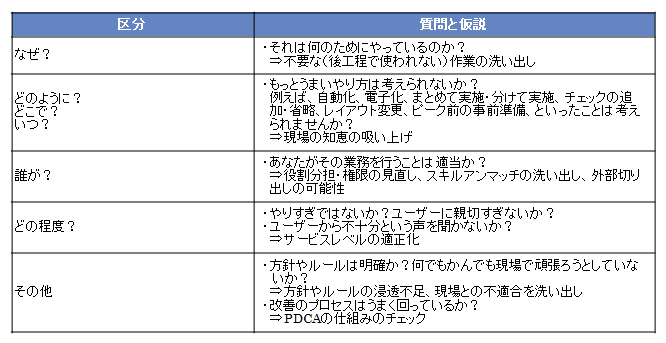
原因分析では、そもそも論から始めるトップダウン的な検討と現場からの知恵を吸い上げるボトムアップ的な検討をミックスさせると良い。また、現場に影響力のあるミドル層を巻き込むことで、以降で検討する打ち手が“絵に描いた餅”となることを防ぐ(後になって現場からそっぽを向かれにくくなくなる)。
ヒント4
打ち手の評価 担当A“原因毎にそれぞれ打ち手が考えられそうだ”
担当B“それにしても、実施すべき打ち手は多いな。本当にできるだろうか...”
原因毎に問題解決の打ち手が考えられたら、 似たような打ち手をひと括りにしたうえで、重要度・難易度・緊急度等で評価する。検討粒度にもよるが、筆者の経験では1部署での約1ヶ月の検討にて400近い打ち手案を導出し、その後数週間で10数個の有望な打ち手に絞り込んだたこともある。
[図表6]打ち手の評価軸の例
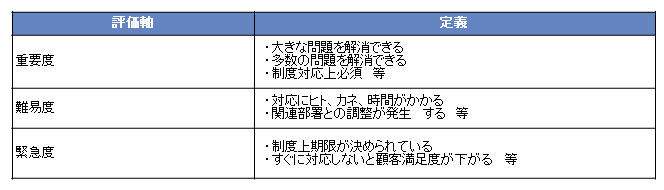
また、カイゼン検討する中で、すぐにでも実行できてしまうクイックヒットが出現するものである。
たとえ小さくてもクイックヒットを拾い上げ、成功体験へ繋げることで、現場がカイゼンへの親しみをもつことは非常に重要である。
掛け声倒れに終わるカイゼン検討を繰り返すと、現場は、“またか、どうせ何も変わらないし面倒くさい”と感じてしまう。
ヒント5
実行計画、実行、効果測定 担当A“打ち手は見えたけど、○○部との調整が難航しそうだ”
担当B“確かに理論派の○○さんを説得するには大変そうだ。”
有望な打ち手が見えたら、打ち手の順序性検討、実現性を見る為の机上検証・実地検証 等を行う。その中で、カイゼンを実行に移すための課題が見えてくるものである。
尚、大きなものだけでも打ち手の効果を測定できるようにしておくと望ましい。目的に立ち返って、カイゼン前の状態(生産性、品質等)を記録、カイゼン後の効果データを自動的に収集できるようにしておくことは重要 である。
最後に
筆者“些細な事ですが、○○すれば省力化できるのでは?”
責任者“確かにその通りだ。それにしても、そのレベルの話しであれば現場に気づいてもらいたいな...”
筆者“現場が気づくために、あなたは何をしていますか?”
カイゼンは、トップが“検討方針”を示すと共に、“真の原因”に対する現場の腹落ちができれば、さほど難しい活動ではない。特にこれまで手が回りにくかった管理部門のカイゼンであればなおさらである。但し、いきなり100点を目指すというよりも、小さなカイゼンの成功体験を積み重ね、1人でも2人でもカイゼンを楽しめる担当者が出てくることが重要と筆者は考える。
本稿が、カイゼン活動を楽しめるきっかけとなれば幸いである。
ちなみに、本稿で述べた5つのヒントは、店舗や物流等、直接部門のカイゼンにも使える。現場の最前線にいらっしゃる方へも参考になると筆者は確信している。

