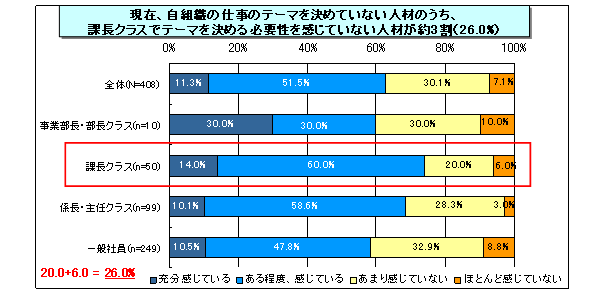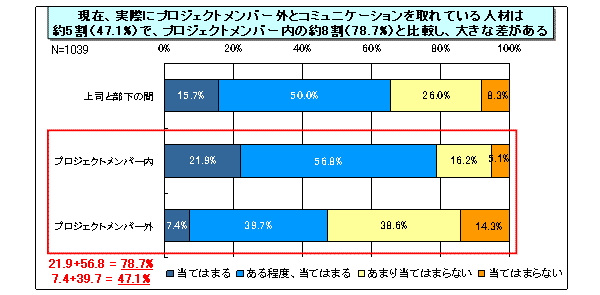調査概要
【補足】 (*2) 「評価レベル」は、あくまでも回答者の自己認識によるものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
調査結果
1. 「転職」についての意識1.1 転職志向◆ 現在、「転職を考えている」人材は約5割(49.1%)で、昨年より4.3ポイント増加現在、転職を考えているかを尋ねたところ、「転職を考えており、志望企業や人材仲介会社と接触している、または予定がある」(7.6%)と「転職を考えており、転職に向けた情報収集を始めている」(13.0%)、「転職を考えているが、具体的な行動は起こしていない」(28.5%)を合わせ、約5割(49.1%)が転職を考えていることが分かった。【図表1-1】またこの割合は昨年の44.8%よりも4.3ポイント増加している。(「IT人材のプロフェッショナル意識調査2008」のニュースリリースを参照) 【図表1-1】転職志向
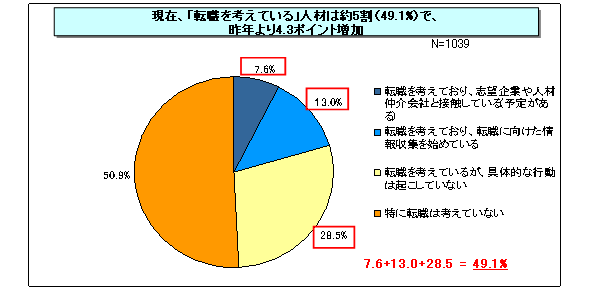 1.2 転職を考えている理由◆ 転職を考えている第一の理由は、「現在勤めている会社の先行きに不安があるため」が約5割(49.0%)転職を考えている人材に限って、転職を考えている理由を尋ねたところ、最も多かった理由は「現在勤めている会社の先行きに不安があるため」が約5割(49.0%)である。次いで「現在勤めている会社では、希望するキャリアを実現できないため」(24.5%) 、第3位として「IT業界のSIからサービスへのビジネス構造転換によるスキルの陳腐化への不安のため」(9.2%)となっている。【図表1-2】
【図表1-2】 転職を考えている理由
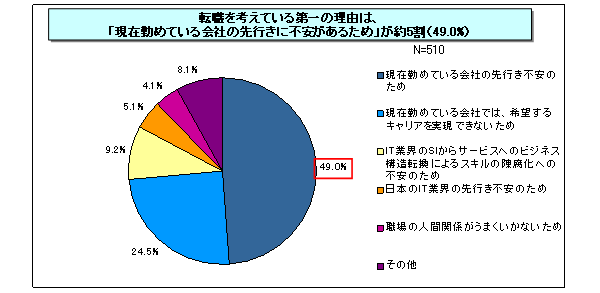 1.3 転職志向と個人年収の変化割合◆ここ1年間で個人年収が「15~20%未満減少した」人材のうち、「転職を考えている」人材は約7割(69.6%)。また「転職活動を始めている」人材は4割以上(41.3%)で、ここ1年間で個人年収が「10~15%未満減少した」人材の2割以上(23.3%)と比較し、約2倍ここ1年間の個人年収の変化割合を尋ねたところ、年収が「15~20%未満減少した」人材のうち、「転職を考えており、志望企業や人材仲介会社と接触している、または予定がある」(15.2%)と「転職を考えており、転職に向けた情報収集を始めている」(26.1%)、「転職を考えているが、具体的な行動は起こしていない」(28.3%)を合わせ、約7割(69.6%)が転職を考えている。 またここ1年間で年収が「15~20%未満減少した」人材のうち、「転職を考えており、志望企業や人材仲介会社と接触している、または予定がある」(15.2%)と「転職を考えており、転職に向けた情報収集を始めている」(26.1%)を合わせ4割以上(41.3%)が転職活動を始めており、「10~15%未満減少した」人材の約2割(23.3%)と比較し、約2倍である。【図表1-3】 【図表1-3】転職志向と個人年収の変化割合
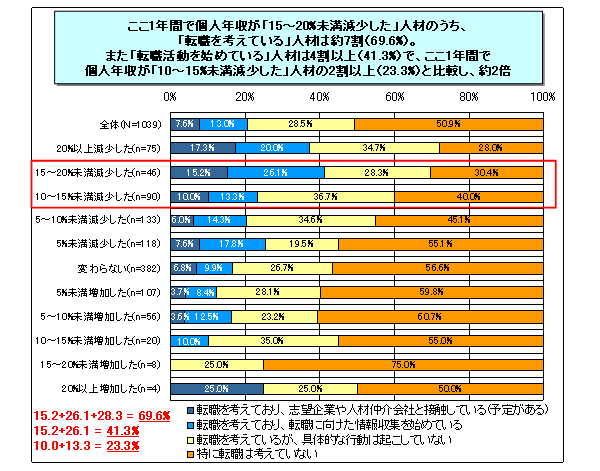 1.4 転職先として希望する業種◆転職を考えている人材のうち、転職先として「ITとは直接関係の無い異業種」を考える人材が3割以上(36.5%)で、昨年より6.5ポイント増加転職を考えている人材に限って、将来転職先として希望する業種を尋ねたところ、最も多かった希望は「ITベンダー」(51.8%)であり、次いで「情報システム部門(情報システム子会社含む)」(47.8%)とIT業界が第1、2位であったが、第3位として「ITとは直接関係の無い異業種」も3割以上(36.5%)の人材が選択肢に入れている。【図表1-4】またこの割合は昨年の30.0%よりも6.5ポイント増加している。(「IT人材のプロフェッショナル意識調査2008」のニュースリリースを参照) 【図表1-4】 転職先として希望する業種
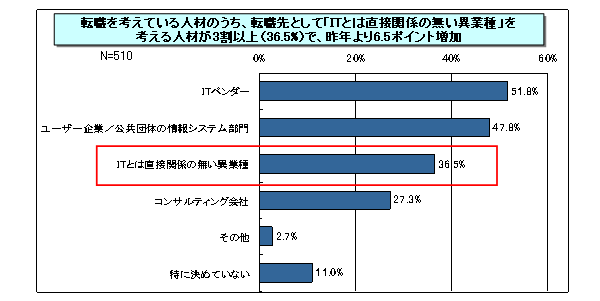
※「ITベンダー」・・・ システムインテグレーター/ハードベンダー/ソフトウエアベンダー/保守サービスプロバイダー 2. 「能力開発」 についての意識2.1 現在の能力発揮の度合◆現在、持っている能力を最大限「発揮できていない」と感じている人材が約4割(39.0%)現在、持っている能力を最大限発揮できているかを尋ねたところ、「ほとんど発揮できていない」(6.8%)と「あまり発揮できていない」(32.2%)を合わせ、約4割(39.0%)が持っている能力を最大限発揮できていないと感じている。【図表2-1】 【図表2-1】現在の能力発揮の度合
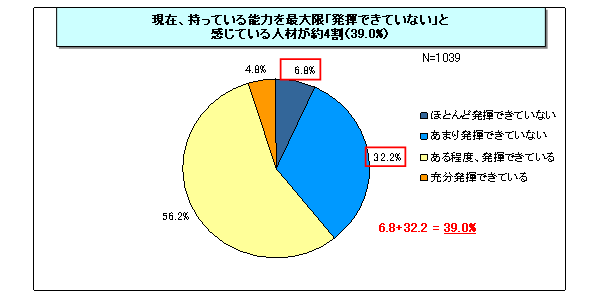 2.2 将来の能力発揮の可能性◆将来、更なる能力を「今の職場・仕事にて発揮するのは難しい」と感じている人材が6割以上(60.3%)将来、今の職場・仕事で、更なる能力の発揮ができるかを尋ねたところ、「今の職場・仕事でも会社内でも、更なる能力発揮は難しいと思う」(22.6%)と「今の職場・仕事では難しいが、会社内には更なる能力を発揮できる職場・仕事があると思う」(37.7%)を合わせ、6割以上(60.3%)が今の職場・仕事のままでは更なる能力の発揮が難しいと感じている。【図表2-2】
【図表2-2】将来の能力発揮の可能性
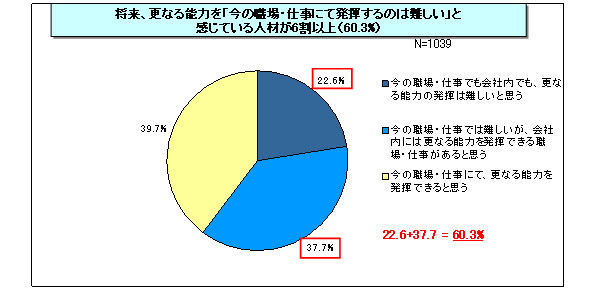 2.3 会社内での能力発揮の可能性◆「会社内に更なる能力を発揮できる職場・仕事がある」と感じている人材が約8割(77.4%)将来、今の職場・仕事で、更なる能力の発揮ができるかを尋ねたところ、「今の職場・仕事にて、更なる能力を発揮できると思う」(39.7%)と「今の職場・仕事では難しいが、会社内には更なる能力を発揮できる職場・仕事があると思う」(37.7%)を合わせ、約8割(77.4%)が会社内に更なる能力を発揮できる職場・仕事があると感じている。【図表2-3】 【図表2-3】会社内での能力発揮の可能性
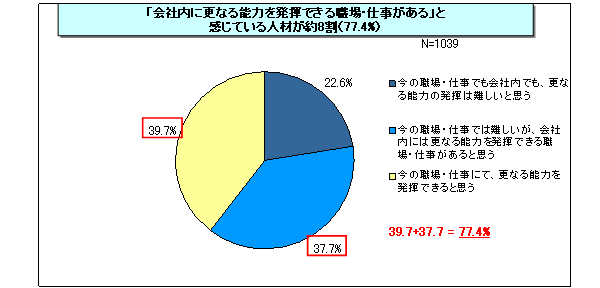 2.4 能力発揮を支援する環境◆会社内に更なる能力を発揮できる職場・仕事があると感じている人材のうち、「自分の趣向・特性にあった仕事をする」ことができれば、能力を更に発揮できると感じている人材が約5割(48.8%)会社内に更なる能力を発揮できる職場・仕事があると感じている人材に限って、将来能力を更に発揮できる環境について尋ねたところ、最も多かった希望は「自分の趣向・特性に合った仕事をする」が約5割(48.8%)であった。次いで「能力を引き出してくれる上司と仕事をする」(25.6%)、第3位として「連帯感を持てる職場で仕事をする」(23.6%)となっている。【図表2-4】 【図表2-4】能力発揮を支援する環境
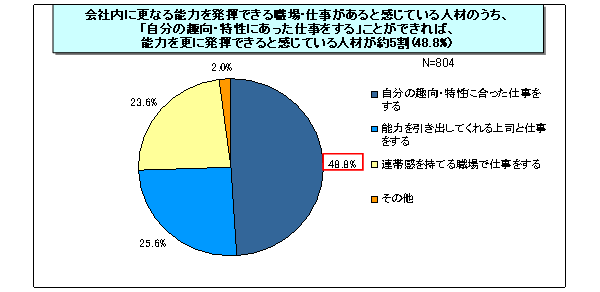 2.5 能力開発の効果◆現在、能力開発が充分「役立っていない」と感じている人材が5割以上(52.4%)現在、勤めている会社が行っている能力開発が充分役立っているかを尋ねたところ、「ほとんど役立っていない」(19.4%)と「あまり役立っていない」(33.0%)を合わせ、5割以上(52.4%)が役立っていないと感じている。【図表2-5】 【図表2-5】能力開発の効果
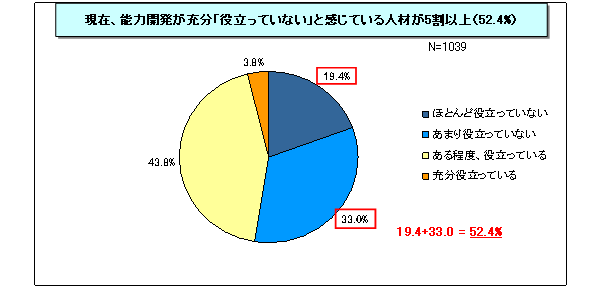
2.6 能力開発が役立っていない理由◆能力開発が役立っていない第一の理由は、「社内の異動が活発でなく、必要な経験を積めないため」が4割以上(40.6%)現在、能力開発が役立っていないと感じている人材に限って、その理由について尋ねたところ、最も多かった理由は「社内の異動が活発でなく、必要な経験を積めないため」が約4割(40.6%)であった。次いで「先輩等が仕事やキャリアについてアドバイスしてくれないため」(24.6%)、第3位として「仕事の細分化により、幅広い能力が身に付かないため」(22.8%)となっている。【図表2-6】 【図表2-6】能力開発が役立っていない理由
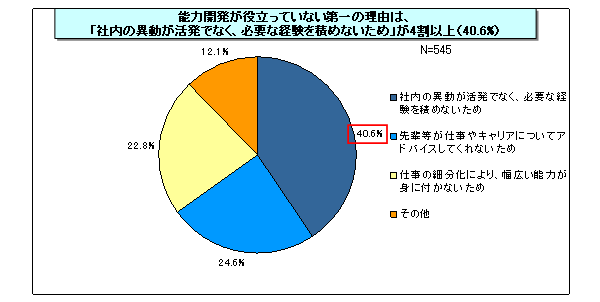 3. 「ワークモチベーション」 についての意識3.1 人員整理・解雇の現状◆ここ1年間で、勤めている会社で人員整理・解雇が行われた人材が約4割(36.0%)ここ1年間で、勤めている会社で人員整理・解雇が行われたかを尋ねたところ、「所属部門内、外の両方で行われたようだ、または行われている」(5.6%)と「所属部門内など、身の回りで行われたようだ、または行われている」(14.9%)、「所属部門以外の社内で行われたようだ、または行われている」(15.5%)を合わせ、約4割(36.0%)が勤めている会社で人員整理・解雇が行われた。【図表3-1】 【図表3-1】人員整理・解雇の現状
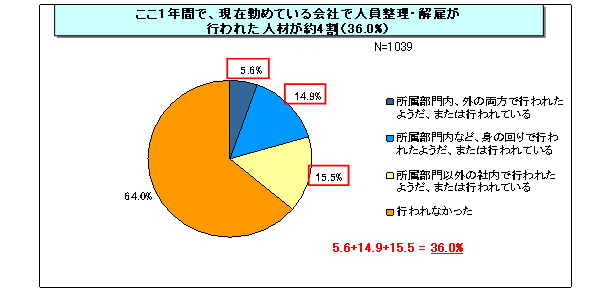 3.2 ワークモチベーションと人員整理・解雇◆人員整理・解雇により、ワークモチベーションが低下したと感じている人材が7割以上(75.4%)ここ1年間で、勤めている会社において人員整理・解雇が行われた人材に対して、それによるワークモチベーションの変化を尋ねたところ、「低くなった」(24.6%)と「どちらかといえば低くなった」(50.8%)を合わせ、7割以上(75.4%)の人材のワークモチベーションが低下したと感じている。【図表3-2】 【図表3-2】 ワークモチベーションと人員整理・解雇
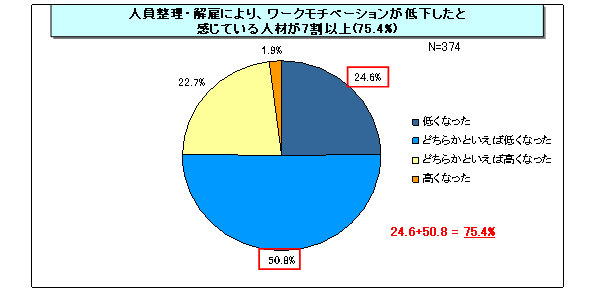 3.3 自組織の仕事のテーマ・実行方法の決定と役職◆現在、課長クラスで、自組織の仕事のテーマを決めていない人材は約3割(31.4%)で、係長・主任クラス(31.1%)とほぼ変わらない現在の仕事の進め方について、自ら自組織の仕事のテーマ・実行方法それぞれを決めているのか尋ねたところ、課長クラスについて見ると、「自ら、テーマは決めていないが、実行方法は決めている」(24.5%)と「全て上司の指示に従っている(自らでは、テーマも実行方法も決めていない)」(6.9%)を合わせ、約3割(31.4%)がテーマを自ら決めておらず、係長・主任クラス(31.1%)とほぼ変わらない。【図表3-3】 【図表3-3】自組織の仕事のテーマ・実行方法の決定と役職
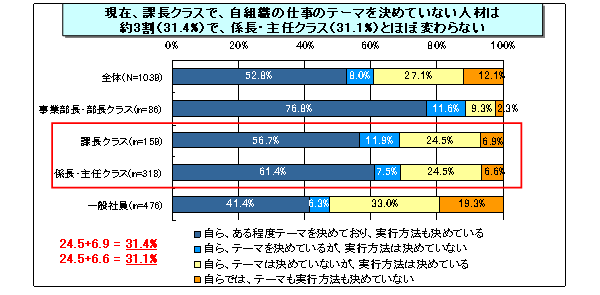
※「テーマ」・・・自組織にとって何をすればよいのか 3.4 自組織の仕事のテーマを決める必要性と役職◆現在、自組織の仕事のテーマを決めていない人材のうち、課長クラスでテーマを決める必要性を感じていない人材が約3割(26.0%)現在の仕事の進め方について、自らテーマを決めていない人材に限って、テーマを決める必要性について尋ねたところ、課長クラスについて見ると、「ほとんど感じていない」(6.0%)と「あまり感じていない」(20.0%)を合わせ、約3割(26.0%)の人材がテーマを決める必要性を感じていない。【図表3-4】 【図表3-4】自組織の仕事のテーマを決める必要性と役職
3.5 ワークモチベーションと自組織の仕事のテーマ・実行方法の決定◆現在、ワークモチベーションが高い人材は、「自ら、ある程度テーマを決めており、実行方法も決めている」人材が8割以上(84.6%)現在の仕事の進め方について、自らテーマ・実行方法それぞれを決めているのか尋ねたところ、ワークモチベーションが「高いと思う」人材について見ると、「自ら、ある程度テーマを決めており、実行方法も決めている」人材が8割以上(84.6%)となっている。これは「どちらかといえば高いほうだと思う」人材の6割以上(63.6%)、「どちらかといえば低いほうだと思う」人材の4割以上(42.0%)と比較して大きな割合である。【図表3-5】 【図表3-5】 ワークモチベーションと自組織の仕事のテーマ・実行方法の決定
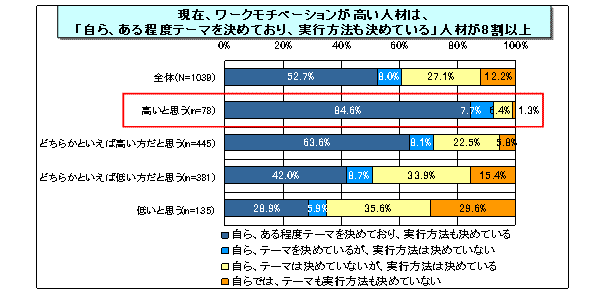 3.6 有能感◆自分を有能だと感じていない人材が4割以上(42.7%)これまでに、自分を有能だと感じたことがあるかを尋ねたところ、「ほとんど感じない」(6.6%)と「あまり感じない」(36.1%)を合わせ、4割以上(42.7%)の人材が自分を有能だと感じていない。【図表3-6】 【図表3-6】有能感
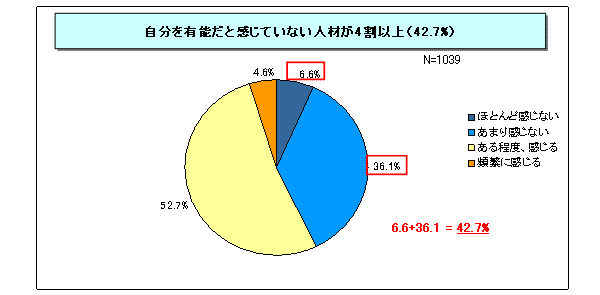 3.7 有能感を感じる場面◆自分を有能だと最も感じるのは、「顧客から評価された時」が約6割(56.5%)将来、どのような場面において自分が有能だと感じるかを尋ねたところ、最も多い場面は「顧客から評価された時」が約6割(56.5%)であり、次いで「自分自身で設定した目標を達成した時」(23.2%)、第3位として「上司から評価された時」(18.2%)となっている。【図表3-7】 【図表3-7】有能感を感じる場面
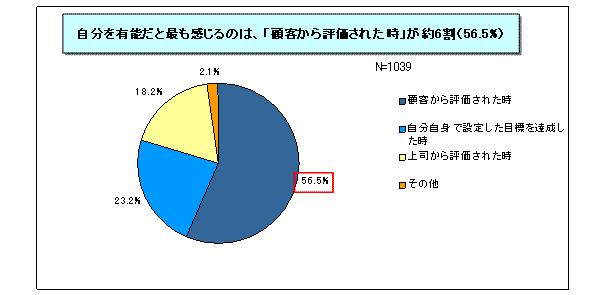 3.8 現在のコミュニケーションの度合◆現在、実際にプロジェクトメンバー外とコミュニケーションを取れている人材は約5割(47.1%)で、プロジェクトメンバー内の約8割(78.7%)と比較し、大きな差がある現在、上司と部下の間、プロジェクトメンバー内、プロジェクトメンバー外それぞれとコミュニケーションを取れているかどうかを尋ねたところ、プロジェクトメンバー外について見ると「当てはまる」(7.4%)と、「ある程度、当てはまる」(39.7%)を合わせ約5割(47.1%)の人材しかコミュニケーションを取れていないと感じている。これはプロジェクトメンバー内の約8割(78.7%)と比較し、大きな差がある。【図表3-8】 【図表3-8】現在のコミュニケーションの度合 3.9 コミュニケーションを取る必要性◆現在、プロジェクトメンバー外とコミュニケーションを取る必要性を感じている人材が8割以上(83.4%)現在、上司と部下の間、プロジェクトメンバー内、プロジェクトメンバー外それぞれとコミュニケーションを取る必要性を感じているかどうかを尋ねたところ、プロジェクトメンバー外について見ると「当てはまる」(34.6%)と「ある程度、当てはまる」(48.8%)を合わせ、8割以上(83.4%)の人材がプロジェクトメンバー外とコミュニケーションを取る必要性を感じている。【図表3-9】 【図表3-9】コミュニケーションを取る必要性
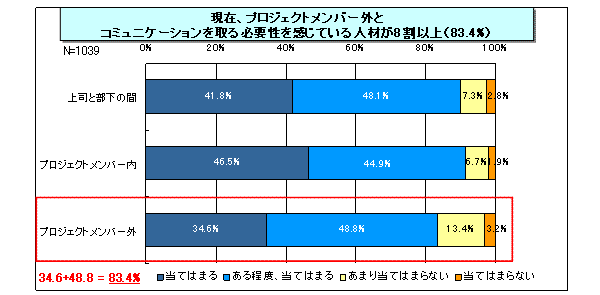 3.10 プロジェクトメンバー外とコミュニケーションを取りたい理由◆プロジェクトメンバー外とコミュニケーションを取る必要性を感じている第一の理由は、「業務効率化のため」が3割以上(33.7%)現在、プロジェクトメンバー外の人材とコミュニケーションを取る必要性を感じている人材に限って、その理由を尋ねたところ、最も多いのは「業務効率化のため」が3割以上(33.7%)で、次いで「いざというときに助け合える人脈構築のため」(28.1%)、第3位に「新しい知識やスキル獲得のため」(24.4%)となっている。【図表3-10】 【図表3-10】プロジェクトメンバー外とコミュニケーションを取りたい理由
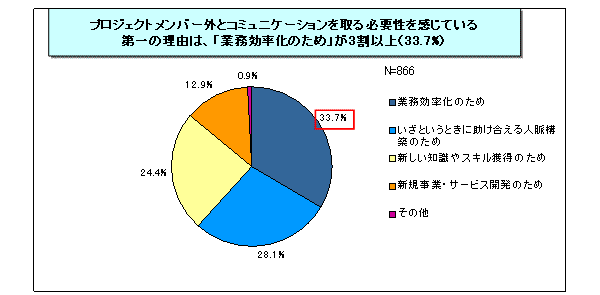
※「業務効率化のため」・・・プロジェクト経験等の共有による業務効率化と推察される 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在ご覧のページは当社の旧webサイトになります。トップページはこちら