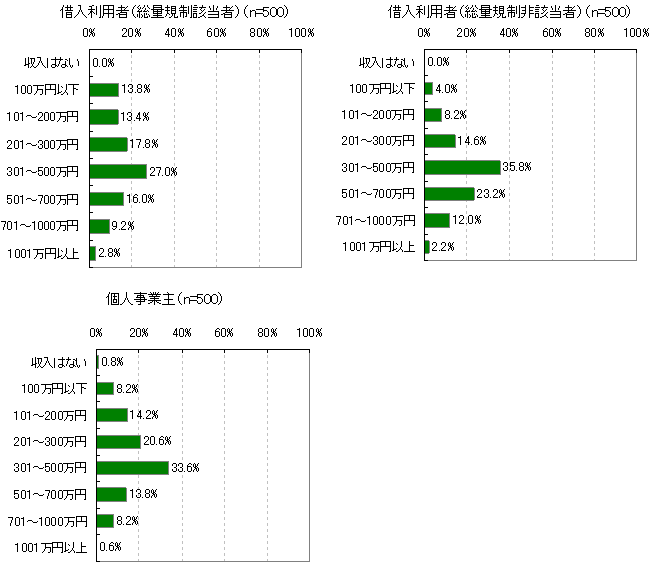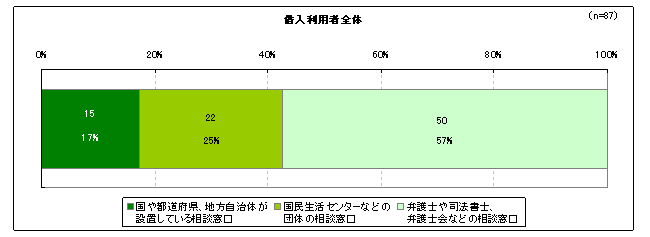調査概要1. 経営実態に関するアンケート調査(ア)調査方法
(イ)標本構成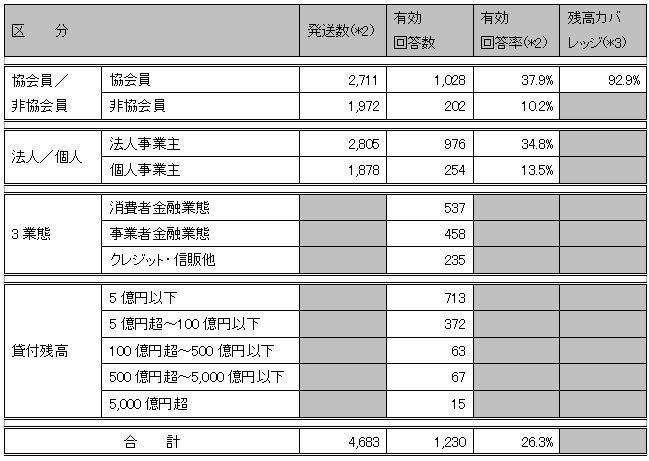
2. 貸金業法改正の認知等に関するアンケート調査(ア)調査方法
(イ) 標本構成~回答者の個人年収の分布
調査結果1. 貸金業法改正による資金需要者への影響
2.業態別にみた貸金業者の経営状況1. 貸金業法改正による資金需要者への影響(1) 初期審査の今後の見通し消費者向け無担保貸付の新規借入申込みに対する初期審査姿勢の今後の見通しについて尋ねたところ(【図1】)、貸金業者の67%が「(今後)厳しくする」、8%が「貸付停止を予定」と回答し、依然として、与信姿勢を厳格化する見込みにある(なお、2006年12月以降の審査状況においても、「厳しくした」の比率が67%であった)。 【図1 初期審査姿勢の今後の見通し】
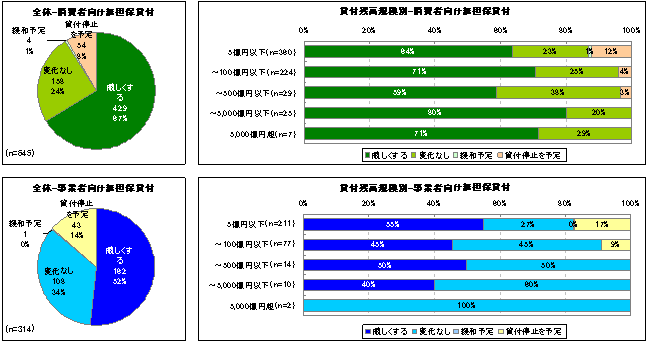 (2) 貸付停止や与信姿勢厳格化による資金需要者への影響前出の初期審査姿勢を「厳しくする」「貸付停止を予定」と回答した貸金業者について、属性に応じて与信対象先を分類したうえで、「改正貸金業法の完全施行による影響の可能性」を尋ねた。 (【図2】及び【図3】)
【図2 初期審査を厳格化する貸金業者による、完全施行に伴う与信姿勢の変化(消費者向け無担保貸付)】
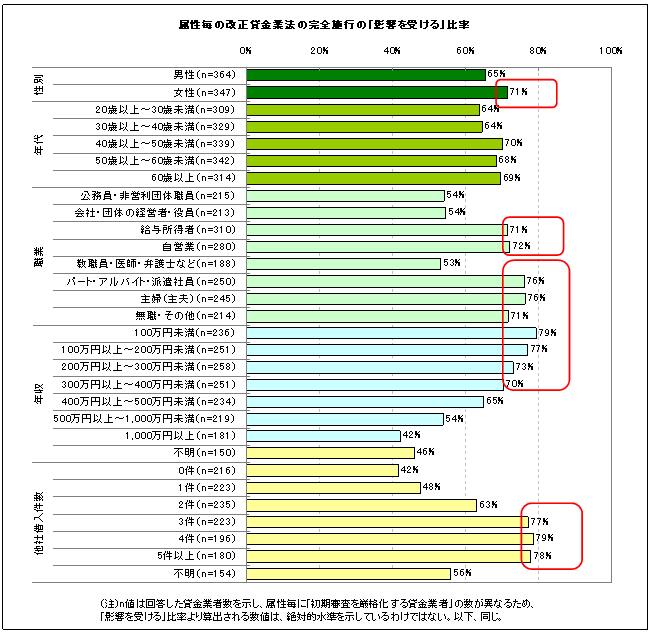 同様に、事業者向け無担保貸付の場合、初期審査姿勢を「厳しくする」「貸付停止を予定」と回答した貸金業者の7割以上が、法改正の完全施行の影響を受ける法人として、「年商1,000万円未満」「個人事業主」「資本金500万円以上~1,000万円未満」「営業年数2年以内」を指摘した。 【図3 初期審査を厳格化する貸金業者による、完全施行に伴う与信姿勢の変化(事業者向け無担保貸付)】 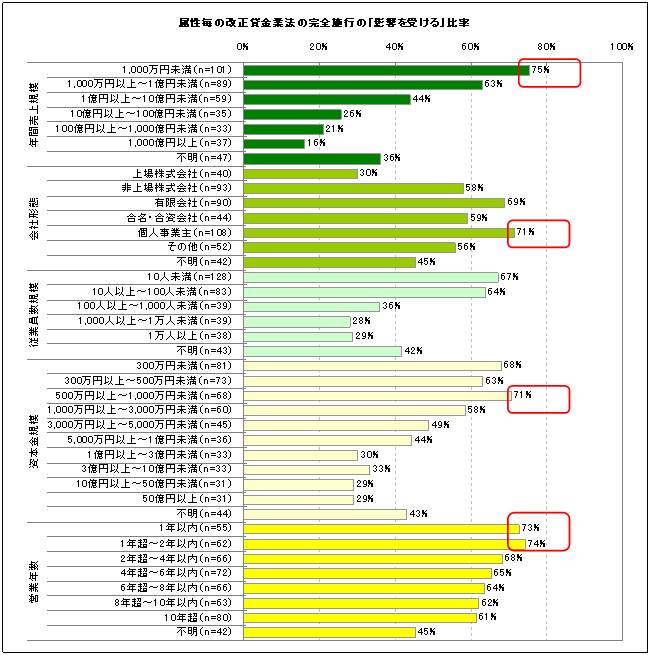 (3) 貸金業法改正に対する認知状況と認知媒体借入利用者に対して、貸金業法が改正されたことを認知しているかどうかを確認し、その中で、法改正に対して認知がある人(「内容も含めてよく知っている」または「詳しい内容はわからないがある程度は知っている」を回答、以下同じ)について、認知に至った媒体を尋ねた。 1)借入利用者の中の総量規制該当者(【図4】) 【図4 貸金業法改正に対する認知状況と認知媒体(総量規制該当者)】
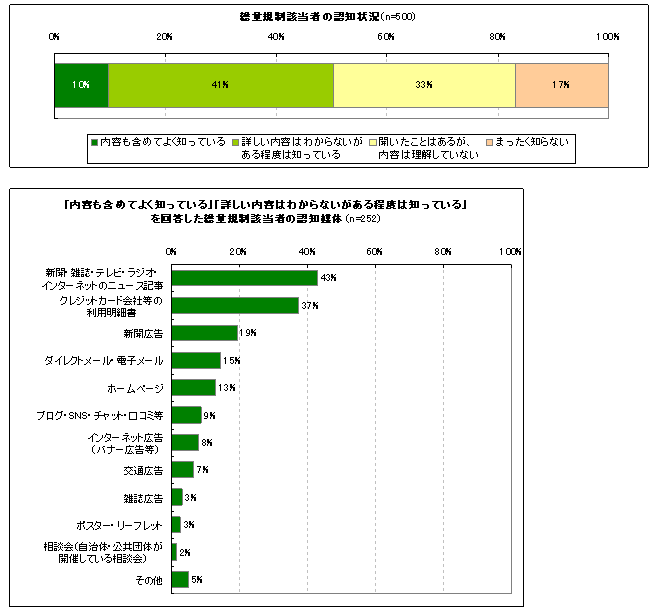
2)借入利用者の中の総量規制非該当者(【図5】)
【図5 貸金業法改正に対する認知状況と認知媒体(総量規制非該当者)】 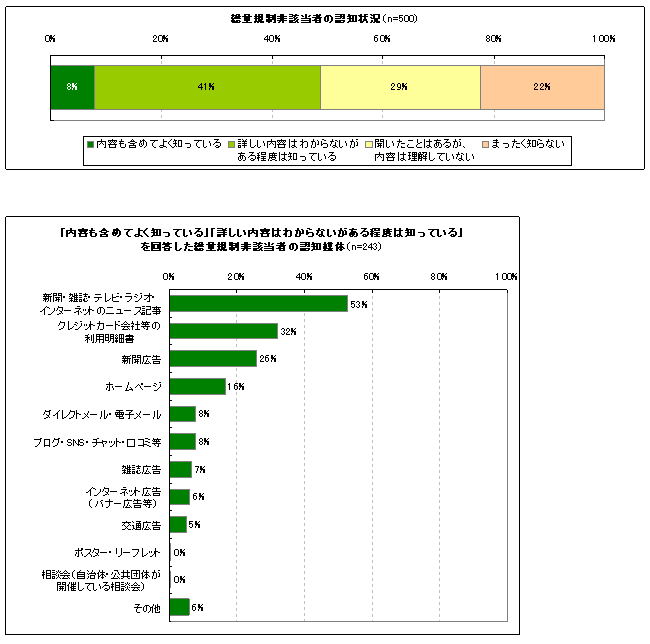 3)専業主婦(主夫)(【図6】) 専業主婦(主夫)における認知がある人の回答割合は37%に留まり、借入利用者全体(総量規制該当者と総量規制非該当者の合計、以下同じ)(50%)よりも低かった。また、認知媒体は、「クレジットカード会社等の利用明細書」が最も高く(45%)、「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットのニュース記事」(33%)、「新聞広告」(20%)が続き、借入利用者と比べて、「クレジット会社等の利用者明細書」による認知が一際高い。 【図6 貸金業法改正に対する認知状況と認知媒体(専業主婦(主夫))】 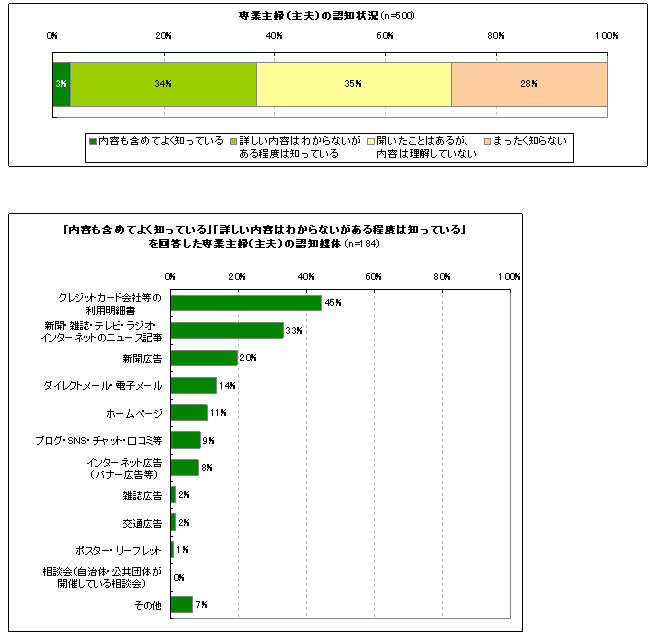 4)個人事業主(【図7】) 個人事業主における認知がある人の回答割合は50%に達し、その認知媒体は、「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットのニュース記事」が最も高く(48%)、「クレジットカード会社等の利用明細書」(39%)、「新聞広告」(25%)が続いた。 【図7 貸金業法改正に対する認知状況と認知媒体(個人事業主)】 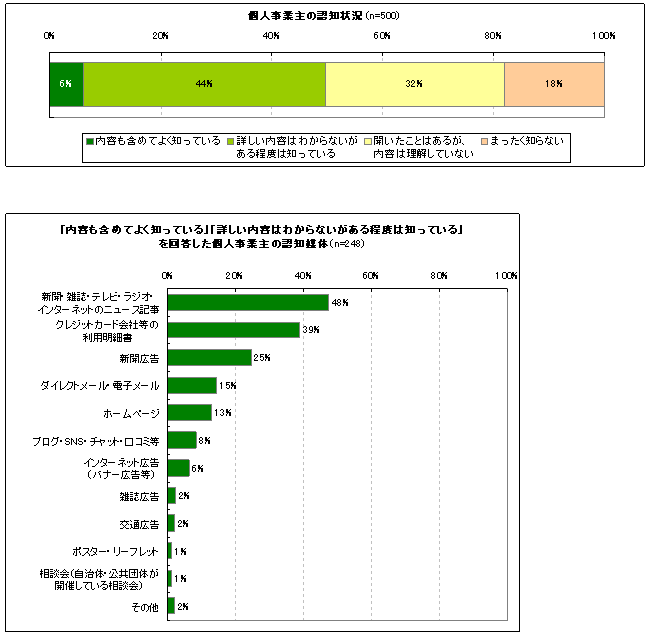 5)借入利用者の年収別(【図8】) 借入利用者の年収別にみると、認知がある人の回答割合は、「300万円以下」(40%)、「301~500万円」(51%)、「501~700万円」(57%)、「701万円以上」(63%)と、年収が少ないほど低かった。 【図8 貸金業法改正に対する認知状況と認知媒体(利用者年収別)】 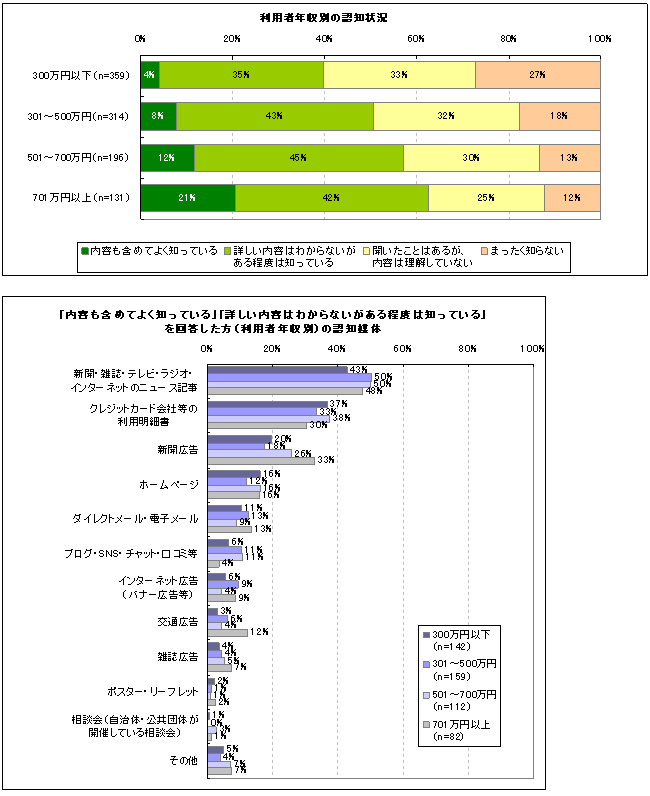 (4) 貸金業法改正についての反応前出の「貸金業法改正に対する認知状況」における回答者を、法改正に対して認知がある人(「内容も含めてよく知っている」または「詳しい内容はわからないがある程度は知っている」を回答)と、認知が不足している人(「聞いたことはあるが、内容は理解していない」または「まったく知らない」を回答)に分け、それぞれに対して法改正内容が自分に関係するかどうかを尋ねた(【図9】)。
【図9 貸金業法改正についての反応(自分自身への関与の可能性)】
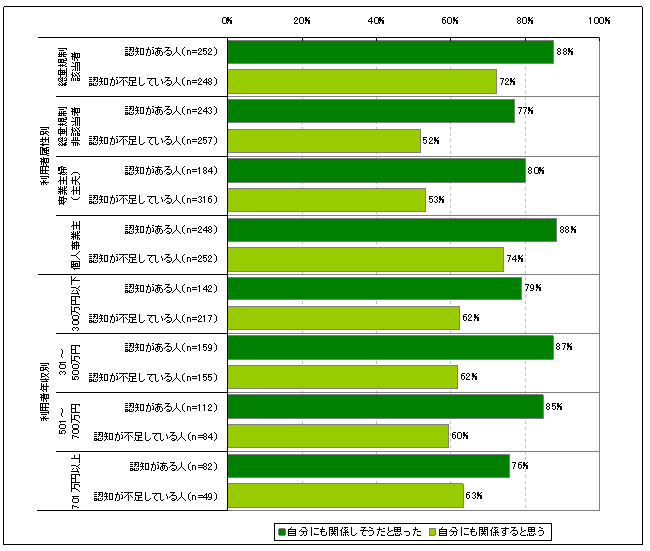 (5) 貸金業法改正を認知した後の借入利用者の行動前出の「貸金業法改正についての反応」において「自分にも関係しそうだと思った」または「自分にも関係すると思った」と回答した借入利用者に対して、法改正内容が自分に関係すると認知した後、どのような行動を取るか尋ねた。 1)借入利用者の中の総量規制該当者(【図10】) 総量規制該当者の法改正を認知した後の行動は、「特に何もしない」が最も多く(32%)、「詳しい内容を調べる」(31%)、「借入金の総額が年収の3分の1以下になるよう借入金の返済を行う」(24%)が続いた。 【図10 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(総量規制該当者)】
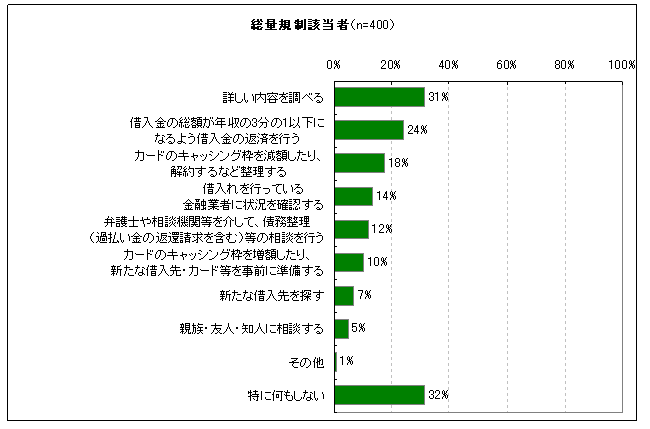 2)借入利用者の中の総量規制非該当者(【図11】) 総量規制非該当者の法改正を認知した後の行動は、「詳しい内容を調べる」が最も多く(35%)、「特に何もしない」(34%)が続いた。総量規制該当者と比較すると、「借入金の総額が年収の3分の1以下になるよう借入金の返済を行う」が7ポイント、「弁護士や相談機関等を介して、債務整理等の相談を行う」が5ポイント、低かった。 【図11 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(総量規制非該当者)】 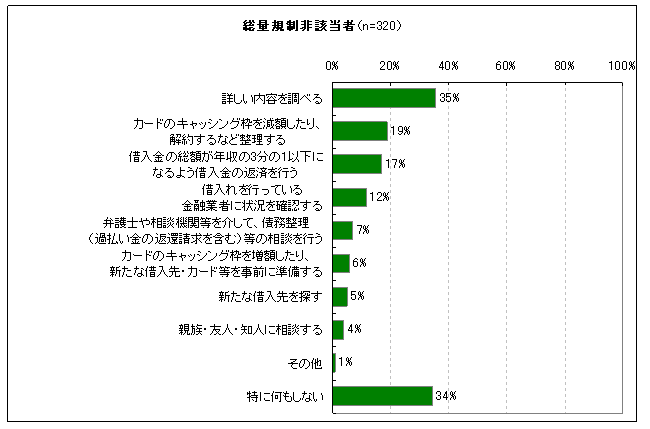 3)専業主婦(主夫)(【図12】) 専業主婦(主夫)の法改正を認知した後の行動は、「特に何もしない」が最も多く(34%)、「詳しい内容を調べる」(31%)、「カードのキャッシング枠を減額したり、解約するなど整理する」(28%)が続いた。借入利用者全体と比較すると、「借入金の総額が年収の3分の1以下になるよう借入金の返済を行う」が7ポイント、「弁護士や相談機関等を介して、債務整理等の相談を行う」が6ポイント低い一方、「カードのキャッシング枠を減額したり、解約するなど整理する」が10ポイントも高く、今後の借入を抑制する行動を取る傾向にある。 【図12 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(専業主婦(主夫))】 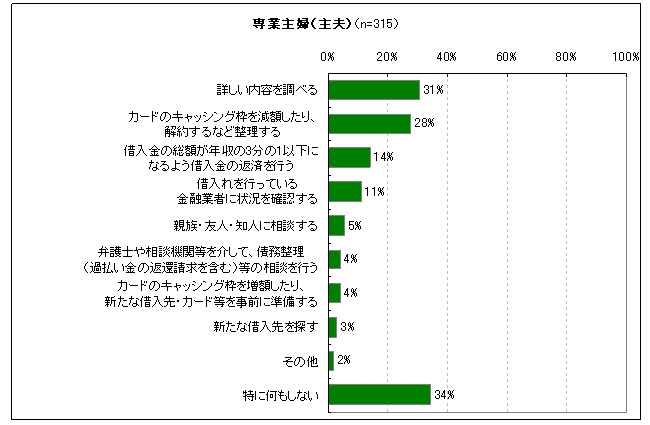 4)個人事業主(【図13】) 個人事業主の法改正を認知した後の行動は、「詳しい内容を調べる」と「特に何もしない」が最も多い(33%)。 【図13 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(個人事業主)】 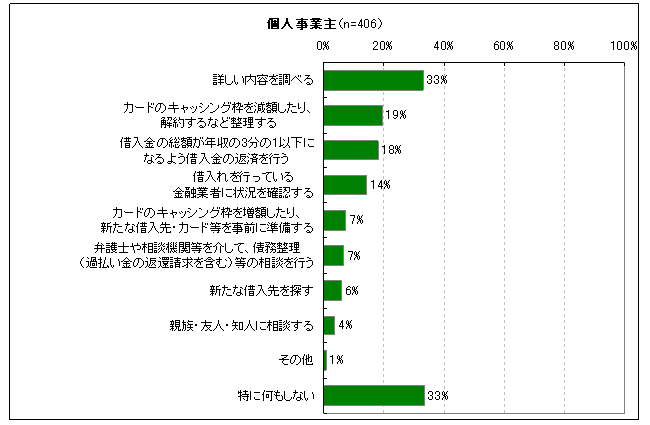 5)借入利用者の年収別(【図14】) 借入利用者の年収別にみると、法改正を認知した後の行動は、全般的に、「詳しい内容を調べる」(31%-36%)と「特に何もしない」(28%-37%)が多い。「300万円以下」の低所得者は、全般的に回答比率が低く、取れる行動が少ないことが窺われた。 【図14 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(利用者年収別)】 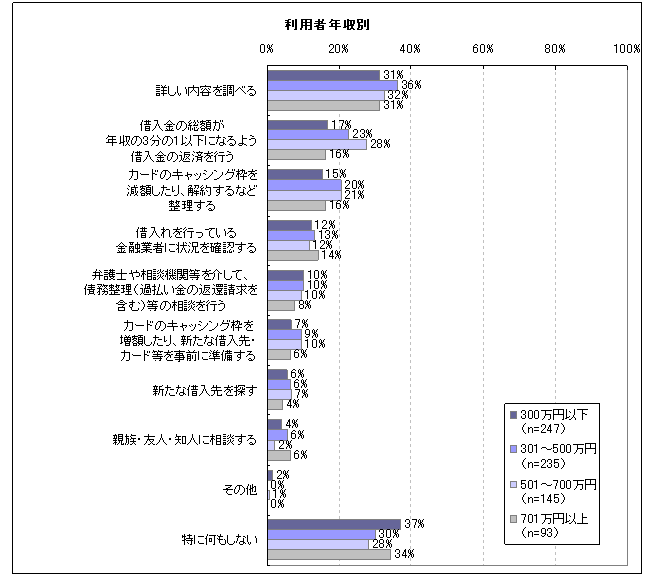 (6) 貸金業法改正に伴う新たな借入先前出の「貸金業法改正認知後の行動」において「新たな借入先を探す」を回答した借入利用者に対して、借入先の候補を尋ねたところ(【図15】)、「正規の貸金業者」(58%)が最も高く、「公的な貸付制度」(37%)が続いた。その一方、「家族や親族」(25%)、「友人・知人」(9%)、「ヤミ金融等非正規の業者」(5%)も少なからず回答があり、更なる多重債務者やヤミ金融被害者・接触者への対策が必要となっている。 【図15 貸金業法改正に伴う新たな借入先】
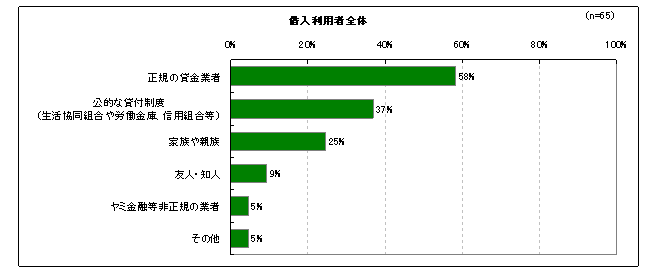
(7)貸金業法改正に伴う相談先前出の「貸金業法改正認知後の行動」において「弁護士や相談機関等を介して、債務整理(過払い金の返還請求を含む)等の相談を行う」を回答した借入利用者に対して、今後相談したい先を尋ねたところ(【図16】)、「弁護士や司法書士、弁護士会などの相談窓口」(57%)が最も高く、「国民生活センターなどの相談窓口」(25%)が続いた。 【図16 貸金業法改正に伴う新たな相談先(今後相談先としたい場所)】
(8)新たな借入れができなくなった場合の行動消費者金融会社から現在も残高があると回答した借入利用者に対して、新たな借入れができなくなると仮定したとき、どのような行動を取るか尋ねた。 1)借入利用者の中の総量規制該当者(【図17】) 新たな借入れができなくなった場合、総量規制該当者(消費者金融会社から借入中)が取る行動は、「生活費を切り詰めて、現在の借入金を返済する」(57%)が最も多く、「アルバイト等により収入を増やす」(32%)、「生活水準を落とさず、毎月のやりくりの中で、現在の借入金を返済する」(28%)、「返済をあきらめて、自己破産・債務整理の手続きを申請する」(21%)が続いた。 【図17 貸金業法改正の影響により借入れができなくなった場合の行動(予測)(あてはまるものすべて) (総量規制該当者)】
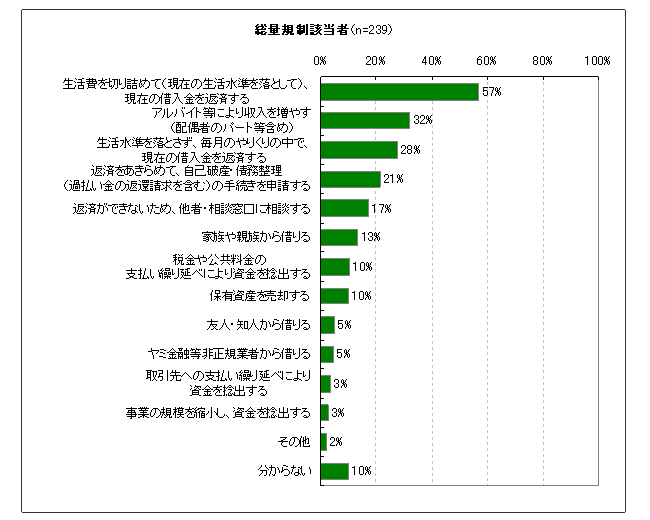 2)借入利用者の中の総量規制非該当者(【図18】) 新たな借入れができなくなった場合、総量規制非該当者(消費者金融会社から借入中)が取る行動は、「生活費を切り詰めて、現在の借入金を返済する」(58%)が最も多く、「生活水準を落とさず、毎月のやりくりの中で、現在の借入金を返済する」(34%)、「アルバイト等により収入を増やす」(27%)が続いた。総量規制該当者と比較すると、「返済をあきらめて、自己破産・債務整理の手続きを申請する」(9%)が12ポイント、「返済ができないため、他者・相談窓口に相談する」(8%)が9ポイント低く、生活破綻を避ける意志が強い。 【図18 貸金業法改正の影響により借入れができなくなった場合の行動(予測)(あてはまるものすべて) (総量規制非該当者)】 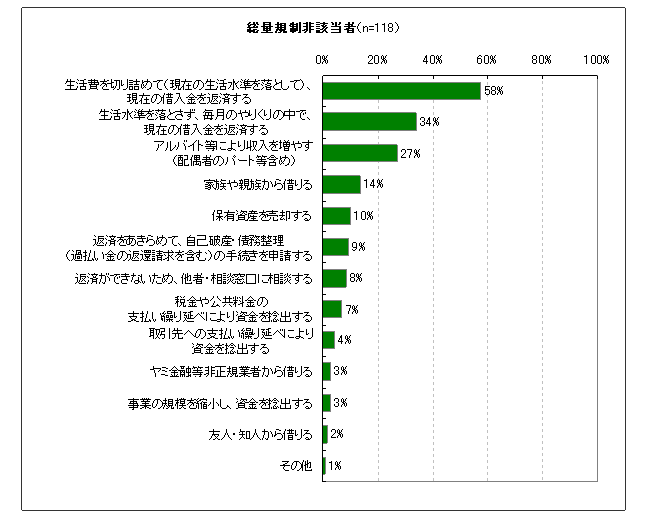 3)専業主婦(主夫)(【図19】) 新たな借入れができなくなった場合、専業主婦(主夫)(消費者金融会社から借入中)が取る行動は、「生活費を切り詰めて、現在の借入金を返済する」が69%(借入利用者全体よりも12ポイント高い)、「アルバイト等により収入を増やす」が54%(同、23ポイント高い)に達し、「家族や親族から借りる」(28%)(同、15ポイント高い)、「生活水準を落とさず、毎月のやりくりの中で、現在の借入金を返済する」(26%)が続いた。 【図19 貸金業法改正の影響により借入れができなくなった場合の行動(予測)(あてはまるものすべて) (専業主婦(主夫))】 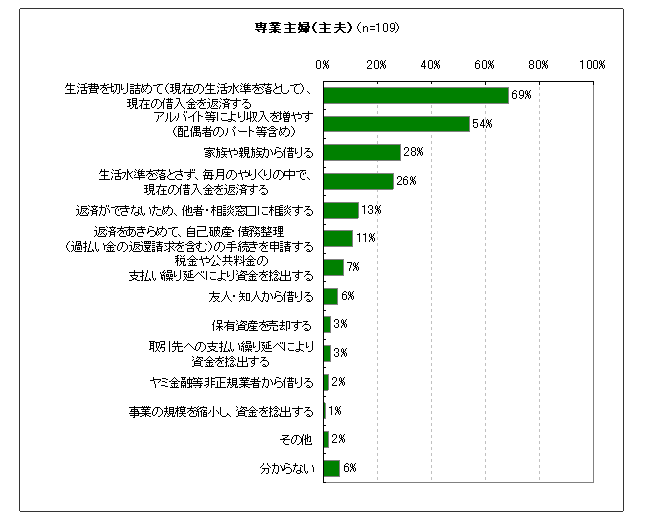 4)個人事業主(【図20】) 新たな借入れができなくなった場合、個人事業主(消費者金融会社から借入中)が取る行動は、「生活費を切り詰めて、現在の借入金を返済する」(62%)が最も多く、「アルバイト等により収入を増やす」(35%)が続いた。借入利用者全体と比較すると、「生活水準を落とさず、毎月のやりくりの中で、現在の借入金を返済する」(20%)が10ポイント低い一方、「返済ができないため、他者・相談窓口に相談する」(20%)が6ポイント、「税金や公共料金の支払い繰り延べにより資金を捻出する」(16%)が7ポイント、「事業の規模を縮小し、資金を捻出する」(11%)が8ポイント、「取引先への支払い繰り延べにより資金を捻出する」(10%)が6ポイント高く、資金繰りを懸念している。 【図20 貸金業法改正の影響により借入れができなくなった場合の行動(予測)(あてはまるものすべて)(個人事業主)】 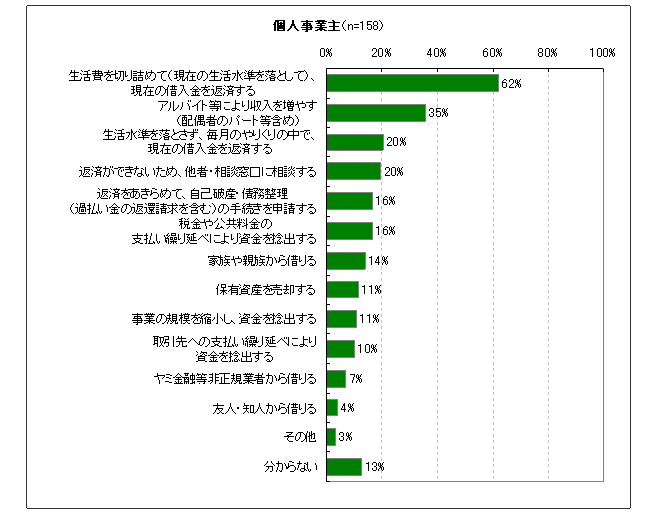 5)借入利用者の年収別(【図21】) 新たな借入れができなくなった場合の行動について、消費者金融会社からの借入中の利用者を年収別にみると、「生活費を切り詰めて、現在の借入金を返済する」(54%-62%)が最も多い。続いて、「300万円以下」の低所得者は、「アルバイト等により収入を増やす」(40%)を挙げる一方、年収「501~700万円」及び「701万円以上」の借入利用者は、「生活水準を落とさず、毎月のやりくりの中で、現在の借入金を返済する」(41%及び32%)を挙げた。 【図21 貸金業法改正の影響により借入れができなくなった場合の行動(予測)(あてはまるものすべて)(利用者年収別)】 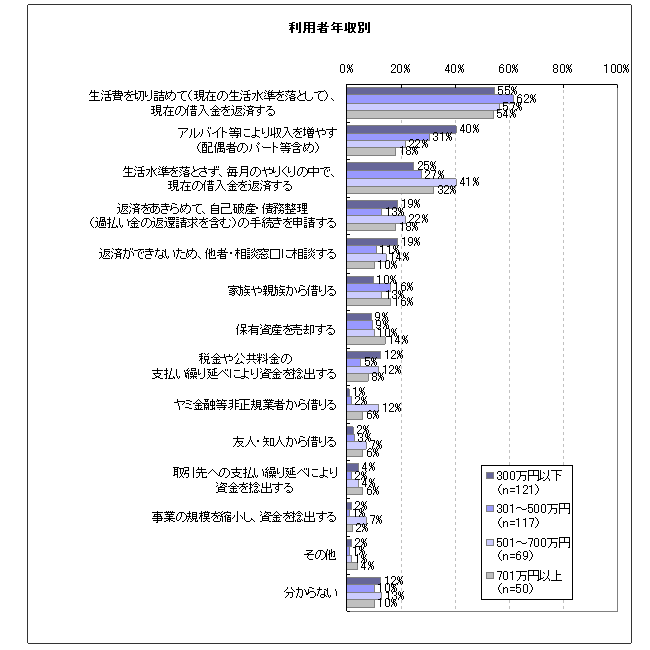 (9) セーフティネットについての認知度借入利用者に対して、セーフティネット(相談窓口)やセーフティネット貸付の認知状況を尋ねたところ(【図22】)、最も高い「弁護士や司法書士、弁護士会などの相談窓口」でも、利用者の属性や年収にかかわらず20%前後(16%-24%)に過ぎず、全般的に認知されていない。 【図22 セーフティネットについての認知度】
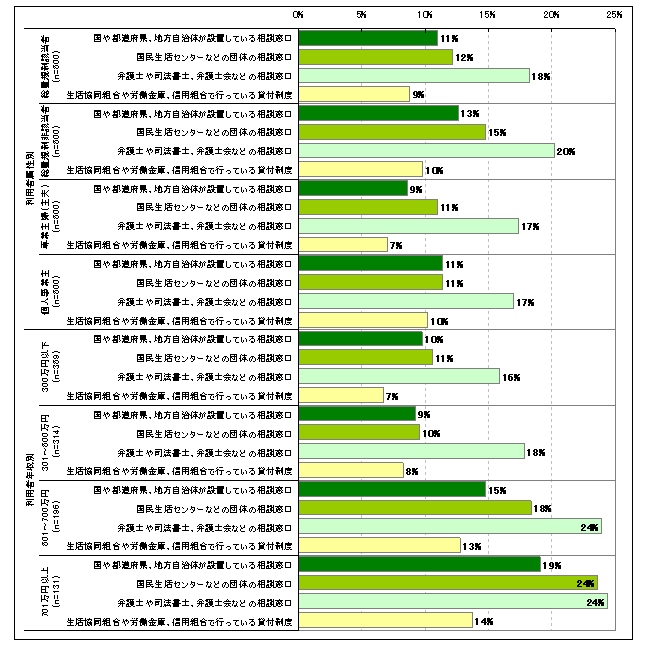
2. 業態別にみた貸金業者の経営状況(1) 損益の状況と見通し貸金業者の損益状況を業態別にみるために、2008年度の営業損益実績及び2009年度の営業損益見通しについて、対前年度の増減状況を業態毎に算出した。(なお、「増益」は、営業利益の増額、営業損失から営業利益への転換、営業損失の減額の合計回答者数。「減益」も同様の概念。)(【図23】) 【図23 貸金業者の損益の状況と見通し(業態別)】
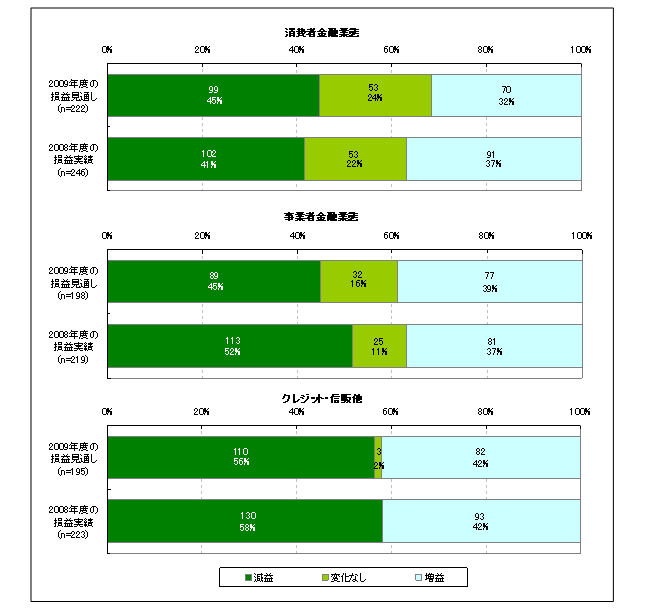 (2) 事業コスト構造の推移貸金業者のコスト構造を業態別に把握するために、営業貸付金残高(平均残高)に対する営業貸付金利息及び営業費用の比率を、2007年と2008年の両年度について、業態毎に算出した。(「営業費用」は、「金融費用」「貸倒償却費用」「その他販売管理費」「利息返還費用」の合計)(【図24】) 【図24 事業コスト構造(業態別)】
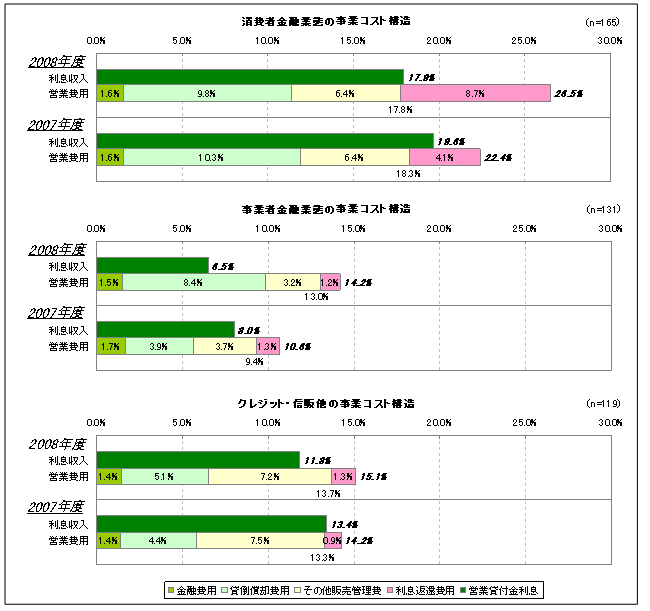 以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在ご覧のページは当社の旧webサイトになります。トップページはこちら