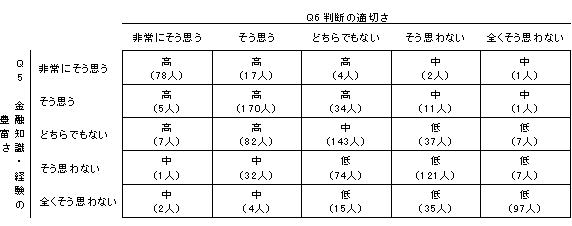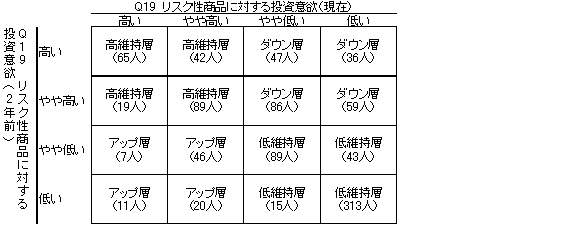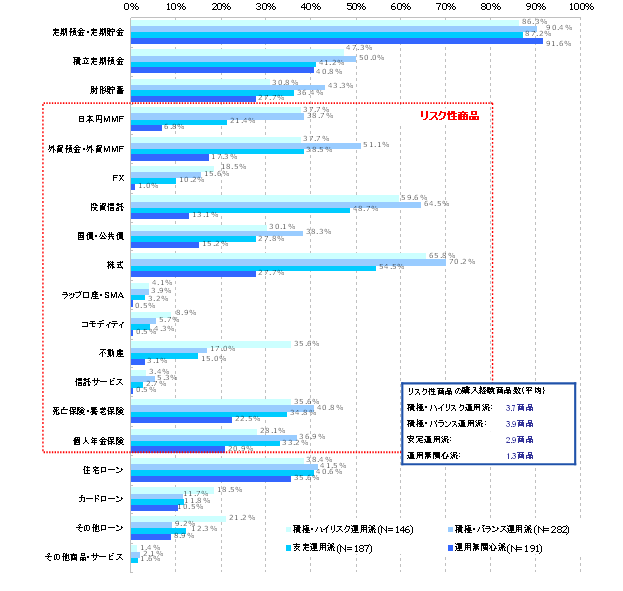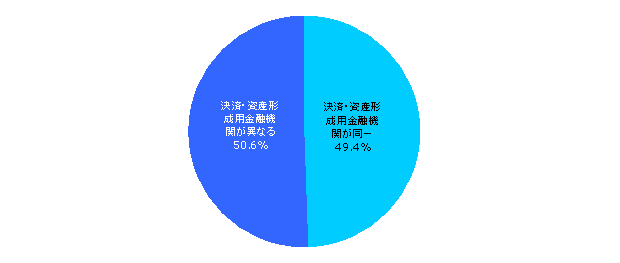調査概要
【補足】 (*2) 金融資産残高 (*3) 金融リテラシー
(*4) 投資マインドパターン
調査結果1. フローリッチの基本属性1.1. 金融資産残高の推移回答者世帯の金融資産残高の推移について尋ねたところ、現在の資産残高が「5000万円~1億円未満」の回答者は全体の16.1%、「1億円以上」が14.5%という結果となった。 【金融資産残高の推移】 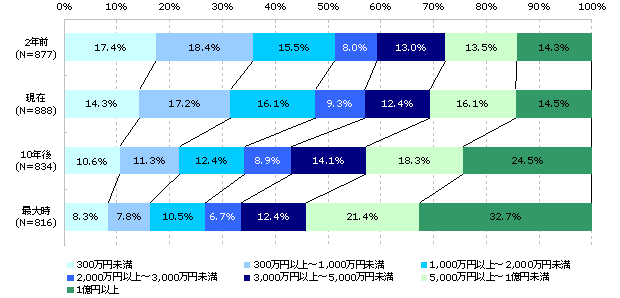
※「わからない」の回答を母数から除いて集計している 1.2. 就業状況次に、職業について尋ねたところ、「会社員(管理職)」が24.9%で最も多く、次いで「経営者・役員(非上場)」(15.6%)、「医師」(12.7%)、「会社員(非管理職)」(11.4%)、「自営業」(8.1%)という順となった。 【あなたの職業】(N=987) 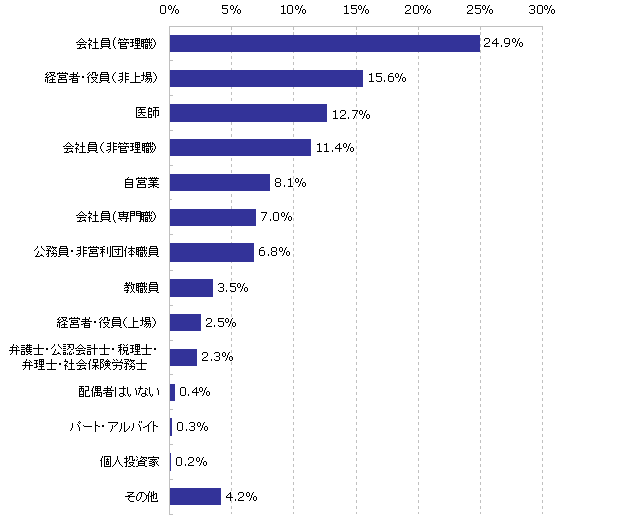
※本人の職業が「専業主婦(主夫)」、「パート・アルバイト」である回答者に対しては、「配偶者の職業」の回答結果に置き換えて集計している。 【共働きの有無】 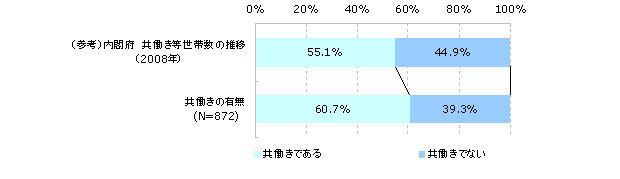 (出典) 内閣府 「平成21年版 男女共同参画白書」 2.運用スタイルパターンと金融取引状況2.1. 運用スタイルパターンとポートフォリオ「運用関心」、「金融リテラシー」、「現在の投資意欲」、「リスク許容度(全金融資産に対する安全性商品の割合)」の回答を元にクラスター分析を行ったところ、「積極・ハイリスク運用派(18.0%)」、「積極・バランス運用派(34.6%)」、「安定運用派(22.8%)」、「運用無関心派(24.6%)」の4パターンの運用スタイルに分類された。 【運用スタイル】 (N=826) 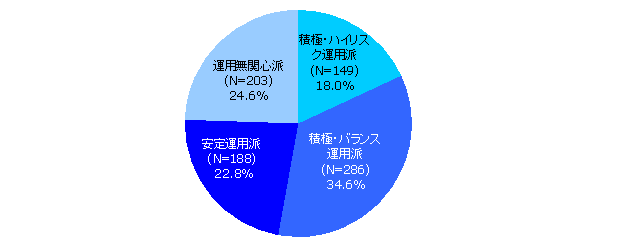
【ポートフォリオ(運用スタイル別)】 (N=826) 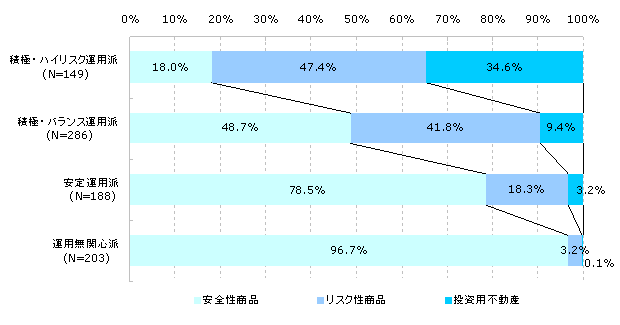 2.2. 購入経験のある商品次に、これまで購入したことがある金融商品を運用スタイル別に見たところ、「積極・ハイリスク運用派」は「FX(18.5%)」、「コモディティ(8.9%)」など、特に値動きの大きいリスク性商品を、「積極・バランス運用派」は「株式(70.2%)」、「投資信託(64.5%)」、「外貨預金・外貨MMF(51.1%)」「国債・公共債(38.3%)」など、様々な種類の金融商品を購入する比率が高い結果となった。 【購入経験商品(運用スタイル別)】(N=806)
※「上記商品の中では何も取引したことがない」の回答者を母数から除いて集計している 2.3. 資産形成目的で利用している金融機関資産形成目的で利用しているメイン金融機関を運用スタイル別で見たところ、「積極・ハイリスク運用派」、「積極・バランス運用派」は、「証券会社(16.1%、18.2%)」、「インターネット専業証券会社(20.1%、12.6%)」、「外資系金融機関(4.0%、8.0%)」の利用率が他と比べて高く、「安定運用派」は「インターネット専業銀行(16.5%)」、「運用無関心派」は「都市銀行(44.3%)」、「地方銀行(17.7%)」を利用する比率が高い結果となった。 【資産形成用メイン金融機関(運用スタイル別)】 (N=826) 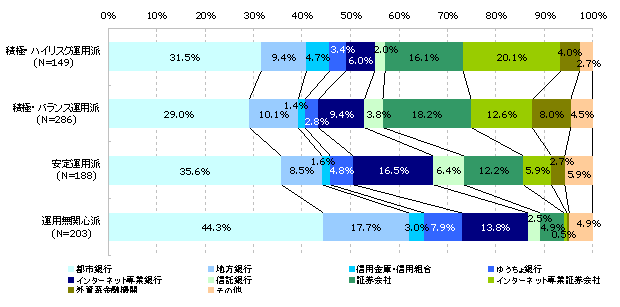 3. 金融機関選定3.1. メイン金融機関(決済用途/資産形成用途)の選定日々の入出金や引き落とし等の決済用途、投資運用商品の購入や相談等の資産形成用途のそれぞれについてメインで利用している金融機関を尋ねたところ、決済用メイン金融機関は都市銀行が57.9%で最も高く、次いで地方銀行(18.8%)、ゆうちょ銀行(6.0%)という順となった。資産形成用メイン金融機関も、同様に都市銀行が36.4%で最も高く、次いで地方銀行(12.9%)、証券会社(11.6%)、インターネット専業銀行(10.8%)、インターネット専業証券会社(8.1%)という順となった。 【決済用メイン金融機関】(N=987) 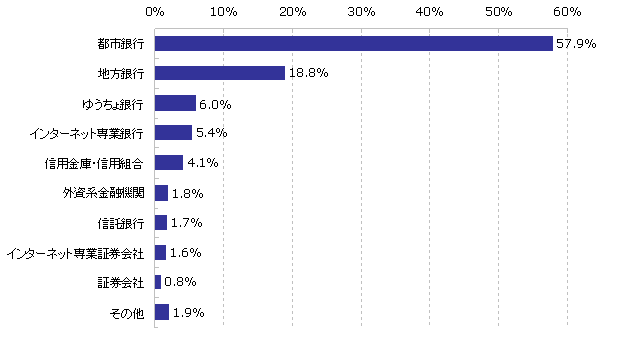 【資産形成用メイン金融機関】(N=987) 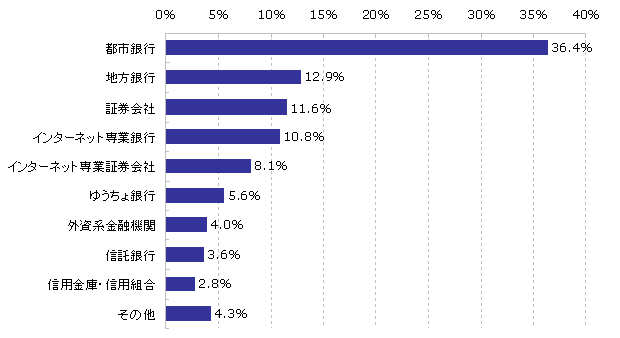 3.2. 決済・資産形成両用途の、同一金融機関選択率次に、決済用途・資産形成用途での金融機関の選択状況を分析したところ、メイン金融機関を決済用途と資産形成用途で使い分けている割合は50.6%という結果となった。
【決済用メイン金融機関に対する資産形成用途での同一機関利用割合】(N=987)
【資産形成用メイン金融機関(業態)先(決済用と異なる金融機関の利用者のみ)】 (N=499) 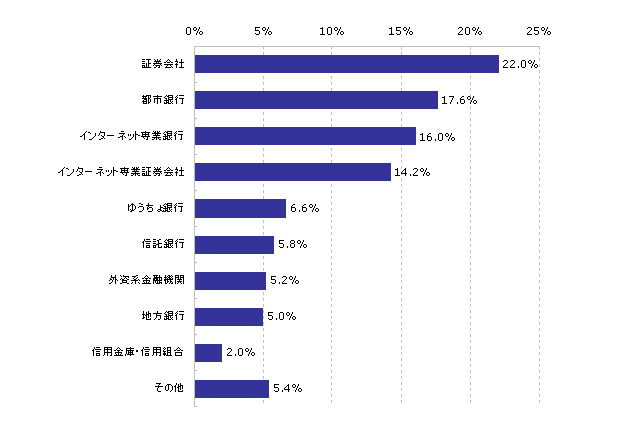 3.3. 資産形成用メイン金融機関の選定理由資産形成用メイン金融機関の選定理由について、決済用途、資産形成用途で同一の金融機関を利用している回答者と、使い分けている回答者の結果を比較した。 【資産形成用メイン金融機関の選定理由(用途での金融機関選択パターン別)】 (N=987) 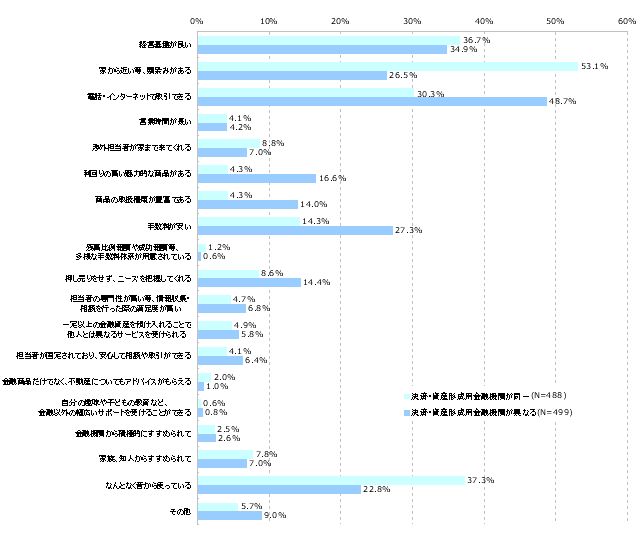 4. 金融機関からの情報収集や相談サービスの利用4.1. 金融リテラシーの高低と情報収集・相談有無金融取引の際に情報収集を行うかどうかについて、金融リテラシーの高低で分析したところ、リテラシーが高くなるほど情報収集実施率が高まる結果となった(高リテラシー:96.7%、中リテラシー:90.4%、低リテラシー:72.3%)。 【金融取引を行う際の情報収集の有無(金融リテラシー別)】 (N=987) 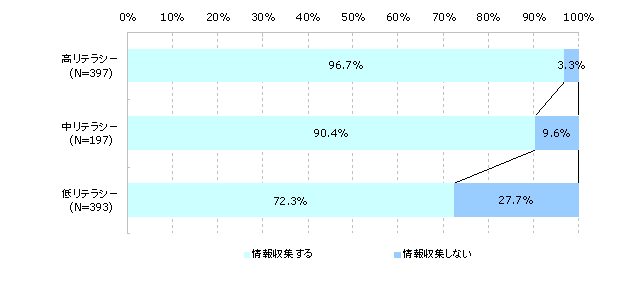 【金融取引を行う際の相談の有無(金融リテラシー別)】 (N=987) 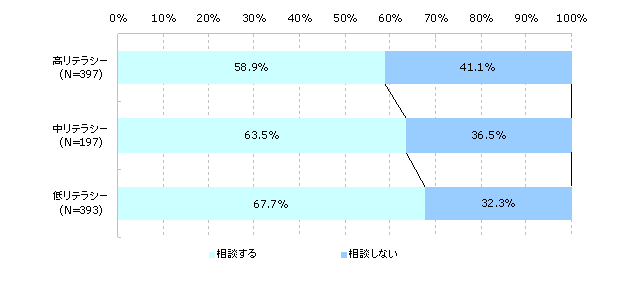
4.2. 金融機関の提供する情報提供・相談サービスの利用次に、情報収集や相談時に、金融機関が提供する情報提供サービス(金融機関の担当者、WEBサイト、DM、セミナー)を利用しているかどうか、相談相手として金融機関の担当者が選ばれているかどうかを資産形成用メイン金融機関(業態)別に分析した。 【情報収集先(資産形成用メイン金融機関(業態)別)】 (N=846) 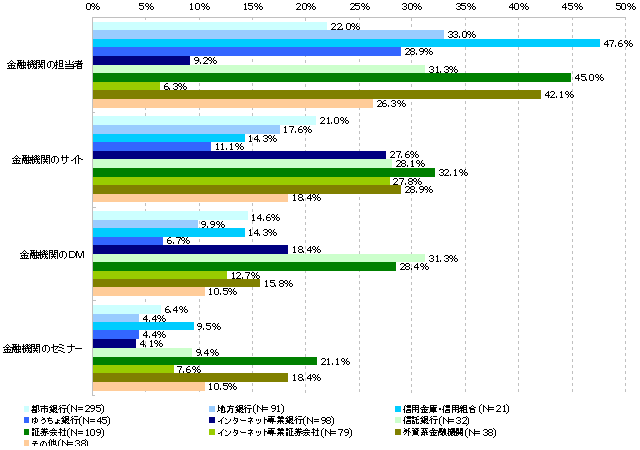 【金融機関の担当者への相談(資産形成用メイン金融機関(業態)別)】(N=625) 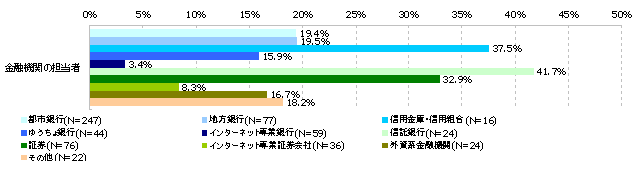
5. 金融危機前後での投資マインドの変化5.1. リスク性商品に対する投資マインドの推移サブプライムローン問題が発生する以前の2007年7月時点と現在におけるリスク性商品に対する投資マインドを尋ねたところ、2年前は44.9%が高い投資マインド(「高い(19.3%)」、「やや高い(25.6%)」)であったが、現在はその割合が30.3%に減少している(「高い(10.3%)」、「やや高い(20.0%)」ことが分かった。 【金融危機前後でのリスク性商品に対する投資マインドの推移】(N=987) 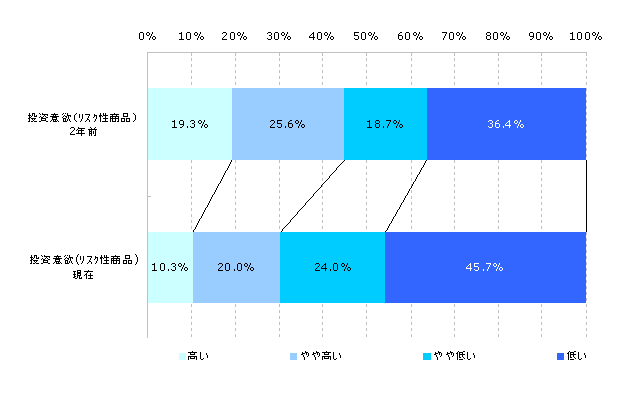 5.2. 金融危機前後での投資マインドパターン2年前の投資マインドから現在の投資マインドへの変化のパターンについて、「投資マインド高維持層」、「投資マインドアップ層」、「投資マインドダウン層」、「投資マインド低維持層」に分類したところ、全体における割合は、「投資マインド低維持層」が46.6%で最も多く、次いで「投資マインドダウン層(23.1%)」、「投資マインド高維持層(21.8%)」、「投資マインドアップ層(8.5%)」の順となった。 【金融危機前後での投資マインドパターン】(N=987) 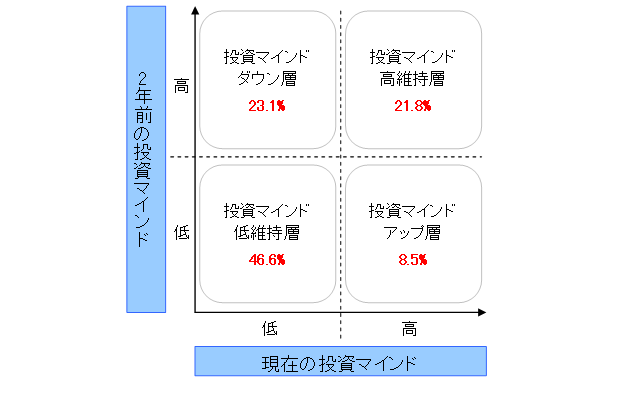 5.3.投資マインドパターン別金融リテラシー金融リテラシー「高」の割合が最も高いのは「投資マインド高維持層」で、全体の64.7%を占める。次いで「投資マインドアップ層(56.0%)」、「投資マインドダウン層(46.1%)」、「投資マインド低維持層(23.0%)」の順となった。 【金融リテラシー(投資マインドパターン別)】(N=987) 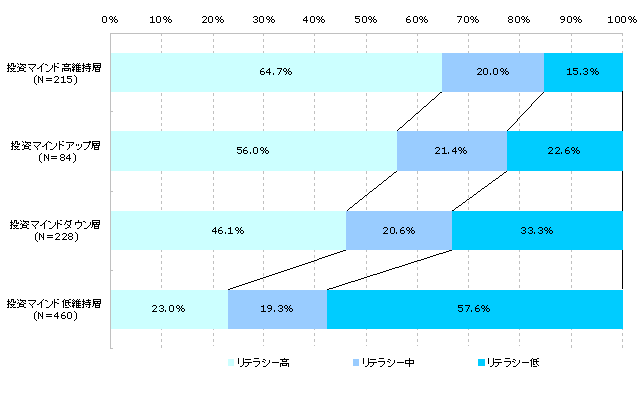
5.4. 投資マインドパターン別直近2年間での投資運用状況サブプライムローン問題が発生する2年前(2007年7月)から現在までの運用成績を尋ねたところ、損失割合が最も高いのは「投資マインドダウン層」で、全体の74.2%が10%以上の損失を出しており、その中でも40.6%が30%以上の損失を計上している。 【直近2年間での投資運用状況(投資マインドパターン別)】 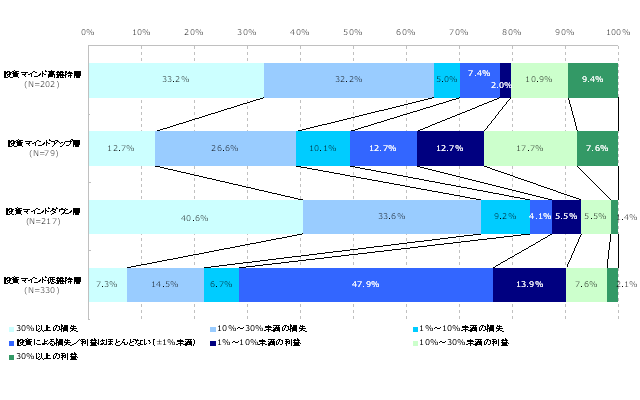 ※「わからない」の回答を母数から除いて集計している
5.5. 投資マインドパターン別情報収集プロセス情報収集の実施有無について、「投資マインド低維持層」の25.2%が情報収集を実施しない一方、その他の3セグメントはほぼ全員が情報収集を実施しているという結果となった。 【情報収集有無(投資マインドパターン別)】 (N=987) 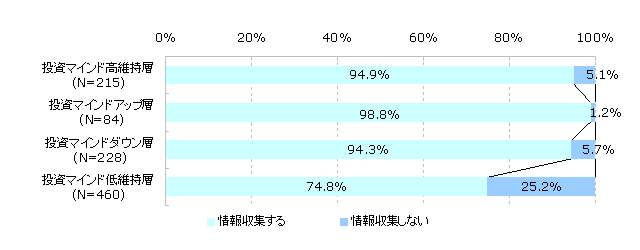 【情報収集先(投資マインドパターン別)】 (N=846)
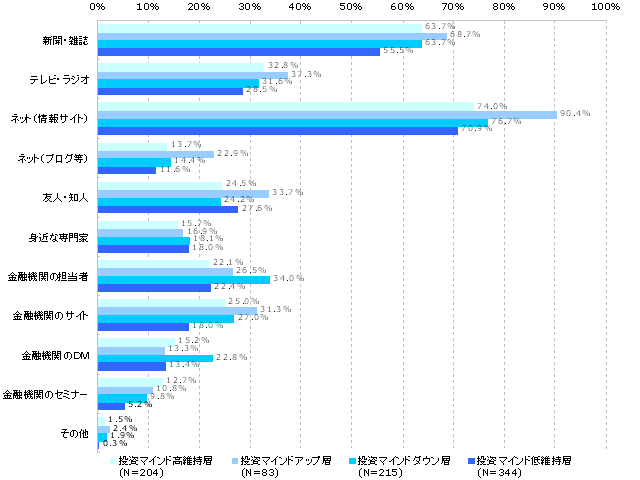 ※「情報収集しない」の回答を母数から除いて集計している 5.6. 投資マインドパターン別相談プロセス相談の実施率は、「投資マインド低維持層」が67.0%で最も高く、次いで「投資マインドダウン層(65.4%)」、「投資マインド高維持層(56.3%)」、「投資マインドアップ層(56.0%)」の順となった。 【相談先(投資マインドパターン別)】 (N=987) 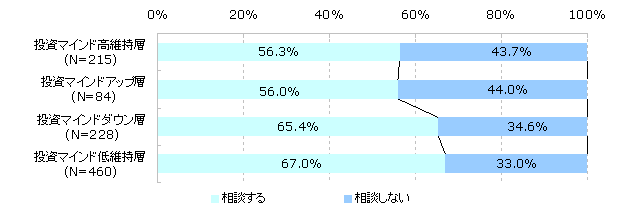 【相談先(投資マインドパターン別)】 (N=625) 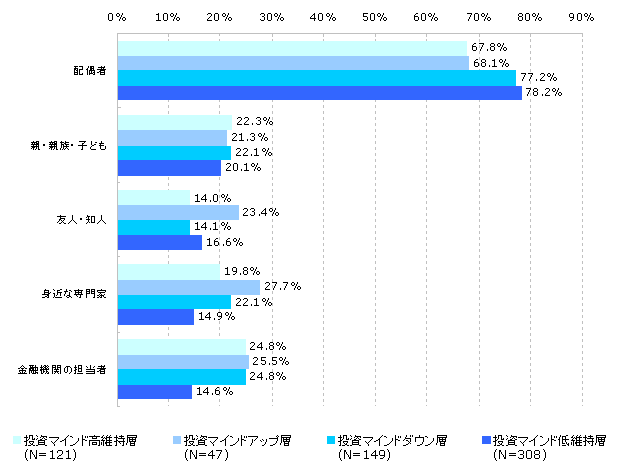 ※「相談しない」の回答を母数から除いて集計している 5.7. 投資マインドパターン別ポートフォリオ推移世帯全体の金融資産を「安全性商品」「リスク性商品」「投資用不動産」に分類して、2007年7月時点と現在におけるそれぞれの保有割合を尋ねた。 【2年前のポートフォリオ(投資マインドパターン別)】 (N=807) 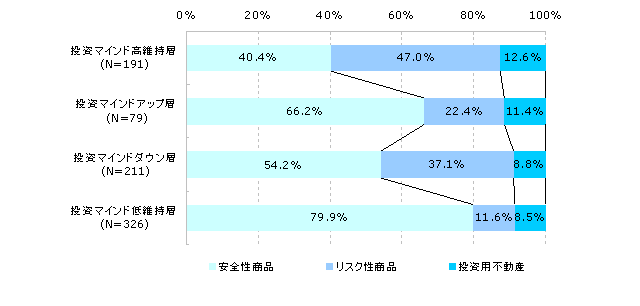
【現在のポートフォリオ(投資マインドパターン別)】 (N=826) 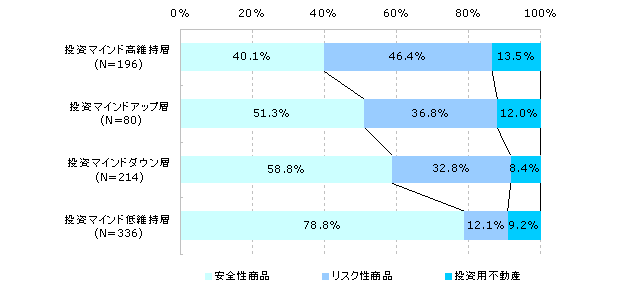 6. 今後の投資方向性6.1.投資マインドパターン別今後の投資方向性投資マインド高維持層は、「投資額を増やしている/増やそうとしている」が44.2%で最も高く、次いで「景気が回復した段階で投資を増やす(20.0%)」、「当面は預貯金で増やすが、一定期間経過後に投資を行う(14.4%)」の順となった。 【今後の投資方向性(投資マインドパターン別)】 (N=987) 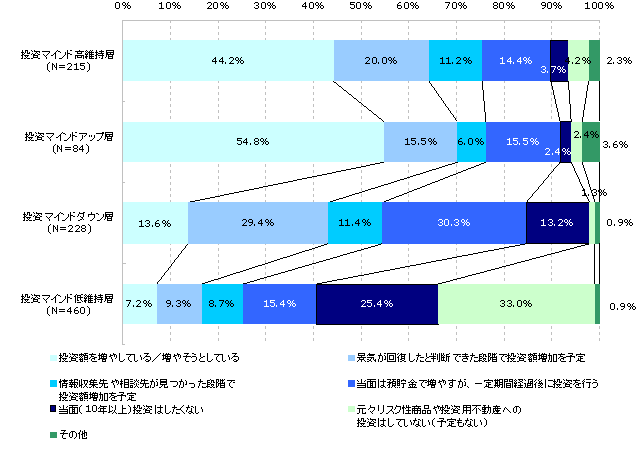 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在ご覧のページは当社の旧webサイトになります。トップページはこちら