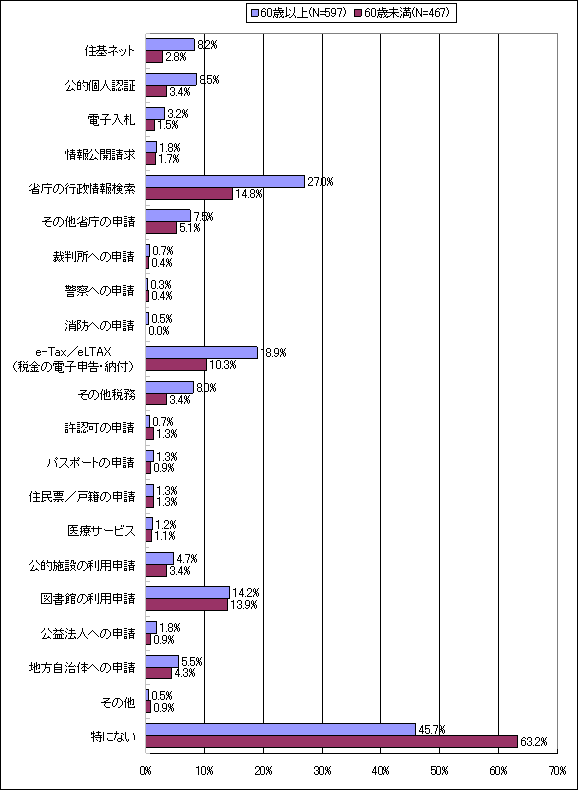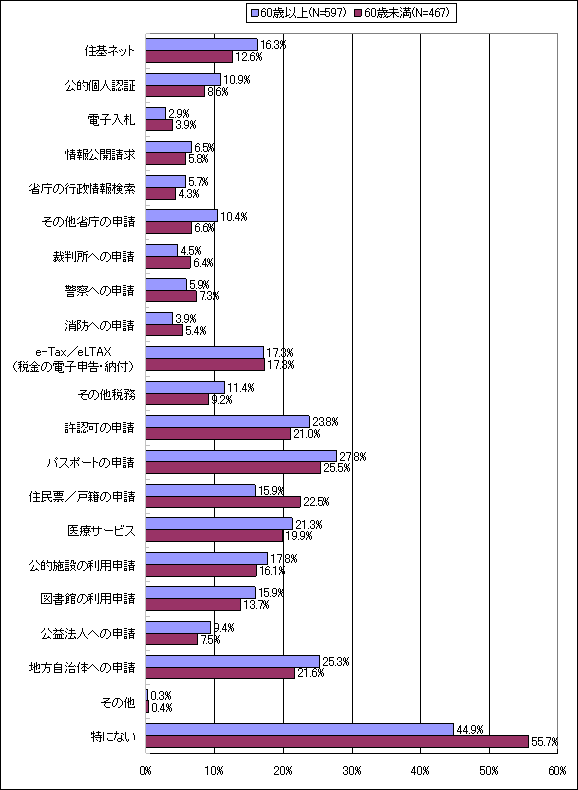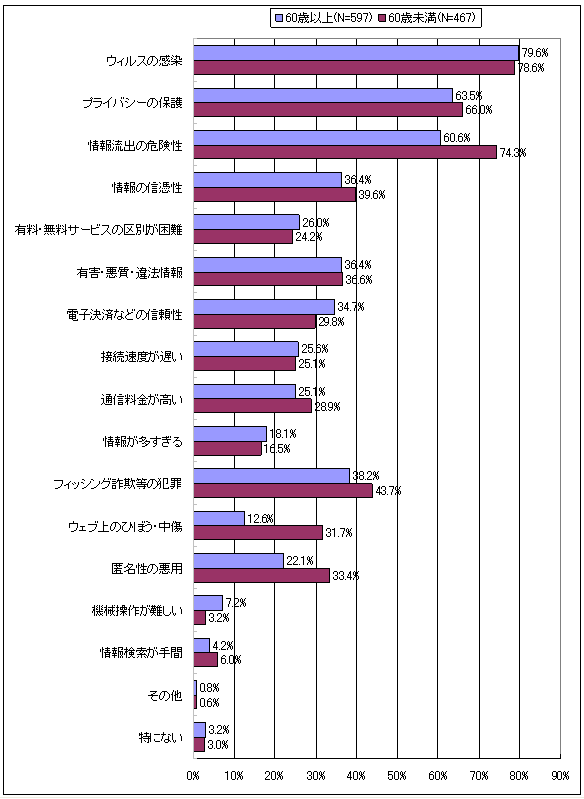調査概要
<性別>
<年齢>
【補足】
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
調査結果
1. 高齢者におけるコンピュータ・リテラシーについてパソコンの操作能力である、「コンピュータ・リテラシー」レベルに関するアンケートによって調査対象者を「高い」、「普通」、「低い」、のいずれかに分類をした。(*2)この調査結果から60歳以上とその他の年代別と比較した時にコンピュータ・リテラシーに大きな差異は見当たらなかった。いずれの世代においても「高い」分類の占める割合が大きく、60歳以上においても同様であった。さらに、今後習得したいパソコンの操作能力についても60歳以上とその他の年代別と比較をした時にも大きな差異は見当たらなかった。 【図表1-1】コンピュータ・リテラシーレベル
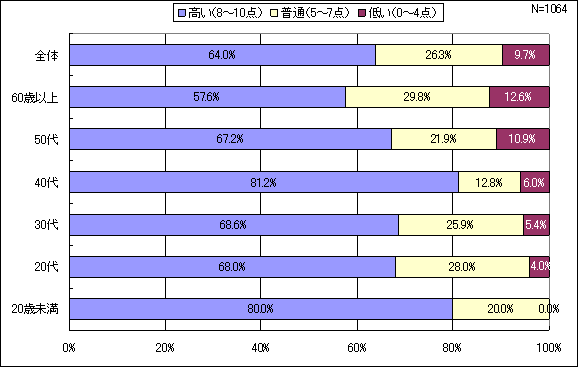 (*2) 「コンピュータ・リテラシーレベルに関するアンケート」質問内容 (単一回答)(1) マニュアル等を参照しながらソフトのインストールや周辺機器の接続・設定ができる。
(2) キーボードとマウスを使用してスピーディな入力ができる。
(3) 使ったことのないソフトでもヘルプやマニュアルを見て、操作できる。
(4) ウェブブラウザや電子メールが自由に使える。
(5) ワープロや表計算ソフトを使用して文書作成ができる。
【図表1-2】 今後習得・達成したいパソコンに関する能力
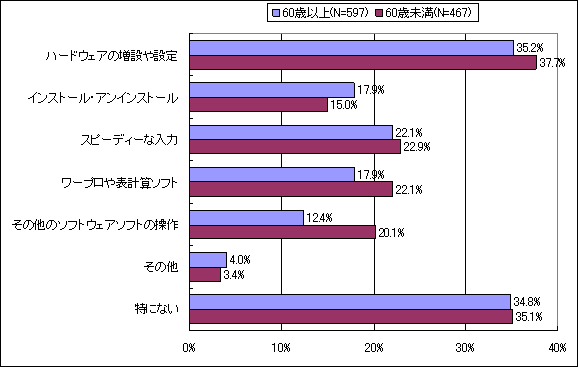 (複数回答) 2.購入に対する基本方針と行動パターン: 購入動機について自身のパソコンを購入した動機について尋ねたところ、60歳以上男女において「インターネットを利用するため」が82.5%と86.0%という回答であった。インターネット接続料金における従量制から定額制への移行を背景に低価格化が進んだことから、近年インターネットの普及は目まぐるしく進んだが、その波及先として60歳以上の高齢者層も例外ではなく、パソコン購入動機の中心となっていることが窺える。それ以外では「仕事で必要」という回答が特に男性において高い割合であるが、これは定年延長や再雇用制度により仕事に再チャレンジする高齢者が増えていることから、仕事や業務を通してもパソコンを取り入れていっていることが窺える。
【図表2-1】 自宅パソコンを購入したきっかけ
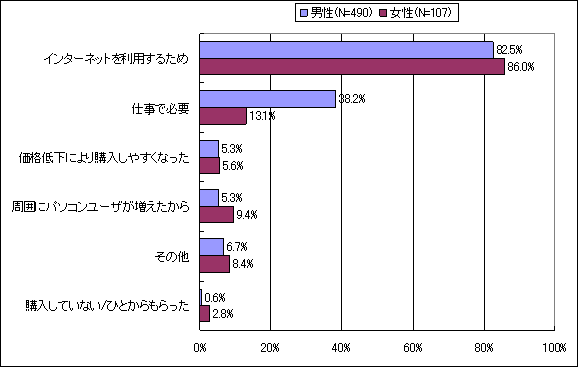 (複数回答) 3.購入に対する基本方針と行動パターン : 情報収集について自宅のパソコンを購入する際、重視する情報源について尋ねたところ、60歳以上男女において、「メーカーのWebサイト」が33.7%と16.4%、「製品比較のWebサイト」が22.4%と8.7%、「雑誌・専門誌等の書籍」が26.3%と4.8%、「販売店の販売員の意見」が32.2%と37.5%、「知人・親類等の意見」が17.7%と45.2%となっている。 この調査結果から高齢者において、男性は自己で判断し得る為の情報を主体に、第三者の意見も合わせて収集しようとする傾向があるが、女性は家族・知人や販売員といった第三者の意見だけを収集する傾向が強いことが行動パターンとして窺える。 またプロバイダ契約についても同様の目的で調査・分析したところ、ほぼ同様の傾向が見られた。「プロバイダのWebサイト」で19.2%と13.1%、「プロバイダ比較のWebサイト」で19.4%と5.6%、「雑誌・専門誌等の書籍」で12.5%と4.7%、「販売店の販売員の意見」で19.0%と13.1%、「知人・親類等の意見」で17.4%と36.5%となっている。
【図表3-1】 自宅のパソコン購入にあたって主に参考にしたもの
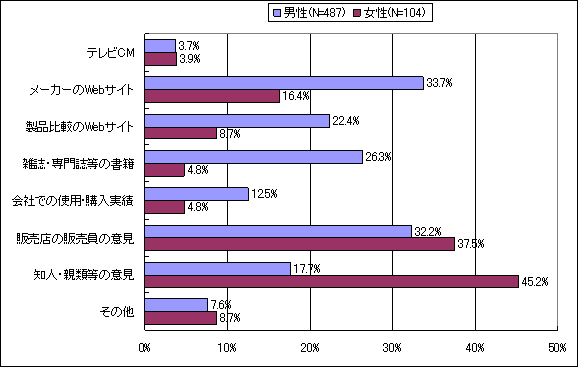 (複数回答) 【図表3-2】 自宅パソコンのプロバイダ選定にあたって参考にしたもの
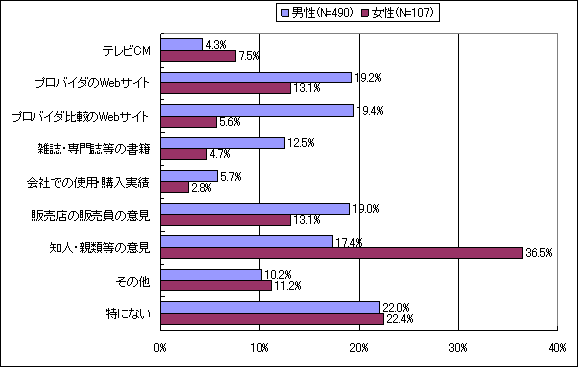 (複数回答) 4.購入に対する基本方針と行動パターン : 比較・選定(基準)についてパソコンを購入するにあたって、重視した選定基準について尋ねたところ、60歳以上・未満において、「値段」を重視するという回答が69.0%と77.0%であり、共に一番の選定基準になっている。それ以外には60歳以上の高齢者において、「使いやすさ」や「メーカー」、「サポート体制」といった選定基準が続いた。特に「デザイン」と「サポート体制」については、60歳以上と60歳未満で回答に差異が見られる。 この調査結果からパソコン購入時の選定理由は、多くが、「値段」を一番に挙げているものの、60歳未満がデザインを重視する反面、60歳以上の高齢者はサポート体制や使いやすさ、メーカー名などの安心を求めていることが窺える。 【図表4-1】 自宅のパソコン購入にあたって選定の決め手
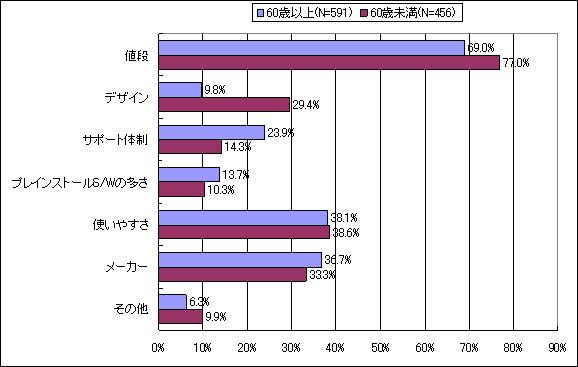 (複数回答) 5.パソコンの利用動向 : 普及実態・使用頻度について高齢者におけるパソコンの普及実態を把握するため、周囲におけるパソコンの所有率について尋ねたところ、60歳以上の高齢者において、「9割以上」が17.6%、「7~8割」が29.1%、「5~6割」が24.3%と周囲の半数以上がパソコンを所有しているという回答が7割を超えた。一方「日常生活におけるパソコンの使用頻度」については、60歳以上・未満において「毎日」と回答した割合が、それぞれ全体の94.8%と95.5%という結果になった。この調査結果より60歳以上の高齢者において、パソコンの所有率の高まりと同時に利用についても毎日の生活において必需品として定着していることが窺える。
【図表5-1】 同世代の知人・親類等で自宅にパソコンを所有している人の割合
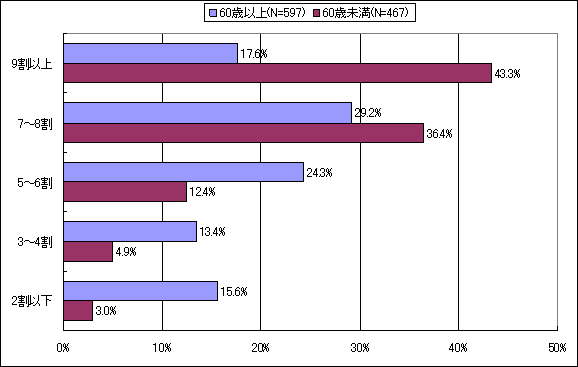 (複数回答) 【図表5-2】 日常生活におけるパソコン使用頻度
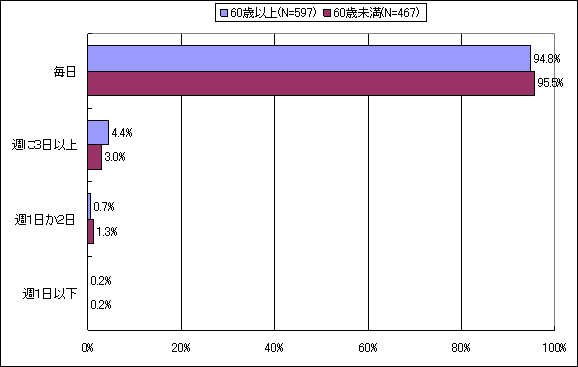 (複数回答) 6.パソコンの利用動向 : 利用用途についてパソコンの主な利用用途について尋ねたところ、60歳以上・未満の多数が「趣味や娯楽」の充実のための利用と回答している。また、それ以外では特に「地域活動」や「仕事」による利用に大きな開きが見られる。この調査結果より60歳以上の高齢者は、趣味や娯楽のためにパソコンを利用する以外に、地域でのコミュニケーションや活動にパソコンを活用していることが窺える。
【図表6-1】 自宅パソコンの主な用途
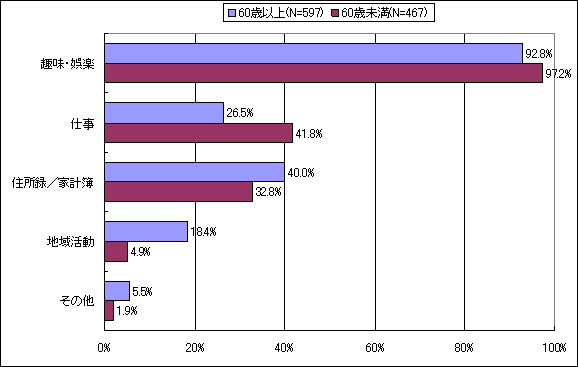 (複数回答) 7.パソコンの利用動向 : ソフトウェアの使用主に使用しているソフトウェアについては、60歳未満はインターネットを介して使用する「電子メール」や「ウェブブラウザ」の使用が中心となっている。一方60歳以上の高齢者においては、「電子メール」の使用が定着していることは窺えるが、同じインターネットを介して使用する「ウェブブラウザ」の使用は比較的低く、むしろインターネットを介さずに使用する「ワープロ」や「年賀状・宛名作成」といったワープロソフトの使用が高くなっていることが分かる。前項で抽出された傾向をつなげて考えるのであれば、60歳以上の高齢者は地域とのつながりを意識していることが分かるが、そのコミュニケーション手段としての「電子メール」、文章や手紙でのコミュニケーションを図る上で便利な「ワープロ」や「年賀状・宛名作成」といったソフトを使用している傾向が強く窺える。
【図表7-1】 自宅のパソコンで利用しているソフトウェア等
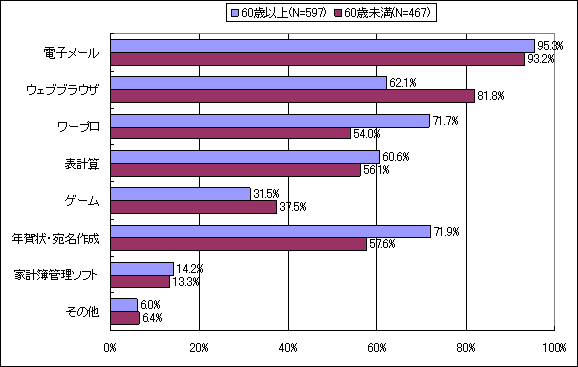 (複数回答) 8.パソコンの利用動向 : インターネットへの接続機器としてのパソコンインターネットを利用する際に最も使用する接続機器について尋ねたところ、60歳以上・未満において98.8%と97.6%が「パソコン」と回答している。次いで使用する・今後使用したい機器についても尋ねたところ、60歳以上・未満において「携帯電話(PHS含)」が33.7%と58.9%と大きな開きがあることが分かる。つまり、60歳以上の高齢者はパソコンのみの利用が大半であり、60歳未満はパソコンのみならず携帯電話やPDAといった移動端末も併用してインターネットへアクセスしていることが分かる。 【図表8-1】 インターネットを利用する際に、最も利用頻度の高い機器
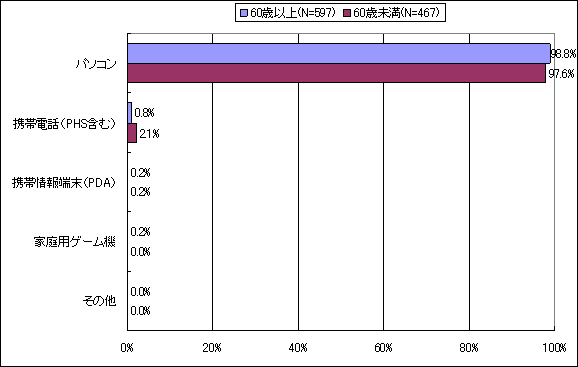 (複数回答) 【図表8-2】 インターネットを利用する際に、最も利用頻度の高い機器以外で使用している、
もしくは今後使用したい機器
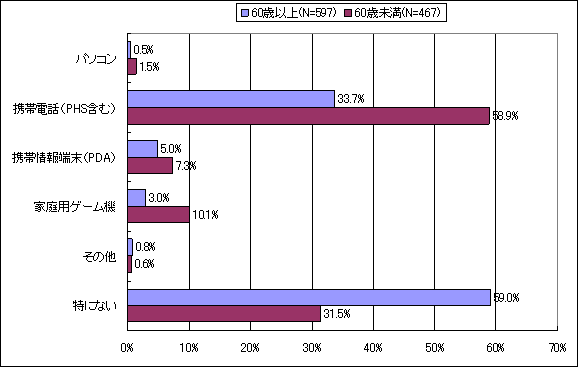 (複数回答) 9.パソコンの利用動向 : セキュリティ対策実施動向インターネットへの接続機器としてのパソコンにおけるセキュリティ対策について尋ねたところ、60歳以上・未満において65.5%と76.2%が「ウイルスチェックソフトの導入」、63.0%と64.2%が「不審なメールは開かない」、44.7%と31.1%が「プロバイダのウイルスチェックサービスを利用」などとなっている。60歳以上の高齢者においては、パソコン上の設定やインストール等の手間がかからず手軽にできる対策として「不審なメールは開かない」や「有害サイトなどの閲覧制限」、「プロバイダがオプションで用意するウイルスチェックサービス」等を取り入れている傾向が窺える。また特記すべきは、60歳以上・未満において「特に行っていない」が2.7%と2.4%という調査結果から、9割以上の方が何かしらの対策を講じていることが窺える。 【図表9-1】 自宅のパソコンで利用・実施しているセキュリティ対策
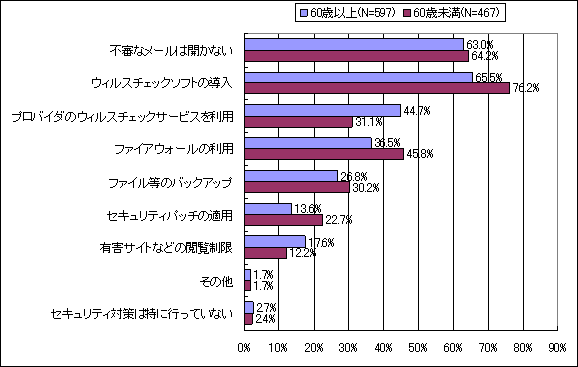 (複数回答) 10.パソコンの利用動向 : ユーザー補助機能の使用についてパソコン操作時のユーザー補助機能の使用について尋ねたところ、60歳以上の高齢者において48.6%と半数近くの割合で「文字サイズを大きくする」機能を使用するという回答を得た。一方で60歳未満においては「特になし」という回答が79.7%を占めた。 この結果を踏まえて今後使用したいユーザー補助機能について尋ねたところ、60歳以上の高齢者からタッチパネル式入力や音声入力、点字入出力、音声読み上げ機能等の補助機能をより使用したいとの回答が得られた。この調査結果から見える60歳以上の高齢者にとって見やすさや入力しやすさといった使いやすさに対するニーズが高いことが窺える。 【図表10-1】 自宅のパソコンで使用しているユーザー補助機能
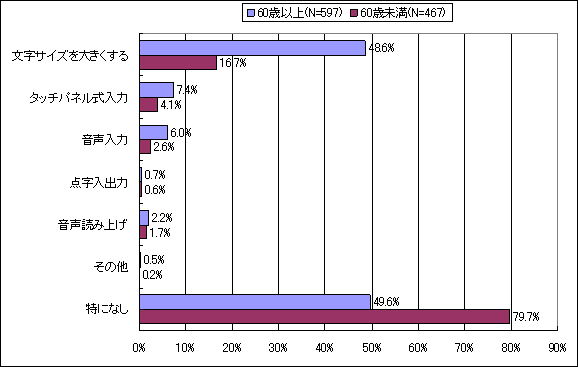 (複数回答) 【図表10-2】 今後使用したいユーザー補助機能
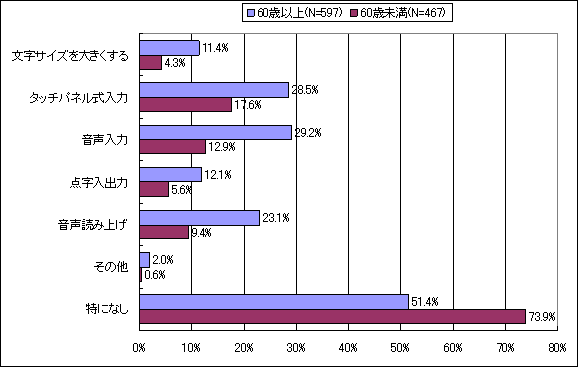 (複数回答) 11. インターネットの利用動向 : 基本利用動向「趣味や生活関連情報の入手」や「ニュース閲覧」、「クイズ・アンケートの応募」といった項目で60歳未満に劣らず60歳以上の割合が高いことから、若年層に比べて比較的余暇がある高齢者も例に漏れず、積極的に趣味や生活などの情報検索にインターネットを活用していることが分かる。これに紐付けて「オンラインショッピング」の利用も比較的高くなっている。 また、特筆すべきは、60歳以上の高齢者は資産運用を目的とした「オンライン証券等取引」の利用が60歳未満に比べ高い。預金金利の低水準や手数料低下などを背景に、近年オンライントレード等の利用が普及拡大しているが、60歳以上の高齢者がこれらを積極的に利用していることが窺える。 さらにコミュニティ系においては、60歳以上の高齢者は「電子メール」の利用は高いものの、「ブログ」、「SNS」、「掲示板・チャット」といったコミュニティサイトの利用は割合低くなっている。高齢者における日常のコミュニケーション手段として、電子メールが定着していることを考えれば、地域活動や趣味の交流を目的としたコミュニティサイトの利用が今後普及拡大していく可能性がある。 【図表11-1】 インターネットの利用用途
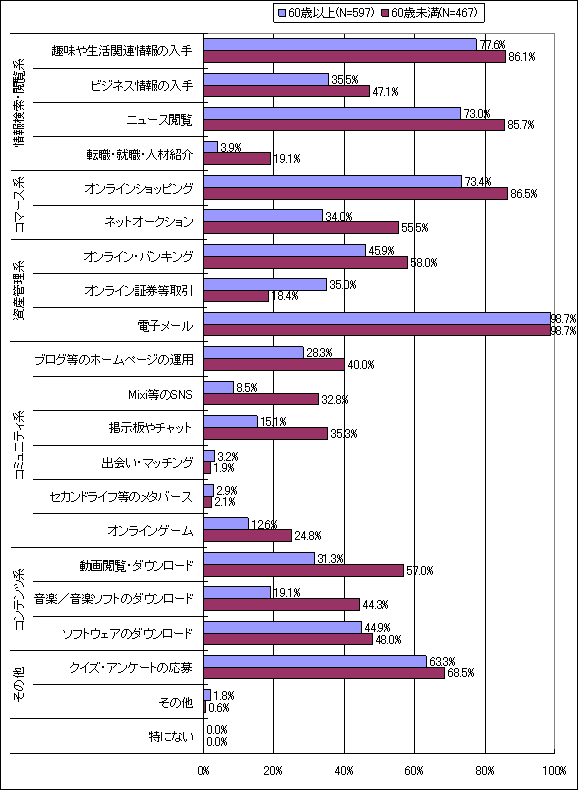 (複数回答) 12.インターネットの利用動向 : 公的機関におけるインターネットサービスの利用状況公的機関が提供するインターネットサービスの利用について尋ねたところ、60歳以上・未満において「省庁の行政情報検索」で27.0%と14.8%、「e-Tax/eLTAX(税金の電子申告・納付) 」で18.9%と10.3%、「図書館の利用申請」で14.2%と13.9%と続いた。特記すべきは「特に無い」という回答で60歳以上・未満において45.7%と63.2%の差異があったことである。この調査結果を見る限りでは、60歳以上の高齢者は60歳未満より公的機関におけるネットサービスに対して関心を持っていることが窺える。 そこで今後の利用について尋ねたところ、60歳以上の高齢者において「パスポートの申請」、「許認可の申請」、「地方自治体への申請」、「医療サービス」、「公的施設の利用申請」、「住基ネット」等の要望が高かった。公的サービスの利用を阻害する要因の一つとして、手続きや申請の煩雑さがあげられるが、こうした煩雑な処理を自宅のインターネットで手軽にできるようになるとすれば、高齢者層にとってより身近なサービスとして利用が拡大することが十分に考えられる。 【図表12-1】 これまでに利用したことのある公的機関の行うインターネットサービス (複数回答) 【図表12-2】 今後利用したい、または提供を期待する公的機関のインターネットサービス (複数回答) 13.インターネットの利用動向 : インターネットに対する不満や不安インターネットサービスにおける不安や不満について尋ねたところ、「ウイルス感染」、「プライバシーの保護」、「情報流出の危険性」に関して、60歳以上の高齢者も60歳未満に劣らず敏感に反応している傾向が窺える。こうした不安はセキュリティ技術の向上である程度対策は打てるものであるが、60歳以上の高齢者にとっては、その高度な技術が逆に難解なこともあり十分な対策を打てていないと考えられる。 一方で「有料・無料サービスの区別が困難」、「有害・悪質・違法情報」、「電子決済などの信頼性」、「フィッシング詐欺等の犯罪」、「ウェブ上のひぼう・中傷」、「匿名性の悪用」といった技術的な対策が困難な事項に対する不満や不安を取り除くには、警察の対応や法律の整備といったソフト面での強化策が必要である。既に高齢者の生活にもインターネットの利用が浸透してきていることを鑑み、より安心して参加できるインターネット環境の整備が急がれる時であると考えられる。 【図表13-1】 インターネットを利用する際に感じる不安・不満 (複数回答) |
||||||||||||||||||||||||||||||
現在ご覧のページは当社の旧webサイトになります。トップページはこちら