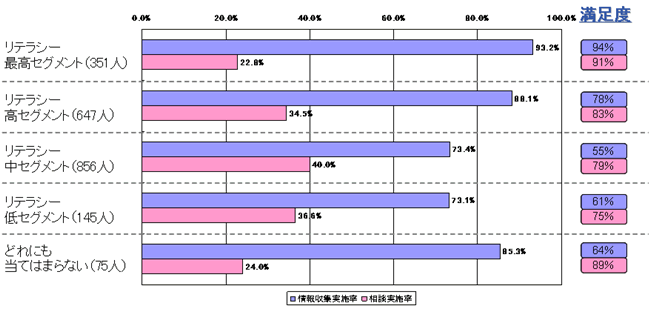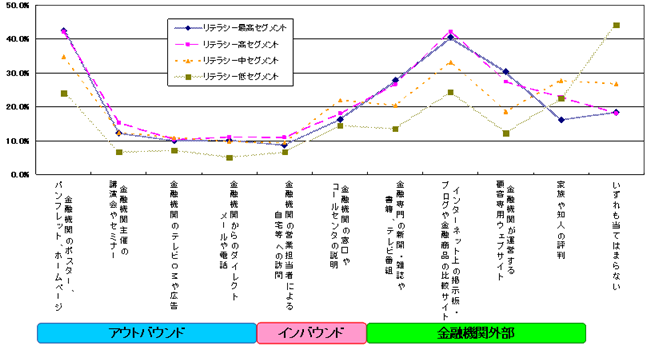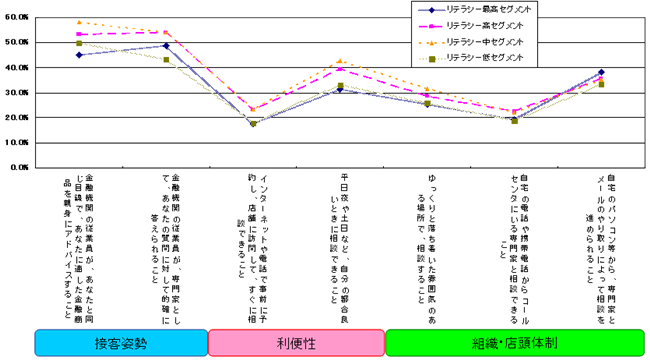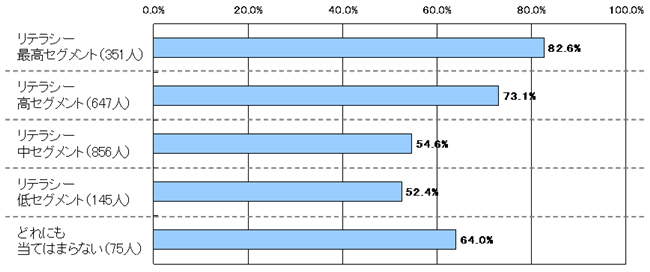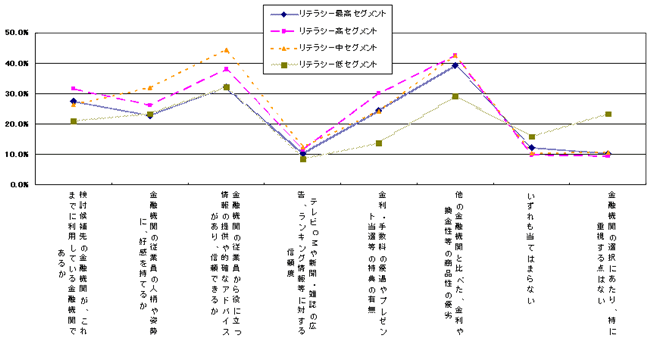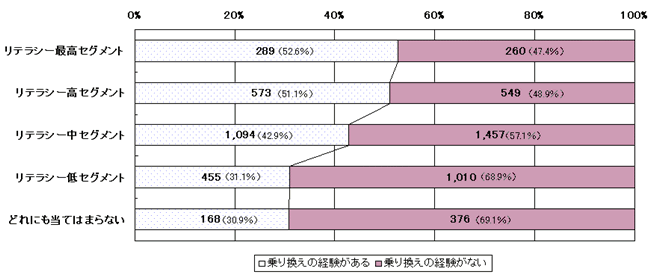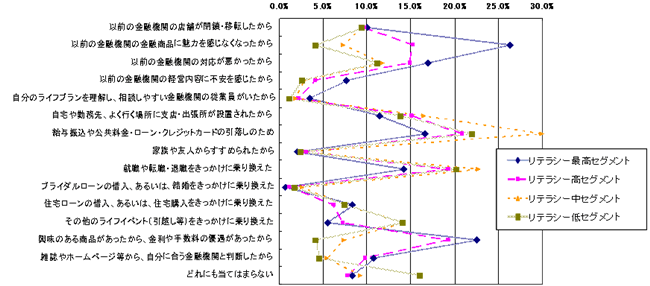(1)顧客の購買行動: 購買の基本方針
自分に最適な金融商品の選択方法について尋ねたところ、まず、「自分ひとりで分析し、自分に合った金融商品を選択したい」の比率は、金融リテラシーの高いセグメントから順に、「最高」が46.6%、「高」が24.4%、「中」が14.6%、「低」が19.3%となっている。一方、「信頼できる人に相談しながら、金融商品を選びたい」の比率は、「最高」が13.7%、「高」が14.6%、「中」が21.0%、「低」が19.8%となっている。
また、投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等、以下同じ)に対する運用方針について尋ねたところ、「多少のリスクが伴っても、高リターン(収益)を見込めること」の比率は、リテラシーが高いセグメントほど高い傾向にある(「最高」が36.8%、「低」が4.8%)結果となった。
Q: 自分に最も適した金融商品は何か、商品内容も含め詳しくご存じですか。当てはまるものをひとつお選びください。(n=6,250)
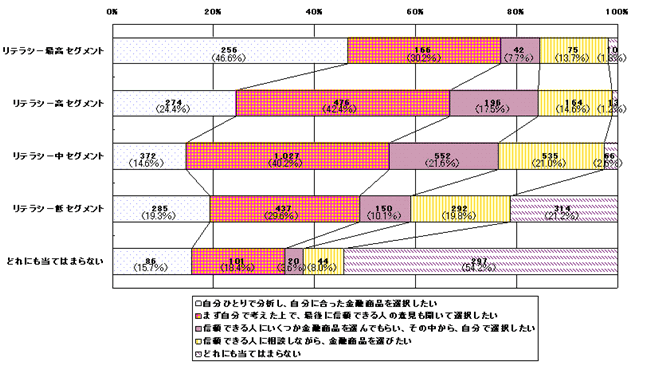
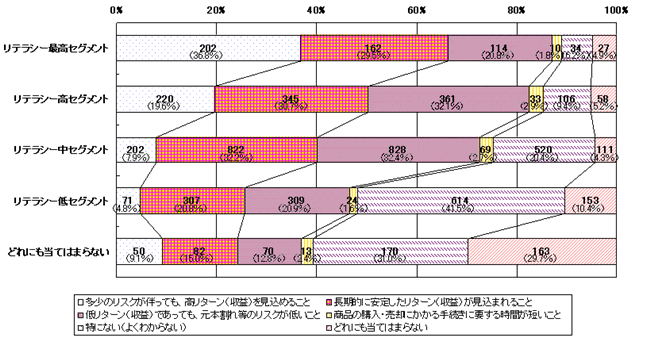 Q: 投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等)を運用する場合、あなたが最も重視する要素として、当てはまるものひとつお選びください。(n=6,250)
Q: 投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等)を運用する場合、あなたが最も重視する要素として、当てはまるものひとつお選びください。(n=6,250)
(2) 顧客の購買行動: 情報収集・相談の経験の有無と満足度
投資系金融商品の購入検討の際、情報収集(金融商品の情報を収集する行為)と相談(自分以外の第三者と金融商品の購買を相談する行為)の実施の有無を尋ねたところ、リテラシーが最も高い利用者の場合、情報収集の実施率が93.2%、相談の実施率が22.8%となっている。その他の利用者における情報収集と相談の実施率は、リテラシーレベル「高」が88.1%と34.5%、「中」が73.4%と40.0%、「低」が73.1%と36.6%となることから、リテラシーが高いほど情報収集を極めて重視、リテラシーが低いほど情報収集への重視度が下がり、その代わりに相談を相対的に重視する、という傾向が読み取れる。
さらに、情報収集や相談を実施した回答者に、どの程度、情報収集・相談を行えたかを尋ねて、情報収集・相談に対する満足度を検証したところ、いずれも、リテラシーが最も高い利用者が最も満足している結果となった(情報収集:94%、相談:91%)。「最高」以外のリテラシーセグメントにおける情報収集と相談に対する満足度は、「高」が78%と83%、「中」が55%と79%、「低」が61%と75%となり、リテラシーが高いほど満足度が高くなる傾向にある。特に、情報収集については、重視度合いを反映した実施率と同様に、満足度も各々のセグメント間の差が大きくなっている。
Q: 投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等)の購入を検討したことがありましたか。検討したことがある場合、ご検討された金融商品の特徴・内容や関連する情報を把握するために、金融機関を通じて、あるいは、ご自身で情報収集を行いましたか。
投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等)の購入を検討した際、どなたかと相談しましたか。
(n=2,074、但し、前段の「情報収集の実施の有無」に関する設問に対する「検討したことがない」回答者を除いた)
Q: あなたは、どの程度、情報収集を行うことができましたか。(n=1,695)
あなたは、どの程度、相談を行うことができましたか。(n=716)
※満足度は、「必要な情報を、ほほ収集できた」と「必要な情報のうち、半分程度、収集できた」の回答比率の合計、「必要な相談をほぼ行えた」と「必要な相談のうち、ある程度、行えた」の回答比率の合計を、当てはめた。
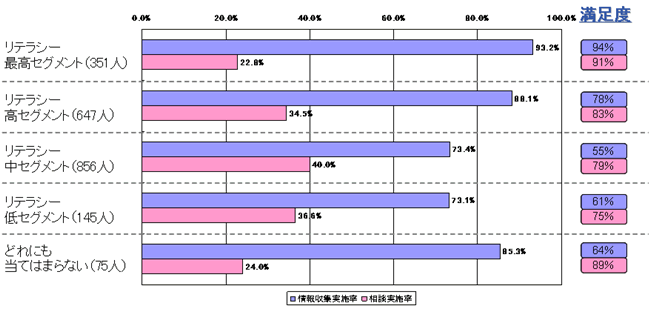
(3) 顧客の購買行動: 情報収集時に重視する情報源
投資系金融商品の購入検討の際、情報収集時に重視する情報源について尋ねたところ、リテラシーが高い利用者(「最高」「高」)ほど、情報収集の実施率の高さを反映して全般的に数値が高く、特に、「金融機関のポスター・パンフレット、ホームページ」や「インターネット上の掲示板・ブログや金融商品の比較サイト」を重視している(「最高」「高」は、いずれも40%を超えているが、「中」は30%台、「低」は20%台にとどまっている)。また、リテラシーが中程度の利用者は、「家族や知人の評判」が27.7%、「金融機関の窓口やコールセンタの説明」が21.8%と、他の利用者よりも重視する選択者の割合が高かった。
Q: 関心のある金融商品の購入や借入などを検討する場合、重視する情報源はどれですか。金融商品ごとに、当てはまるものをすべてお選びください。(n=6,250)
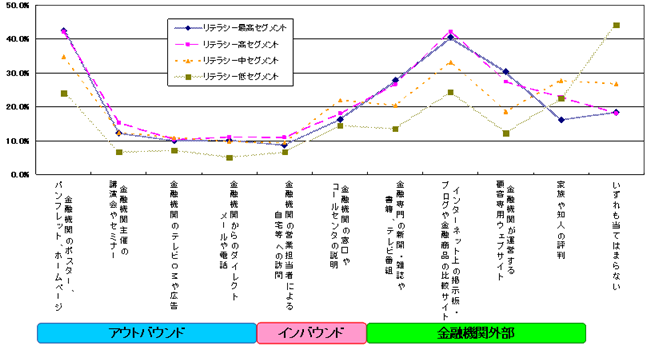
(4) 顧客の購買行動: 相談時の要望
投資系金融商品の購入検討の際、より気軽に相談するために適した環境について尋ねたところ、「金融機関の従業員が、あなたと同じ目線で、あなたに適した金融商品を親身にアドバイスすること」(45.0%~58.1%)や「金融機関の従業員が、専門家としての、あなたの質問に対して的確に答えられること」(43.3%~53.9%)という接客姿勢に関する要望が、全体的に高かった。次いで、「平日夜や土日など、自分の都合の良いときに相談できること」(31.3%~42.8%)が続いた。なお、リテラシーが最も高い利用者は、相談をあまり重視しないため、全般的に他のセグメントよりも数値が低い結果となった。
Q: 金融商品の相談をより気軽にできるようにするためには、金融機関にどのような要素が必要と思いますか。金融商品ごとに、当てはまるものすべてお選びください。(n=6,250)
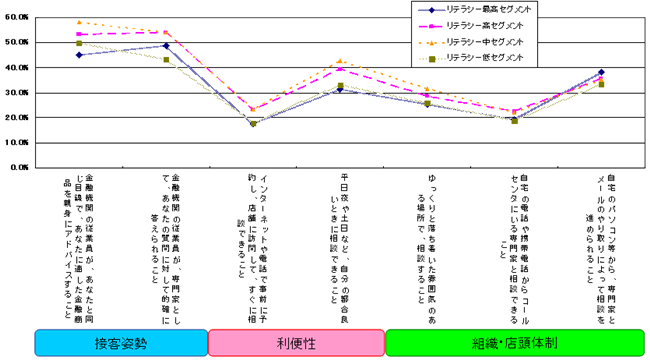
(5) 顧客の購買行動: 金融商品の購入率
投資系金融商品の購入について、情報収集・相談を踏まえた取引決定の有無を尋ねたところ、「最終的に、取引することを決定した」の比率は、リテラシーの高いセグメントから順に、「最高」が82.6%、「高」が73.1%、「中」が54.6%、「低」が52.4%となり、リテラシーの高低が購入率に差異をもたらしている。
また、購入決定の際、取引する金融機関の選択において重視するポイントを尋ねたところ、「最高」「高」「中」セグメントは、「他の金融機関と比べた、金利や換金性等の商品性の優劣」や「金利・手数料の優遇やプレゼント当選等の特典の有無」を重視している。リテラシー中セグメントに関しては、「金融機関の従業員から役に立つ情報の提供や的確なアドバイスがあり、信頼できるか」や「金融機関の従業員の人柄や姿勢に、好感を持てるか」を支持する比率も高い結果となった。
(6)金融機関の乗り換え経験とその理由
一番よく利用する金融機関を乗り換えた経験と、乗り換え経験者の乗り換え理由を尋ねたところ、リテラシーが高いセグメント(「最高」「高」)は、「以前の金融機関の金融商品に魅力を感じなくなったから」(26.3%、15.2%)や「興味のある商品があったから、金利や手数料の優遇があったから」(22.5%、19.2%)等の主体的な理由に基づいて、50%以上が乗り換えを経験している(52.6%、51.1%)。
一方、リテラシーの低いセグメント(「中」「低」)は、乗り換え経験の比率が低く(42.9%、31.1%)、乗り換え理由も、「給与振込や公共料金・ローン・クレジットカードの引落しのため」(29.9%、22.0%)や「就職や転職・退職をきっかけに乗り換えた」(22.7%、20.2%)、「その他のライフイベント(引越し等)をきっかけに乗り換えた」(14.2%、14.1%)など何らかのライフイベントを理由に挙げる回答比率が、相対的に高い結果となった。
Q: これまでに、一番よく利用する金融機関を変更した経験がありますか。(n=6,231)
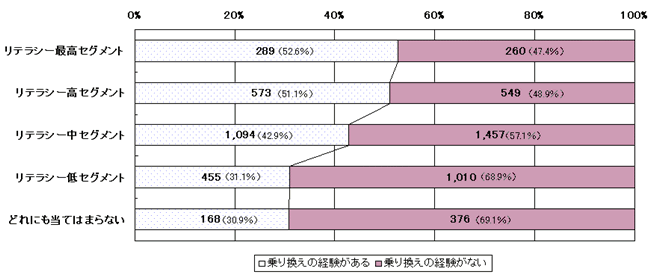
Q: なぜ、一番よく利用する金融機関を乗り換えたのですか。当てはまるものをすべてお選びください。(n=2,579)
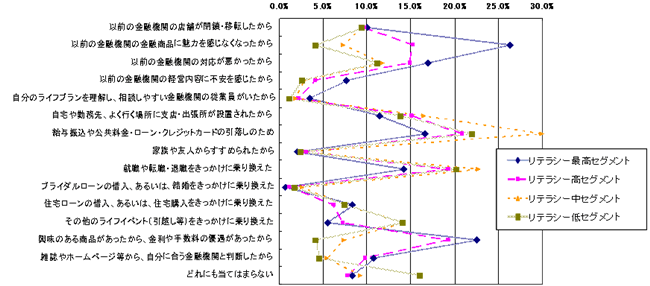


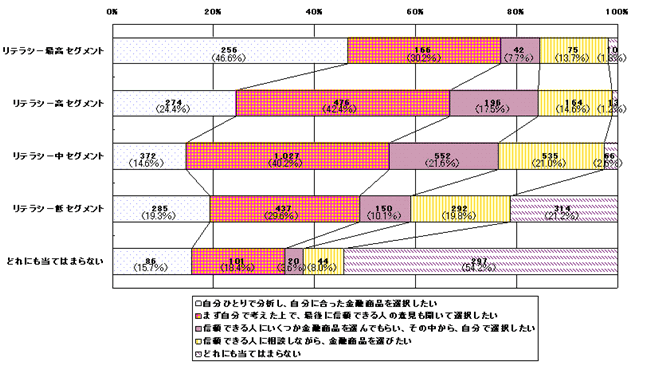
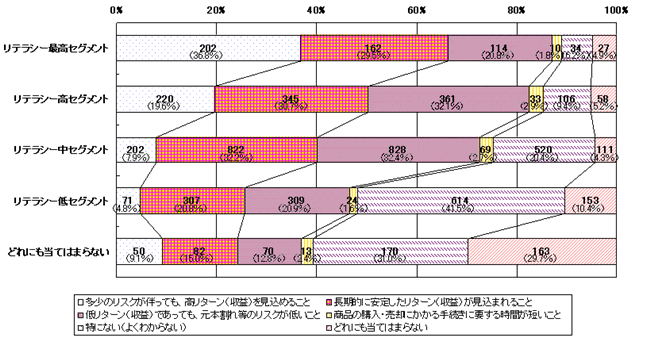 Q: 投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等)を運用する場合、あなたが最も重視する要素として、当てはまるものひとつお選びください。(n=6,250)
Q: 投資系金融商品(外貨預金、国債、株式、投資信託、REIT、FX等)を運用する場合、あなたが最も重視する要素として、当てはまるものひとつお選びください。(n=6,250)