(「月刊金融ジャーナル」2015年3月号より)
オムニチャネル時代
有人店舗の現状と将来像
金融コンサルティングユニット
マネージャー 西原 正浩
ATMやインターネットといった非対面チャネルの利用者が増える中、金融機関の有人店舗への来店客数は減っている。従来の金融機関の店舗はどこも似たようなものが多かったが、今後どのような動きをたどるのだろうか。本稿では、有人店舗数の推移、店舗オペレーションの現状と課題を俯瞰しながら、金融サービスにおいて今後求められる有人店舗のあり方、役割について論じたい。
有人店舗数の推移と
「新たな形態の銀行」の伸び
図表1は我が国における金融機関の店舗数推移を過去30年超にわたって示している。業態別に見みると、最も多い有人店舗網を有しているのは郵便局(ゆうちょ銀行)である。年度による増減はあるものの、ここ30年を見ると増加傾向にあり、現状で2万4,000超の店舗網を有している。逆に、二番目に多い店舗網を有する農協は、半数程度に店舗数を減らしている。他の業態はバブル崩壊までは店舗数を増やしてきたものの、それ以降はいったん減少し、その後は安定的な状況が続いている。
(図表1)主要業態別 国内金融機関の店舗数の推移
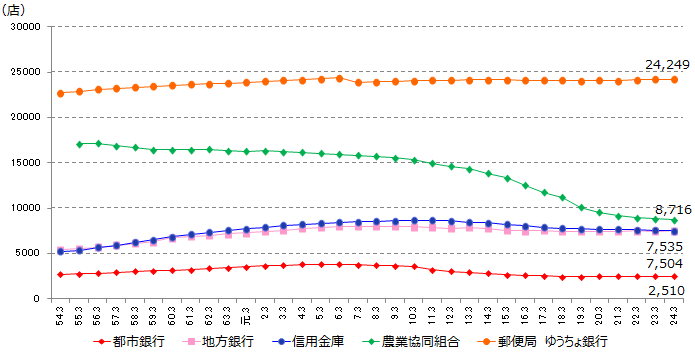
(出典:日本金融年鑑よりNTTデータ経営研究所が作成)
有人店舗数が近年変わらない中で、店舗を持たない「新たな形態の銀行」が急激に規模を大きくしている。図表2はインターネット専業銀行をはじめとした「新たな形態の銀行」の預金量である。これらの銀行の顧客とのアクセスポイントのメインは非対面チャネルである。「新たな形態の銀行」の預金量は2014年度末に11兆円に達し、第二地銀の4分の1、労働金庫の6割程度の規模に膨らみ、大きな存在になっている。
(図表2)新たな形態の銀行の預金残高推移
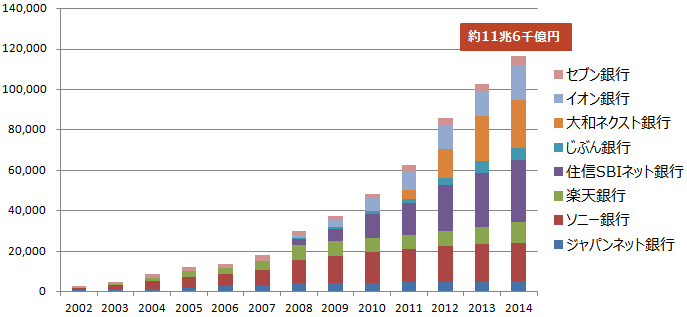
出典:各社IR資料に基づきNTTデータ経営研究所が作成
これらの状況を踏まえると、三点指摘することができる。一点目は、農協が店舗を減らす一方で郵便局が店舗数を維持していることから、郡部特に中山間地域において、郵便局の存在感が相対的に高まっていると考えられる。
二点目は、地方銀行と信用金庫の店舗数がさほど変わらないことである。これは、地域の市街地にある店舗数が、全国的にあまり変化がないものの、地方全体の人口減少や中心市街地の空洞化・シャッター通り化を踏まえると、既存の営業店が来店客数に対してオーバースペックになっている可能性があるものととらえることができる。
三点目は、ネット銀行の伸びを考えると、既存の金融機関の顧客は、若年層や預金金利に敏 感な層を中心に流失しているのではないかと推測できる。
このような状況は、徐々に金融機関の店舗のあり方に影響を与えている。一点目に指摘した 郡部の状況に対しては、二つの動きがある。
まずは支店の代理店化である。2000年代に入って、母店子店制の導入を通じて、来店客数の少ない支店の省力化が図られてきたが、更なるコストダウンと職員の退職年齢引き上げに伴い、代理店を担う銀行子会社を設立し、子会社が嘱託行員を使いながら代理店を運営する形態をはじめている場合がある。
二点目は、一部の銀行において移動店舗車が導入されはじめている。移動店舗車導入は災害対 応の切り札でもあり、筆者が銀行関係者と会話をしていると、導入していない銀行でも関心度合いは高い。
店舗オペレーションの現状
農協を除いて店舗数は維持されているものの、金融機関の店舗内オペレーションを巡る外部環境・内部環境は近年、大きく変化している(図表3)。店舗オペレーションに影響を与えている原因は三点挙げられる。一点目は来店客数の減少である。これはATMやネット銀行といった非対面チャネルに顧客のアクセスポイントが移行していること。特にネット銀行の機能拡大により、来店しなくても各種手続きができるようになったことの影響が大きい。また、地方では店周の人口が減少しており、このことも来店客数の減少の原因になっている。二点目は事務集中化の進展により、支店の事務処理数が減っていることだ。
(図表3)金融機関の店舗を取り巻く影響
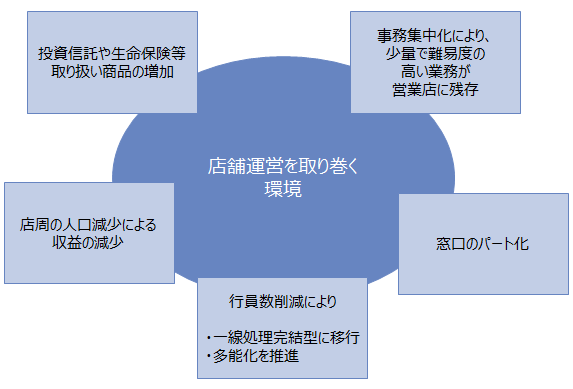
これら二点を原因として、支店に配属される行職員数は減少し、かつパート化が進んでいる。このような状況下で、パート行職員を含めた支店行職員の多能化や、一線処理完結型への移行が見られる。
以上二点は事務処理が減っていくベクトルの話しであるが、三点目は逆の観点で、投資信託や生命保険等、取扱商品数が増大していることにより有人店舗の業務が増大していることが影響している。事務集中化の進展で大量定型処理は支店から事務センターに移管されたものの、少量で難易度の高い事務が支店に残存している。このような中で投資信託や生命保険が導入され、かつこれらの商品を取り扱う際の情報システムによるサポートは、メガバンクを除くと手薄になっていて、店舗オペレーションにおける最大の問題になっている。加えて、投資信託や生命保険は控えを保管する必要があり、書類の集中保管がなされていない金融機関では、店舗スペースを圧迫する要因になっている。
ロビーとカウンターをめぐる状況
現状、金融機関の有人店舗に来店する顧客は、法人顧客、高齢者、相談が必要な用向きの人の三点に大きく分類することができる。このような中で、顧客との接点であるロビーとカウンターにも変化が見られる。ロビーについては「0線化」を図る動きと、ロビースタッフ拡充の二つの動きが見られる。「0線化」とは、ロビーに顧客が操作できるキオスク型端末を設置することにより、ロビーで事務処理を行うことである。
代表的なものは、りそなグループのクイックナビ、西日本シティ銀行などの税公金収納機、信用金庫で導入されつつあるタッチ伝票などが挙げられる。これらは従前のATMで処理できないものを端末設置によって機械処理に移行させる試みである。米国のウェルズ・ファーゴ銀行でもテラーがサポートする新型ATMが導入されつつあり、「0線化」はローコスト運営の一つの解であるととらえることができる。
ロビースタッフは来店客の誘導や伝票記入のサポートが主な業務であったが、近年ではセールス・スタッフの一員と位置付けている銀行がある。そのため、ロビーに管理職を配置するケース、また預かり資産営業やローンの担当者がロビーに立つ銀行もある。
カウンターについては、ここ10年程度で相談ブースが導入されてきているものの、地域金融機関の多くは従来型のハイカウンターとローカウンターの二つのカウンターで顧客に対応している。ハイカウンターは、顧客が高齢化していく中で、立たせて処理するのが難しくなってきているという声をよく聞く。またローカウンターはハイカウンター以上に問題があると認識している。
従来、ローカウンターでは口座の新規契約や定期預金の預け入れなどがメインであったが、投資信託や生命保険の販売により、従来よりも顧客がローカウンターに座る時間が長くなってきている。よって、来店客数が減っているにも関わらず、ローカウンターが不足しているという銀行が出てきている。また、ローカウンターはロビーから丸見えの場合が多く、顧客が座りたがらない場合があるとの声も聴く。これは、長くローカウンターに座っていると、来店した近所の方の目に触れる機会が増え、「あの人は銀行のローカウンターに長く座っているから、お金を持っているのではないか」と変に勘繰られる場合があると、顧客が思う場合があるからである。
投資信託は投資経歴を聞いたり、生命保険は病歴を聞いたりする必要があるが、ローカウンターのようなオープンスペースでは十分な話しができないと指摘する行員も多い。預かり資産系の営業には各種のパンフレットが必要であるが、ローカウンターには営業店端末に加えてノートパソコンが置いてある場合が多く、かつパンフレットも広げるとA3の大きさになるため、カウンターのスペース不足を指摘する声もある。
来店誘致の工夫
金融機関は長らく、顧客を非対面チャネルに誘導して営業店の省力化を図ってきた。しかし、現状では来店する多くの顧客がビジネス拡大にはつながらなくなってきている。どのようにしてビジネスチャンスにつながる顧客を来店させるか、各行が様々な取り組みを行っているが、筆者は、来店誘致の切り札の一つは生命保険ではないかと考えている。
数年前からネット専業生保が出てきているが、これらの企業でも有人店舗で販売するように方向転換を図っている。生命保険は長期サポートをする商品であるため、対面で相談したいというニーズが強い商品である。このようなニーズに対応するため、銀行の中に保険ショップを入れてみたり、コールセンターで生命保険の勧誘を行ったりして、来店誘致につなげる取り組みが行われている。
また、スマートフォンのGPS機能を活用して、支店がどこにあるかすぐにわかるアプリを提供して、来店誘致につなげている銀行もある。
今後の有人店舗
今後の有人店舗は、来店客数の多寡に応じて、フルブランチ機能を有する店舗と、軽量店舗に分化していくのではないかと考えられる。フルブランチ機能を有する店舗では、従来のようなローカウンターとハイカウンターではなく、キオスク端末等を用いて顧客にセルフ処理させるタイプのカウンターと、じっくり相談ができるブースの二つが用意されるだろう。
一方で、軽量店舗を実現させるためには、預金や為替、諸届に関する事務集中化を更に進め、かつ投資信託や生命保険の販売事務プロセスの電子化を行い、金庫レス、ペーパレス、場合によってはキャッシュレスを図っていくことになるであろう。
以上のような店舗装備を整えた上で、来店誘致策として、コールセンターやスマートフォン、更にビーコン等の新しいデバイスを導入して対応していくことが考えられる。
これらに対応するためには、金融機関自らがマーケットや店舗の状況を見ながら、技術革新の動きを取り入れていくことが必要になるだろう。

