2009年7月30日
NTTデータ経営研究所
最新の脳科学技術を幅広く導入した
オープンイノベーションモデルのニューロコンサルティングサービスを開始
~ATR-Promotions、産総研、脳機能研究所ら専門企業・研究機関と幅広く連携~
株式会社NTTデータ経営研究所
株式会社 ATR-Promotions 株式会社 脳機能研究所 株式会社NTTデータ経営研究所(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:谷口和道)は、最新の脳科学技術を国内外の脳科学関連企業あるいは研究者・研究機関から幅広く導入することでお客様の企業活動を支援する、オープンイノベーションモデルのニューロコンサルティング(注1) サービス(以下、本サービス)を2009年8月3日より本格的に開始いたします。 またこれに伴い、株式会社ATR-Promotions(本社:京都府相楽郡、代表取締役社長:正木信夫)、及び株式会社脳機能研究所(本社:横浜市緑区、代表取締役社長:武者利光)の脳科学関連企業2社と業務提携、さらに独立行政法人産業技術総合研究所(理事長:野間口有)の人間福祉医工学研究部門(部門長:赤松幹之)及び脳神経情報研究部門(部門長:久保泰)と協力関係を構築いたしました。今後は、これらの企業及び研究機関に代表されるような脳科学関連企業・研究機関と一層幅広く連携し合うことで、脳科学の産業応用を適切かつ強力に推進して参ります。 脳科学は、我々人間の認知・行動・記憶・思考・情動・意志といった「心」の働きを解明する最先端の科学領域であり、現在飛躍的な発展を遂げつつあります。それと同時に、脳科学は、多様な学問分野及び産業分野から形成される融合型の科学領域であるという特徴を持つことから、そこから生まれる様々な研究成果は広範な分野に応用され、今後産業や社会に革新的なイノベーションがもたらされる可能性が高いと考えられます。 このような認識のもと、NTTデータ経営研究所は、脳科学領域における各種の調査研究や脳科学技術を利用したコンサルティング事業等を通じ、脳科学の産業応用に関する知見やノウハウを蓄積するとともに、種々の脳科学技術を保有する脳科学関連企業や、最先端の研究に取り組む脳科学研究者及び研究機関と幅広いネットワークを構築して参りました。 そして、これらの活動を通じ、「脳科学は広範囲な学問領域に及ぶため理解が難しい」「ビジネスへ応用するノウハウがない」「脳科学技術の選定が難しい」「安全面・倫理面における配慮が難しい」といった民間企業が抱えるいくつかの課題を確認するとともに、産業応用を成功させるためには、これらの課題を適宜解決しつつ、脳科学技術を保有する脳科学関連企業あるいは研究者・研究機関と、ユーザー側である民間企業とを適切にマッチングし、円滑なコラボレーションを促進する仕組みが必要であるとの認識に至りました。 そこで、NTTデータ経営研究所では、これまでに蓄積した知見・ノウハウ及び構築したネットワークを最大限に活かし、お客様の商品開発・マーケティング等の様々な企業活動における個別ニーズにあわせた最適な脳科学技術と、それらを保有する脳科学関連企業あるいは研究者・研究機関と協業して、技術導入から事業化までを支援する、オープンイノベーションモデルのワンストップ・コンサルティングサービスを本格的に開始することに致しました。 本サービスの開始にあたり、NTTデータ経営研究所は、脳科学技術の産業応用について国内で特に数多くの実績を持つ株式会社ATR-Promotions及び株式会社脳機能研究所の2社と業務提携を致しました。 ATR-PromotionsはfMRI(functional Magnetic Resonance Imaging ; 機能的磁気共鳴画像法)を利用した脳機能イメージング支援事業で国内最高峰の技術を有する企業です。また、脳機能研究所は、独自開発の感性評価技術である「感性スペクトル解析システム(以下、ESA)」(注2)を所有する技術先行型の東京工業大学発のベンチャー企業です。 さらに、産業応用性の高い脳科学研究を実施する独立行政法人産業技術総合研究所の人間福祉医工学研究部門及び脳神経情報研究部門と協力関係を構築し、脳科学の最先端の知見について幅広く助言を受けると同時に、これら研究機関の脳科学関連の技術シーズの応用可能性を探索します。 NTTデータ経営研究所は、これら上記の企業や研究機関と緊密に連携し合い、各企業・機関が保有する脳科学技術シーズやノウハウを最大限に活用しながら、お客様の企業活動を支援して参ります。さらに今後もより多くの脳科学関連企業や脳科学研究機関と幅広く業務提携及び協力関係を構築することで、一層コンサルティングサービスの強化・拡充を図って参ります。
(注1) ニューロコンサルティングとは ニューロコンサルティングとは、脳科学技術を利用して、商品開発・マーケティングをはじめとした様々な企業活動の一助とする、NTTデータ経営研究所が独自に開発したコンサルティング手法です。 (注2) 感性スペクトル解析システム(ESA)とは 脳機能研究所が開発した感性スペクトル解析システム(ESA:Emotion Spectrum Analysis)では、供試品や供試環境に対する対象者の心の状態を、従来のアンケート手法だけでは抽出しにくかった人間の感性にかかわる3つの脳波(シータ波・ベータ波・アルファ波)データから、人間の感情を「ストレス、緊張度」、「喜び、満足感」、「悲しみ、落ち込み」、「リラックス」の4つの独立な基本成分に分解して、それぞれのレベルの時間的な変化から心の状態の変化を定量的に分析することができます。 以上 ◆ 本件に関するお問い合わせ ◆
株式会社NTTデータ経営研究所 株式会社ATR-Promotions 株式会社脳機能研究所 [ 補足 ] 【サービス提供の背景】 現在、脳科学研究は、ヒトの脳活動を可視化するニューロイメージング技術の開発により、急速に進展しております。これらのニューロイメージング技術やそれを利用した様々な技術の発達に伴い、脳科学は、以下に示すような幅広い用途への産業応用が進められつつあります。
このように産業界への展開を見せつつある脳科学技術ですが、民間企業がこれらの技術を導入するにはいくつかの課題があります。 まず脳科学は種々の学問分野の知を結集した融合科学領域であることから、その全体像を理解することは容易ではありません。脳活動を計測する技術も、EEG(Electroencephalogram ; 脳電位)やfMRI、NIRS(Near Infra-Red Spectroscopy ; 近赤外分光法)など様々なものが存在するだけではなく、これらの脳活動計測技術を保有する専門企業も多種多様で、どの企業のどの技術を利用すべきであるかを判断するのは簡単ではありません。また実験計画の立案も手探りで始める必要があるだけでなく、脳科学技術を企業内で利用する際には、機器利用上の安全性の保障・高度な個人情報である計測データの管理等倫理面の配慮も必要不可欠です。さらに市場からの信頼を勝ち得るためには、脳科学に関する情報を適切に整理して消費者に発信していくことも鍵となります。 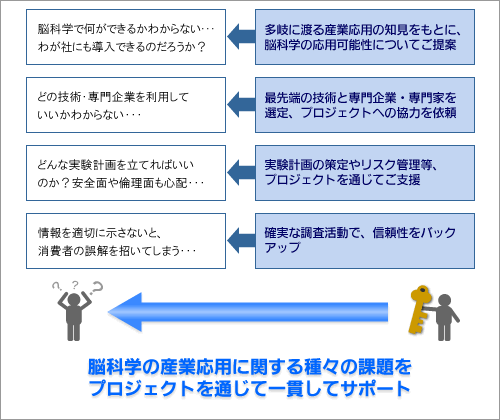 【提供するサービスの概要】 NTTデータ経営研究所では、これらの課題を解決し、近年著しい発展を遂げている脳科学技術を商品開発・マーケティング等の多岐に及ぶ企業活動への脳科学の導入をご支援する、新たなニューロコンサルティングサービスを開始しました。このサービスは、
オープンイノベーションモデルを採用したワンストップ・コンサルティングサービスです。 <新たなニューロコンサルティングのビジネスモデル> 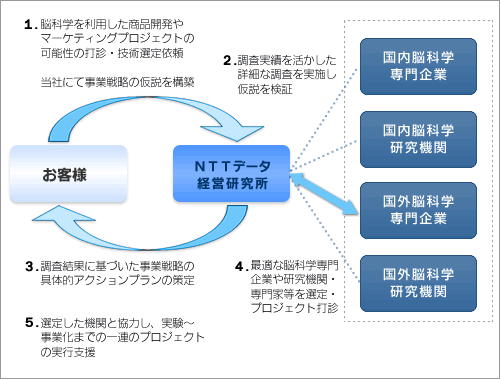 【今後の展開について】現在、脳科学は、飛躍的に発展しつつある研究領域であることから、今後は様々な研究成果が生まれるとともに一層の技術革新が進むものと考えられます。NTTデータ経営研究所では、今後も脳科学に関する最新の知見を継続的に調査し、国内外の脳科学関連企業や研究者・研究機関と幅広く業務提携及び協力関係を構築することで、一層のコンサルティングサービスの強化・拡充を図って参ります。 【本サービスに関連する株式会社NTTデータ経営研究所のこれまでの実績について】NTTデータ経営研究所では、これまで以下に示すようなコンサルティング事業及び調査研究の実績があります。
【株式会社ATR-Promotions及びBAIC事業部について】株式会社ATR-Promotionsは、株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)の研究成果の普及を加速させることを目的として、2004年11月に設立されました。またATR-Promotionsの脳活動イメージングセンタ事業部(BAIC事業部)は、2000年にATR内に設立された脳活動イメージングセンタ(Brain Activity Imaging Center: BAIC)が前身となっています。BAICは、設立当初からATR内の脳活動イメージング研究の支援のみならず、外部機関への脳活動計測装置の貸し出しも行って参りました。そして、2006年にATR-Promotionsの一事業部として組織改変した後は、支援体制をさらに強化しました。 現在、fMRI装置および脳磁計測システム(MEG)を用いた脳活動イメージングの研究環境が利用可能です。多様な実験に対応するため、視覚・聴覚をはじめとする各種の刺激提示装置等の周辺装置も充実しています。また、設備の貸し出しだけにとどまらず、実験計画立案から刺激提示プログラムの作成、データ分析にいたるまで、研究全体のコンサルティングも行います。さらに講習会開催による情報提供や技術指導も行うトータルサポートがサービスの特徴です。 現在、年間約70件の研究プロジェクトがBAICを利用しています。特に外部利用は増加する傾向にあり、利用機関は大学ばかりでなく、民間企業にも及んでいます。 【株式会社脳機能研究所について】脳機能研究所は、1/fゆらぎの研究開発で有名な武者利光(同社代表取締役社長・東京工業大学名誉教授)により、技術研究開発会社として1994年1月に設立されました。 脳機能研究所では、頭皮上電位に現れる感性状態を数値的に計測して秒単位で表示するESAのほか、脳内のシナプス・ニューロン機能低下度を量的に推定する「脳機能低下度推定法(Diagnosis Method of Neuronal Dysfunction ; DIMENSION)」技術やニューロンの異常性を脳表面に表示する技術(Neuronal Abnormality Topography ; NAT)を開発しており、これら技術のさらなる改善や応用技術の開発に取り組んでいます。 また、病院、大学、企業等との同技術の利用に関する共同研究にも積極的に取り組んでいます。さらに、多くの病院や大学等へ脳波解析装置を販売し、実験の企画や脳波解析サービスも行っています。特に、ESAについては、商品デザインや都市環境の評価、精神的ストレスのモニタリングに至るまで幅広く応用されており、数多くの企業で導入事例があります。 なお、脳機能研究所の保有するESAは脳の働きに関係する疾病、例えば、認知症、うつ病、ストレス症候群等の早期発見や脳リハビリテーションの効果測定にも適用可能です。またDIMENSIONは、認知症の初期といわれるMCIの検出にも成功しており、認知症の早期発見と脳リハビリテーションとの組み合わせによる認知症の予防手段および脳機能低下度の高感度モニターとして、病院や脳ドックでの試用が徐々に広がり始めています。さらにNATは、アルツハイマー型認知症やうつ病・脳梗塞等を簡便・安価・安全かつ早期に診断できるとして、産学官医の各方面から注目を集めている技術です。 【独立行政法人産業技術総合研究所の人間福祉医工学研究部門及び脳神経情報研究部門について】独立行政法人産業技術総合研究所は、研究者数や研究レベルの高さにおいて我が国有数の公的研究機関であり、幅広い分野で成果をあげています。 人間福祉医工学研究部門では、健康長寿で質の高い社会の実現に寄与する研究開発を行っています。生活者としての人間や生体システムとしての人間の科学的理解を深め、人間特性・生体特性に適合した製品や環境を創出するための技術を開発し、人間生活及び医療福祉機器関連産業の育成・活性化に貢献することを目的としています。 研究課題は主に3つに分けられます。「高度情報化社会に対応した人間生活工学分野の研究課題」では、携帯電話やITSなどの情報機器の人間特性への適合性を評価するために、人間の認知特性の把握や生活行動の評価技術の開発、複合的な感覚情報に対する人間の感覚情報処理機構の解明などを進めています。「高齢社会に対応した人間生活工学分野および健康福祉工学分野の研究課題」では、高齢者に適合した安全・安心な生活環境を実現するために、加齢効果の著しい有効視野や音声認知などの感覚認知機能についての研究や、身体適応力の維持・改善・向上に関する研究を進めています。「高齢社会に対応した医工学分野の研究課題」では、迅速・正確な医用計測技術、手術の精度と安全性を高める手術ロボット技術や手術スキル評価技術、長期の生体適合性と耐久性を有する人工臓器や高機能生体材料の研究開発などを行っています。医工学分野については、医工・産学官連携により製品開発を目指した研究開発を推進するとともに、産業界で開発される医療機器の円滑かつ迅速な開発・製品化を促進するため、標準化及び技術ガイドラインの策定にも貢献します。 脳神経情報研究部門では、脳の構造と機能の特性を理解することにより、安心・安全で健康な生活を実現するための技術基盤を確立し、関連諸産業の振興に資することを目標として研究を進めています。 脳の構造と機能の特性を理解するためには、異なる研究分野の融合がキーポイントとなっています。神経系で機能するDNA、タンパク質等の分子のレベルから、認知行動やコミュニケーション等、高次機能発現のシステムのレベルに至るまで、ハード面からの生命科学的アプローチとソフト面からの情報科学的アプローチを融合させた研究を展開するとともに、その融合的成果に基づいて関連産業に資すべき技術基盤を確立する必要があります。 脳の物質的な構造と仕組みの理解からは、脳神経系のイメージング技術の開発やバイオマーカーを用いた疾患診断・治療技術の開発により、バイオ産業や医療機器産業の振興に貢献することを目指し、また、脳における情報表現と情報処理機能の理解からは、人間と相性のいい脳型の情報処理技術の開発により、情報関連産業の振興に貢献することを目指します。さらに、両者を統合したブレイン・マシン・インターフェース(BMI)技術の開発により、医療福祉産業の振興に貢献することを目指します。 また、本研究部門では、国際的な学術雑誌等における成果発信はもとより、インターネット等を利用した情報発信や民間企業との共同研究等を通して、社会への直接的な貢献を図っています。さらに研究の推進にあたり、科学技術政策の企画立案への参画や安全かつ効率的な研究環境の整備にも積極的に参画しています。
|

