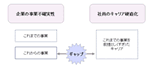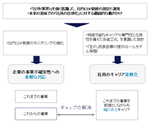変化に対応するキャリア・ディベロップメント・プログラム(CDP)とは 後編
社内CDP制度の活用を阻む2つの限界と、変化に対応するポイントとは
|
|
1.はじめに
前回(前編 「社内CDP制度の特長とは何か)」では、社内CDP制度の全般的な特長について述べた。社内CDP制度自体が、そもそも変化に対応する中で発展してきたことがお分かりいただけたかと思う。しかしながら、昨今のグローバル化をはじめとした急激な環境変化は、社内CDP制度の根幹の考え方すら揺らがすほどのインパクトを持って襲ってきている。
後編では、これらの変化(社内CDP制度を活用した円滑な人材育成を阻む「阻害要因」)について考え、その対応ポイントについて述べていきたい。
2.劇的な環境変化への対応を迫られる社内CDP制度(ケース事例)
外部環境・内部環境の変化や、個人(社員)のキャリア意識の醸成に合わせて整備されてきた社内CDP制度ではあるが、ここに来て急激な変化に対応しきれなくなるケースが見受けられる。
Ⅰ.育成上のキャリアパスの想定を超えた、事業構造の変化
グローバル化や不況を起因とした急激な事業構造の変化が、社内CDP制度で予想していたプロフェッショナルとしての人材像やキャリアパスを、大きく逸脱してしまうような人員配置をせざるを得ない状況が起きている。旧来であれば、人事異動は出世のための経験であり、ゼネラル人材としての育成の機会であったが、キャリアに対する意識が醸成された今の個人(社員)に対しては、企業へのロイヤリティが薄れてしまう事態になりかねない。また、社内CDP制度存在そのものが信頼性を失いかねない状況にもなってしまう恐れがある。
Ⅱ.企業として求める人材像を幾度も変更せざるを得ない程の、価値観の変化
昨今のグローバル化の流れの中で、求める人材像(役割や価値観)についても、その見直しが必要なケースが多くなってきている。多くの企業の場合、社内CDP制度は求める人材像とそのレベルという2軸でのマトリックス上にキャリアパスを表現する仕組みとなっているが、事業構造の変化に合わせて人材像自体も見直しが必要である。しかしながら、そもそも社員が目指すべき人材像が頻繁に変更されると、社員としては自らのキャリアのよりどころ(キャリアの軸足)を築きづらくなり、結果として何を目指していいのか分からない(≒何も目指さない)という、社内CDP制度の目的とは相反する状況(ジレンマ)が起こる可能性がある。
また、制度の定着化自体も変化への対応を困難にしている。
Ⅲ.長期の社内CDP制度運用による、企業施策としての定着化
そもそも個人(社員)のキャリア意識と相乗効果を図ることでうまく機能してきた社内CDP制度が、長年の制度運用の中で「外部(業界など)に通用するプロフェッショナルの育成」から「社内価値を重視したプロフェッショナルの育成」に変化し、個人のキャリアに対する動機付け(刺激)が低下するケースが見受けられる。必ずしも社内価値を重視することが間違いというわけではなく、個人のキャリア意識(成長しようという意識)に対する動機付けが低下してしまうことが懸念点であり、このようなケースに陥ってしまう場合は、往々にして社内CDP制度が「会社から与えられた制度」として社員に認知されていることが多い。つまり社内CDP制度が、自らのキャリア形成のための支援であるとの認識が低くなってしまうのである。
Ⅳ.専門性重視による人材育成の硬直化
ⅠやⅡとも関連するが、社内CDP制度による育成施策は、キャリアアップの縦軸が重視され、横軸(キャリアの幅)については重要性を認めるものの、施策としては対応が薄い場合が多い。このような場合何が起こるかというと、人材の能力が硬直化し、劇的な事業変化が起こった場合の対応が困難となり、また、それ以前の問題として「社員(個人)が、自分の力量の範囲を自ら限定していってしまう」という誤った方向性へ進んでしまう可能性がある。特に散見されるのが「他人材像(職種)の経験は、自らが目指す人材タイプでのキャリアアップにとって『回り道』となる」といった認識である。各自(各人材像を目指す社員)が、利益を追求するために相互研鑽(さん)するという風土になっていれば良いが、多くの場合自らの専門性に固執する余り、業務においての協力性が低くなる(特に自らの役割と他役割で担当する領域があいまいな業務について、積極的に関与しないなど)傾向が見受けられる。
3.社内CDP制度の活用を阻む2つの限界
幾つか変化の事例と、それに応じて社内CDP制度が円滑に運用されなくなったケースを述べてきたが、社内CDP制度が対応していかなければならないこれらの変化は、大きくは2つの阻害要因と言える。
ひとつは「企業の事業不確実性」であり、もうひとつは「社員のキャリア硬直化」である。これらの阻害要因が生じた結果、そのギャップに対応できずにいると、社内CDP制度が円滑に運用されなくなっていくのである。
4.変化に対応するキャリア・ディベロップメント・プログラム(CDP)とは
社内CDP制度は変化に対して、もはや対応することができなくなってきているのであろうか。
上記で述べたような課題を克服し、劇的な環境変化においても社員(個人)のキャリアに対するモチベーションを鼓舞し、企業自体も活性化していくために、変化に対応する社内CDP制度の3つのポリシーに沿って、見直しのポイントを挙げたい。
【変化に対応する社内CDP制度の3つのポリシー】
(1) 個人の自律的学習を加速させるCDP制度
(2) 組織・職場での相互研鑽・相互学習を誘発するCDP制度
(3) 会社の成長と社員の成長をより頑強かつ柔軟にリンクさせるCDP制度
【ポリシーに沿った見直しのポイント】
(1) 個人の自律的学習を加速させるCDP制度~持続可能なキャリア≒専門性と汎用性を備えた多能工化、を意識した設計~
社員が自らの専門性を意識し、業務で実力を発揮しようとするということは、他人材タイプの社員と協業しながら事業成果を作り出すということにほかならない。IT業界で言えば、システム運用工程を意識しないシステム開発などなく、またシステム開発やシステム運用を意識できない営業もあるべき姿とは言えない。このような「ビジネス上の価値」を視座としたキャリア形成の浸透が十分に図れれば、複数のキャリアの軸足を持つことが、キャリア形成においてデメリットであるとの認識は薄れていく。具体的には以下のような観点でのプローチが考えられる。
- 上位レベルでは複数人材タイプを包括した人材タイプとして設計
- 業務プロセスに沿った、他人材タイプとの結節点の育成強化
- 実在の(多能工)人材をベースとしたアプローチの強化((2)で述べる)(2) 組織・職場での相互研鑽・相互学習を誘発するCDP制度~((1)と合わせて)「生の」成長目標の提示(ロールモデル発掘)~
根本的な問題として、人が何かを目指そうとする場合、ある特定の人物に対してのあこがれなどがあって動機付けられることはあっても、文章のみの説明を読んで「その姿を目指そう」と思うことは少ない。よって社内CDP制度は、実在社員をロールモデルとして提示し、社員を動機付けることがセットでないと機能しない場合が多い。また、実在の人物はさまざまな環境変化の中をタフに生き抜いてきた、まさに「キャリアのお手本」である場合が多く、実のところ多能工である場合が多い。いずれにしろ、社員にとって、目指そうと思えるロールモデルであることがまず重要であり、雲の上をつかむようなハイレベルな人材のみをロールモデルとして提示しても、社員にとっては動機付けとならないケースもある。身近な社員のロールモデル化を図ることによって、ロールモデルとなる社員も、またそれを目指す社員も相互に動機付けられるのである。 (経営研レポート「人材開発」機能を強くする!中編」も参照されたい)
(3) 会社の成長と社員の成長をより頑強かつ柔軟にリンクさせるCDP制度~社内CDP制度のモニタリングの強化(CDM「キャリア・ディベロップメント・マネジメント」へ)~
従来、社内CDP制度は、社員のレベルアップ(CDPの軸上での上位レベルへの到達)や、関連する育成施策の受講評価(アンケート等)でその効果が図られることが多かったが、社員を動機付ける仕組みとしての総合的なモニタリング化(マネジメントシステム化)が望ましい。変化に対して、少しずつでも着実に制度の改善を実施していけば、大きな問題となることは少ない。以下に幾つかモニタリング例を記載する。
- 社員の行動変容(知る、気づく、踏み出す、変わる、回りを変える)に対するモニタリング
- 関連施策の育成課題解消度合いに対するモニタリング
- 実践(業務)における活用度に対するモニタリング
特に重要なのは、実務における活用度で、業務と社内CDP制度が互いに関係性がなく独立運営されてしまうと、結果として単なる「研修体系」としてしか機能しなくなり、社内CDP制度として変化に対応する以前の問題(≒形骸(けいがい)化)に対応しないとならなくなってしまう(5.を参照いただきたい)。業務上の目標設定、業務遂行、評価のサイクルに対して、キャリア成長をいかに加味していくかがポイントと言えるだろう。
5.社内CDP制度を形骸化しないために
上述した変化への対応を実施したとしても、そもそも社内CDP制度の運用が形骸化していては意味がない。筆者の社内CDP制度導入経験の中で、共通している成功要因を最後に述べたい。
Ⅰ.「社外(業界)」を強く意識した、社内CDP制度の設計と運用
企業内部での事業不確実性が強まっていく中、社内CDP制度としての軸足をどこにおくべきであろうか。当然各社固有のノウハウやコアコンピタンスの育成が中心ではあるが、より「社外目線」を強化していくことが、結果として社内CDP制度を柔軟、かつ強固なものにする場合も多い。 「社外目線」を制度内に活かす場合に、キャリアフレーム内の要素に社外標準指標(IT業界でいうITSS等)を組み込むことも一案だが、社員にとっては社内CDP制度によってどのように評価されるかが、最もCDPとしてのメッセージを感じられる部分となる(具体的には資格制度化し、認定をしているケースが多い)。評価基準はさまざまなパターンが想定されるが、「社外を意識した育成」をより動機付けたいのであれば、業界標準的なスキルを重点的に評価することがメッセージとしても一貫性を保つこととなる。
| 事例: |
A社では、スキル体系を維持してはいたが、業界全体に通じるプロフェッショナルを育成することを目指し、業界で広く活用されている標準をスキル体系に組み込み、かつ総合的なキャリア育成体系として整備し直した。ただし、単純な導入は社内業務や風土との違和感もあったため、社外目線を起点としながらも、社内キーパーソンで自社の業務や風土に合わせた「翻訳」を行った。 |
Ⅱ.本来の意味での「社員の自律化」に対する継続的な働きかけ
2.のⅢでも述べたように、社内CDP制度は、運用が長期化(社内制度として定着化)するほど、社員(個人)のキャリア意識(成長しようという意識)に対する動機付けが低下してしまう恐れがあり、ともすれば「会社が自分のキャリアの世話をしてくれる」といった誤解を生み出しかねない。そうならないようにするためにも継続的に社員に刺激を与えながら、自律化を促す必要がある。以下に幾つかポイントを記載する。
- 刺激・圧力の創出(本人の緊張感や危機感の喚起するための施策の強化)
- 相互研鑽の促進(ライバルとの競い合い)
- そしゃく・翻訳の支援(「キャリア」を本人の問題として捉えるためのサポート)
| 事例: |
B社では社内CDP制度の施策の柱として、上位レベル者が中心となり下位レベル者を育成していくという、現場中心の運用を行っている。社内CDP制度の同じ人材像を目指していたとしても、所属する部署が違えば取り組み方もさまざまであり、かつ上位レベル者という「実践のプロ」から、リアルな気づきを与えていくことで、継続的な刺激の創出や相互研鑽の場を作っている。 |
6.終わりに
当社が2010年に行った「働きがいに関する意識調査」においても、業務(仕事)が働きがいに密接に関係していることが明らかになっている(経営研レポート「『いま』を大切にして『働きがい』を高める」を参照されたい)。また、複数の人事関連調査結果を見ても、企業が社員の能力開発・キャリア開発を重視しているという結果が出ており、社内CDP制度はますます存在価値が高まってくると考えられる。 本稿で述べた考察も含め、環境変化・事業変化に柔軟に対応し、社員を継続的に動機付けることが、結果として個人の成長と企業の成長の相乗効果を高めていくのである。
以上
|